みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
もし、お金がこの世界から消えたら──あなたの仕事に“価値”は残りますか?
レジもATMも給与明細もない。通貨という概念すら存在しない不思議な国。
でもそこでは、人は働き、学び、モノやサービスを交換し、毎日が回っている……。
このブログでは、そんな“お金のない国”を思考実験として描きながら、
「会計とは何を記録する学問なのか?」
「投資とは、どんな未来に“資本”を預けることなのか?」
という問いに、真正面から向き合っていきます。
通貨が消えた世界では、会計士は「感情のバランスシート(BS)」を作り、投資家は「幸福の損益計算書(PL)」を読み解き始めるかもしれません。
🧠 このブログで得られる3つの視点(ポイント)
- 「価値=お金」ではない時代に、何を尺度とするべきか?
→ 贈与経済・時間銀行・地域通貨・感情資本などの具体例で深掘り。 - 会計が記録するべきは、現金残高ではなく“幸福の履歴”?
→ 「幸福PL」「感情BS」「人間資本」の新しい財務諸表を提案。 - 投資とは“通貨を増やすゲーム”から“共感を配る旅”へ?
→ 無形資産に投じる新しいリターン設計(社会的複利・自然配当)。
これは単なる空想の物語ではありません。
私たちの働き方・生き方・投資のあり方をアップデートするヒントが、この“通貨ゼロ国家”の中にはギュッと詰まっています。
「数字にならない価値」が、これからの社会をどう動かすのか。
あなたの中の“会計士”と“投資家”が、きっと目を覚まします。
さあ、常識の外側へ。新しい「経済」の扉をノックしてみませんか?
目次
通貨が消えた社会に現れる“見えない経済圏”

与えることが通貨になる──贈与経済のリアリティ
通貨が存在しない国で、最初に機能し始めるのは「贈与経済」だ。つまり、お金ではなく“与える”ことそのものが価値を持つ社会だ。現代日本でもその萌芽は見られる。たとえば、友人の子どもの面倒を見たら、後日その親があなたに夕食をご馳走してくれる。これは金銭を介さないが、れっきとした「交換」だ。
こうした贈与型の社会は、かつて人類が通貨を発明する前に普遍的だった。文化人類学者マルセル・モースの研究によれば、ポリネシアの諸島では、腕輪や首飾りといった品が「贈ること」自体に社会的意味を持ち、返礼のタイミングや相手との関係性が人間関係を構築していたという。つまり、帳簿に記されるのは「金額」ではなく、「与えた行為」と「信頼の履歴」なのだ。
バーニングマンというアメリカの巨大フェスティバルでは、金銭の持ち込みが禁止されている。その代わり、参加者は飲食、マッサージ、アートなど自分の“何か”を自由に提供する。このイベントで生まれるのは、「誰がいくら儲けたか」ではなく、「誰がどれだけの笑顔をもたらしたか」。お金がなくても、コミュニティは意外なほど滑らかに動く。
時間こそ、最も平等な通貨──タイムバンクの可能性
通貨ゼロ国家において、次に注目すべきは“時間”という単位だ。たとえば、1時間のベビーシッターと1時間の料理教室を交換する「タイムバンク」制度。日本にもその萌芽があり、子育て支援や介護現場などで小規模ながら実装されている。
面白いのは、この制度が“能力の差”を無効化する点だ。弁護士でも大工でも、1時間は1時間。市場経済が構造的に生み出す「高スキル=高収入」という格差を、時間という単位で“初期化”するのだ。社会的包摂(inclusion)という観点から、タイムバンクは極めて公平性の高い制度と言える。
さらに、これらの記録はすべてデジタル台帳に保存される。見た目はただのポイントシステムでも、れっきとした“通貨代替型の帳簿”が機能している。会計士が介入すべきは、この“時間残高”をどう可視化し、どう信用情報と紐づけるかだ。金銭よりも「時間を預け合える関係性」こそ、最も強固な担保となる。
国家が“モノを配る”世界──インフラと現物主義の逆転
もうひとつ見逃せないのが「通貨を使わなくて済む仕組み」を社会の側で整備するというアプローチだ。たとえば、ベーシックインカム(BI)とは逆に、「ベーシック・サービス(BS)」を無償提供するモデル。イギリスの経済学者たちが提唱する“Universal Basic Services”では、住居・交通・教育・医療・通信などの基盤インフラをすべて無料化することが議論されている。
つまり、そもそも「お金を使わないでも生きられる環境」を制度設計で用意してしまうという発想だ。これは極めてラディカルだが、もしそれが実現すれば、「金を稼ぐこと」より「誰と、何をして生きるか」のほうが価値を持ち始める世界がやってくる。
ここでは会計の役割も変わってくる。国が“物を配る”主体である以上、記録されるべきは「供給した量」と「その分配の公平性」だ。物流データと人口統計こそが、最重要の財務情報となるかもしれない。
このように通貨が消えた瞬間に立ち上がる“見えない経済圏”は、いずれも「信用」「時間」「関係性」「サービス供給」といった、私たちが普段見落としているものを“資本”に格上げする発想で動いています。そして驚くべきことに、これらはすでに世界のあちこちで“実験”され、成功を収めつつあるのです。
「幸福PL」と「感情BS」──会計の再発明は可能か?

“数字”の代わりに記録するもの──幸福の損益計算書
通貨のない国では、従来のように売上や利益を数値で並べる損益計算書(PL)は成立しない。では、会計士は何を記録するのか。そこで登場するのが、「幸福PL(Profit & Loss Statement)」という発想だ。これは金額ベースではなく、個人や組織が生み出した“幸福量”を収益とみなす新しい財務レポートである。
たとえば、ある地域の農家が収穫した野菜を近隣住民に無料で分け合ったとする。その結果、住民の健康が改善し、孤独感が減り、地域の結びつきが強くなった。これを「健康向上スコア」「コミュニティ信頼度」などの非財務指標で定量化し、PLに記載する。ブータンのGNH(国民総幸福量)を応用した指標設計だ。
重要なのは、こうした幸福“収益”の裏には、同時に「負の費用」もある点だ。たとえば環境破壊やストレス、無償労働の過重負担など。これらは損益計算書上の“コスト”として明示すべきであり、実質的な“赤字”として扱うべきだろう。つまり、幸せはただではないし、可視化しなければサステナブルにはならない。
感情は“資産”になり得るか──新しいバランスシートの構想
貸借対照表(BS)とは、企業や国家の持つ「資産」と「負債」、そしてそれらの差額としての「純資産」を示すものだ。しかし、通貨のない世界では、現金や預金、売掛金といった従来の項目は意味を持たない。代わりに浮かび上がるのが、「感情資産」「人的資本」「社会関係資本」といった無形資産の再定義である。
たとえば、ある学校が生徒に対して高い自己肯定感や創造力を育んだとする。これを“人的資産の増加”とみなし、BS上の資産として計上する。一方、過剰な競争や管理体制が教員のバーンアウトを引き起こした場合、それは“感情資本の毀損”としてマイナス項目に記録される。
この考え方に近いフレームワークが、国際統合報告(<IR>)が提唱する「6つの資本モデル」だ。財務・製造・知的・人的・社会関係・自然という6領域の資本が互いに影響し合う構造を描き、投資家に対してより“本質的な持続可能性”を伝える。今後、企業の評価基準は「いくら儲けたか」ではなく、「いかに人的・感情的資本を育てたか」へと変わっていくかもしれない。
“感情の履歴”を誰が記録し、どう監査するか?
問題は、これら無形の価値をどう測定し、誰がその妥当性を担保するか、である。ここに登場するのが、ブロックチェーン技術やスマートコントラクトを使った“感情台帳”という概念だ。参加者が体験したポジティブな感情や、他者への貢献行為がトランザクションとして記録され、コミュニティの信頼ネットワークの中で照合・検証される。
すでに先行する事例もある。オープンソース開発コミュニティ「Sensorica」では、貢献度を記録するバリュー・アカウンティング・システムを導入している。これは、誰がどれだけの時間やスキルを提供したかを細かく記録し、それに応じた“価値の分配”が自動的に決定される仕組みだ。感情や関係性といった曖昧なものを、数値ではなく“ログ”として捉え直す発想といえる。
そして、この“感情の履歴”を監査するのが、新時代の会計士たちだ。彼らはエクセルで金額を合わせるのではなく、データの信頼性・持続性・関与の深さを検証する“関係性アナリスト”として活躍するようになるだろう。
通貨が存在しない社会では、会計とは「何を残し、何を育て、何を損なったか」を言語化する営みとなる。感情も信頼も幸福も、未来に向けた“資本”とみなすことで、数字に還元できない価値が初めて経済の舞台に立てるのだ。そうした会計の姿は、きっと私たち自身の生き方や働き方を問い直すヒントにもなる。
通貨がなくても“投資”は生まれる──価値を託すという行為の本質

未来を預ける“投資”は、通貨より信頼が資本になる
お金が存在しない社会でも、人は“未来を信じて何かを差し出す”という行為をやめない。これこそが投資の本質だ。投資とは、単なる資金提供ではない。限りある資源──時間、労力、知識、信用──を誰かや何かに“託す”ことで、その先の変化や成長に期待する営みである。
通貨がない社会では、投資の対象はより“無形”になる。たとえば、ある地域の若者にプログラミングを教える行為。それ自体は現金を生まないが、彼らが地域に貢献し、さらに次の世代に教えを渡せば、その“知識の複利”はコミュニティ全体を強くする。これは「学びの連鎖」に投資することであり、時間と関係性がリターンを生む構造だ。
そのとき、投資家が見るべきものは収益率ではなく「関与率」だ。どれだけ多くの人がそのプロジェクトに思い入れを持ち、実際に時間や行動を投じているか。それが通貨ゼロ国家における“信頼残高”であり、信用創造の源泉となる。
リターンは“お金”から“インパクト”へ──社会的複利の登場
近年、インパクト投資という言葉が広まりつつある。これは金融リターンだけでなく、社会的・環境的成果を重視する投資スタイルだ。通貨ゼロ国家では、この発想がデフォルトになる。
たとえば、ある人が週に数時間を使って、荒れ地に木を植えるとする。一見、何の利益も生まない。しかし10年後、そこは食糧を育てる森になり、周辺の気温を下げ、水源を守り、人々の集う場所となるかもしれない。この“自然資本”への投資は、まさに社会的複利だ。
こうしたリターンは、数値化が難しい一方で、人々の幸福や未来の安全保障に深く結びつく。その価値を記録する方法として注目されているのが「SROI(Social Return on Investment)」という手法だ。例えば「1時間の教育が、将来的にどれだけの社会的価値を生んだか」を割り出す試みである。従来のROI(投資収益率)が貨幣単位でリターンを測っていたのに対し、SROIは“感情”や“生態系の変化”まで指標に含める。
つまり、投資が“お金のゲーム”から“世界を変える遊び”に進化する。利益を配る代わりに、感動や成長や共鳴を配る──そんな投資の形が、すでに世界各地で静かに始まっている。
ブロックチェーンと共助が担う“新しい金融の土台”
通貨ゼロ社会で最も大きな課題は、担保と清算の仕組みだ。つまり「この人に預けて大丈夫か?」「成果はどう分配するか?」という不安をどう克服するか。ここで鍵を握るのがテクノロジーと“共助モデル”である。
たとえば、ブロックチェーンを使えば、誰がどんなスキルをどれだけ提供し、どんな結果を生んだかを透明に記録できる。オープンソースの開発プロジェクト「Sensorica」では、貢献度に応じて報酬(トークン)が分配されるが、それはすべてスマートコントラクトで自動化されている。信頼を個人に依存せず、ネットワーク全体で担保するという発想だ。
また、通貨が存在しないため、従来の保険やローンといった金融機能は使えない。そこで注目されているのが“共助型ファンド”の設計である。たとえば、災害や病気で困った人がいたら、事前に積み立てられた“時間ファンド”から支援が届く仕組み。これはかつての「頼母子講(たのもしこう)」や「無尽講」のような仕組みを、ブロックチェーンによって透明・自動・分散化した現代版と言えるだろう。
テクノロジーの進化によって、「通貨がなくても金融は機能する」ことが、徐々に証明されつつある。ここには、金利も担保も存在しないが、信頼と連帯と記録がある。そんな“通貨なき金融”が、これからの投資行動の土台になるかもしれない。
お金を媒介としない投資とは、「誰かの未来に、あなたの時間や行動を預けること」だ。そこに必要なのは資金力ではなく、参加する意志と、世界をよくしたいという“情熱”なのかもしれない。
結論:通貨がなくても、価値は循環する
「通貨がなければ、何もできない」──私たちはいつから、そんな思い込みに縛られてしまったのだろう。
でも実際には、お金のない国にも価値はあふれている。人が人を思って差し出す行動、言葉、時間。見返りを求めない笑顔、誰かのために手を伸ばす勇気。それらはすべて、“帳簿には載らない資本”だ。そしてその資本こそが、本来、社会を動かす燃料なのかもしれない。
会計士は、かつて貨幣の動きを記録する専門家だった。でもこれからは、「誰がどれだけの愛と信頼を世界に預けたか」を記録する存在に変わっていく。投資家は、企業の利益率ではなく、「このプロジェクトはどれだけ世界に希望を残すのか」を測るようになる。
通貨がなくても、人は生きていける。いや、通貨がないからこそ見えてくる“本当の豊かさ”がある。もし今、あなたの手元にある通帳の残高がゼロになっても、それは「何も持っていない」ことではない。そこにあるのは、「新しい価値観のスタートライン」だ。
あなたの時間、気持ち、つながり──そのすべてが、世界の誰かにとっての“投資”になる未来が、もう始まっている。お金では測れない、でも確かに存在する価値を信じて、一歩踏み出してみよう。その先にあるのは、きっと数字以上にあたたかい「経済」だ。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
SDGsとパーパスで読み解く責任経営の系譜
日本企業が「持続可能性」や「存在意義(パーパス)」をいかに実践に落とし込んできたかをケーススタディで解説。幸福や社会的価値を組織内外にどのように記録・発信するか、会計や経営の観点から示唆に富んでいます。
これでわかった財務諸表
38年の実務経験を持つ著者による、財務諸表の基礎から「生きた経済とのつながり」までを実例中心に解説。特に、「数値に見えない価値をどう表現するか」という視点は幸福PLや感情BSを考える際のヒントになります。
経営教育 人生を変える経営学の道具立て
最新の経営学理論を「即使えるフレーム」として紹介する一冊。価値創造や社会との関係性を測るツールが豊富に提示されており、無形資産や人的資本をどう捉え、どう育てていくかの視点を補強してくれます。
給料はあなたの価値なのか——賃金と経済にまつわる神話を解く
「賃金=価値」という常識に異を唱え、経済と人間の期待値、貢献と評価の関係を問い直す一冊。通貨だけで価値を判断しない世界観を養うのに最適で、幸福や感情を資本と捉えるブログ内容と親和性が高いです。
経済大国なのになぜ貧しいのか?——幸福の「資本」論
国や企業の“資本”として、GDPでは測れない幸福や社会性をどう捉えるかを論じた本。会計や投資の枠を超え、自然資本や社会関係資本の見える化に関心がある方にとって示唆に満ちた視点が得られます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20363474&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1275%2F9784830951275_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4287359e.f5e60109.4287359f.b52e72d7/?me_id=1309253&item_id=13757825&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooksupply%2Fcabinet%2F04216212%2F359%2F9784532190347.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21515157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4819%2F9784040824819_1_9.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20555250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0557%2F9784622090557.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=15772577&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4935%2F9784894514935.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

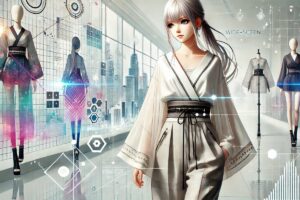











コメントを残す