みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
その“関税の段差”、あなたのポートフォリオにどれだけ効いてますか?
「関税が上がると、なぜ企業の利益が一気にしぼむのか?」——今日のテーマはここです。11月5日、トヨタの4–9月期(上期)純利益が前年同期比で7%減と報じられました。背景には米国の関税引き上げ。日本から米国へ車を売るときに、以前は2.5%だった輸入関税が、2025年夏以降の合意で15%水準に上がり(当初は25%案も取り沙汰)、自動車各社の採算に重くのしかかっています。関税は「政治の話」に見えますが、会計では仕入原価(原価)そのものとして効きます。つまり、材料費や物流費と同じ棚でコスト化され、粗利→営業利益を直接削ります。為替と同じで、政策という名の“原価リスク”です。
この記事では、初心者でも手触り良く分かるように、(1) 関税が損益計算書のどこを直撃するか、(2) 粗利が「どこで蒸発するのか」を一目で追える思考フレーム、(3) 個人投資家が明日から使えるKPI化のコツ(「売上の地域別比率 × 粗利率」=関税感応度)を、具体例つきで解説します。難しい数式は使いません。必要なのは、「関税=原価↑→粗利↓→営業利益↓」という一本線の理解だけ。さらに、米関税の最新状況(足元は15%合意)も軽く触れ、ニュースと会計の橋渡しをします。読み終える頃には、決算資料のセグメント地域売上や粗利率を見る目が変わるはず。関税のニュースに右往左往するのではなく、「どの会社の、どの収益が、どれくらい振れるのか」を自分で見積もれる状態を目指します。投資と会計の視点で、粗利の“消え方”を可視化していきましょう。
目次
関税は“どこで”利益を削るのか

まずは会計の地図を持ちましょう。損益計算書(P/L)は、ざっくり「売上 − 売上原価 = 粗利」「粗利 − 販管費 = 営業利益」という一本道。ここで関税は売上原価に直行します。材料費や部品、物流費と同じ棚に乗るので、発生した分だけ粗利がその場で目減りし、結果として営業利益まで細ります。だからニュースで「米国の自動車関税が上がった」と聞いたら、まずは「原価が増えた=粗利が減った」と機械的に捉えるのがコツ。実際、トヨタの上期(4–9月)では純利益が前年比▲7%、米関税の影響が重いと各社が明言しています。米国の対日(完成車・部品)関税は2025年に一時27.5%まで上がり、その後も従来の2.5%より高い約15%で推移——この差分が、そのまま原価にのしかかるイメージです。
「関税=原価」の見え方
覚え方はシンプルです。
売上 −(材料費+部品+物流+関税)= 粗利。
関税は「税金」という名前に引っ張られますが、法人税のように最終行(当期純利益)の下で計算するものではありません。粗利の上段で効くので、経営の体感としては「仕入が高くなった」に近い。たとえば価格を据え置いたまま関税が+5ポイント上がれば、粗利率はほぼ5ポイント分スライドで下がります(値上げやコスト改善で吸収できない限り)。
粗利が“蒸発”する順路
流れはこうなります。
- 米向けに輸出 → 2) 通関で関税発生 → 3) 会計上は売上原価に計上 → 4) 粗利が減る → 5) そのまま営業利益が減る。
価格転嫁が間に合えば傷は浅く、ディーラー向けの出荷価格や小売価格を上げれば粗利は守れます。ただし自動車は価格弾力性が低くないので、販売数量が落ちるリスクと表裏一体。結果として「台数確保のために値上げを抑える→粗利率が落ちる」という板挟みが起きます。トヨタも上期は売上+5.8%と伸ばしつつ、営業利益▲18.6%と利益側がより強く押された構図が確認できます。
為替と関税は“似て非なる”原価リスク
為替安(円安)は輸出企業にプラスになりやすい一方、関税は原価を直接押し上げるマイナス。どちらも「政策に左右される」という意味で“政策リスク=原価”ですが、挙動は違います。為替は日々のレートでじわっと効くのに対し、関税はレートの段差のように一気にコスト構造を変える。だから決算では、地域別売上×粗利率の掛け算で「どこに段差があるか」を追うのが有効です。米国比率が高く、かつ現地生産比率が低い(=輸出比率が高い)企業ほど、関税の段差をモロに受けます。足元の米関税が一時27.5%→現在15%程度という水準なら、関税負担は旧来2.5%時代より約+12.5ポイント重い——このギャップが当面の「段差」です。
ポイントは、「関税はニュースでは政治の話、会計では原価の話」。ここを腹落ちさせれば、決算資料を開いたときに見るべき場所がはっきりします。次のセクションでは、ニュースを投資で使えるKPIに変えるために、「売上の地域別比率 × 粗利率」で関税の“感応度”を数値として持つやり方を具体的に作っていきます。会社ごと・サプライチェーンごとにどれだけ振れるのか、自分の手で見積もれる形にしていきましょう。
“関税感応度”をKPIにする——売上の地域別比率 × 粗利率
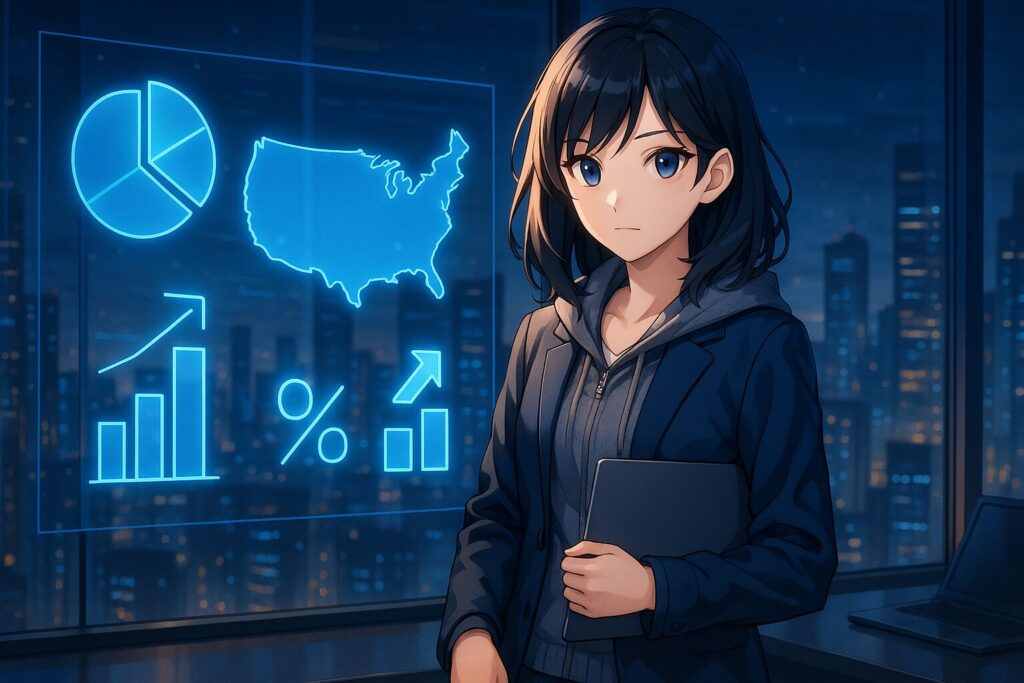
ニュースを投資で“使える”情報に変えるコツは、決算の数字をひとつだけ自分用KPIに落とすこと。ここで提案するのが関税感応度です。考え方はシンプル。米国向け売上の比率(=関税がかかりやすいエリア)× その事業の粗利率。この掛け算が大きい企業ほど、関税の上げ下げが粗利→営業利益に効きやすい。トヨタの最新決算では上期純利益▲7%、営業利益▲18.6%、売上+5.8%という“売上は伸びるが利益は重い”形。背景に米国の関税が2.5% → 27.5%を経て、現在は15%へ低下したものの、依然として負担が残るという状況があります。だからこそ、まずはどれだけ米国に売っているか × その売上の粗さで“効きやすさ”を測る。これが投資家にとっての地図になります。
材料はふたつだけ:地域別売上と粗利率
- 地域別売上比率:有価証券報告書や決算プレゼンに「地域別売上」や「北米の販売台数・売上」が出ています。米国依存度が高いほど、関税の影響を受けやすい素地があると判断できます。トヨタの上期は売上+5.8%、北米も台数・売上が伸びています。伸びる市場に売るほど、関税は「通る門」も増えやすいという見方です。
- 粗利率:同じ1円の関税でも、粗利率の高い事業は利益への痛みが相対的に大きい。逆に粗利が薄い商材は「そもそも薄い中でさらに削られる」ため数量確保の判断が増えがち。どちらにせよ、粗利の厚みを把握しておくと、関税の段差が収益にどう映るかをイメージしやすくなります。
まずはこの2点を拾って、関税感応度=米国売上比率×粗利率という一目KPIを作る。数字はざっくりで十分。重要なのは相対比較です。
5分で作る“自分用ダッシュボード”
- 手順①:米国(または北米)売上比率を拾う。 決算資料の「地域別」ページをチェック。比率が無ければ、北米売上÷全社売上で自作。
- 手順②:粗利率を拾う。 連結ベースの粗利率でも、セグメント別でもOK。なければ「売上総利益÷売上高」。
- 手順③:掛け算する。 例)米国売上比率40% × 粗利率20% = 関税感応度 8(単位は点数でOK)。
- 読み方: 数字が大きい=「米国にたくさん売っていて、しかも粗利が厚い」→関税の上下が効きやすい。数字が小さい=「米国比率が低い、または粗利が薄い」→影響は相対的にマイルド。
- 補足:現地生産の比率。同じ“米国向け売上”でも、米国内で作っていれば関税の直撃は小さい。つまり(米国売上比率 × 粗利率)×(輸出比率)とできれば精度が上がります。公開情報で輸出比率が拾えない時は、工場の所在地や現地生産ニュース(米国内増産計画など)をヒントに“ざっくり補正”で十分。
数字にニュースを差し込む:いまの“段差”はどれくらい?
いまの米国の対日自動車関税は、27.5%から15%へ引き下げ済み(従来の2.5%よりは依然高い)。この+12.5ポイント(対2.5%比)の“段差”が、当面の原価の上乗せ幅として効きます。企業が値上げやコストダウンでどれだけ埋められるかが勝負どころ。
マクロ側でも、関税による車両価格上昇で米国の販売見通しが下方修正される動きがあり、数量面の逆風も頭に置く必要があります。数量×単価×原価の三面から効く——それが関税です。
トヨタの上期実績では純利益▲7%、営業利益▲18.6%。売上は伸びていても、原価側の段差が利益を圧迫している構図がはっきり読み取れます。次の決算でも、関税と現地生産・価格転嫁の動きが読み解きポイントです。
関税感応度=米国売上比率 × 粗利率。これだけで、ニュースを“見える化”できます。さらに余力があれば輸出比率で補正し、現地生産の進捗や価格転嫁(販売価格の改定)のニュースをメモしておく。KPIを1本持っておくと、決算の度に比較ができ、投資判断のブレが減ります。次のセクションでは、このKPIをサプライチェーン銘柄に広げて、「どの部品・物流・素材がどれだけ振れるのか」を実例ベースで見ていきます。
サプライチェーンまで“関税感応度”を広げる

完成車メーカー(トヨタなど)だけでなく、部品・素材・物流まで視野を広げると、投資の地図が一気に立体になります。考え方は同じで、米国向け売上(or 北米依存度)× 粗利率 × 輸出比率。この3つの“掛け算”で、どこが関税の段差に弱いかを見分けます。公開資料にある地域別売上やセグメント粗利を拾えば、初心者でも十分たどれます。たとえばトヨタは最新の上期発表で北米販売の存在感が引き続き大きく、全社の利益は足元減益基調も報告されています(4–9月期・純利益は前年から縮小)。こうした完成車の地合いは、部品や物流へも波及します。
素材・物流は“数量×単価×原価”の三面で効く
素材(鋼板・樹脂・電池素材など)は、米国向けの加工・輸出が多いほど、関税で原価が段差になります。ここは値上げで調整しやすい一方、数量が鈍ると急にしんどい。
海運・自動車船(RORO)は「完成車輸送」の動脈。北米航路の比率が高い会社ほど、台数の波や政策変更の影響を受けやすい構造です。大手の日本勢(NYK/商船三井/川崎汽船)は世界上位の自動車船オペレーターで、北米向けの需要動向が重要な観察点。投資家視点では、各社の統合報告書やIRファクトブックの自動車船のシェア情報、北米向けコメントを拾ってメモしておくと、完成車ニュースと同方向に動くか逆方向かが読めます。
実務ポイント
- 物流は数量敏感:値上げで埋める余地が小さいため、米販売台数の鈍化がダイレクトに効きやすい。
- 素材は価格転嫁のタイムラグ:四半期ごとに調整式の契約も多く、ニュース→業績への反映にズレが出やすい。
- 両者とも、米国依存度(売上や航路の比率)を必ずチェック。
ティア1部品は“北米売上×粗利率×現地生産比率”
トヨタグループのデンソーやアイシンのようなティア1は、北米売上の厚みがまず効きます。たとえばデンソーは北米で1.8兆円規模の売上がある大型プレイヤー。売上の柱が北米にある分、政策・需要の変化が粗利→営業利益へ波及しやすい。一方で現地工場が多く、現地生産比率が高いほど“関税直撃”は和らぐのもポイントです。
アイシンも統合報告・決算資料で地域別売上を開示。北米でのハイブリッド用トランスミッションなど、電動化コンポーネントの増産により売上・利益を積み上げている局面が確認できます。こうした“現地で作って現地に売る”ほど、関税の段差は完成車ほどストレートに効かない——ここは銘柄選びの差分になります。
実務ポイント
- まずは北米売上比率を拾う(決算プレゼン/統合報告の地域別ページ)。
- 同じ比率でも、現地生産の厚みで感応度は変わる(工場所在地・北米増産ニュースをメモ)。
- 粗利率の厚いユニット(電動化・ソフト/ECU系)は“関税の段差”が利益に映りやすい。
“5つの箱”でウォッチリストを組む
サプライチェーンを5つの箱に分け、各社に**関税感応度(米国売上比率×粗利率×輸出比率)**をメモします。
- 完成車:トヨタなど。地域別販売・利益の足元トレンドを確認。北米の利益鈍化や値上げ動向は必ずチェック。
- ティア1電子・電動化:デンソー(北米売上が厚い)。高付加価値ゆえ粗利厚め=感応度も出やすい。
- ティア1機械・駆動系:アイシン(北米でのHVユニット伸長)。現地生産の厚みで関税直撃は緩和されやすい。
- 物流(RORO):NYK/商船三井/川崎汽船。北米向け数量と運賃のサイクルに連動。
- 素材:鋼板・樹脂・電池素材。価格式・契約更改のタイムラグで業績反映がズレる点に注意。
運用のコツ(初心者向け)
- “まず比率”。米国(or 北米)売上比率と粗利率だけ拾って、ざっくり掛け算。
- 余力があれば、現地生産の有無で補正(北米工場の有無・生産計画)。
- 企業ニュースは「価格改定」「現地増産」「数量ガイダンス」の3ワードでメモ。
- 1社ではなく同業2〜3社で相対比較。同じニュースに対して感応度の差を見ると腑に落ちます。
サプライチェーンに関税感応度のものさしを持ち込むだけで、ニュースが“具体的な数字”に変わります。完成車で起きた利益の重さは、物流の数量や部品の粗利、素材の原価へと波紋のように広がる。あなたがやることはシンプルで、米国依存度×粗利率×輸出比率を小さな表にして、四半期ごとに同じ位置で見比べるだけ。トレンドが右肩上がりか、段差に引っかかっているか、自然と見えてきます。上手くいけば、「関税の見出し」が出る前から、どこが効きやすいかを先に感じ取れるようになります。
結論|“政策は原価”と腹落ちしたら、ニュースは地図に変わる
最後にもう一度、一本線で結びましょう。関税は“ニュース”ではなく原価です。通関の瞬間にコストとして計上され、粗利→営業利益をまっすぐ削る。ここが腑に落ちると、見出しに振り回されず、決算を自分の物差しで読めるようになります。
やることはシンプルでした。
- 米国(北米)売上比率を拾う。
- 粗利率を押さえる。
- できれば輸出比率(現地生産の薄さ)で補正する。
この3点を掛け合わせた関税感応度を、銘柄ごと・サプライチェーンごとに並べるだけ。数字はざっくりでOK。四半期ごとに同じ場所を見返すと、トレンドが“見えてくる”状態になります。
価格転嫁やコスト改善で段差は埋められますが、常に数量との綱引きです。上げれば守れる粗利、落ちれば薄まる台数。だからこそ、数字で仮説→次の決算で検証のサイクルが効きます。日々の相場観に頼らず、「なぜこの会社は効きやすいのか/効きにくいのか」を自分の言葉で説明できるようになる。ここが、初心者から一歩抜け出す分かれ目。
“政策は原価”。この短い合言葉は、為替にも関税にも効きます。あなたが今日つくったKPIは、次のニュースを“点”から“線”へ変える道具です。見出しの強弱ではなく、ビジネスの構造で判断する。投資は博打ではありません。仕組みを分解して、確率を上げていく作業です。関税ショックという荒波の中でも、地図を持つ人は迷いません。手元のノートの1ページ目に、関税感応度の小さな表を。次の決算で、すぐに使い始めましょう。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
決算書はここだけ読もう〈2026年版〉
「どこを見れば“粗利→営業利益”の落ち込みが分かる?」に一直線で答える定番。貸借・損益・CFの“見る順番”が決まるので、ニュース→KPI(関税感応度)へ落とす練習に最適。薄くて読み切れるのに要点が強い。まず1冊ならこれ。
これならわかる決算書キホン50!〈2026年版〉
1テーマ見開きの図解で“粗利率”“売上原価”のツボがスッと入る。実在企業の事例も豊富で、関税ショックがP/Lのどこに刺さるかをイメージしやすい。電車移動でもサクッと進む“スキマ読書”向け。
タイパ コスパがいっきに高まる決算書の読み方
外資系金融の思考をベースに、“最短で意思決定に使う読み方”へ寄せた一冊。価格転嫁・数量・原価の三点を素早くチェックする勘所がまとまっていて、「関税=原価」を数字で追う習慣がつく。実務スピードを上げたい人向け。
BCGが読む 経営の論点2026
サプライチェーン再編、経済安保、インフレ下のプライシングなど“いま”の論点を網羅。会計の型を押さえた上で、現場の打ち手(現地生産・価格設計・在庫最適化)までつなぐ橋渡し本。投資メモの“背景理解”が一段深くなる。
サプライチェーンにおける人権リスク対応の実務
一見遠回りに見えて、実は“関税以外の政策リスク”を図解で可視化する実務書。デューデリ/DDの進め方、取引先管理、サプライヤー地図の引き方が学べる。関税だけに目を取られず、政策=原価の全体像を押さえたい人へ。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21678748&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0716%2F9784335450716_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21683845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9113%2F9784502549113_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21013469&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2348%2F9784492602348_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21779713&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2719%2F9784296002719_1_26.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21273907&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6239%2F9784865566239_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す