みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
この上昇は本物の“バリュー覚醒”、それとも政策が見せる蜃気楼?
日本株式市場がいま“大変革”の時期を迎えています。2025年8月、日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)は史上最高値を更新しました。これまで長く低迷気味だった日本株が復活し、「バリュー株の覚醒」とも呼ばれる現象が起きています。でも、この盛り上がりは本物の実力によるものなのか、それとも政策が後押しした一時的なブームなのでしょうか?
本ブログでは、そんな疑問にお答えします。読むメリットは盛りだくさんです!まず、TOPIXが過去最高を記録した背景にある「PBR1倍要請」とは何かを分かりやすく解説します。これは東証が低評価の企業に対して資本効率を上げるよう求めた要請で、日本企業の経営姿勢に大きな変化を促したものです。次に、実際に企業がどんな動きを取ったのか、株主還元(自社株買いや増配)や事業売却など具体例を交えて深掘りします。さらに、会計と投資の視点から、表面的な数字だけでは測れない「本当の企業価値の見極め方」についても触れていきます。
極めつけは、PBR1倍割れ(いわゆる割安株)を再評価するためのチェックリストを大公開!これは私自身が実践で使っているもので、どんなポイントに注目すれば埋もれたお宝銘柄を見つけられるかがわかります。このチェックリストを知れば、「この会社、実は化けるかも?」といった発見ができるようになり、あなたの投資ライフがさらに充実するはずです。
20〜30代の社会人の方にも親しみやすいように、専門用語もできるだけかみ砕いて説明します。「難しそう…」と感じている人も大丈夫!最後まで読めば、日本株市場で今何が起きているのかスッと理解でき、明日からのニュースがもっと面白くなるでしょう。さっそく本題に入りましょう!
目次
TOPIX最高値の背景と“PBR1倍要請”とは?

まず押さえておきたいのは、なぜ今日本株が盛り上がっているのかという背景です。2025年8月7日、東証株価指数(TOPIX)は2991ポイント台まで上昇し、史上最高値を更新しました。株価上昇の原動力には様々な要因がありますが、その一つとして注目されているのが東証による「PBR1倍割れ企業への要請」です。これは一体何なのでしょうか?
PBRって何?というところから簡単に説明しますね。PBR(株価純資産倍率)とは、株価を1株あたり純資産で割った指標です。要するに株価が会社の純資産と比べて割高か割安かを示すものです。PBRが1倍を下回るということは、「市場がその会社の純資産よりも低い評価しかしていない」状態、言い換えれば解散価値以下の値段しか付いていないことを意味します。日本企業には長年、このPBR1倍割れの状態が放置されているものが非常に多かったのです。実際、2023年初め時点では東証プライム市場の約半数、スタンダード市場の約6割もの企業がPBR1倍未満という状況でした。これは世界的に見ても異例で、「日本株は価値に比べて株価が低迷しがち」という“バリュートラップ(価値の罠)”として知られてきました。
そんな状況を変えようと、東証(日本取引所グループ)は2023年3月に重要なアクションを取ります。具体的には「資本コストや株価を意識した経営」を各上場企業に促す要請を発表し、継続的にPBRが1倍を下回る企業は改善策の開示・実行を求めると明言したのです。これは「いつまでも株価が低迷しているようじゃダメですよ。ちゃんと株主に報いる経営をしてくださいね」という東証から企業へのメッセージです。そのインパクトは大きく、海外メディアからは「東京証券取引所が『簿価割れ企業は何か手を打て』と言ったのは劇的な変化だ」と評価されたほどでした。実際、この要請は従来あまり動かなかった日本企業の経営陣に火を付け、「眠れる価値株」にスポットライトを当てる契機となったのです。
では、この要請から時間が経った現在、状況はどう変わったのでしょうか。東証が公開したデータによれば、PBR1倍割れ企業の割合は確実に減少しています。たとえばプライム市場では2022年7月時点で全体の50%がPBR1倍割れでしたが、2025年7月時点では44%まで改善しました(▲6ポイント)。スタンダード市場も同様に、64%から59%へと低PBR企業の比率が下がっています。また、収益性の指標であるROE(自己資本利益率)についても、ROE8%未満の企業の割合がプライムで47%→43%、スタンダードで63%→59%と改善傾向が見られます。グラフで見ると、PBRもROEも低いゾーンから高いゾーンへ企業がじわじわ移動しつつある状況です。
もちろん、まだ道半ばです。先ほど言ったように依然として約半数の企業は依然PBR1倍以下です。しかし、市場と企業のマインドセットは確実に変わり始めました。東証の要請を受けて企業側も「このままではいけない」と重い腰を上げ、株主に報いる姿勢を見せ始めています。実際、大和証券のストラテジストは「企業が決算発表を通じて積極的な株主還元姿勢を示しており、投資家は見直し買いを入れている」と指摘しています。要するに、「どうせ株価なんて上がらないし…」と諦めムードだったのが、「ウチもちゃんとやれば評価されるかも?よしやろう!」という前向きな空気に変わってきたわけです。これはまさにバリュー覚醒の序章と言えるでしょう。
企業のリアクション – 株主還元と資本効率革命の実態

東証の要請をきっかけに、日本企業は具体的にどのような行動を取ったのでしょうか。このセクションでは、企業の“リアクション”を見ていきます。キーワードはズバリ「株主還元」と「資本効率の向上」です。難しく聞こえるかもしれませんが、順を追って解説しますね。
record株主還元ブーム到来!
まず目に見えて増えたのが自社株買い(自己株式取得)です。自社株買いとは、会社が自分の株を市場から買い戻すことで、株主に対する利益還元策の一つです。これを行うと市場に出回る株数が減り、1株あたり利益(EPS)は上がります。また「自社の株価は割安だ」という経営陣からのメッセージにもなるため、市場から好感されやすい面があります。事実、東証が要請を出した直後から「低PBRの解消には自社株買いが効くかも?」との見方が広がり、企業の自社株買いが活発化しました。
数字で見るとその盛り上がりは一目瞭然です。2022年度の日本企業全体の自社株買い額は過去最高を記録し、2023年度もそれを上回る勢いが注目されました。実際、2023年に企業が発表した自社株買いの取得枠合計は約9兆6,000億円にも達し、2年連続で最高更新という猛烈なペースです。これはもう“ブーム”と言っていいほどで、東証の要請が企業の背中を強く押した形です。証券会社の調べによれば、2023年4月以降に新規の自社株買いを発表した企業数は前年同期を上回り、高水準が続いています。まさに「空前の株主還元ラッシュ」ですね。
増えたのは自社株買いだけではありません。配当金の増額(増配)も相次ぎました。たとえばコスモエネルギーホールディングスという石油系の会社では、2023年に発表した中期経営計画で「毎年支払う最低配当額」を従来の1株あたり200円から250円に引き上げる大胆な方針転換をしました。この発表の場で同社の役員は「もたもたやっているとマーケットに見放される」と危機感を露わにしています。東証から「早くやれ」と直接言われたわけではないけれど、市場全体として「もっと早く資本効率を上げろ!」というプレッシャーがある――そんな認識を示したのです。実際、「低PBR企業はぐずぐずしていると株価を置いていかれる」というのは多くの経営者が感じ始めている共通認識でしょう。
さらに具体例を挙げると、日本郵船(大手海運)は2023年3月に2,000億円規模の自社株買いと増配を打ち出しましたし、神戸製鋼所は2024年3月期から配当性向(当期利益に対する配当額の比率)を従来の15〜25%から30%程度に引き上げると表明し、実際に年間配当を前期比で2倍超に増やしました。この神戸鋼の決断について、アナリストは「株価上昇、低PBRからの脱却を図りたいという経営陣の気概は投資家に好感される」とコメントしています。つまり、「なんとか株価を上げて割安状態を脱したい!」という強い意思を持って施策を打つ経営陣に対して、市場も拍手を送っているわけです。
また、事業ポートフォリオの再編(ノンコア事業の売却や資産圧縮)に踏み切る企業も出てきました。例えばトヨタグループの自動車部品大手デンソーは、長年持ち合いで保有していた豊田自動織機の全株式を売却すると発表しました。パナソニックも子会社の一部事業を投資ファンドに売却する一方、成長分野の海外企業を買収するといった事業の取捨選択を打ち出しています。こうした動きは、一見すると直接「株主還元」ではありませんが、収益性の低い資産を手放し、高いリターンが期待できる分野に経営資源を集中するという意味で、広い意味では資本効率を上げて企業価値を高める施策です。不要な資産を抱え込んでROEが低迷しているくらいなら、売却益も得られるうちに手放してしまえ、という判断ですね。【※事業売却益が出ればその期の利益が増えるのでROEは上がりますし、得た現金で自社株買いや負債圧縮をすればさらに財務効率が上がります。】実際、2024年初めには年度末を前に株主還元策や事業再編策の“駆け込み発表”が相次ぎました。企業側も「このタイミングでやらねば!」と急いだ様子がうかがえます。
資本効率アップの会計マジック?その光と影
ここで、会計の視点から「資本効率アップ」のからくりを少し紐解いてみましょう。企業がROEやPBRを改善するためによく取る手段は大きく3つ、「自社株買い」「増配」「資産・事業の売却」です。それぞれ会計上どう効くかというと:
- 自社株買い:
自己株式を取得して消却すると、貸借対照表上は自己資本(純資産)が減少します。同時に市場の株数が減るので、利益が同じでも1株利益(EPS)が増加し、結果としてPERが下がり株価上昇のきっかけになります。自己資本が減ればROE(当期純利益/自己資本)も機械的に上昇します。つまり、分母を減らすことで割合を良く見せる効果があるわけです。ただし株価そのものが上がらないとPBRは上がらないので、言い換えれば自社株買いは「株価を上げばROE改善→PBR上昇」という間接的な効果に期待する策とも言えます。 - 増配(配当の増額):
こちらも会計的には利益剰余金(内部留保)の取り崩しであり、自己資本を減らす点で自社株買いと似た効果があります。加えて、高配当銘柄になることで株主にとっての魅力が上がり、株価上昇を促す狙いもあります。もっとも、一時的に特別配当を出しても「焼け石に水」になりかねないため、継続的に配当方針を引き上げる会社が増えています(前述のコスモや神戸鋼のように)。増配は自社株買いに比べて株価への即効性はややマイルドですが、長期投資家にもアピールしやすいというメリットがあります。配当は一度上げると下げにくい(減配は嫌われる)ため、企業も慎重ですが、その分「腹をくくった増配」は市場の評価が高い傾向です。 - 資産・事業の売却:
利益の出ていない事業や活用しきれていない資産(遊休不動産や持ち合い株など)を売却すると、売却益が発生して当期純利益が増加します。これによりROEの分子(利益)が一時的に増えるため、ROE・ROAは上昇します。また売却で得た資金で負債を返済すれば自己資本比率も上がりますし、不要資産が減れば来期以降の維持コスト削減にもなります。さらに、売却によって本業に経営資源を集中できるため、中長期的な収益力向上につながる可能性もあります。要は「メリハリをつけて身軽になった分、機動力と収益力が上がる」というわけです。会計上は臨時利益で底上げされた部分もあるので、投資家もその点は見極めが必要ですが、少なくとも「動かないで現金や不採算事業を抱えっぱなし」よりは評価するというのが今の市場の空気でしょう。
このように、企業はバランスシートと損益計算書の両面から「資本効率」という数字を改善する策を講じ始めました。ただ、ここで重要なのは数字のトリックに踊らされないことです。自社株買いや増配は確かに指標上の効率を上げますが、「それだけでは持続的な企業価値向上には繋がらない」という指摘もあります。極端に言えば、利益が全く成長しないまま永遠に自社株買いと増配を続けるなんてことは不可能ですし、仮にできてもそれは「縮小均衡」でしかありません。市場もその点は分かっていて、短期投資家は自社株買い発表に飛びついても、長期投資家は冷静だと言われます。実際、東証自身も「PBR1倍超えがゴールではなく、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指すことが本質」という趣旨のコメントを出しています。ニッセイ基礎研のレポートでも「株主還元と合わせて成長戦略も」と強調されており、専門家の多くが「収益力の向上なくして真のバリュー覚醒なし」と見ています。
とはいえ、企業がこれだけ積極的に動き始めたこと自体はポジティブです。市場もその努力に素直に反応しています。低PBRの企業が大規模な株主還元策を発表すると、翌日に株価が急騰するケースが増えました。これは「やっと本気になってくれたか!」という投資家の歓迎の拍手のようなものです。外国人投資家も2023年以降、日本株を大量に買い越す動きを見せています。「日本企業が変わり始めた」と世界が注目し、かの有名なウォーレン・バフェット氏までもが日本の商社株に追加投資したニュースは話題になりました(いわゆる「バフェット効果」ですね)。こうした内外の追い風が、日本市場全体を押し上げ、TOPIXの史上最高値更新につながったというわけです。
ここまでを整理すると、「政策(東証要請)が呼び水となって企業行動が変わり、市場もそれに応えて株価が上がった」という流れです。一連の動きはまさに政策相場的な色彩も帯びています。しかし、その内実は企業の収益構造改革や資本政策の見直しという実体的な変化を伴っており、単なるご祝儀相場・お祭り騒ぎではないとも言えます。では、その“実体的な変化”が本当に各企業の価値向上に結びついているのか、次のセクションでは具体的な企業分析の視点から考えてみましょう。ここで登場するのが、皆さんお待ちかねの「PBR1倍割れ企業再評価チェックシート」です!
プロ直伝!“PBR1倍割れ企業”再評価チェックシート
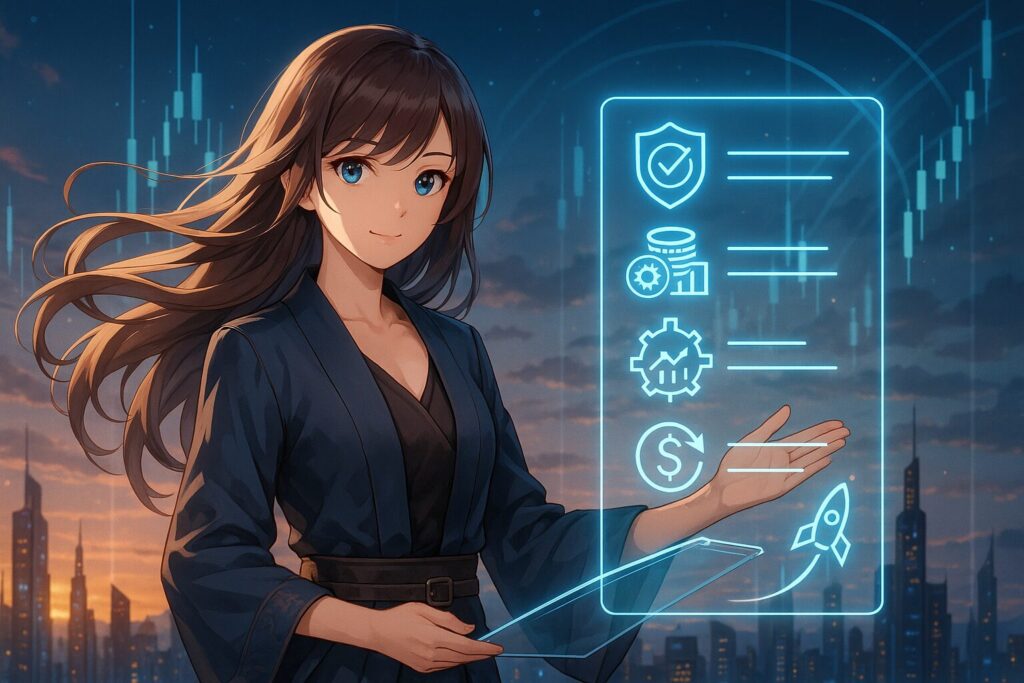
いよいよ、私が日々の投資調査で使っている「PBR1倍以下の割安企業を再評価するためのチェックシート」を公開します。日本株にはまだまだPBR1倍を下回る“眠れるバリュー株”が多く存在しますが、その全てが宝の山というわけではありません。中には本当に企業価値に対して株価が安すぎる“掘り出し物”もあれば、低迷するだけの理由がある“割安に見えるだけの株”もあります。では、どうやってそれを見分ければ良いのでしょうか?以下のチェックポイントに沿って分析すれば、かなりの確率で「本物のバリュー銘柄」を見極められるはずです!
✅財務健全性と余剰資産の把握
まずは財務の基礎体力をチェック。せっかく割安でも財務がボロボロな会社は論外です。自己資本比率や有利子負債の額を確認し、倒産リスクが低いかを見ましょう。次に、現預金の残高や保有資産にも注目です。例えば潤沢なキャッシュや遊休不動産、上場株式などを大量に持っている場合、市場がそこにちゃんと価値を織り込んでいない可能性があります。「キャッシュ>時価総額」なんてケースは典型的な掘り出し物です。また、不要不急の資産を売却すれば資本効率が一気に上がる余地があるので、その点もプラス材料になります。会社の貸借対照表の注記などで「◯◯を売却」「△△を減損」といった動きをチェックすると良いでしょう。
✅収益力とROE低迷の原因分析
次に収益力を見ます。具体的にはROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)、営業利益率などをチェックしましょう。PBRが低い会社はたいていROEも低いですが、その原因が重要です。「利益率が極端に低い」のか、「資本が大きすぎる(資産過多)」のかで対策も違います。前者の場合はビジネスモデルやコスト構造に問題がある可能性があります。一方、後者の場合はまさに前セクションで見たような自社株買いや資産売却で改善余地があるかもしれません。過去数年間の業績推移も確認して、一時的な赤字や特殊要因でROEが下がっていないかも見極めます。例えば大きな減損処理をしたせいで一時的に利益が凹んでいるだけなら、翌期以降ROE回復のチャンスです。逆に恒常的に利益率が低い業界構造なら、根本的改革がないと厳しいかもしれません。
✅経営陣の資本効率向上への姿勢
これは定性情報のチェックになりますが、極めて重要です。経営トップが資本コストや株主還元についてどれくらい意識的かを調べます。手がかりはたくさんありますよ。例えば決算説明資料や株主向け報告書に「資本効率の向上」「ROE◯%目標」「◯◯億円の自社株買い実施」などの記載があるか。最近は東証の要請もあって、多くの企業が「株価やROEを意識しています」といった文言を開示資料に盛り込むようになりました。その有無や熱量を比較するだけでも経営陣の本気度が伝わります。またIR(投資家向け広報)活動にも注目です。投資家との対話を積極的に行い、低評価の原因を真摯に分析・改善しようとしている経営陣は、そうでない場合に比べ株価見直しの可能性が高いです。反対に「うちはうちのやり方でやるんで…」という態度が見える会社は要注意です(残念ながら、まだそういう企業も一部に存在します)。経営陣自らが「株価が低迷しているのは問題だ」と認識しているかどうか——ここを年次報告やメッセージから汲み取ってください。
✅株主還元策の現在地と今後の余地
現在の株主還元状況もチェックしましょう。配当利回りが極端に低かったり(業界平均と比べてみる)、ここ数年自社株買いを全然実施していないような会社は、裏を返せば「伸びしろ」があります。先ほどの例ではありませんが、余剰資金たっぷり・配当性向低めという会社なら、今後株主還元をテコに株価浮上が狙えるかもしれません。逆に既に高配当で配当性向も上限ギリギリ、という会社はそれ以上の還元余地は少ないでしょう。また、過去に株主提案やアクティビスト(物言う株主)からの要求を受けていないかも確認ポイントです。もしそういった働きかけがあったのに何も変えていないなら、将来的にさらに強いプレッシャーが来る可能性がありますし、あるいは経営陣が頑なだとリスクとも言えます。ちなみに最近は海外投資家も日本企業に厳しく目を光らせており、持ち合い株解消や還元策強化を議決権行使で迫るケースも増えています。そうした外圧が掛かりやすい状況かどうかも頭に入れておきたいですね。
✅成長ストーリーは描けているか
最後に、これが一番大切かもしれません。その企業に将来の成長ストーリーがあるかを考えてみてください。いくら現状割安でも、将来も稼ぐ力が伸びない会社はずっと割安のままかもしれません。企業の中期経営計画や、新製品・新サービスの展開状況、業界の将来性などを調べて、「この会社は今後こういう形で利益を伸ばせそうだ」というシナリオが思い描けるかどうかがポイントです。特に東証が求めているのも「成長投資をしっかりやって将来の企業価値を高めること」です。単なるコストカットや財務テクニックだけでなく、売上や利益そのものを拡大させるビジョンが示されている企業は、本当の意味で「バリュー覚醒」する可能性が高いでしょう。逆に「先行きの成長が見えない会社は、いくら還元を増やしても株価のマルチプル(評価倍率)は上がらない」と市場も冷静です。ですから、チェックリストの最後は“未来への物語”。ここがある会社こそ、本物のバリュー株だと私は考えています。
以上、5つのチェックポイントを挙げました。実際には企業ごとに事情は様々ですから、絶対的な基準ではありません。しかし、このチェックシートを使えば「とりあえずPBRが低いから買おう」ではなく「なぜ低いのか?どう上がり得るのか?」を立体的に捉えられるようになります。実践してみると、驚くほど企業ごとのドラマが見えてきて面白いですよ!投資初心者の方でも、この視点で企業研究するとグッと愛着が湧くはずです。
おわりに:覚醒の夜明け、未来へのエール
「バリュー覚醒は本物か、政策相場か?」——記事のタイトルに掲げたこの問いに、今の私なりの答えをお伝えしたいと思います。結論から言えば、「政策相場として始まったが、本物の覚醒へと繋げられるかはこれから次第」という感じです。東証の要請という“きっかけ”がなければ、ここまで企業が動かなかったのは事実でしょう。そういう意味で、この株価上昇劇は政策要因に端を発しています。しかし、その呼び水によって企業経営者の意識改革が起き、投資家の熱い視線が注がれ、長年眠っていた日本株のポテンシャルが今まさに花開こうとしています。これは紛れもなく本物の価値の目覚め(バリュー覚醒)の序章ではないでしょうか。
大事なのは、ここで終わりにしないことです。企業にはこの勢いを持続させてほしいですし、私たち投資家もエンゲージメント(建設的な対話)を通じてそれを後押しできます。企業が本当の意味で変わり、成長戦略を実行に移し、収益力を高めていけば、日本株式市場はかつてない活気と厚みを持つでしょう。それは決して遠い夢物語ではなく、もう動き出している未来です。
皆さんにとって、日本株は少し地味で古臭いイメージがあったかもしれません。でも今、目の前で起きているこの変化は、日本の企業文化・市場文化が新しいステージに進もうとしている瞬間です。バフェット氏が言うように「日本という芋虫が蝶になる時が来た」のかもしれません。だとしたら、こんなエキサイティングな機会を傍観する手はありませんよね。
最後に一つ、私が大好きな投資家の言葉を紹介させてください。それは「株式市場は時に間違える。しかし最終的には真実の価値に収斂する」というものです。長い間、日本株市場は多くの銘柄の価値を正当に評価してきませんでした。しかし今、その歪みが是正されつつあります。企業も投資家も共に変わり、未来への希望を語り始めたからです。バリュー覚醒の夜明けはもう目の前まで来ています。このブログを読んでくださった皆さんが、日本株の新たな時代にワクワクし、自分なりの視点で企業を応援し発掘していくきっかけになれば、とても嬉しいです。共に日本市場の未来を見届け、楽しんでいきましょう!きっと5年後、10年後に「あの頃が転換点だったんだよな」と語りたくなるような、そんな歴史的局面に私たちは立ち会っているのです。
皆さんの投資や仕事が、明日から少しでも実り多いものになりますように。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!では、また次回のブログでお会いしましょう。日本株の未来にエールを送りつつ――。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『企業価値経営 第3版』
企業価値最大化の考え方を最新の会計・ガバナンス潮流でアップデート。PBRやROEを“結果指標”で終わらせず、資本コストと投資配分まで繋げて設計する実務の土台づくりに最適。
『PBR・資本コストの視点からの株価上昇戦略―経営者の意識改革で株価は上がる』
低PBR常態の打破に直結する「資本コスト経営×株主還元×対話」の処方箋。経営サイドの意思決定フレームが整理され、投資家側の評価軸の言語化にも役立つ一冊。
『図解&ストーリー「資本コスト」入門〈第3版〉』
資本コストを“数字の暗記”ではなく、企業の物語(意思決定プロセス)として理解できる定番の最新版。PBR1倍要請の文脈で「なぜ資本コストが起点なのか」を腑に落とせます。
『コーポレートガバナンスの法務と実務――会社法・コード・善管注意義務』
ガバナンス実務の“現在地”を法務面から総覧。取締役会運営、株主還元方針の決定プロセス、情報開示など、PBR改善の裏側にある実務要件を押さえられます。
『日本のトップ100社のコーポレート・ガバナンス 2025』
TOPIX100のデータでガバナンスの“可視化”に挑む年次レポート。女性登用や取締役会構成、開示姿勢など、評価の差が株価やPBRにどう効くかのヒントが拾えます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21622016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5173%2F9784296125173.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21481916&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4895%2F9784322144895_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21473451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8515%2F9784502518515_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21263117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1137%2F9784785731137.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21469096&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1281%2F9784785731281_1_29.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す