みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
地味だけど強いCFを生む“インフラビジネス”を、そろそろ真面目に研究してみませんか?
公営住宅って聞くと、どんなイメージが浮かびますか?
「古そう」「なんとなく暗い」「ビジネスとしてはおいしくなさそう」……だいたいこんなところかもしれません。証券コードもないし、テレビCMも打たないし、キラキラしたベンチャーでもない。正直、投資ネタとしてはめちゃくちゃ地味な領域です。
でも今、公営住宅の「管理」を担う賃貸管理会社が、地域のなかでじわじわ存在感を高めています。公的な住宅を任されているという信頼感から、民間アパートの管理受託が増えたり、新卒採用でも「ちゃんとした会社」として選ばれやすくなったりしている、という記事も出てきています。
この記事では、そんな公営住宅管理ビジネスを、「投資」と「会計」の視点から、あえてじっくり分解してみます。ポイントは三つです。
ひとつめは、「派手さはゼロだけど、インフラっぽい安定キャッシュフロー」というビジネスの骨格です。公営住宅の管理費は、多くの場合自治体からの委託料として支払われます。家賃も入居者から徴収はするものの、制度としてある程度ルールが決まっている世界です。ここには、民間のワンルーム投資とはかなり違う、“公共サービスに近い安定感”があります。
ふたつめは、家賃を「売上」、修繕費を「設備投資(CAPEX)」、空室を「減損リスク」と見立てて、PL(損益計算書)・BS(貸借対照表)・CF(キャッシュフロー計算書)の全部で眺めてみることです。難しい専門用語はできるだけ使わずに、「お金の出入り」と「ストックとしての建物」をどう管理しているのかを、イメージしやすい言葉で整理していきます。会計初心者でも、「ああ、こういう見方をすればビジネスの安定度がわかるのか」と感じてもらえるはずです。
みっつめは、人口減少・地方創生とセットで考える将来シナリオです。地方では空き家が増え、自治体の財政も厳しくなる一方で、「住宅を必要としている人」は確実に存在します。公営住宅はその受け皿のひとつであり、その管理を担う事業者は、ある意味で“社会インフラ運営会社”のような立ち位置になりつつあります。長期的な需要やリスクをどう見ればいいのか、ざっくり将来像も一緒に眺めていきましょう。
この記事を読み終えるころには、
- REITや不動産クラウドファンディングを眺めるときに、「こういう地味だけど強いCFのビジネス、裏側にいるかも」と想像できるようになる
- 不動産会社のIR資料や決算を見たときに、「この会社、公営住宅管理をどれくらいのポジションで扱っているんだろう?」と一段深く読み込める
- 「派手な成長ストーリーはないけれど、インフラ型ビジネスとして長く生き残りそうか」という視点で、地方や人口減少ニュースを眺められる
こんな“投資家脳”が少し育っているはずです。
YouTubeの「伸びるビジネス10選!」みたいな派手さはありませんが、その代わり、コツコツ安定してお金を生み出す仕組みとして、公営住宅管理の世界を一緒に覗いてみましょう。
目次
公営住宅管理ビジネスってどんな仕事?

まず最初に、「公営住宅ってそもそも何だっけ?」というところから整理しておきます。公営住宅は、ざっくり言うと「収入があまり多くない人でも、安心して住めるように自治体が用意している賃貸住宅」です。日本全国で見ると、公営住宅のストックはざっと約213万戸あります。
つまり、タワマンほど目立たないだけで、裏側ではかなり巨大な“住宅インフラ”が動いているわけです。
この213万戸を、自治体だけで直接すべて管理するのは現実的ではありません。そこで登場するのが、民間の賃貸管理会社です。自治体は、家賃の徴収、入退去の手続き、建物や設備の点検や修繕、住民からの問い合わせ対応などを、民間の会社にまとめて任せることが増えています。ここが、今回のテーマである「公営住宅管理ビジネス」の入り口です。
公営住宅の多くは、応募倍率が全国平均で3〜4倍ほどあり、東京など都市部では十数倍に達するところもあります。
つまり「入りたくても入れない人がいる」レベルで需要があり、入居者の入れ替わりはあっても、ゼロから営業して空室を埋める民間アパートとは少し違う世界です。この“安定需要”の存在が、のちほど出てくる「強いキャッシュフロー」につながっていきます。
ここからは、公営住宅管理ビジネスをもう少し分解して見ていきましょう。
主役は「自治体+民間管理会社」のコンビ
公営住宅のオーナーはあくまで自治体です。土地も建物も、基本的には市や県などのもの。ただし、実際の日々の運営は民間に任せるケースが多く、そのときによく使われる仕組みが「指定管理者制度」です。
指定管理者制度というのは、本来自治体が自前で運営していた施設――たとえば体育館や図書館、福祉施設など――について、「民間やNPOなどの団体も管理者として指定できるようにした制度」です。
公営住宅もこの枠組みを使って、民間の賃貸管理会社が「指定管理者」として選ばれ、一定期間、団地全体の運営を任されることがあります。
ここで大事なのは、関係が「大家=自治体」「管理会社=民間」「入居者=低所得者や高齢者など」という三角形になっていることです。普通のアパート管理だと、大家は個人や不動産会社で、そこに管理会社がぶら下がる形が多いですが、公営住宅では“相手が自治体”になります。契約相手が行政なので、契約期間や業務内容がある程度決まっていて、途中でいきなり「やっぱりやめた」は起こりにくいという特徴があります。
もちろん、指定期間が終われば公募で別の事業者に変わる可能性もありますが、「自治体の公募に通り続ける限り、比較的安定した仕事が続く」という構造になっているわけです。ここが、インフラっぽい安定感の源泉のひとつです。
売上の源泉は「管理委託料+家賃事務」という安定収入
では、このビジネスの“売上”はどこから生まれているのでしょうか。
イメージとしては、自治体から支払われる「管理委託料」がメインの収入になります。これは、建物や共用部の清掃、点検、修繕の手配、入居者募集の事務、家賃の徴収事務など、一式まとめて「年間いくら」という形で支払われることが多いです。民間アパートのように、「空室が増えたら管理料がガクッと減る」というよりも、「団地全体の面積や戸数、業務内容に応じて、比較的読みやすい金額が設定される」イメージです。
家賃そのものは、入居者から集めて自治体に納める役割を担うケースも多く、「集金業務」としての手数料や事務費が別途加算されることもあります。ここでも、家賃水準や入居者の属性は法律や条例である程度決まっているので、「相場が急に半額になった」みたいなブレは起こりにくい世界です。
もちろん、老朽化した団地で空室が増えれば、管理業務の見直しが入ったり、建て替えによって一時的に業務が減ることもあります。ただ、日本全体を見ると、公営住宅への入居希望はまだ一定数あり、特に都市部では応募倍率が高い状態が続いています。
そのため、「短期的には安定、長期的にはストック配置の見直しと一緒にジワジワ調整されていく」という、比較的読みやすいビジネスになりやすいのです。
投資の目線で言うと、「家賃=売上」「管理委託料=フィー収入」として、PLのトップラインがそこまで大きくブレにくい点がポイントです。しかも、相手は個人の大家ではなく自治体なので、売掛金が回収できないリスクや、突然の解約リスクも相対的に小さくなります。
なぜ公営住宅を任されると「地域ブランド」が上がるのか
ここからが少しおもしろいところで、最近は「公営住宅の管理を受託したことで、賃貸管理会社の地域での認知度がかなり上がった」という事例が出てきています。
住民からすると、「この団地の管理をしている会社=自治体から任されているちゃんとした会社」というイメージがつきやすくなります。団地内の掲示板や案内板にも管理会社の名前が載りますし、入居者対応を通じて地域の人と直接接する場面も増えます。その結果、「自分のアパートの管理も頼みたい」「知り合いの大家さんに紹介したい」といった形で、民間物件の管理受託につながるケースが出てきています。
さらに、新卒採用や中途採用の場面でも、「自治体から公営住宅を任されている会社」という肩書きは、信頼の“お墨付き”として機能します。就活生や親世代から見ても、「怪しい投資会社」ではなく「地域の住宅インフラを支える会社」として認識されやすくなるわけです。
ここまでくると、公営住宅管理は単なる「地味な仕事」ではなく、会社のブランド資産を積み上げるプロジェクトでもあります。短期的に爆発的な利益が出るわけではありませんが、安定した収入と、地域からの信頼という無形資産を同時に手に入れられるのが、このビジネスの美味しいところです。
こうして見てくると、公営住宅管理ビジネスは、派手さがない代わりに「自治体という大口の取引先」「応募倍率に支えられた一定の需要」「地域ブランドの向上」という三つのポイントで、“インフラっぽい安定性”を持っていることがわかります。次のセクションでは、このビジネスを「家賃=売上」「修繕費=CAPEX」「空室=減損リスク」という投資家目線に置き換えて、PL・BS・CFの三つの表に落とし込みながら、もっと深く覗いていきます。
PL・BS・CFで読む、公営住宅管理ビジネスの“安定感”

ここからは少しだけ投資家モードに切り替えて、公営住宅管理ビジネスを「財務三表」で眺めてみます。財務三表というのは、損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(CF)の三つのことです。ざっくり言えば、「どれだけ稼いだか」「どんな資産と借金を持っているか」「お金の出入りはどうなっているか」をまとめた三枚の表だと考えてください。
難しい専門用語は置いておいて、「家賃=売上」「修繕費=設備投資(CAPEX)」「空室リスク=減損リスク」とラフに置き換えながら、公営住宅管理の安定感を一緒にイメージしていきましょう。
PL(損益計算書):家賃と管理委託料がつくる“ゆるやかな山”
まずはPL、つまり「どれだけ儲かったか」を表す損益計算書のイメージです。
公営住宅管理会社の売上にあたる部分は、主に自治体からの管理委託料と、家賃に関する事務の対価です。公営住宅は、令和3年度末時点で約213万戸という大きなストックがあり、全国平均の応募倍率は3.6倍、東京都では16.9倍というデータも出ています。
つまり、入居希望者は多く、一定の需要が続いている状況です。空室が多くて管理料が大きく落ち込むというより、「団地単位で安定して稼働している」前提で委託料が決まっているイメージになります。
普通の民間アパートの管理では、空室が増えると管理料が減って、PLの売上がガクンと下がることがあります。しかし、公営住宅の場合は、管理業務の範囲と委託料が契約で決まっていて、相手も自治体なので、年ごとの売上のブレは比較的小さくなりやすいです。「今年は満室で大儲け、来年は空室だらけで大赤字」といったジェットコースターになりにくく、ゆるやかな山が続くようなPLになりやすいのです。
一方で、費用側を見ると、人件費や日常的な修繕費、清掃や設備点検の外注費などが中心になります。ここでも、業務量がだいたい決まっているので、売上と同じく費用も大きく振れにくい構造です。ざっくり言えば、「大きくは伸びないけれど、毎年コツコツ利益を積み上げるタイプのPL」になりやすいビジネスだと言えます。
BS(貸借対照表):建物を持たない“軽めのバランスシート”
次にBS、つまり「資産と負債の棚卸し」のイメージです。
公営住宅のオーナーは自治体なので、建物そのものは自治体のBSに乗ります。管理会社側は、公営住宅の建物を自分の資産として抱えないことが多いです。つまり、巨大な団地を何棟も持っているのに、自社の貸借対照表は比較的スリム、という不思議な立ち位置になります。
管理会社側のBSに載る主な資産は、運営に必要なシステムや事務所の設備、社員の働くオフィスなどです。もちろん、自社で保有する賃貸物件があれば、その分は資産として膨らみますが、「公営住宅管理部分だけを切り出す」と、かなり軽めのバランスシートになることが多いでしょう。
ここで「修繕費=CAPEX」という観点を重ねてみます。本来、建物の大規模修繕は、建物オーナーが負担する設備投資に近い支出です。公営住宅なら自治体側のCAPEXに相当します。管理会社は、その計画を立てるサポートや、工事の手配、住民対応などを担い、その対価として報酬を得ることが多くなります。つまり、自分では大きなお金を建物に突っ込まず、他人(この場合は自治体)のCAPEXに寄り添う形でビジネスをするモデルです。
投資の目線でいうと、「自分で巨額の設備投資を抱えずに、インフラに近い住宅ストックの上に乗っかっている」構造なので、バランスシートのリスクが相対的に小さくなります。逆に、自治体側のBSは、老朽化した公営住宅ストックを抱え続けることになり、建て替えや用途変更などの政策判断が必要になっていきます。公営住宅数は213万戸前後ですが、空き家率は15%、約32万戸が空き家になっているという指摘もあり、ストックの見直しが課題になっています。
この「重い資産を持つ自治体」と「軽い資産で運営する管理会社」という役割の分担が、公営住宅管理ビジネスの安定感と、リスクの所在を分けているポイントです。
CF(キャッシュフロー):インフラっぽい“定期収入”と空室という見えない減損
最後にCF、つまり「お金の出入り」を見てみます。
キャッシュフロー計算書は、決算期間中にどれだけ現金が入ってきて、どれだけ出ていったかを追いかける表です。
公営住宅管理会社のキャッシュインの多くは、自治体からの委託料や事務手数料です。これらは、契約に基づいて決まったタイミングで入金されることが多く、「今月はなぜか家賃が半分しか入ってこない」といった不安定さが比較的少ない収入です。
一方、キャッシュアウトは、社員の給料、協力会社への支払い、システム費用、日常的な修繕の手配などに分かれていきます。ここでも、業務量が大きく変わらない限り、支払いのパターンは安定しやすいです。そのため、営業キャッシュフローは、インフラ系の事業に近い「じわじわプラスが積み上がる形」を描きやすいと言えます。
では、「空室リスク=減損リスク」という話はどう入ってくるのでしょうか。ここでは、二つのレイヤーで考えるとわかりやすくなります。
ひとつは、自治体側のレイヤーです。空室が増えて団地の一部が長期的に使われなくなってしまうと、建物の価値は会計上も実態としても目減りしていきます。極端にいえば、「もうこの棟は使わないから解体する」となれば、それまでの建設コストが十分に回収できないまま終わる、という意味で減損に近い状態になります。公営住宅の空き家率が15%に達しているというデータは、まさに「ストックの一部が眠っている」サインです。
もうひとつは、管理会社側のレイヤーです。団地の一部が長期空室になれば、委託料の見直しが入ったり、将来的に団地ごと廃止になって管理業務がなくなる可能性も出てきます。これは、PLの売上がじわじわ減っていく形で現れ、最終的にはその案件からのキャッシュフローが消えてしまう、という意味で「将来キャッシュフローの減損」に近いリスクです。
ただし、ここがポイントなのですが、公営住宅は「全国平均応募倍率3.6倍」というデータに象徴されるように、「入りたい人がいるのに入れない」という状況も同時に存在します。
つまり、場所や団地ごとの差が大きく、「空室ばかりで沈む団地」と「応募が殺到する団地」が混在している構図です。管理会社としては、自治体と一緒にストックの再配置や建て替え、用途変更に関わりながら、「長くキャッシュを生み出す団地」をポートフォリオとして持ち続けられるかが重要になってきます。
投資家目線でまとめると、公営住宅管理ビジネスは、PL・BS・CFの三つを通して見ても、「資産を重く抱えずに、インフラ的なストックから安定キャッシュフローを得るモデル」としてかなり特徴的です。その代わり、「人口減少やストック老朽化に伴う空室・減損リスク」が、長い時間軸でじわじわ効いてくる世界でもあります。
ここまでで、公営住宅管理ビジネスの“安定感”と、その裏側にある会計的な構造をざっくりイメージできたと思います。次のセクションでは、人口減少や地方創生といったマクロな流れの中で、このビジネスがこれからどう変わり得るのか、「将来の需給シナリオ」を投資家視点でゆるく描いていきます。
人口減少・地方創生・公営住宅管理のこれから
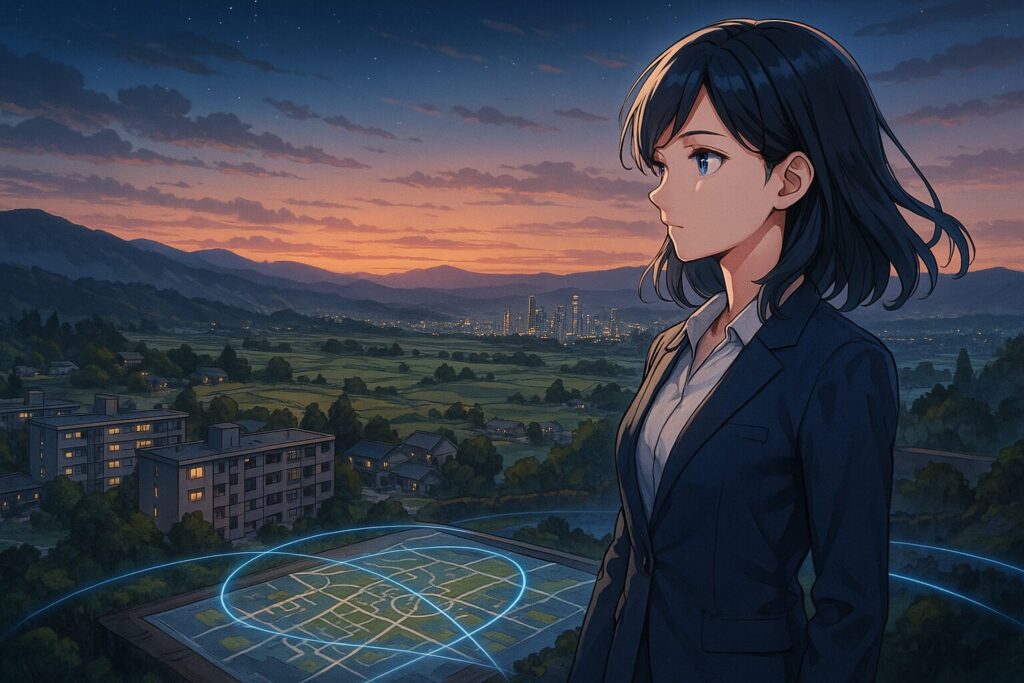
ここまで見てきたように、公営住宅管理ビジネスは「今の姿」だけでも十分インフラっぽくて安定した世界です。ただ、日本はこれから人口減少と高齢化がさらに進みます。地方では人が減り、都市部にはまだ人が集まり続ける、このアンバランスな状況の中で、公営住宅とその管理ビジネスはどう変わっていくのでしょうか。
このセクションでは、少し長めの時間軸で、公営住宅管理の「需要」と「供給」がどう動きそうかをイメージしていきます。そして最後に、投資家目線で見たとき、「どんな管理会社が生き残りやすいのか」をゆるく描いてみます。
人口減少=需要減とは限らない、公営住宅という“最後の受け皿”
まず、「人口が減る=公営住宅の需要も減る」と考えがちですが、現実はもう少し複雑です。
たしかに、日本全体で見ると人口は減っていきます。地方の小さな町では、すでに空き家が目立ち、「そもそも人がいないから、公営住宅を維持しきれない」というエリアも出てくるでしょう。こうした場所では、公営住宅の棟を減らしたり、別の用途に変えたり、統廃合のような動きが増えていくはずです。この流れは、公営住宅ストックの「整理・縮小」という方向に働きます。
一方で、高齢者の単身世帯や、非正規雇用が多い若年層、ひとり親世帯など、「民間賃貸にずっと住み続けるのがしんどい層」はむしろ増えています。家賃がじわじわ上がる都市部では、「収入はそこまで増えないのに、住居費だけが重くなる」というパターンが増えています。そうなると、「民間賃貸だと詰むかもしれない人たちの最後の受け皿」として、公営住宅の役割はむしろ重くなっていきます。
つまり、人口が減る時代でも、公営住宅は「いらなくなる」のではなく、「本当に必要としている人にどう届けるか」が課題になっていく、というイメージに近いです。管理会社は、この“最後の受け皿”を支える現場のプレーヤーとして、入居者の状況を一番近くで見ています。そこには、単なる「部屋を貸す・管理する」を越えた、生活サポートに近い役割もにじみ始めています。
地方創生とセットで進む、「団地の再編」とリノベーション
次に、地方創生との関係を見てみます。
地方では、人が減るエリアと、意外と人が集まり続けるエリアが混ざっています。駅が近くて生活インフラが揃っている地域や、工場や物流拠点が集まるエリアには、これからも一定の住宅ニーズがあります。一方で、山間部や交通の便が極端に悪いところは、「そもそも住みたい人が少ない」という状況になりやすいです。
公営住宅も同じで、「場所がいい団地」と「使いづらい団地」に分かれていきます。使いづらい団地は、棟を減らしたり、他の用途(高齢者向け施設や子育て支援施設など)に変えたりする動きが出てきます。逆に、場所がいい団地は、エレベーターの新設、バリアフリー化、間取りの変更、外壁や共用部のリノベーションなどを行って、「長く使い続けるストック」へと作り替えていく流れが強まっていきます。
ここで管理会社が担う役割は、単に清掃や点検をこなすだけではありません。入居者の年齢構成や生活スタイル、空室の出方など、現場でしかわからない情報を自治体にフィードバックし、「どの棟を改修するか」「どこを縮小するか」といった判断の材料を提供する立場にもなっていきます。
場合によっては、リノベーションの企画段階から関わり、「この間取りに変えると若い子育て世帯が入りやすい」「ここは高齢者用にした方がいい」といった提案をすることもありえます。公営住宅が、ただの「古い団地」から、「地域の暮らしのハブ」に変わっていくとき、その運営ノウハウを持っている管理会社の価値は、今よりも高く評価されるはずです。
投資家目線の“将来シナリオ”と、生き残る管理会社の条件
最後に、投資家として「こんな管理会社は強そうだな」というイメージを描いてみます。
ひとつは、「自治体との関係性を長期で築いている会社」です。指定管理者の公募は定期的に行われますが、そのたびに入れ替えが起きるわけではなく、実績のある事業者が継続して選ばれることも多い世界です。入居者対応のクレームをきちんと処理し、団地内のトラブルを大きくさせず、自治体とのコミュニケーションも丁寧に続けている会社は、「次の更新でもお願いしたい」と思われやすくなります。つまり、「信頼」がそのまま将来のキャッシュフローの源泉になっていくタイプのビジネスです。
もうひとつは、「公営住宅だけに依存せず、民間賃貸の管理もバランスよく持っている会社」です。人口減少が進む中で、すべての公営住宅が生き残れるわけではありません。団地の廃止や統廃合が進めば、その分の管理収入は減っていきます。そのとき、民間アパートやマンションの管理をしっかり持っている会社は、ポートフォリオ全体でリスクをならすことができます。逆に、公営住宅に極端に依存しすぎていると、自治体の政策変更の影響をモロに受けてしまう可能性があります。
三つめは、「DXやデータ活用にきちんと投資している会社」です。家賃の滞納管理、修繕履歴、入居者属性、空室の出方など、公営住宅の運営には大量のデータが発生します。これを紙や経験だけに頼るのではなく、システム上で見える化し、どこに課題があるかを示せる会社は、自治体にとっても心強いパートナーになります。「この棟は高齢者が多いので、見守りサービスを組み合わせましょう」といった提案も、データがあるからこそ説得力が出てきます。
投資の視点でいうと、「安定した委託収入」「軽いバランスシート」「自治体との長期的な関係」「データ活用による提案力」を持っている管理会社は、公営住宅という“インフラ資産”の上に乗りながら、長期的にキャッシュフローを積み上げやすい存在だと考えられます。株式上場している不動産管理会社の中には、公営住宅管理を一つの柱にしている企業もあり、そのIR資料を読むときには、「このビジネスは、どれぐらい安定CFの源泉になっているんだろう?」という目線で見てみると面白くなります。
人口減少と地方創生という、ニュースで聞くと少し遠く感じるテーマも、公営住宅管理という具体的なビジネスに落とし込んでみると、「社会課題×安定キャッシュフロー×インフラ」という、なかなか味わい深い世界が見えてきます。ここまでで、公営住宅管理ビジネスの現在と未来を、ざっくり立体的にイメージできるようになっていたらうれしいです。
結論:地味な団地の向こう側にある、“インフラ投資家マインド”
公営住宅管理というテーマをここまで追いかけてきて、どう感じましたか? おそらく最初に抱いていた「古くて地味な団地」というイメージから、少しだけ見え方が変わってきたのではないでしょうか。
派手な成長ストーリーも、ニュースになるような大型M&Aもない。だけど、自治体という大口の相手から、契約に基づいて安定したお金が入ってくる。建物そのものという重い資産は自治体側が持ち、管理会社はその上に乗ってサービスを提供する。PLでは売上のブレが小さく、BSでは資産が軽く、CFではコツコツとプラスのキャッシュが積み上がる。こうやって並べてみると、公営住宅管理ビジネスは、まさに「インフラに寄り添うビジネス」だとわかります。
そしてもう一つ大事なのは、このビジネスが単なるお金の話ではないことです。入居者の多くは、「ここが最後の安心できる住まいかもしれない」という気持ちで公営住宅に住んでいます。家賃を少しでも抑えたい高齢者、子育てで精一杯のひとり親、非正規雇用で将来が読みにくい若い世代。そういう人たちの生活を、裏側から支えているのが管理会社です。ゴミ出しのルールひとつ、共用部の照明ひとつ、エレベーターの点検ひとつが、「ここに住んでいていいのか」という安心感に直結します。
投資家目線で言えば、公営住宅管理は「社会課題とキャッシュフローが同時に存在する」珍しいフィールドです。人口減少や財政の厳しさといったマイナス方向のニュースの裏側で、「それでも住宅は必要だし、最後の受け皿は誰かが支えなきゃいけない」という現実があります。その現実に、静かに、しかし長期でコミットしているのがこのビジネスです。
もしあなたがREITや不動産クラファンのページを眺めることがあるなら、次からはちょっとだけ視点を変えてみてください。華やかなオフィスビルや商業施設だけでなく、「ストック型の住宅インフラをどう支えるか」というテーマが、どこかの銘柄やビジネスモデルの中に隠れていないかを探してみるのです。そこには、表舞台には出てこないけれど、長期投資家が好きそうな「じわじわ効いてくるCFの源泉」が眠っているかもしれません。
そして日常生活の中でも、公営住宅の団地を見かけたら、「あの裏側には管理会社がいて、自治体との契約があって、現場で動いている人たちがいるんだな」と少しだけ思い出してみてください。その瞬間、ニュースの「人口減少」「地方創生」という言葉も、決算書の数字も、ただの遠い話ではなく、ひとつのつながったストーリーに見えてくるはずです。
派手さはない。けれど、社会の土台を支えながら、静かにキャッシュフローを積み上げていく。そういうビジネスを見つけて、じっくり付き合っていくことこそ、大人の投資の楽しみ方のひとつなのかもしれません。公営住宅管理ビジネスは、その入口としてちょうどいい「教材」だと思います。この文章が、あなたの中の「インフラ投資家マインド」を少しだけ育てるきっかけになっていたらうれしいです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『収益性・節税・資産保全・相続対策まで完全網羅! 不動産投資の成功法則』藤原 正明
不動産投資を「収益性・節税・資産保全・相続対策」という4つの目的ごとに整理し、失敗しないためのポイントを体系的にまとめた一冊です。著者は収益物件の運用実務をやっているプロで、「1エリア・2指標・3物件・4融資・5管理」という5つの法則で、どこをチェックすれば“危ない投資”を避けられるかを教えてくれます。
このブログで書いた「キャッシュフローが強い不動産ビジネス」に興味を持った人が、次のステップとして自分の投資に落とし込みたいときにちょうどいい内容です。節税や相続までカバーしているので、「どうせやるなら10年・20年単位で資産設計をしたい」という人ほど刺さります。楽天ブックスで紙と電子書籍の両方が選べるので、「とりあえずスマホで読み始めたい」人にも勧めやすい一冊です。
『図解即戦力 資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書』伊藤 亮太
NISAや投信だけでなく、不動産を含めた「資産運用の全体像」をやさしく整理してくれる教科書です。お金の基本から、複数の投資商品の仕組み、税制優遇の使い方、ポートフォリオの組み方まで、一通りまとまっています。図解が多くて、分厚いのにサクサク読めるタイプの本です。
今回の記事で「インフラっぽいビジネスモデルって面白いな」と感じた人が、そのまま“資産運用の全体設計”に進むのにちょうどいいです。公営住宅管理のような安定CFの考え方を、自分のポートフォリオ設計にどう活かすか、イメージしやすくなります。これ1冊持っておくと、他の投資本を読んだときの“地図”にもなってくれるので、最初の1冊としてかなりコスパが高いと思います。
『教養としての「会計」入門』金子 智朗
「PL・BS・CFって聞くだけで眠くなる」人向けに、会計の原理原則から財務三表の読み方、経営分析の考え方までを“ちゃんと面白く”解説してくれる入門書です。決算書の構造や、ROE・安全性指標といった数字の意味、会計と税金の関係などを、実例を交えながら噛み砕いて説明してくれます。
この記事では、公営住宅管理ビジネスをPL・BS・CFでざっくり眺めましたが、この本を読むと「数字を使ってビジネスの安定度を見る」という感覚が一気にクリアになります。上場している不動産管理会社やREITの決算資料を読むときにも役立つので、「数字でビジネスを見たい社会人」は持っておいて損はない1冊です。
『PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本』寺沢 弘樹
官民連携(PPP)やPFIと呼ばれる、公的施設を民間と一緒に運営していくスキームを、現場の視点からわかりやすく解説した本です。自治体の事例が豊富で、単なる制度本ではなく、「どういう発想でプロジェクトを組み立てると、自治体と民間が一緒にうまく回るのか」という実務寄りの話が多いのが特徴です。
公営住宅管理ビジネスは、まさに自治体と民間が組んでインフラを運営する典型例の一つです。この本を読むと、「公営住宅以外にも、こんな形でインフラビジネスに民間が関われるんだ」という視野が一気に広がります。地方創生や公共施設マネジメントに興味がある人、将来“地域インフラ系のビジネス”に関わりたい人には特におすすめです。
『公民連携まちづくりの実践 公共資産の活用とスマートシティ』越 直美
元・大津市長が、自身の市長時代の経験をベースに、公民連携で公共施設や駅ビルをどう生まれ変わらせていったのかを具体的なケースで紹介している本です。ランドマークの再生、稼げる公共施設の作り方、スマートシティの取り組みまで、「公共資産をどう活かせば、まちの平熱が上がるのか」という視点で語られています。自治体の公民連携担当者やデベロッパーの実務書として位置づけられているくらい、実務寄りの内容です。
この記事で扱った公営住宅管理ビジネスも、「公共資産をどう使いこなすか」という文脈のど真ん中にあります。この本を読むと、「団地」や「公営住宅」が、単なる古い箱ではなく、まちづくりの重要なピースとして見えてきます。投資家目線で読むと、「インフラとしての不動産が、政策と組み合わさるとこんな価値の出し方ができるのか」とワクワクしながら読み進められるはずです。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21547023&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0898%2F9784295410898_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21325027&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3718%2F9784297143718_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20887349&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0082%2F9784534060082_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20323323&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1348%2F9784313121348_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20417314&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7891%2F9784761527891_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す