みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
国が大盤振る舞いしたツケ、最後に払うのは誰だと思いますか?
政府が13.5兆円規模の追加経済対策を閣議決定し、市場では財政拡大が懸念されています。このブログを読むことで、
- 膨らむ予算と債務が市場にどんな影響を与えるのか、
- 金利上昇が国の財政にどう跳ね返るのか、
- そして投資家・家計は何に備えるべきか、
という視点を得られます。専門的になり過ぎず、会計の視点や投資目線を交えつつ、身近な例えで解説します。これを知れば、ニュースで見聞きする「国債」「金利」「財政」のキーワードを、より深く理解できるようになります。
目次
財政拡大と市場の反応

新政権は11月21日に総額21.3兆円(一般会計17.7兆円+税制11.7兆円分)の大型景気刺激策を閣議決定しました。これはコロナ禍以降最大級の規模で、財源は税収増と「必要分の」追加国債発行で賄う方針です。市場はこの財政拡大を受け、「国債が増える→供給過多で利回り上昇」という単純な図式を警戒しました。実際、米国株の乱高下の影に隠れて、日本では超長期国債利回りが記録的な高水準まで上昇し、円相場は10か月ぶりの円安に沈んでいます。
市場の反応は鮮明です。「巨額の財政赤字と金利上昇への警戒感が連鎖して、株も債券も円も一斉に売られるという異例の展開」(Trading Dayコラム)。特に長期金利の上昇は著しく、たとえば20年物が過去最高、40年物も最高値に達しました。背景には、市場が新首相の拡張的姿勢を強く見込んだことがあります。実際、11月中旬には与党内部から「25兆円規模の補正予算を組むべきだ」との提案が出て、これがさらなる利回り上昇を招きました。
追加経済対策の規模
今回の追加対策は、生活費高騰の対策や成長産業への投資などを含み、うち消費喚起策が11.7兆円にのぼります。これほど巨額の予算は日本では異例で、前年の補正(13.9兆円)を大きく上回ります。首相は「財政持続性は考慮済み」と述べていますが、実際に財源をどうするかは不透明です。税収増に加えて使途不明の「必要分の」国債を発行するとされていますが、その額は去年6.69兆円を超える見通しです。
債券市場の悲鳴
国債の追加発行観測は、債券市場に即座に影響しました。長期金利(超長期国債の利回り)は急騰し、過去最高を更新。市場は日本の財政悪化を懸念し、「国の借金が膨らむ→金利が上がる」という悪循環を想定しました。円安も顕著で、対ドルで6%程度下落。ロイターによれば、「資金調達のために国債発行が増えれば円安・金利上昇は不可避」との見方が市場に広がっています。つまり、政(政治)と策(政策)と債(債券)が連動し、典型的な財政拡大ショックの様相を呈しました。
海外投資家と市場の揺れ
海外勢の動きも注目点です。伝統的に超長期JGBを買ってきた機関投資家(生保や年金)が利回り急騰で買い渋り、利回りはさらに上振れしました。一方で、政治的な不確実性を嫌う動きもあります。あるヘッジファンドが「日本の全体的なデュレーション(期間)を引き続きアンダーウェイト、BOJは市場予想より早く動くと期待している」と述べており、早期利上げ観測も加速しています。海外マネーの行方次第では、いったん冷静さを取り戻しつつある金利曲線も、再び乱高下し得る状況です。
財政支出拡大は文字どおり「大判振る舞い」ですが、それが市場では悲鳴を誘っています。巨額の追加予算案を受けて、長期金利は歴史的な高水準に跳ね上がり、円安も進行しています。増発による将来の利息負担への警戒感が、金融市場に大きな逆風をもたらしているのです。
「利払いは国の販管費」

ここからは財政を会計の視点で見てみましょう。日常家計と同じく、政府にも「収入と支出」があり、赤字は国債発行で埋め合わせます。増発→利回り↑の流れが繰り返されると、その分だけ利払いが膨らみます。これはまさに国の「販管費」が上がるようなもの。企業でいえば利益を圧迫する固定費が増えるのと同じです。実際、2025年度当初予算での国債利子+償還費(国債費)は14.3兆円に達しており、いまや税収の一部が文字通り借金返済に消えています。
簡単会計:増発→利払い増
現行制度では、国債を発行しても元本返済はいつまでも先送りできますが、利子(国債費)は毎年発生します。例えば財務省の試算では、短期間で金利が2%台に乗れば、国の利払いコストは25年度の約10.5兆円から28年度に16.1兆円へと50%以上増える見通しです。これは家計に例えると、住宅ローンの利率が急上昇して毎月の返済額が急増する状態と似ています。つまり、金利上昇分だけ国の固定経費が増えるわけで、国家予算の中で非常に厄介な重しとなるのです。
「国の販管費」としての利子
企業会計でいう販管費(販売管理費)には、営業活動に直接関わらない様々な費用が含まれます。政府の場合、その販管費に当たるのが「借金に対する利子」です。これを「国の販管費」と呼べば、政府はまるで家賃や光熱費と同様に、発行済み国債に対して毎期利払いを義務づけられていることが理解できます。さらに恐ろしいのは、財政当局も予算編成時に利払い金額は「動かない固定費」と見なしている点です。一度上がった利払いは、歳出削減でまかなわない限り止まりません。日本の財務戦略資料にも「金利上昇・利払い増大は政策的支出を圧迫する」と警告されています。要するに、いくら経済成長があっても、高い金利により膨らむ利払いは財政に重くのしかかるのです。
将来世代へのツケ
「増発→利上げ→利払い増大」という流れの最終的な帰結は、将来世代へのツケです。政府が支出を先送りし続けても、金利が上がればいつかは皆が負担しなければなりません。今はゼロ金利で済んでいるかもしれませんが、世界的な金利正常化が進めば、日本も他国同様に利払い負担は雪だるま式に増えます。財務省も「『成長率が金利を上回る』という前提は楽観的過ぎる」と認めており、恒常的赤字のまま金利上昇が続けば、歳出を圧迫する深刻なリスクを抱えることになります。まさに国債の利子は、累積した借金の「固定費」であり、これが際限なく増えれば、国家財政全体が立ち行かなくなる可能性も否定できません。
国債発行に伴う利払いは、政府にとって「必要経費」というよりも将来への投資(負担)です。巨額の財政支出には必ず利払いの負担が伴い、それは法人でいう販管費のように純粋にコストとなります。金利上昇リスクを無視して財政を膨らませれば、結果的に国全体の固定コストが膨大化し、家計にたとえるなら大赤字を抱えたままローン返済だけが増えるような状況に陥るのです。
投資家・家計の視点:今できる対策

では個人や投資家はどうすればよいでしょうか。答えは「備えあれば憂いなし」です。金利上昇局面で債券価格が下落することは自明ですが、だからこそ前もってポートフォリオの感度を調整し、ショックシナリオを想定しておくべきです。以下ではシンプルな債券投資のポイントを押さえ、金利リスクに強い家計の「備え」について考えてみましょう。
デュレーションと金利リスク
債券投資で使う重要指標に「デュレーション」があります。これは金利変動に対する価格感応度を表し、ざっくり言えばデュレーション(年数)が長いほど金利変動で値動きが大きくなる性質があります。たとえば、利回り3%の10年債のデュレーションは10年弱、20年債なら18年超です。もし金利が1%上がれば、デュレーション20年の債券価格は約18%下落する計算です。この性質を理解していれば、長期金利ショック時の損失リスクを事前に把握できます。実際、最近の超長期債利回り急騰で「今や債券はもう安全資産ではない」という声も聞かれます。しかしデュレーションを味方につければ、動揺する市場でも適切に対応できます。
債券保有の見直し
具体策としては、まず保有債券のデュレーションを短くすることが挙げられます。今回はモーニングスターの報告(参考:reuters.com)にもあるように、政府も超長期債の発行減を検討し、代わりに短期債を増やす方向に傾いています。つまり市場全体が「長期金利は当面高止まり、短期金利も上がるかも」と見ているわけです。個人投資家としては、例えば10年物の日本国債のかわりに短期国債や割安になった米国債を検討するなど、できるだけデュレーションを短縮すると安心感が増します。海外では日本債に慎重な動きもあり、「日本へのデュレーションは従来より低い水準に留めるべきだ」と大手機関も指摘しています。これは「日本の金利がもう少し上がると予想して、まだ持っている長期債を減らす」という投資家の姿勢を示しています。
金利ショックへのシミュレーション
さらに一歩進めるなら、金利ショックを想定したシミュレーション表を作りましょう。具体的には、自分の資産配分ごとに「金利が1%・2%上昇したらポートフォリオ全体が何%下落するか」を試算してみるのです。これを家計の収支管理にあてはめるなら、たとえば変動金利住宅ローンが2%上がったらどれだけ月々の支払が増えるか、など具体的な数字で把握するイメージです。債券価格だけでなく株式や為替への波及も含めれば、家計の最悪ケースが見えてきます。特に年金や保険で国内債を持つ人は、年初時点の想定以上に利息負担が減るシナリオも念頭に入れ、安全マージンを取ることが必要です。こうした「感度表」は投資判断だけでなく、万一の資産減少に備えた精神的備えとしても有効です。
金利変動リスクに対しては、ポートフォリオのデュレーションを短めに設定し、金融商品ごとの価格感応度をつかんでおくのが基本です。日銀の出口戦略や財政事情で金利が上下する局面では、自分自身で金利ショックのシナリオを描き、早めに対策できるようにしておきましょう。準備をしていれば、国の財政が揺れても家計や資産運用は安定させられます。
結論:知識が未来を支える
今回の激しい市場反応が教えてくれたのは、財政政策は決して遠い話ではなく、自分たちの家計や投資に直結しているということです。政府が「大判振る舞い」をすれば国債は「泣く」――つまり、借金のツケと金利負担は必ず返ってきます。しかし私たちは防御策も取れます。利払いを「販管費」として捉えなおせば、無駄遣いすればその分だけ家計が圧迫されるのと同じ。逆に言えば、得た知識を武器に適切な準備をすれば、激動の中でも被害を最小限にできます。
未来に備えるには、まず現実を正しく把握すること。この記事で見てきた政策の中身や会計の仕組み、投資戦略のヒントは、読者の家計簿にも活かせる学びです。今は不安定かもしれませんが、大切なのは恐れることではなく「知る」こと。知っていれば、少なくとも驚きとパニックは避けられるでしょう。私たちの生活も国家も、複雑に絡み合っています。この記事が「財政って面白いかも?」と思えるきっかけとなり、何度でも読み返したくなるような橋渡しになれば嬉しいです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『日本国債入門 ― INTRODUCTION TO JAPANESE GOVERNMENT BONDS』服部孝洋
「国債って、結局なに?」をプロの現場目線でガッツリ理解したい人向けの決定版です。
著者は証券会社と財務省で国債の最前線にいた人で、発行の仕組み、入札、利回りカーブ、投資家の構造までを、実務寄りに整理してくれます。
ブログで触れた「国の販管費としての利払い」を、もっと本格的な制度・市場の構造から掘り下げたい読者に刺さる一冊。読み終わるころには、ニュースで「国債増発」「長期金利1%台」と出ても、だいぶ景色が違って見えるはずです。
『イラスト図解 知っているようで知らない 国債のしくみ』久保田博幸
こちらは図解たっぷりの“国債ビジュアル入門”。
国債とは何か、日本の財政とどうつながっているのか、誰がどれくらい保有しているのか…といった基礎が、イラストと図でスルスル頭に入ってきます。
「文章だけだと眠くなる…でも日本の借金問題はちゃんと理解しておきたい」という20〜30代の読者には、まずここから入るのがおすすめ。
ブログで書いた「大盤振る舞いの裏側で国債が泣いている」構図を、視覚的にイメージできるようになるので、家計と国のバランスシートをリンクさせたい人にも相性◎です。
『国債ビジネスと債務大国日本の危機』山田博文
「日本の政府債務、GDPの2.7倍ってマジで大丈夫?」という不安を、かなりシリアスに直視してくれる一冊です。
国債がどう“ビジネス化”され、誰が得をし、どこにリスクがたまっているのかを、日銀・銀行・機関投資家・家計の関係まで含めて立体的に描きます。
ブログでは「利払い=国の販管費」として触れましたが、この本を読むと
その販管費が膨らみ続けた先に、どんな政治・社会リスクが待っているのか
が、かなり生々しく見えてきます。
「国債は安全って聞くけど、反対意見もちゃんと押さえておきたい」という慎重派・リスク大好き分析派のどちらにもおすすめです。
『0からわかる! 金利&為替超入門』森永康平(監修)
金利と為替を“生活目線”で理解したい人用の、カラー図解つきの入門書です。
金利の基本、円安・円高の仕組み、インフレ・利上げが家計や投資にどう響くかが、ニュースの具体例つきで解説されています。
ブログで書いた「家計で金利ショックの感度表を作っておこう」という話を、
✔ 住宅ローン
✔ 預金・債券・投資信託
✔ 外貨・為替
などに広げて考えるのにぴったり。
「FPの勉強まではしたくないけど、金利と為替くらいは社会人の教養として押さえたい」という読者に気持ちよく刺さる内容です。
『教養としての「金利」』田渕直也
最後は、ちょっと大人な“金利教養”本。
金利の計算や種類だけでなく、歴史、金利と景気の関係、ゼロ金利・マイナス金利が何を意味しているのかまで、ストーリー仕立てで深掘りしています。
この本を読むと、今回のブログテーマである「財政拡張→国債増発→利回り上振れ」が、単なる一時のニュースではなく、
長い金利史の中で今どの局面にいるのか
という視点で眺められるようになります。
“金利ある世界”に戻りつつある今、長く使える基礎体力をつけたい人の一冊目の教科書としておすすめ。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21135025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3867%2F9784322143867_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20965940&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4853%2F9784262174853_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21082223&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7683%2F9784406067683_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21117785&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4467%2F9784802614467_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20887355&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0075%2F9784534060075_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



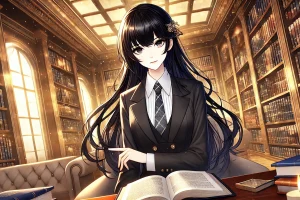









コメントを残す