みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
神々の叡智に学ぶ、投資と会計の本質―古事記が示す資本戦略の極意とは?
古事記は日本最古の歴史書でありながら、その物語の奥深さや神々の葛藤が、いまを生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。
古事記をただの神話として読むのではなく、投資と会計の視点を加味して読み解くことによって、私たちが現代の資本市場で陥りがちなリスクや心構えについて、多面的に洞察を得ることができるのです。
例えば、神々の“長期的視野”と“目的意識の明確化”、さらに“信頼やブランド”の大切さなどは、ビジネスや投資の世界でも重要なファクターとなります。
投資活動の中では、運用先の企業に対する深い理解や、定量的な会計分析だけでは捉えきれない“目に見えない要素”がパフォーマンスに大きく影響する場面が少なくありません。
古事記の世界観を活用することで、こうした無形資産やリスク管理の考え方を補うヒントが得られるのです。
さらに、本ブログでは投資家としての視点とともに、会計的な観点からも古事記を紐解きます。
財務諸表をどう分析し、企業の成長ストーリーをどう読み解き、そしてどのようにポートフォリオを組んでいくか―。
神話の物語をたとえにしながら考えていくことで、退屈になりがちな投資論や会計の話をより楽しみながら学ぶことができます。
結果、読者の皆さまは「いかに長期視点を持ちつつ、リスクとリターンをコントロールし、相場に翻弄されない自分の軸を作るか」という点に関して、明確なヒントを得られるでしょう。
本記事は以下のような方に特におすすめです。
- 長期投資を志向しているが、目先の価格変動につい振り回されがちな方
- 会計知識はあるが、企業や資本市場を“神話的視点”で俯瞰してみる経験が少ない方
- 日本古来の物語から、投資や人生観に新たなインスピレーションを得たい方
神話と投資が交わる少し不思議な世界に足を踏み入れつつ、現実的な資産運用戦略にも通じるエッセンスをしっかりと掴んでいただければ幸いです。
それでは早速、古事記の物語を3つの視点で深掘りしていきましょう。
イザナギ・イザナミの創造神話と“長期的視座”

神々の誕生と投資における“種まき”の重要性
古事記の冒頭では、高天原(たかまがはら)において、神々が次々と生まれてきます。
そしてイザナギとイザナミという男女の神が、国土を形づくるための使命を授かるのです。
ここでの重要なポイントは、二柱(ふたはしら)の神が“国土を固め、国を生み出す”という壮大なプロジェクトに対して、最初から完璧なプランニングを持っていたわけではないという点です。
海をかき回してみたら陸地ができるかもしれない―そんなある種の“実験”や“種まき”精神が、長期的な結果を生む始まりになるわけです。
投資の世界でも、スタート時点から完璧なポートフォリオを組むことは難しく、ある程度試行錯誤をしながら微調整を重ねていく必要があります。
イザナギ・イザナミが“大いなる国土創造”を目指して、最初は手探りで矛(ほこ)を海に差し入れたように、私たち投資家もまずは自分なりの投資原則を持ちながら、小さく仕掛けてみる姿勢が重要です。
たとえ小さな資金であっても、運用の“種”をまき続けることが、やがて大きな果実を得るための第一歩になります。
創造過程における失敗とリスク管理
イザナギとイザナミの神話では、最初の試み(性の結合)で“ヒルコ”という失敗作のような子が生まれてしまいます。
このエピソードは、「結果を急ぐあまりプロセスを省略すると、大きな誤りを犯す可能性がある」ことを示しています。
実際、ヒルコはやがて捨てられてしまうのですが、“大いなる創造”の過程では、こうした失敗がつきものだという点に注目したいところです。
投資においても、一つの投資先が期待どおりの成果を出さない、いわば“失敗作”がポートフォリオの中に生まれることは珍しくありません。
大切なのは、リスク管理の視点でいかにその失敗を最小化し、かつ他の成功によって十分にカバーできるポートフォリオを構築しているかです。
投資家としては、失敗をゼロにすることは不可能であり、むしろ失敗にきちんと向き合いつつ、ポートフォリオ全体のバランスをとることが大切だといえます。
イザナミの死と“サンクコスト”をどう捉えるか
イザナミは“火の神”カグツチを生んだ際に命を落としてしまいます。
イザナギは彼女を追いかけるために黄泉の国へ向かうものの、帰らぬ者となったイザナミを見て、その現実を受け入れることができません。
この場面は、投資家にとって“サンクコスト”問題を思い起こさせます。
すでに費やしてしまったコストや時間、感情的な執着が強すぎるあまり、合理的な判断を下せなくなる状況です。
イザナギはイザナミをどうにか連れ帰ろうとしますが、黄泉の国の食べ物を口にしたイザナミは“戻れない存在”になってしまっています。
これはまさに「一度黄泉の国(大幅な含み損や倒産寸前)に行ってしまった投資先は、合理的な面から見れば撤退が賢明かもしれない」という投資のリスクとオーバーコミットメントのメタファーでもあるでしょう。
もちろん現実には企業が立ち直るケースもありますが、感情や執着だけで継続保有すると、さらに傷を広げてしまうことがあるのです。
総じてイザナギ・イザナミの物語は、投資家が長期的な視野を確立するうえでの試行錯誤、失敗との付き合い方、そしてサンクコストとの向き合い方を示してくれます。
長期投資の前提には必ず不確定要素があり、その中でどれだけ柔軟かつ冷静に判断を下せるかが成功のカギとなります。
アマテラスとスサノオの葛藤から学ぶ“ブランド・信頼”の価値

天岩戸伝説と「公の舞台」からの離脱リスク
古事記の物語の中でも特に有名なのが、“天岩戸伝説”です。スサノオの乱暴狼藉に怒ったアマテラスは、天岩戸に隠れてしまいます。
すると世界が闇に包まれ、農作物は育たず、神々も困り果てることになります。
これは企業活動や資本市場においても、“中核となる存在”が離脱した際のリスクを象徴的に示していると見ることができます。
例えば、企業の創業者が病気やトラブルなどで急に経営から手を引かざるを得なくなったり、あるいは大企業のリーダーが不祥事で辞任するケースを想像してください。
経営トップの信用が失墜すると、株価は大きく動揺し、ブランドや取引先との関係にも悪影響が及びます。
このとき、市場が求めるのは「早急なリーダーの復帰または後継人材の育成」と「公の場における情報開示の回復」です。
アマテラスが天岩戸から出てくることで世界に光が戻ったように、企業においては“信頼の回復”が何より重要となります。
投資家としては、企業の重要人物や中核技術、ブランド価値がどれほどのウエイトを占めているのかを冷静に見極め、それが欠けるとどれほどのダメージがあるのかを想定しておくことが大切です。
スサノオのような“暴れ神”に翻弄されるリスクを警戒する意味でも、過度な集中投資や特定の経営者への依存には注意が必要です。
“株主総会”としての神々の会議――協力体制と議論の可視化
天岩戸に閉じこもったアマテラスをなんとか外に出そうと、ほかの神々は「どうしたらアマテラスを引き出せるか」を真剣に議論し、協力します。
神々は多くの知恵を結集し、最終的にはアメノウズメの舞いによって、アマテラスの興味を引き出し、岩戸を開けることに成功するのです。
このプロセスは、株主総会や取締役会、あるいは投資家とのカンファレンスコールで行われる企業のディスカッションに通じる部分があります。
一人の強烈なリーダーシップだけではなく、多角的な視点を取り入れて協力体制を築くことが、危機を乗り越える重要な要素となります。
投資家としては、企業がどのように対話を行い、問題解決へ向けて組織的に動いているのか――つまり企業ガバナンスの質をしっかりと見るべきなのです。
アマテラスを岩戸から引っ張り出すために多くの神々がアイデアを出し合ったように、企業の経営陣がオープンマインドで情報を共有し、新たな施策を立案・実行するプロセスがきちんと機能しているかがポイントになります。
アマテラスの“ブランド力”と投資判断
古事記においてアマテラスは“天照大御神”という名が示す通り、文字通り太陽を司る神であり、神々の中心的な存在です。
彼女がいることで世界は“光”を得て、秩序が保たれ、農作物や産業が成立するわけです。
これは企業でいえば、圧倒的なブランド力や市場シェアを握っている状況に近いと考えられます。
投資家視点で見ると、アマテラス級の“ブランド力”を持つ企業は、たとえ一時的に業績が落ち込んだとしても、リバウンドの可能性が高い場合が多いです。
強いブランドは“信用”とも言い換えられ、顧客はその企業の商品・サービスを「ほかには代替できない」と感じやすくなります。
そのため投資判断の際には、財務状況だけでなく、“ブランド”という無形資産に注目することが大切です。
定量化しづらい要素ですが、古事記におけるアマテラスの存在感をイメージすると、その力の大きさが理解しやすいでしょう。
オオクニヌシの国づくりと“バリューアップ戦略”
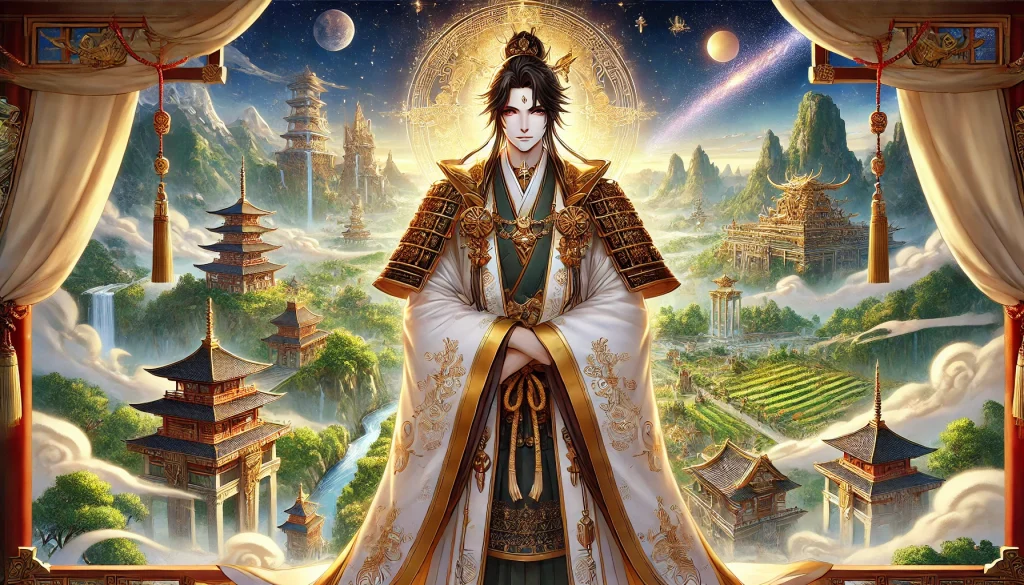
試練を乗り越える“シナリオ構築力”
オオクニヌシは多くの困難な試練を乗り越えながら、出雲の国を中心に国づくりを進めていきます。
特に有名なのが、ヤマタノオロチ退治はスサノオと関連しますが、その他にも意地悪な兄神たちに何度も命を狙われたり、さまざまな難局に直面しながらも、それを乗り越えていく姿が描かれています。
これは企業が成長していく過程、あるいは起業家が事業を拡大していく過程にも似ています。
投資家としては、企業に対して「どのような試練が想定され、それを乗り越えるためのシナリオやリソースがあるか」を見極める眼力が求められます。
オオクニヌシの成功は、彼自身の柔軟な対応力や機転に加え、神々からの支援を適切に活用できたことにも大きな要因があります。
同様に、企業が「この成長ステージでどれだけの資金を調達し、どのようなパートナーと提携し、ビジネスモデルのリスクをどのようにカバーしていくのか」―これをしっかりと説明できているかが重要です。
“国譲り”と経営権の移転――M&Aや事業承継に学ぶ
オオクニヌシの物語のクライマックスの一つは“国譲り”です。
天孫(あめみま)ニニギノミコトが高天原から降臨してくるにあたり、オオクニヌシは自主的に国を譲り渡し、自身は出雲の社(やしろ)に鎮座することを選びます。
これは、現代の企業経営におけるM&Aや事業承継の要素を想起させます。
すなわち、それまで築き上げてきた事業や組織を“次のステージ”へとつなぐために、経営権を譲り渡すという決断です。
投資家にとっても、経営陣がどのタイミングで事業を売却したり、次の経営者にバトンタッチを行うのかは重要な関心事です。
創業者やオーナー経営者が出口戦略をどう考えているのか、その移行がスムーズに行われるかどうかで、投資リターンや企業価値にも大きな影響があります。
オオクニヌシが国を譲る際に、出雲大社という神殿を要求し、自らがそこに祀られるよう望んだ点は、「権力は手放しても、ブランドや存在意義は残す」という一つの成功モデルといえるでしょう。
バリューアップのための“神のサポート”――信頼関係の醸成
オオクニヌシのエピソードの中には、多くの神々とのやり取りがあります。
時に助言を受けたり、試練を課されたりしながらも、最終的には広大な国を作り上げる。
そのプロセスでは、神々との信頼関係を構築した結果、強力なサポートを得られる場面が何度も登場します。
これは現代のビジネスや投資でいうところの「ステークホルダーとの関係構築」に相当します。
取引先や金融機関、地域社会とのつながり、あるいは従業員との信頼関係をどのように醸成し、維持し、さらに価値を高めていくか―これは企業にとっての“バリューアップ戦略”の大きな柱になります。
企業は単独では成長できません。
様々なステークホルダーからの支援やコラボレーションがなければ、長期的かつ安定的な発展を遂げることは難しいのです。
投資家の立場からも、企業がいかにして“神々=ステークホルダー”を味方につけているのかを見極めることは、投資先選定の上で非常に重要となります。
結論:神話に学ぶ投資家の心構え
古事記は単なる神話ではなく、時空を超えて私たちの人生や経済活動に通じる普遍的なメッセージを多く含んでいます。
投資や会計の世界に当てはめて考えることで、次のようなポイントが浮かび上がります。
- 長期的視野と柔軟性
イザナギ・イザナミの神話から学べるのは、新たな価値を創造する際の試行錯誤や失敗との付き合い方、サンクコストを乗り越える冷静な判断力です。
投資家としては目先の変動に一喜一憂するのではなく、長期的なビジョンを持ちながらも、必要に応じて方針転換を行う柔軟性が求められます。 - ブランドとガバナンスの重要性
アマテラスとスサノオの物語からは、“中核的存在”の信用とブランドがいかに大切か、そしてそれが失われたときに生じるリスクを痛感します。
また、チームとして問題解決に当たるガバナンス体制があって初めて、危機を乗り越えられるという点も大きな学びです。
定量的な会計データだけでなく、“信用”や“ブランド”、そして組織的な意思決定プロセスも投資判断に組み込む視点が必要でしょう。 - バリューアップのシナリオとステークホルダーとの関係構築
オオクニヌシの国づくりの過程は、企業が試練をどう乗り越え、成長シナリオを実行していくかを映し出します。
M&Aや事業承継はもとより、日々のバリューアップ策において、いかにステークホルダーの力を借りながら発展していけるかは大きなポイントです。
投資家の立場でも企業のステークホルダー戦略を読み解くことで、中長期的なリスクとリターンをより正確に予測できるようになります。
こうした神話的な物語は、一見すると現代社会の投資家には関係のない“壮大なフィクション”に思えるかもしれません。
しかし、古事記の中に織り込まれた人間らしい感情、失敗や執着、信頼関係や決断―そういった要素は、投資家の日常にも深く関係しているのです。
ときには神話をヒントに、普段は意識していない視座から投資活動を見直してみましょう。
新しい発想やインスピレーションを得て、ポートフォリオ全体のバランスやリスクマネジメント、企業選定の基準などに少し変化を加えるだけで、投資成果が変わってくる可能性があります。
最後に、このブログで紹介したエッセンスを振り返りながら、あらためて自分の投資スタンスや会計的な分析手法を見つめ直してみてください。
イザナギ・イザナミのように“創造”を恐れずに挑戦し、アマテラスのような“信用とブランド”を意識し、オオクニヌシのように“試練を乗り越え”つつ新たな国を築いていく―それこそが、古事記から学ぶ“神々の投資術”なのです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『信長の経済戦略 国盗りも天下統一もカネ次第』
織田信長の天下統一の陰には、巧みな経済戦略がありました。
本書では、信長の経済政策や財政運営を分析し、現代のビジネスや投資に通じる戦略を探ります。
『けっきょく、お金は幻です。』
日本一の個人投資家と称される竹田和平氏が、お金や投資に対する独自の哲学を語ります。
お金の本質や投資の心構えについて深く考えさせられる一冊です。
『マネーの代理人たち』
元フジテレビキャスターであり、米国の投資運用会社で働いた著者が、市場を動かすプレーヤーたちの実像を描きます。
投資マネーの流れや金融市場の裏側を知ることができます。
『世界一やさしい株の信用取引の教科書1年生』
株の信用取引について、初心者にもわかりやすく解説した入門書です。
再入門にも最適で、リスク管理や戦略の立て方を学ぶことができます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=18786988&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3302%2F2000008013302.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=13209362&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2468%2F2000001872468.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=18963946&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2154%2F9784799322154.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=17606749&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0252%2F9784800720252.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す