みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
2025年、ドルは跳ねるのか、それとも沈むのか?
2025年、ついにトランプ前大統領が返り咲き、その一挙一動が世界経済に再び大きな影響を及ぼしています。
「トランプ2.0」とも呼ばれる新たな政権下では、減税や関税政策の再強化、さらにはエネルギー政策の大転換など、実際に前例のない変化が次々と起きています。
結果として、為替や金利、株式市場、さらには企業会計や投資戦略にいたるまで、あらゆる面で不確実性が増しているのが現状です。
本ブログを最後まで読んでいただければ、あなたは次のような恩恵を得るでしょう。
- 為替の本質的メカニズム
「FRBが利上げをしたからドル高」「利下げしたからドル安」という単純な図式では、もはや語れない時代です。
長期金利とリスクプレミアム、インフレ期待がどのように相互作用し、2025年のドル円を動かすのか。その根本原理を深く理解できるようになります。 - “トランプ2.0”の具体的政策と投資・会計への影響
すでに始動しているトランプ政権の大幅減税政策やインフラ支出、輸入関税の再設定などが、企業価値や財務戦略にどのようなインパクトをもたらすのか。
会計処理やリスク管理の視点から、あなたのビジネスや資産運用に役立つ知見を提供します。 - 2025年のドル円相場を読む“思考回路”
「具体的にいま、何をどのようにウォッチすれば良いのか?」「どんなシナリオを想定すれば、円安・円高の振れ幅に対応できるのか?」といった実践的な読み筋が身につきます。 - 投資家・経営者・会計担当者が今すぐ動くべきポイント
企業会計においては、ドル建て資産・負債の管理や為替予約、リスク評価などがますます重要になってきます。
投資家にとっては、ドル円だけでなく、株式や債券、不動産などの資産配分をどう最適化するかがカギです。
このブログでは、あらゆる立場の方が応用できる視点を押さえています。
「為替や金利の動きがこれからどうなるか、もう少し深いところまで知りたい」と思っている方は、ぜひこのまま読み進めてください。
トランプ大統領の新政権がもたらす2025年のマーケット動向を、投資と会計の視点から徹底的に掘り下げていきます。
目次
トランプ2.0政権がもたらした2025年現在のドル円相場
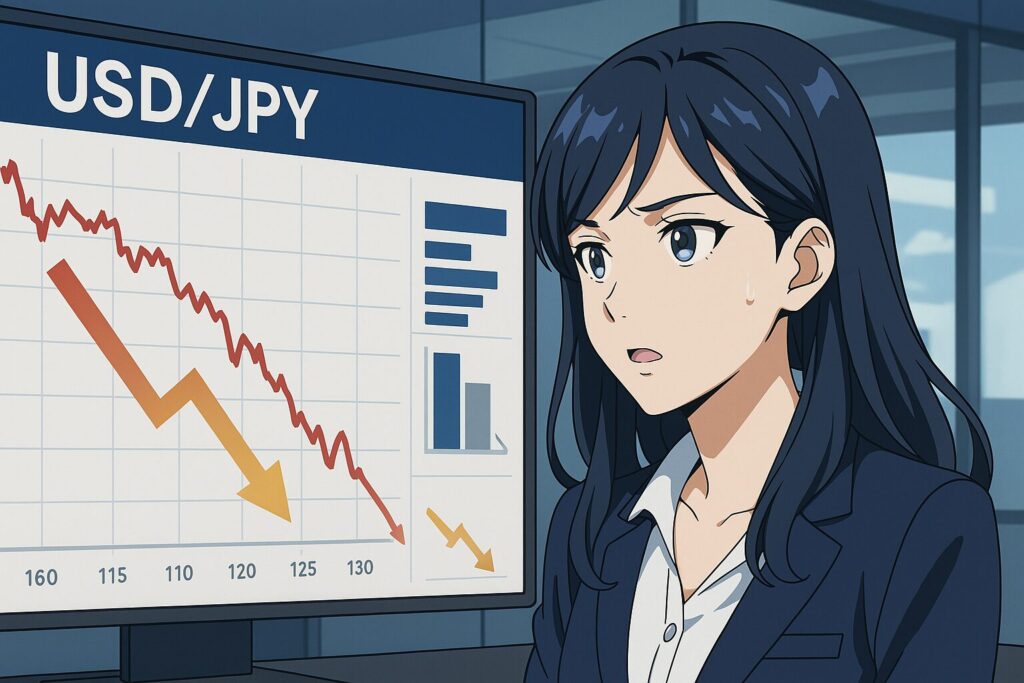
「期待」と「不安」が交錯する新政権
2025年初頭、トランプ氏がホワイトハウスに返り咲くと同時に、マーケットは大きく反応しました。
前回(2017~2021年)の政権時と同様に、「大幅減税を再び実施するのではないか」という期待感が株式市場を押し上げ、一方で「財政赤字の拡大による国債の信用リスク上昇」が意識され、債券市場は動揺しています。
さらに今回の「トランプ2.0」政権では、以下のような政策がすでに本格化しています。
- 法人税・所得税の一段の引き下げ
企業活動や個人消費を促す狙いがある一方、財政赤字を拡大させるリスクが否めません。 - 関税の再設定・引き上げ
対中関税のみならず、新たにEUや他のアジア諸国との通商交渉にも強硬姿勢を見せています。
輸入物価が上がりやすく、インフレ加速要因となる可能性があります。 - 移民規制のさらなる強化
労働力不足が深刻化し、賃金コストの上昇→コストプッシュ型インフレをもたらすリスクも取り沙汰されています。
こうした政策は、短期的には米国内の企業利益や雇用拡大を促す面もあるため、株式市場にはプラス材料となりやすい半面、インフレ圧力や財政不安を高める要素として長期金利には上昇圧力がかかりやすい構造を作り出しています。
「ドル高」か「ドル安」か? 交錯するシナリオ
トランプ政権と言えば「ドル高・株高」というイメージが強かったかもしれませんが、2025年の市場は必ずしも一方向には動いていません。
大きく分けると、以下2つのシナリオが同時に語られています。
- ドル高シナリオ
減税・インフラ投資などによって内需が加速し、企業収益が伸び、さらにFRBがインフレ抑制のために利下げを控え、むしろ利上げペースを再加速する。
金利差拡大によってドルが買われる流れが再燃する可能性があります。 - ドル安シナリオ
一方で、「トランプ2.0が財政規律を無視し、国債の増発を余儀なくされる⇒リスクプレミアムの高まり⇒米国債の信認低下⇒安全資産としてのドル離れ」という見方も根強い。
また、世界各国が対抗手段として利上げや通貨政策を強化し、ドルの相対的な強みが薄れる可能性もゼロではありません。
これらが同時進行する中、ドル円相場が「一気に120円台へ下落する」可能性もあれば、「再び140円台、150円に向けて上昇していく」可能性もある―という、まさに不確実性が増幅した世界となっているわけです。
“短期金利”ではなく“長期金利”を見るべき理由
ここで押さえておきたいのが、為替は短期金利よりも長期金利に強く連動するという定石です。
FRBが政策金利を動かしたとしても、それは主に短期金利に直接影響を与えるもの。
しかし、投資家がより注視しているのは10年債や30年債といった長期金利です。
- 長期金利の上昇要因
- インフレ率の上振れ
- 景気拡大による需要増
- 国債増発に対する投資家のリスク懸念(リスクプレミアム上昇)
- 長期金利の下落要因
- 景気後退リスク(安全資産としての国債買いが進む)
- FRBの量的緩和策(ただし、トランプ政権下では再度の量的緩和は政治的に対立の種となりやすい)
- 世界経済の落ち込みで、米国に相対的な資金流入が起きる場合
「トランプ2.0」という新政権が何をするかだけではなく、その政策を市場参加者がどう評価するかが、長期金利を動かす最大のドライバーになります。
そして長期金利の動きがドル円相場の行方を大きく左右するのです。
インフレ再燃と長期金利へのインパクト:トランプ政権下の“火種”

インフレを加速させる3つの政策要素
トランプ政権が再び掲げている政策の中で、とりわけインフレを後押ししやすいのが以下の3点です。
- 恒久的な減税(法人税・所得税の引き下げ)
前政権(2017~2021年)でも大幅な減税を断行しましたが、今回はさらに踏み込んだ恒久減税が検討・実施されています。
企業収益や個人消費を刺激する一方で、「財政赤字のさらなる拡大」が懸念され、米国債の需給バランスを崩すリスクがあります。 - 高関税政策の継続・強化
「アメリカを再び偉大にする(MAGA)」ために、海外からの輸入に高い関税を課す政策を強化。
輸入コストが上昇すれば、米国消費者物価に直接的な上昇圧力がかかります。
これは期待インフレ率を押し上げる要因になりやすい。 - 移民規制の強化による賃金上昇リスク
不法移民の排除や合法移民枠の縮小により、労働供給がタイト化。
企業は労働者確保のために賃金を引き上げざるを得ず、それがコストプッシュ型のインフレにつながりやすい構図です。
これらが積み重なると、FRBは「利下げどころか、利上げ継続もしくは少なくとも利下げ停止」という判断を迫られます。
すでに2024年終盤から2025年にかけて、利上げスタンスをどこまで維持するのかが議論の的になっていますが、トランプ政権との政治的対立も含めて不透明感が強まっているのが現状です。
“良い金利上昇”と“悪い金利上昇”の分かれ目
長期金利が上がることは、必ずしも「ドル高」や「経済好調」を意味するわけではありません。
投資家が警戒するのは、“悪い金利上昇”―すなわち、財政不安や信用リスクの高まりが原因となる金利上昇です。
- 良い金利上昇
潜在成長率が高まり、企業業績が拡大する。
投資家が「株式やリスク資産のリターンが良い」と判断して国債を売り、金利が上がる。
景気が堅調に推移する限り、ドルにとってはプラス材料。 - 悪い金利上昇
国債の増発や財政赤字拡大によって、国債の需給バランスが崩れる。
投資家が「アメリカの債券はリスクが高い」と見なして売り浴びせることで金利が上がる。
これは“信用リスク”増大を意味し、ドル下落の引き金にもなり得る。
トランプ政権の積極財政が「良い金利上昇」をもたらすか、「悪い金利上昇」をもたらすかは、今後の議会との連携や歳出規模、さらには世界情勢にも左右されます。
いずれにせよ、2025年時点では「金利上昇=ドル高」と単純には言い切れない複雑な局面を迎えているのが実態です。
エネルギー政策とインフレ
ここで注目したいのが、トランプ氏が再度掲げる「ドリル・ベイビー・ドリル(掘って掘りまくれ)」政策。
化石燃料の国内生産拡大を推奨し、原油価格やガソリン価格を下げることで、インフレ抑制を狙う狙いがあるように見えます。
しかし、実際には以下のような懸念があります。
- 価格が下がりすぎると企業の掘削インセンティブが失われる
一時的に増産するものの、採算が合わなくなると、設備投資が萎縮し、その後の生産量が減って価格が跳ね上がるリスクがある。 - 地政学リスクとの連動
オペックプラス(OPEC+)諸国の政策や、ウクライナ情勢などの地政学リスクが絡むと、米国内の増産だけでグローバル価格を安定させられない可能性が高い。 - グリーンエネルギーへの移行圧力
欧州やアジア諸国、さらにはアメリカ国内の一部州も再生可能エネルギーへの転換を加速しており、化石燃料への長期的な投資に対する慎重姿勢が続いている。
需要自体が将来的に読みづらい。
結果として、エネルギー政策がインフレをどこまで抑えられるかは不透明です。
むしろ、アメリカ国内が減税・需要拡大で盛り上がっている一方、エネルギー価格の世界的な乱高下が発生しやすい局面といえるでしょう。これは市場の“期待インフレ率”を乱高下させ、長期金利のボラティリティを高める材料にもなっています。
会計・投資の視点から見る「これからの戦略」
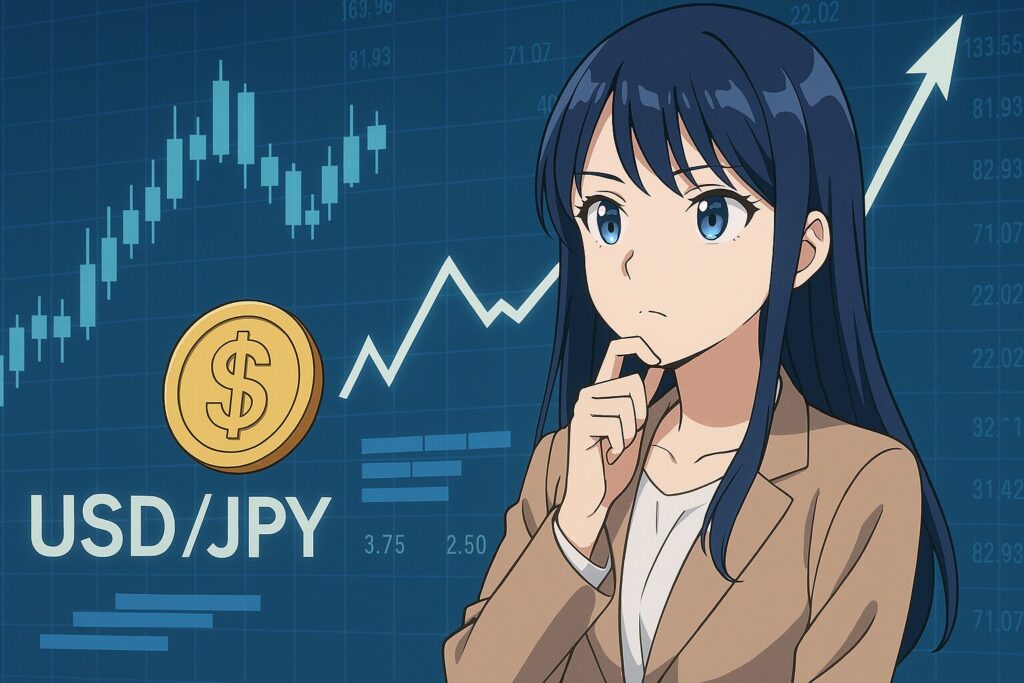
3-1. 企業会計に与える影響:為替リスクと財務戦略
2025年の「トランプ2.0」下におけるドル円相場は、大きく上にも下にも振れ得ます。
そのため、企業の財務担当や会計担当が優先して考慮すべきは、為替変動リスクのコントロールです。
- 為替予約やデリバティブを使ったヘッジ戦略
輸出入企業はもちろん、海外に生産拠点や販売子会社を持つ企業にとって、ドル円の大幅変動は業績を瞬時に左右します。
為替予約やオプションを使って、一定範囲内の変動リスクを限定するのは必須の時代に入りました。 - 多通貨建て取引の見直し
中国や欧州など、ドル以外の通貨圏との取引拡大も検討すべきタイミングかもしれません。
トランプ政権の高関税政策が長期化すると、取引コストが上がりやすい。
サプライチェーンを分散化し、決済通貨も分散させることでリスクを薄める方法があります。 - 財務諸表への影響を考慮
ドル高になれば、海外子会社の資産価値を円換算した時にプラスに働く一方、仕入れコストが円ベースで上昇するケースもあり得ます。
逆にドル安になれば、輸入コストは抑えられるものの、輸出採算が悪化するリスクも。
こうした複合的な影響を織り込んだ上で、期中の予実管理を徹底する必要があります。
投資家の視点:ポートフォリオ分散と“金利の内訳”を読む
個人投資家や機関投資家にとっては、ドル円の方向性はもちろんですが、長期金利の内訳をしっかり把握することが鍵です。
- 潜在成長率
トランプ政権が掲げる減税やインフラ投資は、短期的にはGDP成長率を押し上げる可能性があります。
これが継続的に潜在成長率を高められるか否かを見極めることで、株式投資や不動産投資の大きな方向性をつかめます。 - 期待インフレ率
高関税や移民規制が想定以上に物価上昇を促す場合、FRBが再度引き締め政策を強化するリスクが高まります。
期待インフレ率が上振れすれば、債券価格は下落しやすく(利回りは上昇)、一方で実物資産やコモディティ投資が注目されるかもしれません。 - リスクプレミアム
トランプ政権の財政拡大が国債の信認を損ねれば、米国債を敬遠する動きが出る可能性があります。
株式も含めてアメリカの資産全般が「リスク資産」と見なされれば、ドル安・米国債安(=金利高)という局面が同時に進行するかもしれません。
投資家としては、「ドル資産一択」というわけではなく、ユーロやアジア通貨、金や原油などのコモディティ、さらには暗号資産まで含めた国際分散投資の戦略を練ることが欠かせません。
特に2025年現在のように、トランプ2.0政権下で政策が急転しやすいときこそ、柔軟なポートフォリオがリスク分散に効果を発揮します。
経営者がとるべきアクションプラン
企業経営者にとって、ドル円相場と長期金利の急変は事業計画にダイレクトな影響を及ぼします。
以下のポイントを意識することで、“不確実性”をある程度コントロールできるでしょう。
- 資本コスト(WACC)の再評価
長期金利が上がれば、企業の割引率(WACC)も上昇しがちです。
新規投資の採算ラインが厳しくなり、投資回収期間も長引きやすい。
投資計画の優先順位を再検討し、必要に応じて自己資本の強化や社債発行のタイミングを見直すことが重要です。 - サプライチェーンの再設計
高関税政策によって海外からの部品調達コストが上がり、ドル円の変動リスクが加算されると、ビジネスモデルが根本的に変わる可能性があります。
生産拠点や流通網の複線化など、サプライチェーンを地理的・通貨的に分散させる戦略が必要です。 - 経営と会計の“連動”を強化する
経営者が掲げるグローバル戦略を、会計部門が適切に数値化し、リアルタイムでリスクをモニタリングできる仕組みが求められます。
とくに、為替・金利リスクを正しく試算できるシステムや体制が整っているかを再点検することが欠かせません。
結論:2025年のドル円を左右するのは“トランプ2.0”と“市場の読み”を読む力
トランプ氏が大統領に返り咲いた2025年、私たちは新たな不確実性の只中にいます。
かつての「ドル高・株高トランプ相場」をイメージして安易に乗っかると痛い目を見るかもしれませんし、逆に「財政破綻が近いからドル安だ」と決めつけても、成長加速や利上げスタンスが強化されればドル高に急旋回するリスクがあります。
では何を見ればいいのか?
- 長期金利の動向
為替は“短期金利”でなく“長期金利”と強く連動します。
その長期金利は、潜在成長率・期待インフレ率・リスクプレミアムの3つの要素で構成されており、その背後にある政治判断や財政政策の評価が大きく作用します。 - インフレ率とFRBの対応
トランプ政権が仕掛ける高関税政策や減税政策に対するインフレの動き。
そしてFRBがインフレ抑制のためにどう金融政策を舵取りするか。
その二つの相互作用がドル円の値動きを左右するカギとなります。 - 財政赤字とリスクプレミアム
大胆な減税や支出拡大が進めば、長期的に財政赤字が膨張し、国債金利にリスクプレミアムが上乗せされる可能性があります。
その場合、金利が上がってもドルが買われない(むしろ売られる)“悪い金利上昇”が起きるかもしれません。 - グローバルな通貨・金融環境の変化
世界はもはや米ドル一極支配ではなく、新たな通貨圏の登場やデジタル通貨の普及、地政学リスクなどさまざまな要因が複雑に絡み合っています。
BRICS諸国の動向や、欧州・アジアがどのように通貨・貿易面で米国に対抗するかも見逃せません。
結論として、2025年のドル円相場を的確に読み解くには、“トランプ政権が打ち出す政策自体”だけではなく、それを受けた“市場参加者の思惑”や“評価の変化”を深く観察することが不可欠です。
投資家としては、ドル円の値動きに一喜一憂するのではなく、シナリオ分析をもとにポートフォリオを分散し、ヘッジ戦略を組み合わせることが求められます。
企業としては、会計と経営を連動させたリスク管理がこれまで以上に重要になってくるでしょう。
不確実性が大きいということは、裏を返せば大きなチャンスでもあります。
相場が荒波を立てれば立てるほど、正しい知識と柔軟な発想で行動した人が大きく飛躍できる可能性があるのです。
ぜひ本記事で得た知見をベースに、あなたの投資戦略・事業戦略を再点検してみてください。
「未来は誰にも分からない」と言われますが、それでも情報と分析を駆使することで、“より明晰な未来像”を描くことはできます。
トランプ2.0という新しい風が吹き荒れる2025年、この波乱の時代を制するのは、金利の内訳を読み解き、為替のメカニズムを深く理解し、リスクを分散しながら積極的にチャンスを狙っていく投資家・経営者かもしれません。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『2023年 超円安の波に乗ってお金持ちになる 日本版「ニフティ・フィフティ」株が大化けする』
2023年の円安トレンドを活用し、日本版「ニフティ・フィフティ」とも言える有望株を紹介。投資家が注目すべき銘柄とその戦略を解説しています。
『日本経済 本当はどうなってる?』
ファイナンシャルプランナーの生島氏と元為替ディーラーの岩本氏が、最新の法改正や経済動向を踏まえ、日本経済の現状と今後について対談形式で解説しています。
『為替でわかる世界経済』
ドル・円相場などの為替水準が世界経済の構造変化を反映していることを解説。為替を通じて経済の先行きを見通す指針を提供しています。
『円安が日本を滅ぼす – 米韓台に学ぶ日本再生の道』
円安が日本経済に与える影響を分析し、米国、韓国、台湾の事例から日本再生の道を探る内容となっています。
『世界一堅実な“米ドル”投資の教科書』
円安時代における米ドル投資のメリットと具体的な運用方法を解説。年利3%~6%の運用実績を基に、初心者でも取り組みやすい投資術を紹介しています。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20844521&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5822%2F9784198655822_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21233421&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6961%2F9784413046961_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=19573287&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3357%2F2000008993357.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20645781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5386%2F9784120055386_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20773936&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8231%2F9784341088231_1_37.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す