みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
その減益、いまの“痛み”か、それとも将来CFへの“投資”ですか?
セブン&アイ・ホールディングスの決算、チェックしましたか?今期(2025年2月期)の純利益は1,730億円(前年比▲23%)。売上こそ増えましたが、利益は大きく落ち込み、株価も一時2000円割れ。見た目だけだと「大丈夫?」と不安になりそうです。しかし実は、この落ち込みは一時的な費用が原因。この記事では、決算短信の注記を手がかりに、何がどれだけ計上されているのかを投資家視点&会計視点で詳しく解説します。 具体的には、「今はなぜ痛いのか」「その先に何があるのか」を数字でひも解き、将来キャッシュフローや中期計画にどうつながるのかをご紹介します。読み終える頃には、セブン&アイの“今”がクリアに見え、将来の見通しにも納得感が持てるはずです!
目次
決算概観:23%減益の主因は?

今期は前年に比べ営業利益が4,209億円(▲21.2%)、経常利益が3,745億円(▲26.1%)、そして親会社株主に帰属する当期純利益が1,730億円(▲23.0%)でした。ただし、このマイナスは会社予想を下回ったわけではなく、むしろ前年の一時要因が大きかったためです。特に前年は百貨店事業売却に伴う巨額損失(1,296億円)がありましたが、今年はそれがなくなりました。
むしろ今期の損益悪化を引き起こしたのは、決算注記に記載された「事業構造改革費用」です。決算短信にも「事業構造改革費用28,858百万円→25,605百万円」とあり、この約256.05億円のコストが利益を圧迫しました。経常利益ベースでは前年より下振れしていますが、来期26年2月期は構造改革の一巡で純利益を2,550億円(前年比+47.3%)と大幅回復させる計画です。まさにこの決算の「痛み」は一過性。投資家はこの説明を理解すれば、来期以降の回復に安心感を持てるでしょう。
決算ハイライト
- 営業収益:11兆9,727億円(前期比+4.4%)
- 営業利益:4,209億円(同▲21.2%)
- 経常利益:3,745億円(同▲26.1%)
- 当期純利益:1,730.68億円(同▲23.0%)
来期以降の見通し
- 2026年2月期予想:営業利益4,240億円(+0.7%)、純利益2,550億円(+47.3%)。
- 中期計画(2030年度目標):営業総利益3.4兆円(FY24比+26%)、1株当たり利益を約210円(現状の2.5倍)、ROICを12.6%まで引き上げる計画。
- 株主還元:2030年度までに2兆円の自社株買いおよび配当拡充を表明(実施中)。
これらを見ると、経営陣は「一時的費用を引き受けた先に大きな成長・還元を実現する」方針が明確です。株主還元として2030年度までに2兆円(自社株買い)を実施する計画はIRプレゼンでも明記されています。
事業構造改革費用の詳細分解

決算短信の注記に目を向けると、事業構造改革費用(下期の特別損失)約256.05億円の内訳が明らかになっています。主な項目をまとめると:
- 減損損失:191.92億円(前期140.69億円)
- 固定資産廃棄損:15.78億円(前期0円)
- 転進支援金:11.25億円(前期91.55億円)
- その他:37.08億円(前期56.32億円)
- 合 計:256.05億円(前期288.58億円)
これら費用のうち、最大を占めるのは減損損失(約192億円)です。これは過去に取得・投資した店舗や不動産の価値見直し分で、海外を含むグループ全体で生じています。固定資産廃棄損(15.78億円)は、主に業績不振店舗の撤退・解体などに伴う損失です。
そして今年注目すべきは「転進支援金」約11.25億円。これは報道にもあったとおり、本部社員が「加盟店オーナーに転身」する際に支払われる支援金です。実際、セブン‐イレブン・ジャパンでは社員から加盟店オーナーになった人への特別加算金(※退職金とは別途)が最近大幅に増額されました。この施策に伴う支払いが「転進支援金」として計上されているものとみられます。
IR側もこれら一時費用の存在を明確に認めており、プレゼン資料では「事業構造改革費用等の一過性の費用を計上したため、当期純利益が減少」と説明されています。つまり、今年度の減益はあくまで「計上上」のことで、実態としては将来の利益につながる投資(損切りや先行投資)なのです。
収益性回復の道筋
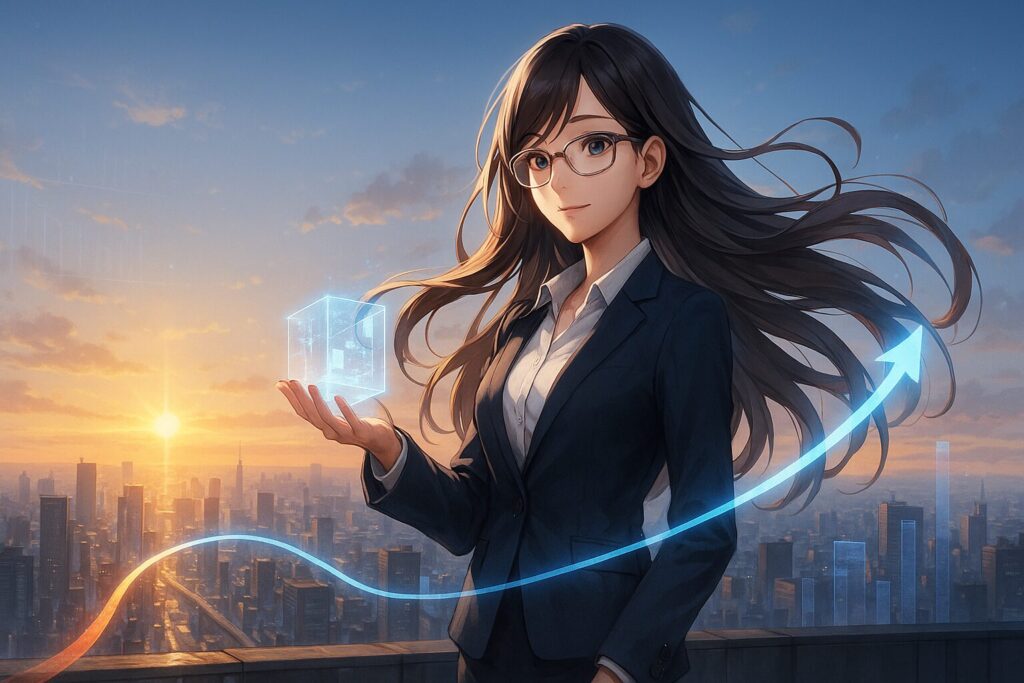
これら一時費用を除けば、本業の収益力は着実に積み上がっています。国内外のコンビニ事業は堅調で、先行投資の効果も期待されるため、来期は一気に利益増が見込まれます。実際、来年の営業利益予想は4,240億円(+0.7%)、純利益は2,550億円(+47.3%)です。これは構造改革に伴う前期の過大損失が一巡し、足元の現金収支が次期から反映されるためです。
さらに中長期視点では、2030年度までに営業総利益3.4兆円(24年度比+26%)を目指します。CEOデイカス氏はこれによりEPSを約210円(現状の約2.5倍)、ROICを12.6%まで高める計画と公言しています。また資本政策では、2030年度末までに累計2兆円の自社株買いを行うことを明示。こうした株主還元強化も、投資家にとっては大きな安心材料です。
投資家視点の要点
- 構造改革費用は「一時の痛み」:前項の通り一過性の費用計上で、これが終われば利益率は大きく回復する。IRでも「一過性の費用が減益をもたらした」と説明済。
- 来期の回復見込み:経常利益ベースで26年2月期はほぼ横ばいだが、税負担減や一過性費用減で当期純利益は大幅増となる見通し。
- 中計との整合性:今期の支出は2030年目標を実現するための先行投資の一部と位置づけられる。2兆円買い戻しを含む大規模な株主還元策もあり、総じて「成長への種まき」として理解できる。
- 安心材料:長期的に高シェアを持つコンビニ事業に加え、金融・ネットなど他セグメントの安定成長、そして北米事業IPOによる資金調達など、将来キャッシュフローを生む複数の柱がある。
これらを総合すれば、投資家としては「今期の減益は予定調和の結果」と納得できます。掲げた目標(EPS210円・ROIC12.6%・2.8兆円還元)と現在地が繋がっているのを確認できれば、不安はむしろ和らぐはずです。
結論:投資家としての納得感
決算説明会でも経営陣は「活発化する株主還元策」や「活用可能な手元資金」を強調しています。特にCFOの丸山氏は、構造改革は完了間近であり、今後は利益を上げて余剰資金を株主に還元していくと明言しました。実際、現在の株価(約2000円台)では、以前提案されていたTOB価格(2700円)超のバリューが十分自力で実現可能との見方も出ています。
読者の皆さんにとって、このブログを読むメリットは、「数字の裏側にあるストーリー」を把握できることです。表面的な減益に惑わされず、「これは投資」という大局観をもって決算を評価できるようになります。中計の実行プランや株主還元策が具体化していれば、株式市場での不当な低評価を相対的に理解でき、長期的な安心感につながるはずです。
主な投資家向けポイント
- 将来キャッシュフローへの楽観:構造改革費用計上により当面の利益は落ち込みましたが、その分、不要事業整理や成長投資が進んだ。これらは将来の現金利益を増やす「種まき投資」です。
- 長期計画の実現性:2030年度への目標数値は高いものの、具体策(北米IPO、M&A、買収の解消、配当・自社株買い)と今回の資金捻出策が整いつつあります。IR資料でも「株主価値最大化のための全選択肢を追求する」と意気込んでいます。
- 今後の株主還元:大規模な自社株買い2兆円(2030年度まで)+配当増加は、長期投資家にとって強力なバックアップ。実質的にマイナス金利分以上のリターンを狙う明確な方針です。
結論として、「今年度の決算悪化」は悲観すべき材料ではなく、未来への投資です。東日本大震災直後の節電のように、短期的には酷ですが長期では恩恵をもたらす施策と言えます。今回の記事で数字の裏側を読み解けば、次に四半期決算や株価が発表されたとき、きっと冷静に判断できるでしょう。最後に一言:今回の「痛み」をしっかり見極めてこそ、真の価値を享受できる――この知識があなたの投資判断に大きな自信を与えてくれるはずです!
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
決算書はここだけ読もう〈2026年版〉
最新の実在企業事例を使い、B/S・P/L・C/Fの“要点読み”をテンポよく押さえる入門〜実務向け。注記や科目のどこを拾えば「一次損益(特損・減損など)の含意」が早回しで見抜けるかの“視点の置き方”が身に付きます。
決算書「分析」超入門2026(100分でわかる!)
収益性・安全性・効率性のスクリーニングを“手順化”してくれる実務コンパクト本。ブログで扱った「構造改革費の一時的な痛み」と「来期以降の回復見込み」を、数式・比率・トレンドでサクッと整理する型を作れます。
有価証券報告書で読み解く 決算書の「超」速読術
有報(特に注記・セグメント情報・リスク情報)を20分で“プロ並みに”あらすじ把握するための読み方を指南。特損・減損・店舗閉鎖関連の開示を、どの順で拾い、何と突き合わせれば将来CFのガイダンスに繋がるかが具体的です。
企業価値評価 第7版(上下)〔マッキンゼー『Valuation』最新版の邦訳〕
2024年版の定番。DCFの作法、ROICと成長の関係、非経常項目(減損・事業再編費)をどう正規化して“本来収益力”へ戻すかまで丁寧。今回のテーマ「一時損益のPLインパクトを価値評価へ橋渡し」に最適です。
会社法決算の実務〈第19版〉— 計算書類等の作成方法と開示例
2025年3月期以降対応の最新実務書。注記・開示例が豊富で、構造改革に伴う特別損失や店舗閉鎖・減損の注記の“記載筋”を具体的に学べます。投資家目線でも「何が注記に出やすいか」を先読みする助けになります。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21678748&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0716%2F9784335450716_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21710681&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0814%2F9784022520814.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21202611&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7284%2F9784761277284_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20525863&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2878%2F9784478112878.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20525862&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2885%2F9784478112885.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21528276&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8217%2F9784502528217_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












コメントを残す