みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
あなたは、自分という会社に投資していますか?
100日チャレンジの舞台裏に、資産形成のヒントが隠れていた。
「やってみたい気持ちはあるけど、何から始めたらいいのか分からない」
「自己投資って結局、何がリターンになるの?」
そんな迷いを抱えている20代〜30代の社会人に、今日は“とびきりリアル”なストーリーをお届けします。
今回ご紹介するのは、大塚あみ美さんによる『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』。
一見すると「意識高い系」の挑戦記かと思いきや、実はこの本、ビジネスやお金のセンスが自然と身につく“行動資産形成”の教科書なんです。
このブログでは、そんな本書の魅力を「会計」と「投資」の視点から読み解いていきます。
あなたの“行動”や“継続”が、どのように資産に変わっていくのか──。
読み終える頃には、自分自身を「経営」したくなること間違いなしです。
📌このブログのポイントは、以下の3つ!
- 「継続=資産」になる仕組みを会計視点から読み解く
- 「恥をかく=損失」ではなく、「投資コスト」になるという思考法
- 「自分株式会社」をどう成長させるかという投資的戦略のヒント
この続きでは、“凡人でも再現できる資産形成モデル”としての100日チャレンジを、じっくり深掘りしていきます。
目次
継続は「キャッシュフローを生む資産」だった

習慣は未来のキャッシュフローを生む装置
『#100日チャレンジ』の根幹にあるのは、「継続」そのものだ。毎日アプリを作って投稿し続けるという一見無謀な取り組みは、実は非常に「再現性」の高い行動パターンでもある。これを会計の視点で捉え直すと、著者が取り組んだ100日チャレンジは、目に見えない「のれん」や「人的資本」のような無形資産の蓄積に他ならない。実際に会計の世界でも、ブランド力やスキル、知的財産など、将来キャッシュフローを生むと見込まれる資産は“のれん”や“ソフトウェア”としてバランスシートに計上される。
著者がやったことは、毎日アプリを開発し、SNSに投稿し、そこからフィードバックを得てまた次のアプリへという、学びと改善のサイクルの連続だった。これは自己資産(スキル)を磨くだけでなく、社会的信用(フォロワーや評価)という“市場価値”を高める運動だったとも言える。このように、継続とは未来に向けたキャッシュフロー創出活動であり、いわば事業のフロントエンジンのようなものなのだ。
SNS投稿は「開示行為」、学びのコストは「研究開発費」
さらに注目したいのは、著者が毎日の成果物をSNS(特にX)で「外に出し続けた」点である。これは、いわば企業が財務諸表を開示するIR活動にあたる。どんなに優れたスキルも、どんなに面白いアイデアも、外部に伝わらなければ評価されず、信用にも資金にも結びつかない。だからこそ、アウトプット=開示のプロセスが必要不可欠なのだ。
一方で、アプリ開発には当然「時間的コスト」がかかる。これも会計的に見れば「研究開発費(R&D)」に該当する。R&Dは短期的には費用(損失)として処理されることが多いが、将来的には大きなリターンをもたらす可能性を秘めた“希望的投資”である。著者が1日10時間も費やしたという努力は、目先の評価では測れないが、彼女のスキルと信用を劇的に引き上げ、最終的には書籍出版や論文発表という“資本化”へとつながっている。
フローの連続が「ストック」に変わる瞬間
継続という行動は、日々の努力(フロー)を、徐々にストック(資産)へと転換させていく。この転換には、時間と粘り強さが必要だ。著者は決まった時間に大学へ行き、作業するというルーティンを守った。これは、事業におけるキャッシュフロー計画や工場の稼働率に似ている。継続は感情ではなく、設計されたルールで維持されるべきものという点も重要だ。
この「習慣という資産」は、いわば自動的にキャッシュを生む装置となる。100日後に得た成果は、1日単位の努力の延長ではなく、“資本として複利的に蓄積された信頼と実力”の成果だった。会計の世界でよく使われる“資産の償却”という概念と逆で、ここで蓄積された無形資産は減価せず、むしろ雪だるま式に成長するのが最大の魅力だ。
このように、「ただ頑張った」ではなく、「継続を仕組み化した」著者の行動は、まさに未来キャッシュを生む“会計的に再現可能なモデル”だったのです。次章では、この継続の裏に潜む「恥と恐れ」の正体を、投資の視点で読み解いていきます。
恥は「損失」ではなく、「投資コスト」だった
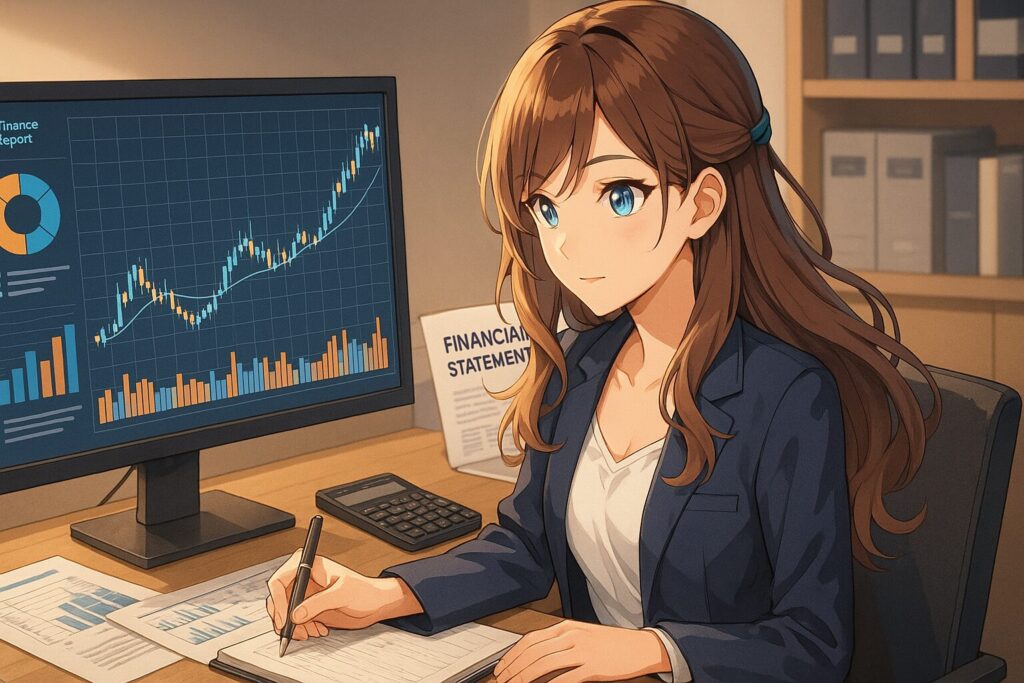
公開する勇気が、唯一の成長エンジンになる
『#100日チャレンジ』の中盤、著者・大塚あみ美さんがぶつかった大きな壁。それが「このアプリ、本当に公開してもいいのだろうか?」という恥の感情だった。完成度の低いアプリをSNSで公開することに強い不安を感じ、「笑われたらどうしよう」「無能と思われたらどうしよう」という葛藤に苛まれたという。
これは多くの社会人にも心当たりがある感覚だろう。仕事でも、副業でも、学びでも、「できていない自分」を見せることへの抵抗感は強い。でもここで考えたいのは、「それって本当に“損失”なのか?」ということだ。実はこの“恥ずかしさ”は、会計的に言えば「先行投資のコスト」に近い。
つまり、未完成な状態でも外に出すという行為は、「売れるかどうかまだ分からないけど、新商品を試験販売してみる」ことに等しい。この“公開”というアクションは、結果的に本人のブランド価値や、将来の信頼残高(人的資本)にリターンをもたらす可能性を秘めている。出さなければ評価も改善もされない。公開こそが、唯一の成長エンジンなのだ。
ネガティブな感情こそ、リスクマネーに変換せよ
投資の世界では「リスクを取らなければリターンもない」とよく言われる。ところが我々は、自分の中にある「失敗しそう」「批判されそう」といった感情を、リスクではなく“障害”として扱いがちだ。これは極めてもったいないことだ。
なぜなら、恥や恐れといったネガティブな感情こそが、最も重要な“リスクマネー”の源泉になるからだ。たとえば著者が作成したフォント変換ツール。初めてのコード、初めてのデザイン、うまく動かない中で何とか形にし、夕方にXへ投稿したという。その後に押し寄せた「これで大丈夫かな…」という不安もまた、彼女が実際にリスクを負って市場に挑戦した証拠だ。
この“恥”の感情に打ち勝つことは、株式市場で言えば「誰もが怖がっている暴落時に買い向かう行動」と似ている。勇気を出して1歩踏み出すからこそ、反応が得られ、改善され、価値が生まれる。そう考えると、恥は損失ではなく、行動を生むための“エントリーフィー”とも言えるだろう。
インプット偏重から脱却し、「市場に出す人」になる
もうひとつ注目すべきなのは、著者がただ学びを深めるだけでなく、徹底的にアウトプットにこだわった点である。普通なら、もっと完璧にしてから出したくなる。だがそれを待っていたら、100日どころか一生出せない。
これは、経営者で言えば「永遠に企画段階で止まっている新規事業」と同じ。机上のプランは1円も生まない。未完成でも市場に出すこと、それこそが実践の第一歩だ。著者はSNSという「疑似市場」で、自分の商品(アプリ)を出し、そこで得た声や反応から、次の方向性を微調整していった。
これは“市場テスト”と“フィードバックループ”の実践に他ならない。どんなに優れた経営戦略も、実行してみなければわからないし、仮説は検証されなければ意味がない。つまり、大塚さんがしていたのは、毎日1本ずつ「自分株式会社」の新商品を市場に投下し続けた、極めて投資的なアプローチだったのである。
恥や不安は、成長のためのコストであり、リターンを得るための入場料でもある。だからこそ、「公開すること」から逃げないことが、すべての始まりになる。完璧じゃなくていい、うまくいかなくていい。やってみることにこそ、価値がある。次章では、この「やってみた結果」が、どんなレバレッジ効果を生み出したのか──人的資本という観点から掘り下げていきます。
人的資本という「非上場企業」を育てる投資視点

自分という“未上場企業”をどう評価するか?
著者・大塚あみ美さんが取り組んだ100日チャレンジは、一見すると学生の創作活動のようにも見えるが、実態はまるでスタートアップのプロトタイプフェーズに酷似している。最初は完成度も信頼もなく、周囲からの資金調達(=応援や支援)もゼロ。しかし、日々のアウトプットを積み重ねることで徐々に社会的信用が蓄積され、やがて論文発表、書籍出版、企業からの注目といった「外部評価」がつき始める。
これを投資の視点で言えば、まさに非上場企業の企業価値をどう育てていくかというプロセスそのものだ。企業が未上場の段階で重視されるのは、PL(損益)よりも「事業アイデア」や「創業者の情熱」、そして「継続力と実行力」だ。人的資本とは、まさにこの3つの掛け算によって価値が立ち上がっていく。
つまり、自分自身がまだ収益を生まない段階だとしても、「どれだけ試作を重ねてきたか」「どんな挑戦をしてきたか」「どんな失敗と向き合ってきたか」という“実行履歴”こそが、人的資本のバリュエーション(評価額)を構成していくのだ。
行動は資本構成を変えるレバレッジ装置
もうひとつ見逃せないのは、著者の“行動力”が実際に他者の資本を引き込んでいく過程である。たとえば、大塚さんをサポートした大学教授・伊藤先生は、彼女の努力に感銘を受け、自腹で40万円のMacBookを譲渡し、学会への同行までしてくれる。これが何を意味するかというと、人的資本への“外部資本注入”が起きているということだ。
これはスタートアップがエンジェル投資家からシードマネーを得る流れと極めてよく似ている。まだ実績は小さくても、行動している姿に魅力を感じた投資家(この場合は教授)が、リスクをとって資本(支援)を提供する。そしてこの資本注入が、さらに行動を加速させ、新たな信頼と成果を生む好循環をつくる。
つまり、人的資本はレバレッジ可能な資本であり、行動によってその倍率を高めることができる。逆に言えば、行動しない限り、どれだけポテンシャルがあっても他人の資本は引き出せない。信用もチャンスも、すべては動き出した瞬間にしか降ってこないのだ。
上場しなくても価値がある「私企業」の経営者になれ
多くの人は「有名になること」や「フォロワーを増やすこと」にばかり目がいくが、本当に大切なのは、自分の内側にどれだけ“持続可能な価値”を育てているかである。言い換えれば、「市場での注目度」よりも、「市場に出しても耐えられるだけの自己資本」をどれだけ積み上げているかが問われる。
人的資本の面白い点は、自己投資の結果が“可視化されにくい”ことにある。会計上の貸借対照表には載らないし、時価評価もできない。だが、たったひとつ行動を変えただけで、その価値が一気に“収益化”される瞬間がある。著者がスペインの学会で論文を発表し、それが書籍化に繋がったように、行動によって眠っていた価値が突然評価される“バリュエーションの跳ね上がり”が起きるのだ。
我々一人ひとりも、自分のキャリアやスキルセットを「上場企業のように評価されるもの」に仕立てていく必要はない。むしろ、非上場だからこそ、柔軟に再投資し、失敗を許容し、成長を設計できる自由がある。それこそが「自分株式会社」の経営者になるということなのだ。
人的資本は目に見えない。でも確実に、成長する。そして育て方を間違えなければ、驚くようなリターンを返してくれる。本書はその生きた証明だ。最終章では、この100日チャレンジが、どう人生全体に複利の力を与えていったのか──振り返ります。
結論:人生最大の資産は「やってみた自分」だけが持っている
『#100日チャレンジ』は、特別な才能の物語ではありません。むしろ「やる気がなかった普通の学生」が、たった100日だけ「続けてみる」と決めたことで、人生の座標軸が劇的に変わっていった、ごく普通の人の、誰にでも起こりうる奇跡です。
途中、何度も「これでいいのか」「意味があるのか」と悩みながらも、彼女は一歩ずつ、自分の手で“見えない資産”を積み上げていきました。スキル、習慣、信用、そして他者の応援──それはどれも、今すぐに数字にはならないけれど、確実に将来を変えてくれる“資本”でした。
わたしたちはつい、「何かがうまくいってから始めよう」と考えてしまいがちです。でも本当は逆で、うまくいくのは、始めた人だけに与えられる特権なのかもしれません。
恥をかく勇気も、時間を差し出す覚悟も、うまくいかない日を越えて続ける強さも──全部ひっくるめて、「やってみた」人の中にしか育たない資産です。
人生を変えるのに、大きな目標も、完璧な計画もいりません。必要なのは、ほんの少しの“やってみよう”と、その小さな火を絶やさない仕組みだけ。
あなたという会社の、今日の経営判断はどうですか?
始めてみませんか? あなた自身に“出資”する、その一歩を。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学
お金の貯め方・増やし方・稼ぎ方に加え、年金や税金、投資信託まで網羅。初心者でも分かりやすい解説が魅力です。
会計HACKS!—楽しんで資産を増やすお金のコツと習慣
バランスシートを基本に、家計やスキルを“会計的に”捉え直す一冊。資産形成の視点をブログ内容と重ねたい方におすすめです。
全面改訂 第3版 ほったらかし投資術
シリーズ累計7万部を誇る定番。シンプルで実践的、インデックス投資メインの手法をわかりやすく解説しています。初心者におすすめ。
転換の時代を生き抜く投資の教科書
63万人フォロワーを持つ元日経記者による、現代の投資環境に関するハンドブック。お金の稼ぎ方と資産マネジメントの両方を網羅。
ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣
習慣術のベストセラー。小さな習慣の積み重ねが大きな変化を生むことを科学的に裏付けています。継続のメカニズムを深掘りしたい方に最適。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21483151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1067%2F9784296071067_1_41.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=11683603&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4940%2F2000000254940.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20582206&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1670%2F9784022951670_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21164539&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1538%2F9784296001538_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19808151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2154%2F9784775942154.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


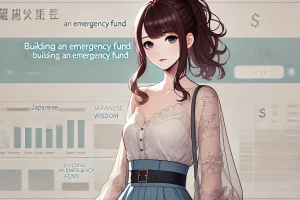










コメントを残す