みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。Jindyです。
“なんかうまくいく人”って、何を見ているの?
「スキルはあるのに、なぜか結果が出ない」
「たいした努力もしてなさそうなのに、あの人はうまくいってる」
そんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか?
この違いを生み出しているもの──それが「センス」です。
でもこの“センス”、ただの才能や運ではありません。じつは、繰り返される思考習慣と鋭い視点の積み重ね。つまり、「再現可能な技術」なんです。
この記事では、センスとは何か?どうすれば身につけられるのか?を財務分析という一見ドライな分野にまで落とし込んで、言語化していきます。
特に注目してほしいのは、数値には表れない「微差」にどう気づき、判断につなげるかという視点。
この記事を読むことで、「ふわっとした感覚」に対して、論理と構造でアプローチする知的なおもしろさを体感できます。
センスの正体に迫ることで、あなたの「仕事の質」が劇的に変わるかもしれません。
目次
センスとは何か?──「感覚」ではなく「再現可能な視点」の集合
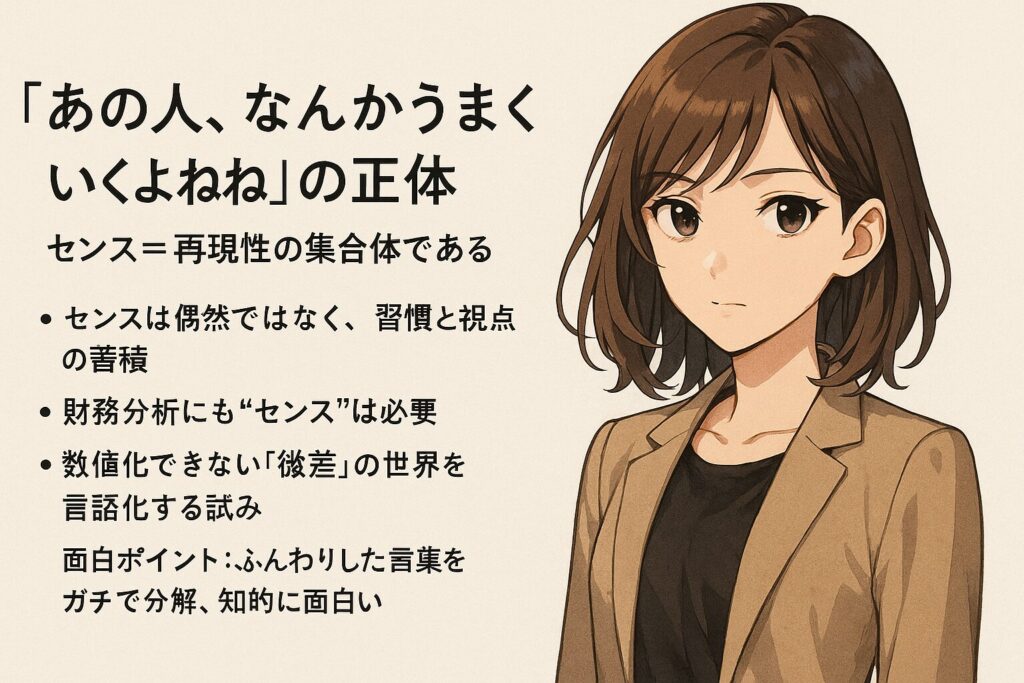
「センスがある」「センスがない」といった言葉は、日常的に使われるにも関わらず、非常に曖昧です。
では、本当に“センス”とは何を指しているのでしょうか?それは、単なるひらめきや直感ではなく、「ある状況で何を見るか、何を重視するか」という“視点”の質と量のこと。つまり、繰り返し観察・経験し、構造化されたものがセンスなのです。
センスは“情報の取捨選択力”である
たとえば、ビジネスの場面で「この提案、通るかどうか」の判断を求められたとき。
センスのある人は、一見同じ資料を見ていても、注目するポイントがまったく違います。数字の裏にある意図、文脈、ステークホルダーの空気感……。それらを無意識に総合して、最も本質的な情報を抽出するのです。
これが「情報の取捨選択力=センス」の正体。多くの情報が飛び交う現代において、この力の差が結果を大きく左右します。つまりセンスとは、偶然の産物ではなく、日々の観察と振り返りによって精度が増す技術なのです。
経験がセンスを育てる「素材」になる
「センスがある」と言われる人ほど、実は過去に多くの失敗や違和感を積み重ねています。
失敗をした時、彼らは「なぜ失敗したか」「何を見落としていたか」を徹底的に掘り下げ、記憶に刻みます。それが「次の一手」を判断する材料になる。
つまり、経験そのものに価値があるのではなく、経験をどう解釈し、次にどう活かすか──この“意味づけのプロセス”がセンスのコアなのです。センスとは、無意識のデータベース。多様な視点を蓄積し、瞬時に引き出せるようにしておくことで、瞬間的な判断力が磨かれていくのです。
センスは“構造”で鍛えられる
センスが属人的で再現性がないように見えるのは、「暗黙知」として処理されがちだからです。でもそれを言語化し、構造に落とし込むことで、他人にも伝えられるようになります。
たとえば、デザインのセンスがある人は「配置のバランス」「色のトーン」「余白の取り方」といった“ルール”を無意識に使いこなしている。これを構造として理解すれば、誰でもトレーニング可能です。
仕事においても同様です。営業に必要な“空気を読む力”も、相手の表情・声色・反応の「型」を知り、経験から法則性を見つけることで再現可能になります。
センスとは「感覚的な天才」の話ではなく、「思考習慣の集積」。
日々の観察・経験・言語化のプロセスを経ることで、誰でも磨ける技術なのです。
財務分析における“センス”──数字に現れない違和感を掴め
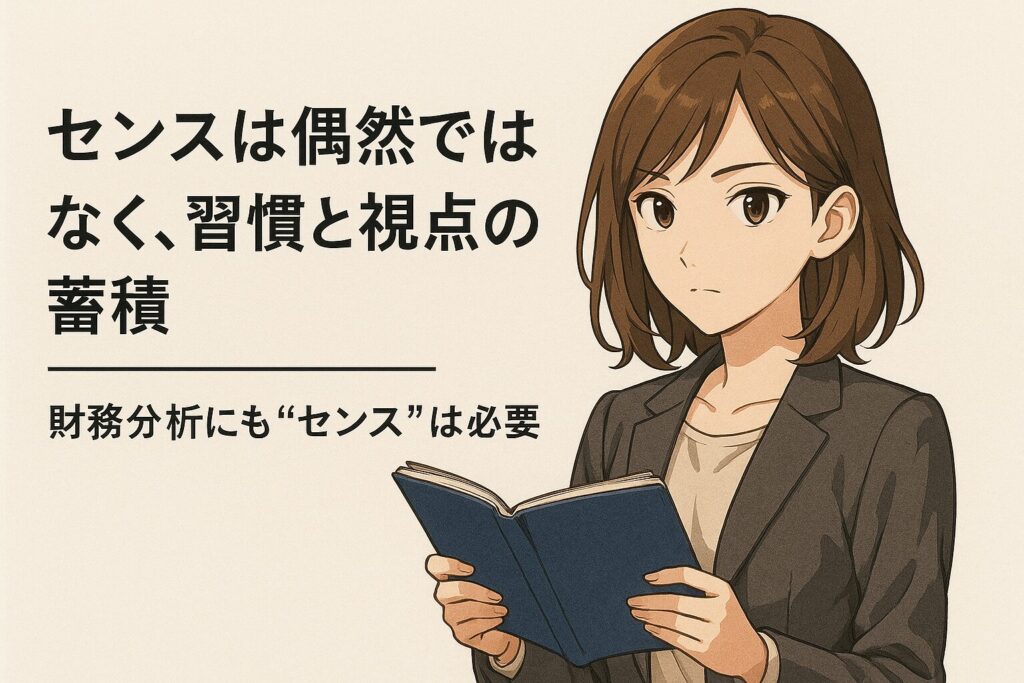
「財務分析」というと、数字を追いかけるだけの冷静な作業に思われがちですが、実はそこにも“センス”が必要とされます。
同じ財務諸表を見ても、ある人は「問題なし」と判断し、別の人は「何かが変だ」と直感する──この差こそが、センスの有無なのです。
“あれ、ちょっと変だな”が見える人になる
PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)を読むとき、多くの人は前年対比や利益率など、見える数字だけに目を奪われがちです。けれどセンスのある人は、その裏にある微妙な“揺らぎ”に気づきます。
たとえば、売上が微増しているのに、なぜか営業キャッシュフローが減少している。棚卸資産が不自然に増えている。これらの違和感を「誤差」と流さず、「構造的な変化かも?」と仮説を立てて掘り下げる。
このように、「数字の揺らぎ」と「現場の実感」を結びつけて考えるのが、財務センスの第一歩です。
数字の背後にある“物語”を読む
財務諸表とは、いわば企業の「物語」です。数字は単なる記号ではなく、企業の意思や戦略が表れた痕跡。だから、センスのある人は数字を読むだけでなく、そこからストーリーを読み解こうとします。
たとえば、急に広告宣伝費が増えた場合、「攻めの姿勢」と捉えるのか、「焦りの裏返し」と見るのか。どちらも正解になりうる中で、「これまでの流れと整合的か?」「業界トレンドと合っているか?」と多角的に検証する。
つまり、数字だけではなく「背景」を洞察する力。これが、財務分析における“センス”を支える大きな軸です。
微差にこそ本質が宿る
センスを持つ人は、「大きな変化」よりも「小さな違和感」にこそ価値を見出します。
たとえば、粗利率が0.5%落ちている。その原因を「誤差」として見過ごすか、「ビジネスモデルが変質している兆しかも」と仮説を立てるか。このわずかな視点の違いが、大きな未来の差を生み出すのです。
また、数字そのものに現れない「現場の肌感覚」──例えば、営業の“気合いが空回りしている”といった空気感もまた、センスのある人は拾い上げます。そして、それを経営指標に落とし込むための問いを立てる。
財務分析とは、“数字を使った経営への問いかけ”であり、センスとは“数字の奥にある未来の予兆”を掴む力なのです。
数字を信じすぎてもダメ、疑いすぎてもダメ。そのちょうどいいバランス感覚こそが、財務センスの真髄です。
センスは磨ける──習慣と視点のアップデート法
「センスは持って生まれた才能」と思い込んでいる人が多いですが、実際には後天的に鍛えることが可能です。
センスとは、“気づく習慣”と“見る視点”を繰り返し更新していく中で徐々に蓄積されるもの。つまり、それは「学習可能な技術」なのです。
日常を“観察フィールド”に変える
センスを磨く第一歩は、「日常の中にヒントはある」と意識することです。
たとえば、コンビニの商品配置、飲食店のオペレーション、同僚の言葉づかい──それらを単なる背景として受け流さず、「なぜそうなっているのか?」を自分に問いかけるクセをつける。
この「問いを立てる習慣」が、センスの源泉です。
「なぜ、あの店の回転率が高いのか?」「なぜ、この上司の話はわかりやすいのか?」と身の回りの現象を構造的に見ることで、抽象的な思考力が磨かれていきます。
フィードバックを“センスの肥やし”にする
自分の感覚が正しいかどうかを確かめるには、第三者の視点が欠かせません。
センスのいい人は、必ずと言っていいほど「レビュー」を重視します。提案書の感想をもらう、プレゼンに対して本音のフィードバックを求める、自分の分析を他人と比較してみる──こうした外部の視点こそ、思考の盲点を発見する最大のヒントになります。
フィードバックを単なる批評ではなく、「自分のセンスを再構築する材料」として活かす。この姿勢があるだけで、成長のスピードは桁違いに加速します。
“センスを言語化する力”が本物をつくる
本当にセンスのある人は、自分の思考プロセスを言語化できます。「なんとなく」「直感で」ではなく、「こういう情報があって、こう解釈したから、こう判断した」と論理的に説明できる。
この言語化のプロセスこそが、“再現性”を生み出します。逆に言えば、言語化できないセンスは、他人には伝わらず、自分でも成長を実感しにくい。
「なぜそう思ったのか?」を自分自身に問い続け、思考の型を可視化する。これがセンスを“技術”へと昇華させる最短ルートなのです。
センスとは、“感覚”に頼らず“観察・言語化・検証”のサイクルを回すことで、誰でも磨けるスキル。
視点を変えれば、世界がまったく違って見えてくる──そんな可能性に満ちた力なのです。
センスとは、人生を変える「再現可能な魔法」である
「センスがある人」に憧れても、「自分にはセンスがない」と諦めていた過去の自分へ。
この記事を読んだ今、もう一度言います──センスは、磨けます。
私たちは日々、無数の選択をしています。何を見て、何を感じ、どう判断するか。その一つひとつの積み重ねが、人生の“結果”となって現れます。つまり、センスとは単なるスキル以上に、「人生そのものの質」を決める重要なファクターなのです。
誰かの成功を「センスの差」として片づけるのは簡単です。でも、そこで終わってしまうのはもったいない。
センスとは、「気づく力」「選ぶ力」「伝える力」──そのすべてを内包した、磨けば輝く知的資産です。
あなたの中にも、すでにセンスの“原石”はあります。日常の中でふと感じた違和感、なんとなく気になったパターン。それを放置せず、言語化して、検証して、もう一歩深く考えてみる。その一手間が、未来を変える大きな差になります。
センスのある人になることは、ただ「デキる人」になることではありません。
それは、世界をより豊かに感じ取り、深く理解し、他人に貢献できる力を手にするということ。
今日から、あなたもセンスを磨きはじめましょう。
それはきっと、“爆速で稼ぐ”以上の価値を、あなたの人生にもたらしてくれるはずです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
センス入門
“センスとは何か”を、クリエイターやビジネスパーソン向けにやさしく整理した入門書。知識や経験が「センスの基盤」であると説き、再現性持ってアイデアを生む思考法を解説。
コンセプト・センス: 正解のない時代の答えのつくり方
“正解のない問い”に向き合う力を鍛えるためのメソッドを紹介。抽象化・再構築・言語化のプロセスを通じて、「センス」を体系化する思考アプローチが学べる1冊。
再現可能性のすゝめ
タイトル通り「成果を再現できる仕組みとは何か?」を探求。思考や行動を再現可能にするための枠組みや習慣づくりを実践的に学べ、センスと直結する内容です。
ビジネス・センス
社会人向けに「ビジネスの場で発揮されるセンスとは何か?」を整理。情報選別力、視点の更新、構造化など、記事で扱った思考習慣と深く共鳴する一冊。
SENSE: インターネットの世界は『感覚』に働きかける
感覚的な“センス”が、現代のマーケティングや情報伝達にどう影響するかを分析。センスが偶然ではなく“規則性”と“文脈の解像度”で構成されていることを理論的に裏付けています。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=16327115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6726%2F9784480816726.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21153649&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4740%2F9784866214740_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19075670&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2438%2F9784320112438.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=16774370&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2Fnoimage_01.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20761972&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1224%2F9784296001224_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す