みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
あなたの投資、本当に“自分の選択”ですか?
「オルカンは持ってないんですか?」
「えっ、三菱商事買ってないんですか?」
──そんな“空気”を感じたことはありませんか?
SNSやYouTubeで話題になる投資先が、なぜか「正解」とされていく。そしてそれに乗らないと「非国民」のような居心地の悪さを覚える。そんな経験がある人にこそ、この記事は刺さります。
本記事では、「オルカン教」「三菱商事教」とも揶揄されるような、投資クラスタに見られる“宗教的信仰”のようなムーブメントを会計・経済の視点から解き明かしていきます。
投資とは本来、合理性と再現性を追求する「科学」のはず。しかし現実のSNS界隈では、それが「信仰」のように変質していく。なぜそんなねじれが生まれるのか? そしてその信仰に、果たして“勝てる”根拠はあるのか?
以下のポイントに絞って、深掘りしていきます:
- なぜ「オルカン」「三菱商事」が“信仰”化するのか?
- 集団心理がリスク評価を狂わせるメカニズム
- 投資における「安心」と「錯覚」の関係を会計視点から見る
「あるある」と笑いながらも、自分の投資スタンスを見直すきっかけになるかもしれません。
では、“投資宗教”の実態を、冷静に、でもちょっと皮肉を込めて見ていきましょう。
目次
なぜ「オルカン」や「三菱商事」が“信仰”化するのか?
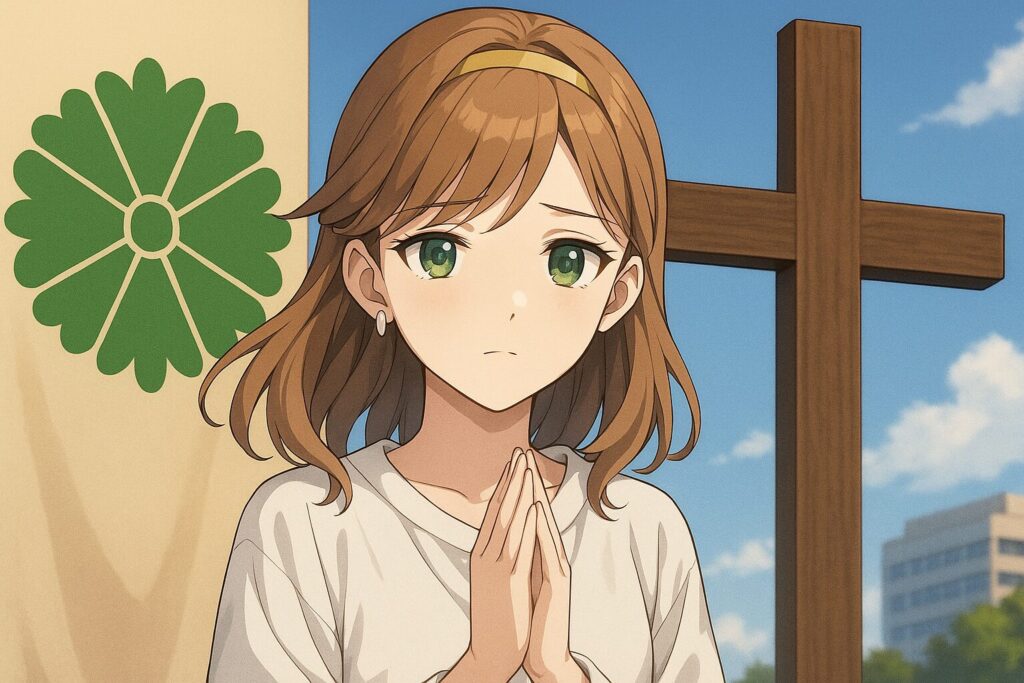
集団の中で生まれる「安心神話」
「オルカン買っておけばOK」
「三菱商事は絶対潰れない」
このような“安心神話”は、投資初心者にとって福音のように響きます。なぜなら、「何を買えばいいか分からない」という最大のストレスから解放してくれるからです。とくにSNSでは、フォロワー数の多いインフルエンサーが「これ買っておけばOK」と明言すれば、それが“公式”のように扱われてしまう。これが、「合理性のように見える信仰」の始まりです。
「みんなが持ってるから安心」という心理は、実は極めて非合理です。投資の原則は「他人と違う判断をして初めてリターンが得られる」こと。しかし“安心”は、思考を止めさせます。「考える投資」ではなく「従う投資」へと変質する瞬間です。
「教祖」の存在とシェア文化の罪
この“信仰”を拡大するのが、SNS時代特有の「教祖と信徒」の構造です。インフルエンサーが語る「成功体験」は、具体的な数字やグラフとともに「納得感」を伴って拡散されます。たとえば「10年前に三菱商事に100万円投資していたら、今は◯◯万円!」という投稿。これがバズれば、もう議論の余地はなくなります。
もちろん過去の実績は参考にはなりますが、未来を保証するものではありません。しかし、感情と数字の“物語”に人は惹かれやすい。特に日本人は「空気を読む」ことに長けており、「みんながやってる=正解」という思考に傾きがちです。これが“教祖”を生み出し、信仰が強化される土壌となるのです。
オルカン=最適解の錯覚
オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、確かに分散投資の面で合理的な商品です。MSCI ACWIに連動し、世界中の株式に投資でき、手数料も低い。ここまでは“正しい理屈”ですが、それが「他を選ぶのは愚か」とまで言われるようになると、それはもはや「合理的選択」ではなく「選ばされた選択」に変わってしまいます。
重要なのは、「全員にとって最適な投資は存在しない」という原則です。例えば、年齢、資産額、リスク許容度、ライフプランによって、本来の“最適解”は変わるべき。しかし、投資クラスタ内ではその前提が無視され、「オルカン買っておけば正義」という一元的価値観が支配し始める。ここに、“信仰”と“合理性”のねじれが生まれます。
「自分で考えることをやめたとき、投資はただの模倣になる」
これは、投資における最も危うい姿かもしれません。
集団心理がリスク評価を狂わせるメカニズム

「みんながやってる」が最大のリスクになる paradox
投資の世界では「リスクとリターンは表裏一体」と言われます。しかし、SNSや投資系メディアで繰り返される“正解”があまりにも強固になると、人々はリスクを感じなくなります。それどころか、「みんなが買ってる=リスクが低い」と誤認するようになる。これが最も危うい錯覚です。
たとえば、三菱商事は高配当・増配・安定収益と三拍子そろった“優等生”として語られます。しかし、エネルギー価格の変動や為替の影響など、外部リスクにさらされている事実は見えにくくなります。なぜなら、「大企業=安心」という認知バイアスが強く働くからです。
このようなバイアスは、「再現性のある投資判断」ではなく、「みんなと同じだから安心」という集団心理に基づいた擬似的安全領域を作り出します。そして、実際にその資産が下落し始めたとき、人々は初めて「え?これってリスクあったの?」と目を覚ますのです。
リスクの“可視化”を妨げる情報環境
情報の氾濫もリスク評価を狂わせます。タイムラインには「◯年で資産◯倍!」の成功体験と、「暴落時も信じて握っていれば勝てた」という成功ストーリーが溢れています。そうしたポジティブ情報に埋もれ、「損した人の話」や「失敗した原因分析」が届きにくくなっているのです。
これはいわば、ポジティブな情報フィルターによる“情報の偏り”。本来なら、投資判断にはリスク・リターンの両方の評価が必要です。しかし、現代のSNS環境では、リターンばかりが可視化され、リスクは「語られないもの」として扱われる。
さらに、フォロワー数が多い人ほど「リスクを語る=ネガティブと思われる」というジレンマを抱えています。そのため、発信内容はどんどんポジティブに寄っていく。これが、結果として“リスクに鈍感な投資クラスタ”を育てる構造になっているのです。
「逆にリスクを取っていないことがリスク」論の危険性
最近よく耳にするのが、「現金で持ってる方がリスク」「インフレ時代に投資しないのは機会損失」という論調です。もちろんこれは理論上は正しい場面もありますが、これが「だから全員が株を持て」と直結してしまうと、話は別です。
会計的に見れば、リスクとは「予測の不確実性」そのものです。投資対象に値動きがある以上、必ずリスクは存在します。なのに、そのリスクを「取って当たり前」とされると、結果的に“リスクの存在そのもの”が軽視されてしまう。
「リスクを取らない=愚か」という空気が蔓延すれば、リスクに対する健全な恐れが失われます。そして、「下落しても信じていれば大丈夫」という“信仰的メンタリティ”が支配し始める。これはもう、投資ではなく祈りの世界です。
本来、リスクは敬意をもって扱うべき存在です。
「みんながやってるから安心」という心のバランスが崩れたとき、投資は“合理”からもっとも遠ざかるのです。
投資における「安心」と「錯覚」の関係を会計視点から見る
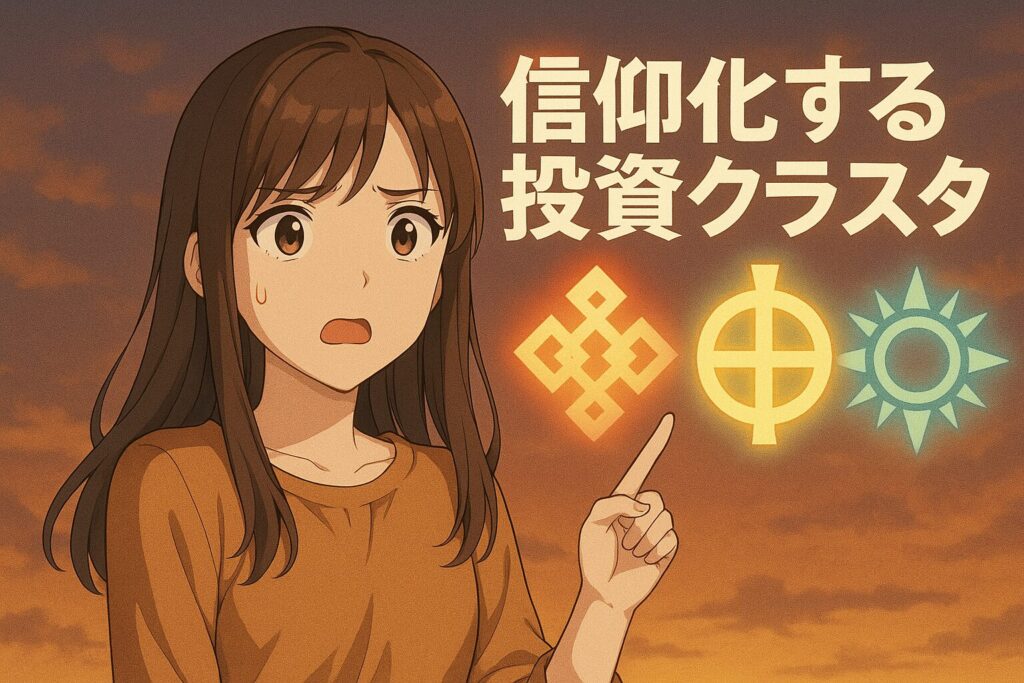
「安心=利益」ではないという誤解
投資クラスタにおいて、“安心できる銘柄”はとても人気があります。オルカン、S&P500、三菱商事、NTT──どれも「持っていて落ち着く」「人に話しても恥ずかしくない」銘柄です。しかし、ここで一つ冷静に考える必要があります。「安心だから利益が出る」わけではないということです。
会計的に言えば、企業の価値(バリュエーション)は将来キャッシュフローの割引現在価値で決まります。つまり、どれだけ利益を生み出し、それが安定して再投資・配当されるかにかかっています。「安心感」は評価に含まれません。
むしろ、多くの投資家が“安心”だと信じた銘柄ほど、市場価格にはその安心感がすでに織り込まれており、割高になっていることすらあります。これは、安心が利益を生むどころか、“錯覚としてのリスク”になっている状態です。
「安心して買える銘柄=すでに過小評価されていない銘柄」という逆説は、長期投資において忘れてはならない視点です。
利益と安心の“ずれ”がもたらす落とし穴
たとえば、三菱商事のような高配当銘柄は「持っていれば配当がもらえるから安心」と思われがちです。しかし、配当とは企業のキャッシュフローの使い道の一つであり、それが企業価値にどう影響するかは複雑です。
会計上は、内部留保を成長投資に回す企業と、利益を配当に回す企業では“資本効率”の観点で評価が分かれます。つまり、「配当=善」ではなく、「配当を出せるほど内部の成長機会が乏しい」という可能性もあるのです。
この構造を理解せずに、「配当あるから大丈夫」「人気銘柄だから下がっても戻る」と思い込んでしまうと、リスクの本質が見えなくなります。
投資は“物語”ではなく“数字”で成り立っている。だからこそ、安心と利益は常に分けて考えるべきなのです。
信仰が投資を鈍らせる構造
信仰が悪いという話ではありません。ある銘柄に愛着を持つことも、応援したくなることも、投資の魅力の一部です。しかし、それが「その企業を客観的に評価する目」を曇らせるなら話は別です。
オルカンにしても、S&P500にしても、それぞれ市場動向や経済環境によってリスク要因は存在します。たとえば米国株が長期的に低迷した場合、オルカンも当然その影響を受ける。しかし、“全世界に分散してるから安心”という信仰が強すぎると、その可能性すら検討されなくなります。
「安心だから大丈夫」という言葉の裏に、「本当は何が起きうるか?」という問いを置けるかどうか。それこそが、会計的思考の強みであり、信仰投資から脱却するための第一歩なのです。
“信じる投資”から“考える投資”へ──その転換こそが、あなたの資産を守る最大の戦略になるかもしれません。
結論:それでもあなたは、何を信じて投資しますか?
投資の世界には、「正解」が存在しない。
それなのに、SNSやコミュニティの中では、まるで一つの答えがすでに決まっているかのような雰囲気が生まれがちです。オルカンを持たないのは非常識、三菱商事を買ってないのは情弱。そんな空気の中で、私たちはいつの間にか「自分の投資」ではなく「他人の投資」をしてしまっているのかもしれません。
本来、投資は自分自身の価値観、ライフステージ、リスク許容度に基づいて組み立てるべき“個別設計”のはずです。それを“集団的安心感”によって一色に塗られてしまうと、「なぜそれを選んだのか?」という問いが曖昧になり、いざ市場が崩れたときに耐えられなくなります。
「信仰」は安心を与えますが、「思考」は強さを与えてくれます。
どんなに人気があっても、どんなにインフルエンサーが推していても、それがあなたにとって合理的かどうかは、最終的にはあなたしか判断できません。
時に孤独に感じるかもしれません。みんなが買ってる中、自分は違う選択をすることに不安もあるでしょう。でもそれこそが、投資の本質です。誰かの成功談ではなく、自分の数字で勝負すること。合理性と信念を両立させること。
“投資は科学か、宗教か”──この問いに答えはありません。
けれど、自分の中で信じられるロジックを持ち、その上で選び続ける限り、それは立派な投資です。
だから今日も、騒がしいタイムラインの中で、静かに問い続けてください。
「それ、本当に自分にとって合理的?」
そうやって思考するあなたこそが、“信仰の群れ”を抜け出した本物の投資家なのです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
財務諸表開示行動と投資者心理
企業の財務諸表開示の姿勢が投資者心理にどう影響するかを研究。SNSやIR情報に翻弄される集団の行動パターンが会計視点から分析され、信仰的投資への理解を深められる一冊です。
投資賢者の心理学
市場で成功した投資家の心理パターンをマンガ形式で学ぶ一冊。感情と数字のギャップを埋める具体的なケース分析は、SNS投資に染まりやすい読者にも刺さります。
図解 証券投資の経理と税務〈令和6年度版〉
最新の会計・税務処理に対応した実務書。ETFや株式など証券投資の裏側の仕組みがQ&A・図解で整理されており、「安心=利益」の錯覚を訂正する会計知識を提供します。
2024年度版 法人投資家のための証券投資の会計・税務
法人向けではありますが、仕訳例や実務処理が丁寧に解説されており、投資対象選定における「数字の裏付け」を強化できます。個人投資家にも有益な視点が詰まっています。
金融市場の行動経済学 ― 行動とマーケットに見る非合理性の世界
著者が金融市場における投資家や取引参加者の非合理な振る舞いを、「認知バイアス」「集団心理」「感情のゆらぎ」などの視点から解説。SNSやインフルエンサーによる“安心バイアス”が市場価格や株価形成にどう影響するかを、理論と実例を交えて学べます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21062574&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5875%2F9784794415875_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=14835624&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3518%2F2000003503518.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21419184&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7518%2F9784502517518_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21406873&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7100%2F9784539747100_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21552117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1502%2F9784296121502_1_52.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す