みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
家を買うって、本当に“情弱”の選択ですか?
マイホームを買うべきか、それとも賃貸で身軽に暮らすべきか――そんな論争に終止符を打つ視点を提供します。
インターネット上では「マンション買う奴は情弱(情報弱者)」なんて過激な言葉まで飛び交い、持ち家派VS賃貸派のバトルはヒートアップしています。でも本当に家を買うのは“情弱”なのでしょうか?
このブログを読めば、住宅購入の損得勘定だけでは測れない真実が見えてきます。ファイナンシャルプランナーや不動産のプロの知見、投資や会計の観点から、マイホームにまつわるお金のメリット・デメリットを徹底解説。
さらに、経済合理性だけでは語れない心理的な安心感や満足感といった「疑似資産」としてのマイホームの価値にも迫ります。
読み終える頃には、損得だけに惑わされず自分なりの答えを見つけるヒントが得られるでしょう。肩肘張らずカジュアルに、本音ベースでお届けします。お金と心の両面からマイホーム購入のリアルを深掘りしますので、将来の住まい選びにきっと役立つはずです。それでは本題に入りましょう。
目次
持ち家は本当に“負債”?お金の損得で考えるマイホーム

「家なんて買ったら損だ、賃貸の方がトク!」という声、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実際、投資や経済の目線で見るとマイホーム購入は“割に合わない”という主張には一定の根拠があります。例えばベストセラー『金持ち父さん 貧乏父さん』で有名なロバート・キヨサキ氏は、「居住用の住宅はお金を生まない負債だ」と断言しました。自宅は家賃収入などのキャッシュフローを生まない一方、ローン返済や維持費でお金が出て行く一方だからです。この考え方に影響を受け、「持ち家=負債」という見方が若い世代にも広まっています。
また、日本では高度成長期に「住宅神話」と呼ばれる「家は資産価値が上がるもの」という信仰がありましたが、現代ではその理屈は崩れています。にもかかわらず「家賃払い続けるのはもったいないから買った方が得」という意味不明な議論が未だに一人歩きしており、それが持ち家志向を支えている面もあります。しかし不動産市況が右肩上がりだった時代と異なり、今や購入から35年後には建物が古ぼけて価値が大幅に下がるケースが大半です。郊外の新築一戸建てやマンションも、年月を経れば「ぱっとしない物件」になりかねず、投資としてみた場合リターンが期待しにくいのが現実です。
さらに、お金の観点でマイホーム最大のリスクは長期ローンでしょう。多くの人は数千万円規模の住宅ローンを組み、30〜35年かけて返済します。これは自分の将来の収入をあてにした巨大な投資であり、資産そのものが生む収益に頼らない点で通常の不動産投資とは決定的に異なります。言い換えれば、家を買うことは自分自身にベットする行為なのです。終身雇用が崩れた現代、35年もの間ずっと安定して働き続けられる保証はありません。著名な実業家の堀江貴文氏も、「年収1000万円にも届かないサラリーマンが何千万円もの借金を35年ローンで抱えるなんて狂気の沙汰だ」と痛烈に批判しています。確かに、30年先の健康や雇用の状況など誰にも分かりません。ローン完済前に病気やリストラで収入が途絶えればたちまち行き詰まるリスクがあり、住宅ローンは人生を縛る重荷にもなり得ます。
そして見落とせないのは、住宅購入には目に見えないコストも多いことです。ローン利子はもちろん、購入時には印紙税や登記費用、火災保険・地震保険料、仲介手数料などもかかります。マンションなら毎月の管理費・修繕積立金、固定資産税も負担しなければなりません。これらは賃貸なら大家負担か家賃込みだった部分で、持ち家だとすべて自分持ちです。トータルで見ると、生涯支払う住居費は賃貸と持ち家で大差ない、もしくは持ち家の方が高くつく可能性もあります。そのため「結局お金の面では損」とする声が出てくるのです。
こうした数字上の損得勘定だけ見れば、「家を買うなんて情弱のすること」と揶揄する意見があるのも理解できます。実際、「賃貸派」の多くは自分のバランスシート(財政状態)を身軽に保ちたいという考えから持ち家を敬遠します。家を買えば資産と同額の負債を抱え、個人のBS(バランスシート)が一気に膨らむ。いわば「不動産」が「負動産」になる(不動産が負債に転じる)との皮肉もあります。流動性が低く現金化しづらい不動産を抱え、さらに固定資産税や維持費も発生するため、持ち家は重たい資産だというわけです。賃貸なら大きな借金を負わずに済み、ライフスタイルの変化に合わせて自由に住み替えられるメリットがあります。「身動きが取りやすいし、家なんかに縛られたくない」という感覚は、まさに賃貸派の利点でしょう。
極端な意見では、「今どき家を買うなんて時代遅れ、住宅なんて借りとけばいい」と切り捨てる向きもあります。堀江氏は持ち家派の心理を「不動産屋の不安煽りビジネスに乗せられているだけ」と喝破し、老後の賃貸不安を理由にする人を「なんて情弱でナイーブなんだ」と嘆いています。たしかに「高齢になると賃貸を借りられなくなる」というのは過度に不安を煽った説とも言えます。現実には公的支援や保証人サービスも広がり、高齢単身でも入居可能な物件は増えつつあります。それでもなお「老後の住まいが心配だから若いうちに家を買え」という文句は、営業トークの側面が強いでしょう。その点で、不安に駆られて慌ててマイホームを買うのは考えものです。「お金の損得だけ」を冷静に見れば、マイホーム購入は必ずしも経済的正解ではない――この事実はまず押さえておく必要があります。
家がもたらす“プライスレス”な安心感と行動力アップ

ここまで聞くと「やっぱり家なんて買わない方が良さそうだ…」と思うかもしれません。しかし話はお金だけで終わりません。マイホームにはお金では測れない心理的メリットがあるのも確かなのです。実は多くの人が家を欲しがる背景には、人間の深層心理や本能が関係しています。ファイナンシャルプランナーの関根氏は「人がマイホームを持つとホッとして落ち着く」とよく言われるのは、「巣作り本能」によるものだと指摘しています。人類は太古の昔から自分や家族のために巣(住処)を作ってきました。その本能が現代にも残っており、快適な住空間を所有すること自体が人間にとって自然な欲求なのです。特に子どもが生まれるタイミングで家を買いたくなるのは、鳥がヒナを育てるために巣を作るのと同じで、本能的な行動と言えるかもしれません。
持ち家には、賃貸暮らしでは得られない心理的な開放感があります。例えば賃貸では壁に穴を開けることすら躊躇しますが、自分の持ち家なら好きなようにリフォームや模様替えができます。壁一面にお気に入りの色を塗ったり、ペット用のステップを取り付けたりと住まいを自分好みにアレンジできる自由は、何物にも代えがたいものです。この「自由にできる!」という感覚は、住む人に大きな自己決定権の満足感を与えます。自分の城を自分の思い通りにできる喜びは、日々の生活の充実度を確実に高めてくれるでしょう。実際、「DIYで家をカスタマイズしているうちに愛着が湧き、家にいる時間が一番の幸せになった」なんて声もよく聞きます。持ち家だからこそ味わえる帰属意識や「やっぱり我が家が一番だ」という安心感は、多くの人にとって心地よいものです。
また、マイホームを持つことは精神的な安定剤にもなります。自分と家族が安心して帰れる場所があるという事実は、生活全体の安定感につながります。家があることで心にゆとりが生まれ、「ここが自分たちの帰る場所だ」という拠り所ができるのです。その結果、生活リズムが整い、仕事にも前向きに取り組めるようになる人もいます。実は「家を買ったら仕事を頑張るようになった」「ローンを背負ったことで責任感が増し、むしろキャリアアップの原動力になった」といった話も珍しくありません。ある種、マイホームは購入者にスイッチを入れる効果があるとも言えるでしょう。大きな買い物をした分「もっと稼がねば」と奮起したり、家族のためにと努力する姿勢が芽生えたりするのです。ローンというプレッシャーはありますが、それが良い意味でのモチベーションアップにつながるケースもあるわけですね。
一方で、持ち家は安心感と同時に不安も抱える二面性があります。マイホーム購入は「安心を買う一方で不安も買う行為」です。具体的には、「これでやっと一生住む家が手に入った」という安堵と、「何千万円もの借金を抱えて本当に大丈夫だろうか…」という不安がセットになるのです。住宅ローンには団体信用生命保険(団信)という仕組みがあり、万一ローン返済中に契約者が亡くなった場合はローン残高がゼロになります。そうした保障があるとはいえ、生きている限りは返済に追われるプレッシャーから逃れられません。「希望と不安」「光と影」が常につきまとうのがマイホーム所有の心理的特徴なのです。
それでも多くの持ち家派が口を揃えるのは、「それらを差し引いてもマイホームは最高の安心感を与えてくれる」という点です。家族と過ごした年月の思い出が詰まった我が家は、何ものにも代え難い宝物になります。実際、関根氏も「お金が無くてローン返済に不安で眠れなかった時期もあったが、それでも子どもたちに実家を作ってあげられて良かった」と振り返っています。自分が育った家や、家族と築いた我が家にはプライスレスな価値が宿るものです。そこには純粋なお金の計算だけでは表せない幸福感があります。もし将来子どもが「やっぱり実家が一番落ち着く」と言ってくれたら、それだけで家を買った甲斐があったと思えるでしょう。マイホームは、人に心理的安定や幸福感を与えてくれる最強の“疑似資産”とも言えるのです。
投資と生活、どちらの目線で見る?「安心のBSインフレ」を考える
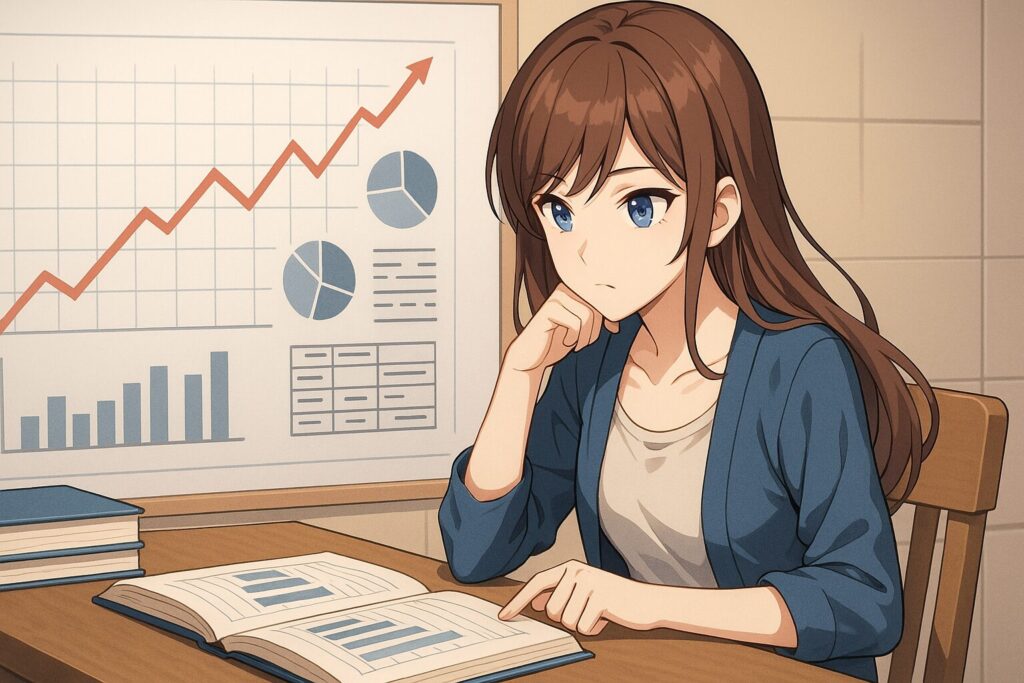
ここで改めて整理してみましょう。マイホームは資産か負債か?――この問いに対する答えは、一概には決まりません。それは「どの目線で見るか」によって評価が変わる二面性を持つからです。まず純粋な投資目線で言えば、前述のように自宅は収益を生まないため投資対象にはなりにくいです。特にローンを伴う場合、購入と同時に個人のバランスシート上は資産と同額の負債が計上され、資産と負債が一気に膨らむことになります。この現象を、仮に「BS(バランスシート)インフレ」と呼んでみましょう。手元資金ほぼゼロでも巨額の不動産を手に入れられる代わりに、負債も同時に膨れ上がる。帳簿の上では純資産が増えたように見えても、実質的にはローン完済まで自分のものではないのです。企業会計の視点で言えば、自己資本比率が低下しキャッシュフローは悪化します。いくら資産評価額が大きくなっても、それをすぐ現金化できない以上、財務的な身軽さは失われるわけです。
しかし一方で、生活者の目線から見ればマイホームは将来への備えという面も見逃せません。人生100年時代、老後までずっと家賃を払い続けることへの不安は誰しも感じるでしょう。持ち家であれば、ローンさえ完済すれば住居費の大部分から解放されます。定年退職して収入が年金だけになった時、毎月の家賃支払いが無いというのは大きな安心材料です。実際、多くの住宅ローンは定年頃に完済するスケジュールで組まれており、「老後の住まいは確保しておきたい」という考えが反映されています。老後に賃貸派だった人が改めて家を買おうとしても、高齢ではローン審査が厳しかったり資金的に難しかったりします。しかし持ち家派であれば、老後に住み替えやリバースモーゲージといった選択肢も持てます。例えば今の家を売って地方のコンパクトな家に移り住んだり、駅近マンションにダウンサイジングしたりと、持ち家が資金源にもなり得るのです。さらにリバースモーゲージを活用すれば、自宅を担保にお金を借りて、亡くなった時に家を処分して返済に充てることもできます。こうした制度を使えば持ち家も実質的に流動資産として機能し得ます。
要するに、持ち家は人生後半のセーフティネットになり得るのです。賃貸で一生暮らす場合、生きている限り家賃の支払いは終わりませんが、持ち家ならある時点で住宅費が頭打ちになります。家は確かに維持費や税金がかかる「コスト」でもありますが、長い目で見れば「住まいを先払いしておく」行為とも言えます。月々のローン返済はある意味強制貯蓄のような役割も果たし、払い終わればそれ相応の資産が手元に残る(市場価値がどうあれ、少なくとも無償の住処が得られる)。この点を踏まえると、「損得勘定では負債だけど、将来の安心を買う保険のようなもの」とも言えるでしょう。銀行のコラムでも「ローンによるマイホーム購入はB/S上資産を大幅に増やす一方、負債も増やす行為。当然B/Sやキャッシュフローは悪化する。しかし愛する家族のことを考えれば多少の損得は度外視する場合もあり、プライスレスな部分も考慮して多面的に検討すべき」と述べられています。まさに投資(お金)と生活(心)のバランスシートをどう見るかがポイントなのです。
最後に、持ち家派がよく言う「マイホームは究極の安心資産」というフレーズについて考えてみましょう。経済的なリターンは乏しくとも、マイホームには見えない価値のインフレが起きます。年月を経て家族との思い出や愛着が積み上がることで、その家の「心の資産価値」はどんどん膨らんでいくのです。購入当初は借金だらけのバランスシートに不安を覚えたとしても、やがてローン残高が減り資産が純資産へと振り替わっていくにつれ、手に入る安心感は増していくでしょう。たとえ市場評価額は下がっても、「我が家」という心の豊かさはむしろ上がっているかもしれません。こう考えると、マイホームは心理的最強の“疑似資産”と言っても過言ではないのです。
おわりに:マイホーム論争、その先にあるもの
持ち家VS賃貸――長年繰り返されてきた不毛な論争かもしれません。しかし本当に大切なのは、その人にとって何に価値を置くかではないでしょうか。お金の損得だけを追求するなら、確かにマイホームは「負債」に見えるでしょう。けれど、人が安心して幸せに暮らすための拠り所と考えれば、マイホームほど心強いものもありません。経済的合理性と心理的充足、その両方を天秤にかけて初めて見えてくる答えがあります。
このブログで見てきたように、家を買うことは光と影の両面を持ちます。巨大なローンという重荷を背負う影の部分がある一方で、家族の笑顔や「我が家」という掛け替えのない光も手に入る。どちらが優先かは、人それぞれの人生観次第です。だからこそ「持ち家派=情弱」「賃貸派=正解」といった単純なレッテル貼りに意味はありません。損得勘定に囚われず、プライスレスな価値まで含めて考えることが大事なのです。
最後に一つ、感動的なエピソードをご紹介しましょう。ある家庭では、親が長年かけて住宅ローンを返済し終えた日に、子ども達が手作りの「ありがとう」のカードを渡したそうです。「この家で過ごした時間は一生の宝物だよ」と書かれたカードを見て、親御さんは涙が止まらなかったとか。確かに通帳残高だけ見れば家を買わず投資に回した方が増えたお金もあったかもしれません。でも、その瞬間に感じた満たされた気持ちや家族の絆は、お金では決して買えないものです。マイホームとは、そんな人生の幸せを実感させてくれる舞台なのかもしれません。
経済的には必ずしも正解じゃないかもしれない。それでも心理的には最強の“資産”になり得る――それがマイホームという存在です。あなたにとって本当に大切なものは何なのか? もし安心や家族の思い出といった価値を重んじるなら、マイホーム購入は決して情弱の愚行などではなく、人生で最も賢い選択になるでしょう。お金と心のバランスシートを自分なりに描きながら、ぜひ後悔のない住まい選びをしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。あなたの選択が、どうか素晴らしい未来に繋がりますように――。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『マンションバブル41の落とし穴』
最新の不動産バブルやマンション価格の動向に詳しく、実際に“得する”住宅購入を見極める視点を提供。セクション1の「経済的視点」にぴったりの一冊です。
『グレートリセット後の世界をどう生きるか 激変する金融、不動産市場』
金融・不動産市場の構造変化を分析し、これからの住宅購入や資産形成に必要な視野を提示。長期ローンや市場リスクへの備えに通じます。
『2030年の不動産』
コロナ後、少子化、テレワークなど社会変化を踏まえた未来予測を解説。住宅市場の見通しと、自分に合った住まいを選ぶヒントが学べます。
『世界のプロが学ぶ会計の教科書 資産負債アプローチで使える知識を身につける』
会計的視点で「BSインフレ」や資産・負債の真価を理解するための基礎書。セクション3のバランスシート分析にもフィットします。
『100年使える「箱の家」をつくる』
長寿命住宅=長期的視点での住まい選びに焦点を当て、「建物の耐久性」や「土地と立地」のバランスを解説。セクション2・3の心の安心感と財務的分析の両輪にマッチします。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21249061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4712%2F9784098254712_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21365220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4767%2F9784098254767_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21522725&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0260%2F9784296120260_1_51.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20915841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5983%2F9784296115983_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19295225&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2114%2F9784295402114.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












コメントを残す