みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
“儲からない”はずの図書館が、なぜあなたの人生にいちばん大きな配当を出せるの?
あなたは最近、図書館に足を運びましたか? もし「行ってないな…」という人も、このブログを読み終える頃には図書館に対する見方がガラリと変わるかもしれません。図書館は市民が無料で本を借りたり静かに勉強したりできるありがたい場所ですが、お金儲けにはまったくならない“赤字覚悟”の施設でもあります。それなのに世界中どこに行っても図書館が存在し、何百年も存続してきたのはなぜでしょう?
本稿では、その理由を「図書館=知識の公益配当装置」というユニークな視点から紐解いていきます。読めば、あなたは「儲からないのに無くならない図書館」という経済的に不合理な奇跡の秘密を知ることになるでしょう。そして、社会人として“コスパ”だけでは測れない投資の本当の価値に気づき、知識を配当として受け取ることの贅沢を再発見できるはずです。
図書館はなぜ“赤字”でも必要とされるのか

一見すると、図書館は財政的に見ると常に赤字の施設です。そもそも日本の法律(図書館法第17条)では、「公立図書館は入館料その他いかなる対価も徴収してはならない」と定められており、利用者からお金を取ってはいけないことになっています。つまり図書館は本を貸し出したりサービスを提供しても直接的な収入を得られず、運営費用はすべて税金でまかなわれます。当然、自治体から見れば図書館は収益を生まないコストセンターであり、厳しい財政状況下では予算削減のターゲットにもなりがちです。事実、近年は多くの自治体で図書館予算が年々削られ、正規職員の採用も抑えられているため、図書館で働く人の約75%が非正規雇用という状況にもなっています。こうした運営の苦境、ご存知でしたか?
このように経済的な合理性だけで見れば「儲からない施設」になってしまう図書館ですが、それでも社会から必要とされ続けています。その背景には、図書館が単なる娯楽施設ではなく社会に不可欠な公共インフラだという認識があります。図書館学者の薬師院はるみ氏は「図書館は本そのものを届ける場所というより、“本に記録された情報・文化・知識を万人の手に届くものにする”公的な仕組みです」と述べています。図書館は自治体が住民に提供する知的インフラであり、民主主義社会において誰もが知識や情報にアクセスできるよう保障するための装置なのです。だからこそ、「公共施設とは採算が取れなくても(極端に言えば赤字でも)人々の生活に絶対必要な施設のことだ」という指摘もあります。要するに、図書館は利益が出なくても存在し続けることが社会的に正当化される、特別な存在なのです。
しかし現実には、自治体の財政論理と図書館の使命との間でジレンマも生じています。ある研究レビューでは、公立図書館における「自治体(お金)の論理」と「図書館(知の奉仕)の論理」の不整合が問題の根底にあると指摘されています。簡単に言えば、「お金にならないけど大事なもの」をどう扱うかという葛藤です。それゆえ近年では、図書館も生き残りを図るために民間の指定管理者制度を導入したり、カフェを併設して利用者数を増やそうとするなど、サービス向上と経費削減の両立に挑んでいます。とはいえ、「本来は公共施設である図書館が存在意義をアピールしなければならない状況」に違和感を覚える専門家もいます。図書館は本来、利益や集客を追求する商業施設ではなく、市民に知の配当を届ける公益施設なのですから。
こうして図書館は収支上は赤字でも、社会にとって必要不可欠な「黒字以上の価値」を提供していると考えられています。次のセクションでは、その図書館が生み出す計り知れない社会的価値について具体的に見ていきましょう。
図書館が社会にもたらす計り知れない価値
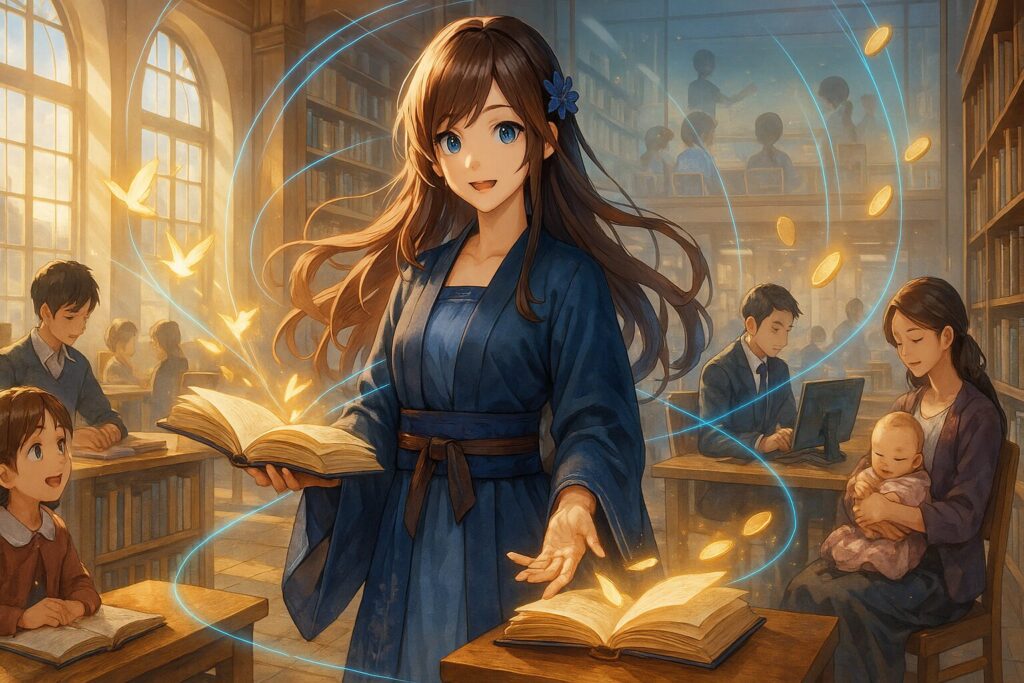
図書館が「儲からない」のは確かに事実ですが、それはお金に換算できない価値を提供しているからとも言えます。では、その社会的価値とは具体的に何でしょうか?いくつか挙げてみましょう。
- 知識への平等なアクセス:
図書館は老若男女、富裕層でも困窮者でも関係なく、誰もが等しく知識や情報にアクセスできる場を提供しています。本来数千円する専門書やベストセラー小説も無料で借りられるのは、利用者にとって大きな恩恵です。経済状況に左右されずに学び、楽しめる機会を提供する点で、図書館は社会の知的格差を是正する役割を果たしています。 - 生涯学習と自己成長の場:
図書館は学生の勉強だけでなく、社会人のスキルアップや子どもの読書習慣づけにも貢献しています。資格試験の参考書からビジネス書、育児書まで幅広い蔵書があり、人生の様々な局面で学び直しを支えてくれる場所です。図書館で開かれる読書会や講演会、児童向けおはなし会などのイベントも、人々の視野を広げ教養を深めてくれます。まさに「人と、心を育てる図書館」なのです。 - コミュニティと社会包摂:
静かに本を読むだけが図書館の役割ではありません。地域の情報拠点や交流の場としての機能も重要です。例えば就職情報の提供やパソコンの無料利用サービスにより、職探し中の人を支援したり、調べものをする学生をサポートしたりしています。居場所のない高齢者やホームレスの方にとって、図書館は安心して過ごせる数少ない公共空間にもなっています。社会のあらゆる人々を包み支える懐の深さこそ、図書館が持つ優しさと言えるでしょう。 - 経済効果と暮らしの質の向上:
一見すると意外かもしれませんが、図書館には経済面での波及効果もあります。図書館の建設や運営が地域に雇用を生み、利用者が図書館を訪れることで周辺のカフェや書店の売上が増えるケースもあります。また、図書館利用者へのアンケートでは「図書館のおかげで暮らしの質(QOL)が向上した」と感じている人が多いとの報告もあります。無料で利用できる図書館を活用して自己啓発に努めた結果、良い仕事に就けたり生活が豊かになったりすれば、それは経済的な効果と同時に人生の価値向上と言えるでしょう。
こうした多面的な社会的価値を「見える化」するために、世界各地で図書館の投資対効果(ROI: Return on Investment)を測定する研究も行われています。ROIとは簡単に言えば「投資した1円(1ドル)が何円分の利益を生んだか」を示す指標です。もちろん図書館の価値を完璧に数字で表すのは難しいのですが、それでも興味深い結果が数多く報告されています。例えば、米国フロリダ州では「図書館に1ドル投資すると約6.54ドルの便益がある」と試算されています。この中には、利用者が本を購入せずに済んだ金額や、図書館の支出が地域経済に波及して生まれる生産誘発効果などが含まれています。同様に、ピッツバーグ市のカーネギー図書館の調査では「1ドル投資あたり3〜6ドルの利益」と算出され、年間9,100万ドル(約101億円)もの経済効果を地域にもたらしていることが明らかになりました。さらにフロリダ州全体の分析では、図書館への支出1ドルが地域のGDPを9.08ドル押し上げ、州全体の所得を12.66ドル増加させるとのデータもあります。数字の細部は研究によって異なりますが、総じて「図書館は投入した費用以上の価値を社会に還元している」と示唆する結果が多いのです。図書館情報学の国際的な調査を行うIFLA(国際図書館連盟)も、「図書館は投資額以上の価値を生み出しているという研究は数多く存在する」と報告しています。
要するに、図書館という存在は金銭的な利益を生まない代わりに、人々の知識・生活・地域社会に莫大なリターンをもたらしているのです。利益が目に見える形の「配当金」ではなく、知識や幸福度といった形で我々一人ひとりに配当されていると言えるでしょう。それこそが図書館が経済的合理性だけでは計れないゆえんであり、多くの人に愛され支えられてきた理由なのです。
「知の配当」を享受する投資としての図書館

図書館が社会にもたらすリターンは、企業の株式に例えるなら「配当金」のようなものです。ただしそれはお金ではなく「知識」や「機会」という形で私たちに配られます。冒頭で「図書館=知識の公益配当装置」と称しましたが、図書館とは市民が行う知的な投資から生まれる果実を、万人に配当する仕組みだと言えるでしょう。
考えてみてください。私たちは税金という形で図書館に出資し、その見返りとして無料で本や情報を得ています。いわば市民全員が「知の株主」であり、図書館はその出資に対するリターンを知識という価値で還元しているのです。面白いことに、一人の市民が図書館から多くの本を借りても、他の市民の取り分が減るわけではありません。知識は共有されても減らないという性質を持つため、この配当は皆で分かち合うほど社会全体が豊かになるのです。企業の配当金とは違って、「配れば配るほど増えていく」──図書館にはそんな魔法じみた側面すらあります。
さらに長期的に見れば、図書館への投資は将来の社会コスト削減や経済成長にも貢献します。人々が図書館で学び教養を身につければ、雇用機会が広がり生産性が上がる可能性があります。知識へのアクセスが犯罪や貧困の抑止につながるという指摘もあり、図書館は福祉や治安維持の面でも間接的な効果を持ちます。経済学者の宇沢弘文氏は公共図書館のことを直接には言及していませんが、道路や水道のように社会の基盤となる「社会共通資本」という概念を提唱しました。知識を供給し災害時には一時避難の場にもなる図書館は、まさに社会共通資本として扱うべき存在ではないでしょうか。短期的な採算には合わなくても、長期的・公共的な視点では図書館は未来への投資そのものなのです。
では最後に、この「経済的に不合理な奇跡」である図書館が私たちに教えてくれるメッセージについて考えてみましょう。それは、本当に大切な価値はお金では測れないというシンプルな真実です。豊かな知識や文化、誰もが学べる機会、困ったときに立ち寄れる居場所──それらは帳簿上は利益を生まないかもしれません。しかし、それらこそが私たちの暮らしを豊かにし、社会を前に進める原動力であることを、図書館という存在が示してくれているのです。
おわりに:奇跡の共有者として
図書館が黒字か赤字かという問いの答えは明白です。お金の勘定では赤字かもしれない、しかし社会の損益計算書では計り知れない黒字──それが図書館です。経済の論理だけでは説明がつかない“不合理”さで今日も開館し、人々に知と喜びを配り続ける図書館という存在。それは冷徹な効率性だけが重視されがちな現代において、ひときわ人間的で希望に満ちた奇跡と言えるでしょう。
この記事を読み終えた後、ぜひ最寄りの図書館に立ち寄ってみてください。何万冊もの本が並び、子どもから高齢者まで思い思いに知の世界に浸っている光景は、よく考えるととても贅沢で奇跡的なものです。それを自分も享受できていることに気づけば、図書館の見えない価値にきっと心が震えるはず。そして、その奇跡の共有者として、知識という配当を存分に受け取りましょう。図書館はきっと、何度でもあなたに新たな発見と感動をもたらしてくれるに違いありません。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『新訂 図書館の法令と政策 ― 教育・文化・自由を支える制度』
最新の法改正を反映し、公共図書館・学校図書館・大学図書館までを横断して制度と政策の全体像を整理。図書館の「無料原則」や住民サービスの根拠条文を押さえたいときの決定版。
『2050年の図書館を探る ― 何が変わり・変わらないのか』
25年先を見据え、DX・コミュニティ機能・学びの場としての進化を多角的に展望。教育投資の長期的ROI(人材育成・リテラシー)を語る際の“未来図”資料として有用。
『新しい時代の図書館情報学(第3版)』
司書課程対応のスタンダードを最新統計で更新。図書館の役割・制度・サービスの基礎を短時間で俯瞰でき、ブログの前提整理や数値のあたりを付けるのに便利。
『教育の経済価値 ― 質の高い教育のための学校財政と教育政策』
教育が生む経済的・社会的便益と、継続的な公共投資の必要性をエビデンスで解説。図書館を“教育投資の一部”として位置づける論を補強できる。
『生涯学習・社会教育行政必携(令和8年版)』
最新の制度・通知・実務情報を網羅する実務書。自治体が図書館を“生涯学習の中核”としてどう運用・連携するかを具体的に押さえられる。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21437977&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4015%2F9784883674015_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21528925&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0416%2F9784816930416_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21431636&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2397%2F9784641222397_1_105.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21109903&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6563%2F9784750356563_1_17.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21588522&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7421%2F9784474097421_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す