みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
あなたの根回し、投資回収できていますか?
「根回しって、結局“昭和の慣習”でしょ?」——そう思っているなら、今日から見え方が変わります。根回しは“時間を食う面倒事”ではなく、プロジェクトのボラティリティ(不確実性)を下げ、成功確率を引き上げるためのリスク投資です。本記事では、日本の意思決定文化を尊重しつつ、ファイナンスの物差しで“やる/やらない”を判定する方法を提示します。読み終わる頃には、次の3つが手に入ります。
- 「事前合意=ボラティリティ低下→成功確率↑」のメカニズム
なぜ根回しが意思決定の揺れ幅を縮め、実行段階でのブレや差し戻しを減らすのか。確率と分散の言葉で説明します。 - ロジ/利害/情の“三層シナリオ設計”フレーム
資料のロジック(事実・数字)だけでなく、各ステークホルダーの利害(損得・KPI)と情(面子・不安・安心材料)までを織り込む設計図を具体化します。会議室に入る前に、どの順序で誰に何を渡すかがクリアになります。 - 「根回しコスト<やり直し特損」を数式化した投資判定式
NPV(正味現在価値)で“根回しの費用対効果”を即断できるシンプルな不等式を提示。
たとえば簡易形:
根回し実施 ⇔ C_nema < Δp × ΔV + Δr × C_rework
(C_nema=根回しコスト、Δp=成功確率の上昇、ΔV=成功と失敗の価値差、Δr=やり直し発生確率の低下、C_rework=やり直し一回あたりの特損)
「何人×何時間まで根回しOK?」が、感覚ではなく数字で説明できます。
ターゲットは、日々プロジェクトを前に進める20〜30代のビジネスパーソン。意思決定工学×ファイナンスの視点で、根回しを“説明可能な投資行為”にアップグレードします。この記事の主張はシンプルです。根回しは“丁寧さ”ではなく“分散コントロール”であり、NPVで見ればやるかどうかは一発で決まる。 そのためのフレームと数式、使い方を、実務に落ちる粒度で解説します。
目次
なぜ「根回し」は“投資”と言えるのか

会議前の根回しは、単なる礼儀でも社内政治でもありません。ファイナンスの言葉に置き換えると「不確実性(ボラティリティ)を下げて、成功確率を上げるためのリスク投資」。ここでは、初心者でもすぐ使える直感とカンタン数式で、根回しの価値を見える化します。
失敗コストの正体は「差し戻し+再稟議+機会損失」
プロジェクトが会議で否決・保留になると、再資料作成や追加検討、関係者の再集約が発生します。これが差し戻しコスト。さらに、意思決定が遅れたぶん市場の好機を逃す機会損失も膨らみます。たとえば新キャンペーンの承認が1か月遅れると、繁忙期を逃して売上が月100万円減るかもしれない。実は根回しの1〜2時間より、やり直し1回の方が桁違いに高いのが現実です。だからこそ「根回し=コスト削減の先行投資」という発想が効きます。
ボラティリティを下げる=「分散を小さくし、確率を動かす」
会議はサイコロではありません。出席者の理解度・不安・利害がばらつくほど、結論は揺れます。根回しとは、事前に論点を潰し、反対の理由を細かく“分解”して処理する行為。すると「想定外のツッコミ」や「会議中の感情のブレ」が減り、結論の分散が縮む=可決・条件付き可決に着地しやすくなります。直感的に言えば、会議を“初見プレイ”から“チュートリアル済みプレイ”に変えるイメージ。プレイの上達(理解共有)が成功確率pを底上げし、同時に差し戻し発生確率rを下げます。
5分で使える「根回しNPV」—やるか・やらないかの不等式
根回しを投資判断する最低限のパラメータは5つだけです。
- Cₙ:根回しコスト(人数×時間×時給相当)
- Δp:成功確率の上昇幅(例:0.35→0.50なら0.15)
- ΔV:可決時と否決時の価値差(粗利・NPV差など)
- Δr:差し戻し発生確率の低下幅
- Cᵣ:差し戻し一回あたりの特損(作業+遅延の損失)
判断式はシンプルにこうなります。
根回し実施 ⇔ Cₙ < Δp × ΔV + Δr × Cᵣ
ミニ例で感覚を掴みましょう。
- 根回し:4人×0.5h×8,000円/h=Cₙ=16,000円
- 事前調整で:Δp=0.15(賛成増)、Δr=0.30(差し戻し減)
- プロジェクト価値差:ΔV=1,000,000円
- 差し戻し特損:Cᵣ=500,000円(作り直し+1か月遅延の機会損失)
右辺=0.15×1,000,000+0.30×500,000=150,000+150,000=300,000円
左辺=16,000円
→ 300,000>16,000 なので「根回しはやるべき」。わずか30分の事前調整が、30万円分の期待価値を生む計算です。
—ポイントは、「丁寧だからやる」ではなく「期待値が上がるからやる」に言い換えること。パラメータは厳密でなくてOK。チームでざっくり見積もって、“右辺が左辺を十分に上回るか”だけを見ます。右辺が小さいなら、やることは2つ。①根回しの質を上げてΔp/Δrを伸ばす(論点の当たり方を変える、ステークホルダーの順番を入れ替える)。②根回しのやり方を軽量化してCₙを下げる(短い1対1、資料は箇条書き、決裁者の懸念だけ先に潰す)。この2軸で設計すれば、多くの案件で「短く深い根回し」が最適解になります。
最後に、この式の肝は“価値差ΔVを具体化する”こと。売上や粗利だけでなく、ブランド毀損の回避や重要KPIの前倒しも数字化して入れてください。価値が見えると、根回しの時間は“気合い”ではなく投資額に変わります。
ロジ/利害/情でつくる“根回しシナリオ”

「正しい資料なのに通らない…」その多くは“ロジック不足”ではなく、“設計の層”が足りないせいです。根回しは、ロジ(論理)/利害(損得)/情(感情・場)の三層をそろって設計してこそ効きます。ここでは初心者でもすぐ試せる、三層の作り方と順番をやさしく解説します。
ロジ:まず“結論→理由→根拠”を90秒に圧縮する
ロジは「正しさの芯」。でも厚い資料は会う前には読まれません。なので90秒ピッチを用意しましょう。
- 結論:今回の意思決定で“何をYesとしてほしいか”。
- 理由:数字で2〜3点だけ(例:粗利+〇%、回収◯ヶ月、カニバなし)。
- 根拠:前提・計算式・比較案。前提差分(どの前提が結果を最も動かすか)も一枚で示す。
さらに、選択肢比較表を作ります。A案・B案・据え置き案を横並びにし、NPV、投下コスト、主要リスク、代替案時の損失(機会損失)を記載。ここまでで相手の頭の中にΔV(可決と否決の価値差)が入ります。
ポイントは「読み手が“自分の言葉”で語れるか」。相手が第三者に説明しやすいほど、会議当日の“想定外質問”が減って分散が縮む=反対が出にくくなります。
利害:ステークホルダーのKPIに“自分ゴト変換”する
次に「相手のKPIで語る」。まずステークホルダー表を作ります。
- 誰が:決裁者、実務責任者、関連部門、現場。
- 今のKPI:売上、粗利、在庫回転、CS、開発リードタイムなど。
- メリット:その人のKPIがどう上がるか(WIIFM=What’s In It For Me)。
- 懸念:予算・人手・失敗時の責任。
- 交換条件:リソース補填、リスク分担、スモールスタート等。
この表に、数字で“小さな配分”を添えます(例:「広告費の◯%を移し替え」「工数◯人週は他案件を延期」「成果配点の◯%をチームに付与」)。利害は“口約束感”だと効きません。配分・時期・責任分界を小さくても具体にすると、Δp(賛成増)が一気に伸びます。
コツは優先順。①影響力が強い人、②実務が詰まる人、③決裁者の順で1on1。上流で「利害の芯」を固めてから、最後に決裁者へ“もう反対理由が残っていない状態”で入るのが鉄板です。
情:不安とメンツを先に“安全化”する
人は“正しいから”ではなく、“安全だと感じるから”動きます。ここで使うのが情の設計。
- メンツの確保:「あなたの懸念を軸に対策した」と事前に名指しでクレジットする(例:「在庫リスクは◯◯さん案で回避」)。
- 不安の分解:最も怖いのは“責任の帰着”。パイロット版(限定ユーザー・限定期間)を提示し、撤退条件を先に合意しておく。
- 言い換え:「許可してください」より「リスク低減済み案の最終確認」。「検討します」より「2週間の実装→指標△以上で本格移行」など、行動が小さく区切られていると人はYesしやすい。
- 反論先出し:「コスト高では?」→“高い時の条件”を先に出し、代替も示す。「もし◯◯ならB案で回避」。反対の余地を残したYesは、会議での対面反論を減らし、Δr(差し戻し確率の低下)に効きます。
- 場の整え:資料は1枚要約+補遺。会議前に要約だけ配り、当日は“論点決定”に時間を使う。席順や誰が最初に口火を切るか(序盤に中立〜賛成の人を置く)も、立派な“情の設計”です。
三層を重ねると、式の中身が具体になります。ロジはΔVの納得、利害はΔpの押し上げ、情はΔrの引き下げ。 つまり“勝ちやすく、やり直しにくい”状態を事前につくること。最小限の根回しでも、設計の順番(ロジ→利害→情)を守るだけで期待値は大きく動きます。今日から1案件、三層表をつくって1on1に臨んでみてください。驚くほど会議が“穏やかに”終わるはずです。
「根回しコスト<やり直し特損」をサクッと数式化する
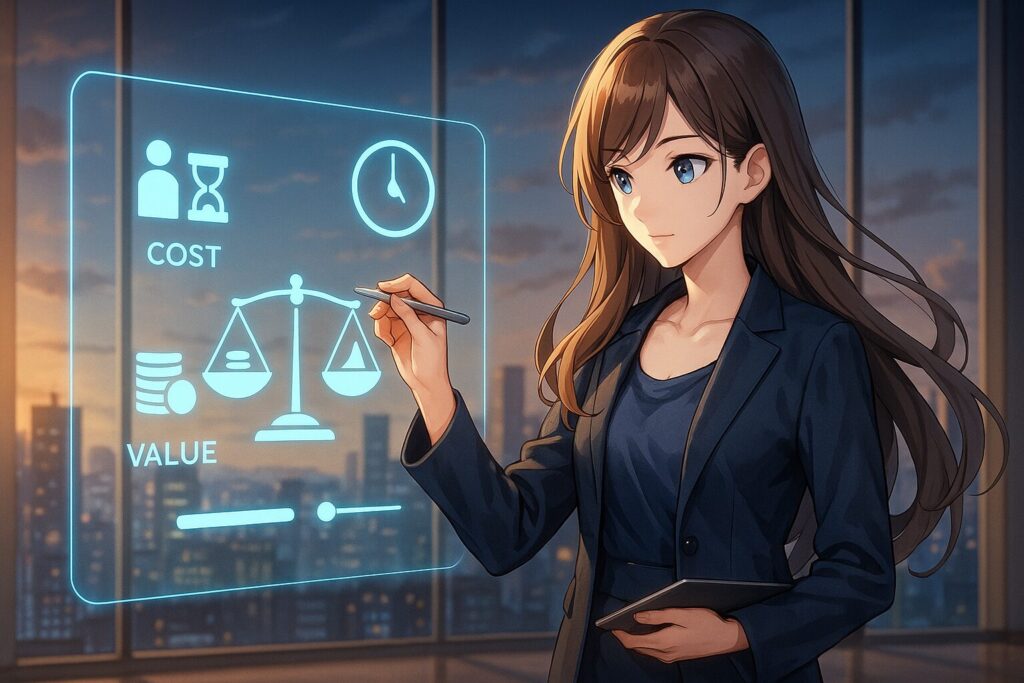
ここでは、根回しにかける時間と手間が“本当に見合うのか”を一行の不等式で判断できるようにします。数式といっても小学生レベルの足し算・掛け算だけ。電卓なしでも3分で判定できます。
判断式はこれだけ
使うのは次の一行です。
根回しをやる ⇔ Cₙ < Δp×ΔV + Δr×Cᵣ
- Cₙ(根回しコスト)=(関与人数)×(1人あたり時間[h])×(時給相当)
- Δp(成功確率の上昇)=根回し後p−前p(例:0.35→0.50なら0.15)
- ΔV(可決と否決の価値差)=承認時のNPV−否決/延期時のNPV
- Δr(差し戻し確率の低下)=根回し前後の“やり直し発生確率”の差
- Cᵣ(やり直し特損)=再作業工数+遅延の機会損失(1回あたり)
直感的には、右辺=根回しで増える“期待価値”、左辺=払う時間コスト。右>左なら投資妙味あり、です。
3分クイック見積もり手順
Step1|Cₙを出す
関わるのは誰?何分?をざっくり積む。例:4人×30分×8,000円/h=16,000円。
Step2|ΔpとΔrを決める
「論点が前もって潰れる分、可決にどれだけ寄る?」をチームでざっくり。反対主因を1〜3個つぶせるなら、Δpは0.1〜0.2、Δrは0.2〜0.4が多い感覚値。
Step3|ΔVとCᵣを置く
ΔVは“この案件が通ったら粗利やNPVでどれだけ得か”。Cᵣは差し戻し1回で失う時間×時給+遅延1か月あたりの粗利で概算。
Step4|代入して判定
右辺と左辺を比べて、右が大きければGO。迷う時は最悪値(ΔpとΔrを半分に、Cᵣを8割に)でも右>左かチェック。
“最大根回し時間”を逆算する
忙しい現場では「どこまで根回ししていいの?」を秒で決めたい。そこで許容根回し時間の上限 h*を逆算します。
h* =(Δp×ΔV + Δr×Cᵣ)/(関与人数×時給)
このh*以内に収めるのが基本ルール。例えば、Δp=0.12、ΔV=120万円、Δr=0.25、Cᵣ=40万円、関与3人、時給6,000円なら、
右辺=0.12×1,200,000+0.25×400,000=144,000+100,000=244,000円
h*=244,000/(3×6,000)=13.5時間。
3人合計で13.5時間=一人あたり約4.5時間まで根回し可。ここから逆に「1on1各30分×6人+10分フォロー」で設計すればOKという具合です。
例題:販促A/Bの承認
- Cₙ:PM+営業+制作+データ担当の4人で各20分→10,600円(時給8,000円/人で端数丸め)
- Δp:反対の主因が“在庫リスク”と“広告流入の質”。事前に在庫上限と品質閾値を決めるので0.38→0.53、Δp=0.15
- Δr:差し戻しは3割→1割、Δr=0.20
- ΔV:可決で繁忙期に間に合うと粗利+120万円、否決/遅延なら±0→1,200,000円
- Cᵣ:再稟議+1か月遅延で600,000円
→右辺=0.15×1,200,000+0.20×600,000=180,000+120,000=300,000円
左辺=10,600円。余裕でGOです。最悪シナリオ(Δp=0.07、Δr=0.10、Cᵣ=500,000)でも右辺=0.07×1,200,000+0.10×500,000=84,000+50,000=134,000円>左辺。
現場でのショートカット
- Δp/Δrのコツ:“論点の数”ではなく“結節点の数”で見積もる。決裁者が気にする3点のうち2点を先に潰せるなら、Δpは0.1以上のことが多い。
- Cᵣのコツ:工数だけでなく遅延の機会損失(粗利/週×遅延週数)を必ず入れる。ここを漏らすと根回しが過小評価になりがち。
- h*運用:h*の30〜50%を“最低根回し枠”に、残りは“追加論点が出た時のバッファ”にする。
以上。数式はシンプルですが、意思決定の“納得感”は劇的に上がります。「なぜ今30分の1on1を回るのか?」が数字で説明できるからです。チームで一度テンプレを作り、案件ごとにサクッと代入して運用してください。会議は“度胸”ではなく期待値設計で勝てます。
結論|根回しは“丁寧さ”ではなく、意思決定のリターンを底上げする投資
最後にもう一度、ポイントをやさしく一本に束ねます。根回しは「礼儀」や「政治」のためにやるのではありません。意思決定のボラティリティを下げ、成功確率を上げ、やり直しの特損を避けるための投資です。ファイナンスの目で見ると、私たちがやるべきことは明快でした。
- 事前合意は“分散”を縮める。初見の驚きを消し、論点を事前に潰すことでΔp(成功確率の上昇)が生まれる。
- 情報の抜けや不安を分解して処理すると、Δr(差し戻し確率の低下)が起きる。
- その効果は、Δp×ΔV+Δr×Cᵣという“期待価値”に変換できる。
- もしそれが根回しコストCₙを上回るなら、根回しは投資として正、というだけの話。複雑な理屈はいりません。
実務では、「ロジ/利害/情」の三層設計があなたの味方です。ロジでΔV(通ったとき・通らないときの価値差)を短く示し、利害で相手のKPIに変換し、情でメンツと不安を先に安全化する。順番は、ロジ→利害→情。この順で1on1を回すだけで、会議室の空気は穏やかに、議論は短く、決定は強くなります。根回しを“長く・重く”する必要はありません。今日からは、h*=(Δp×ΔV+Δr×Cᵣ)/(人数×時給)で上限時間を逆算し、短く深い根回しに切り替えてください。上限の30〜50%を最低枠、残りをバッファとすれば、忙しい現場でも回せます。
そして、数字は“自分を守る盾”になります。
「なぜ今、30分の1on1が必要?」と問われたら、静かにこう返せます。
「この30分で、期待価値が30万円ふえるからです」。
根回しの会話が、単なる“お願い”から投資判断の言語に変わる瞬間です。
思い出してください。再稟議、作業やり直し、繁忙期を逃す遅延——これらは見えにくいけれど大きな損失でした。チームの疲弊も、機会損失も、すべてはCᵣに含まれます。あなたが今日、会議前に10分だけ要約スライドを磨き、主要ステークホルダーに1本の電話をかける。その小さな行動が、未来の1か月を救います。根回しは時間を奪うのではなく、未来の時間を買い戻す行為です。
最後の背中押しを。完璧を待たなくて大丈夫。推定でいい、ラフでいい。右辺(Δp×ΔV+Δr×Cᵣ)が左辺(Cₙ)を上回りそうなら、もうGOです。今日の案件で、三層シナリオの表を作り、3人にだけ先に当たってみましょう。会議の冒頭で、中立の一人が「事前に聞いていて、納得しています」と言うだけで、勝負は半分ついています。根回しは文化ではなく、確率と期待値のデザイン。あなたの意思決定は、もっと速く、もっと強く、もっと穏やかにできる。さあ、次の会議を“初見プレイ”から“勝ち筋プレイ”に変えていきましょう。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法
“決める瞬間”を構造化。選択肢比較や基準設計の型がまとまり、根回し=分散コントロールという本稿の主張と相性◎。
ビジネススクールで身につけるファイナンス×事業数値化力
NPV・DCF・回収期間など“ΔVを数字にする”基礎がコンパクト。根回しNPVの右辺を見積もる実務感が身につきます。
超ざっくり分かるファイナンス「知識ゼロ」の人のための
WACCやNPVを“まずは直感”で掴む入門書。若手メンバーに共有して、チームで同じ土台を作るのに最適。
世界一やさしい 会議ファシリテーションの教科書 1年生
会議の設計・アジェンダ・役割の基本を平易に解説。ロジ/利害/情の“三層設計”を現場で回す具体手順として使えます。
心理カウンセラー弁護士が教える 気弱さん・口下手さんの交渉術
相手の不安を下げる言い回しや、Noから始める着地づくりなど“情の設計”に効く会話術。Δr(差し戻し確率の低下)に直結。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21332557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0736%2F9784478120736_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20729159&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5389%2F9784296115389_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20686982&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3164%2F9784334953164_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20620669&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1006%2F9784800721006_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21055844&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0594%2F9784534060594_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

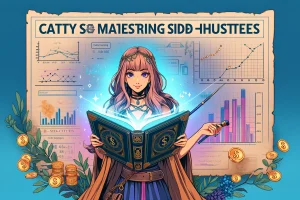










コメントを残す