みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
見出しに踊る前に——ARMの“内訳”を一緒に覗いてみませんか?
最近、ARM(アーム・ホールディングス)の株価が大きく揺らぎました。米NVIDIAが英Intelに50億ドルを投資して提携すると発表したニュースを受け、Intel株が急騰(+23%超)する一方で、ARM株は約3.7%下落しました。同じくARMの競合であるAMDも売られ、ARMにも陰りがさしたとの見方が出ています。投資家は「NVIDIAがGPUで提携し、今後はx86(Intel/AMD系)重視か?」と騒ぎ、センセーショナルなヘッドラインに踊らされかねません。しかし、このブログを読めば、表面的な「競合連携」報道に惑わされず、ARMの事業構造や会計数字の本質を見る手がかりが得られます。
本記事では、単なるニュースの解説に留まらず、ARMの収益構造(ロイヤリティとライセンス)や研究開発費の会計処理、主要顧客の存在感など会計・投資の視点で詳しく掘り下げます。また、注目されやすい見出しニュースに引っ張られる投資心理(可用性ヒューリスティック)にも触れ、どう冷静に業績開示を読み解くかを解説。読者の皆さんが「これからどう判断すべきか」が見えてきます。日々の株価騰落に左右されず、本質的な投資判断力を身につけたい社会人にとって役立つ内容です。
目次
騒動の概要:一夜にして急落した背景

まず、この突然の下落の経緯を整理しましょう。9月18日(米国時間)の市場では、NVIDIAがIntel株の4.9%にあたる50億ドル分を取得し、両社の戦略的提携を発表したと伝わりました。このニュースを受け、Intel株はわずか一日で23.27%もの急騰(時間外で150ドル超へ)、それを見たAMD株も売られ、ARM株も大きく値を崩しました。一例として、米AInvestの記事は「NvidiaのIntel投資発表で半導体市場が動揺し、ARM株は3.7%安、Intelは23%高の乱高下を記録した」と報じています。
ARMとIntelはどちらもCPUアーキテクチャの世界的プレイヤーです。ARMはエネルギー効率の高い設計でスマホ市場を席巻してきましたが、IntelはデータセンターやPC向けx86技術で優位です。今回のニュースを背景に、投資家の一部は「NVIDIAは自社のGrace CPUでARMを使っていたが、今後はIntelと組む動きかもしれない」と懸念を示しています。みずほ証券のジョーダン・クライン氏は「NVIDIAはかつてGrace CPUにARMを使用しているが、今回はx86(Intel)へ移行しようとしているようだ」とコメントし、これがAMDだけでなくARMにも圧力をかける可能性を指摘しました。
一方で、同日にはARM自身から業績見通しに関するニュースも流れました。ソフトバンク・グループ傘下のARMは2025年7月末に2025年度第1四半期(4~6月)の決算を発表し、売上高10.5億ドル(前年同期比12%増)、1株利益35セントと好業績を示しました。売上高は予想どおりでしたが、第2四半期(7~9月)見通しについては1株あたり29~37セントと予想平均(35セント)にギリギリ届かない数値を出しています。これを受け時間外取引でADR(米預託証券)が約5%下落しました。つまり、直近の決算では業績自体は堅調でしたが、将来への先行投資増加による慎重なガイダンスが悪材料と受け止められたのです。
まとめると、ARM株下落の遠因には「NVIDIA-Intel提携報道」と「業績見通しの慎重さ」の二重奏がありました。しかし後者(業績発表)は予め開示されていた情報であるのに対し、前者は突然のニュースです。この見出しニュースだけに反応しないことが大事であることを、後述する行動経済の視点でも触れます。
会計の視点:ARMの“稼ぎ方”を解析
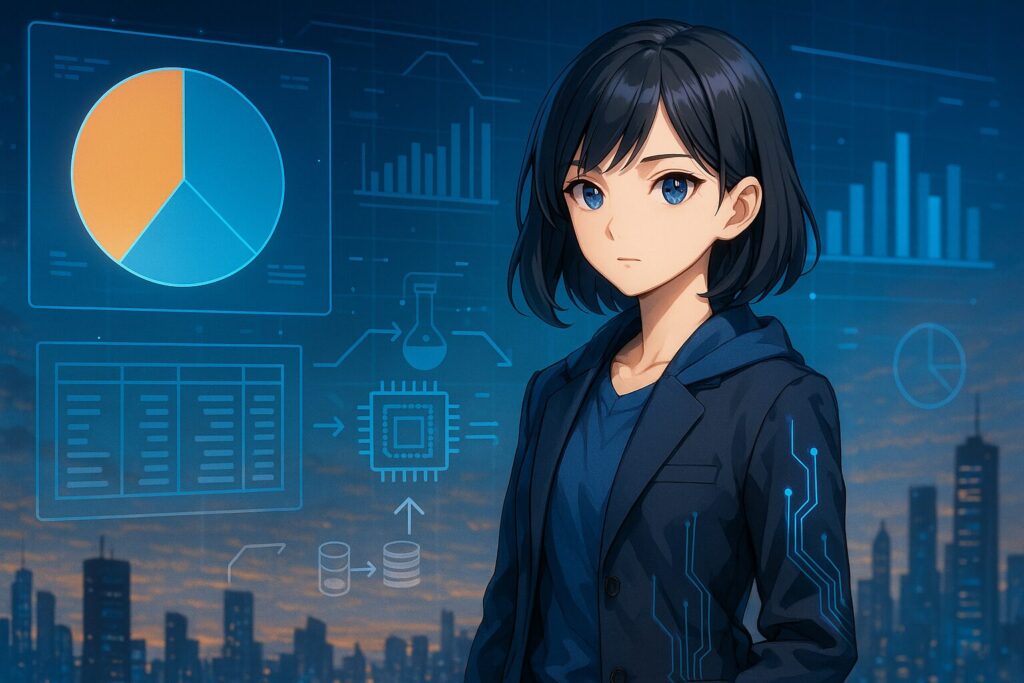
では次に、ARMのビジネスモデルと会計処理に注目しましょう。ARMは「設計図だけを売る」企業であり、自身でチップを製造しません。収益は大きくライセンス収入とロイヤリティ収入に分かれます。ライセンス収入は顧客がARMの設計を採用する際に前払いする契約金(ライセンス料)やサポート費用などで、売上に計上されます。一方ロイヤリティ収入は、その設計を使ったチップが製造・販売された分だけ支払われるもので、継続的に入ってくる売上です。
実際の数字を見てみましょう。2025年6月期第1四半期(MLQ記事より)の業績では、合計収入10.53億ドル中、ロイヤリティ収入が5.85億ドル(前年同期比+25%)、ライセンスおよびその他収入が4.68億ドル(同-1%)となっています。つまり全体の約56%がロイヤリティ、残り約44%がライセンス収入です。ロイヤリティ収入が大きく伸びているのは、AIデータセンターや自動車市場でARMアーキテクチャが採用拡大しているためです。一方、ライセンス収入は大口契約やその時期によるブレがあり、四半期ごとに増減が大きい傾向があります(大口契約が入るときは一気に伸び、そうでないと下支えしにくい)。
会計上、「ライセンスおよびその他収入」には何が含まれるかも押さえましょう。ARMのSEC資料によれば、ライセンス収入にはライセンス契約料のほか、「ソフト開発ツール料、設計サービス費、トレーニング費用、サポート・メンテナンス費用」なども含まれます。つまり、「設計受託(カスタムチップ設計の支援)」もライセンス収入の一部と考えられ、ARMはライセンス契約を軸に広くサポートサービスで収益を得ています。一方、チップ製造後のロイヤリティは「ロイヤリティ収入」として別勘定に分かれ、チップの単価や台数に応じて後払いされます。
この仕組みのポイントは一度ライセンス契約を結べば長期の安定収入が見込めることです。SEC資料には「主要顧客上位10社は平均20年以上にわたりARM製品を導入している」とあり、同じ顧客から継続的に新製品世代分のロイヤリティ収入を得る長期ビジネスモデルが特徴です。例えばスマートフォン向けCPUなら、ある顧客の次々世代機にもARMコアを使えば、その分ずっとロイヤリティ収入が入ります。
ただし注意点もあります。ARMの売上は大手顧客や市場(特にスマホ・民生機器)が中心です。例えば2023年度のデータでは、スマホ・家電向けロイヤリティが売上全体の50%以上を占めていました。主要顧客の動向や市場環境変化に左右されやすい構造です。SEC資料にも「主要顧客を失えば業績に大きく響く」と記載されています。投資家としては、売上が数社に依存していることをリスク要因として見ておく必要があります。
さらに会計処理面で注目すべきは研究開発費の扱いです。ARMはエンジニア重視の資本集約型企業で、従業員約80%が研究開発(R&D)に従事しています。しかしSEC資料によると、ARMは製品向けソフトウェア開発費をほとんど資産計上せずに費用計上しています(その区間で実質的に資産に載せるほどの規模に達しないからです)。つまり、四半期の利益を見るときには多額のR&D費用が一気に費用になっているため「実質的な投資の成果」がまだ利益に反映されていない状態ともいえます。投資家は、あくまで単純な当期利益にとらわれず、これらの投資が将来の製品価値につながる構造を理解しておくと良いでしょう。
以上をまとめると、ARMは「前払いライセンス収入」と「後払いロイヤリティ収入」の両輪で成り立つビジネスです。ARMはほぼ一つの事業セグメントしか持たないため財務諸表にセグメント別数値はありませんが、その収益構造の内訳を知ることが重要です。株価騰落に一喜一憂するのではなく、四半期レポートや決算説明資料にある「ライセンス契約獲得状況」や「ロイヤリティの伸び」、「顧客別シェア」などの記述を丁寧に拾い読みする習慣をつけたいものです。
行動経済学的視点:見出しに踊らされず“解像度”高い目を持つ

次に、投資家心理の観点から考えてみましょう。人は誰しも「目についた情報」に強く影響されやすいものです。行動経済学でいう「可用性ヒューリスティック」とは、記憶に残りやすい例やニュースで発生確率を過大評価してしまう心理傾向のことです。今回のように大きなヘッドラインが出ると、どうしてもその印象で将来を過度に悲観・楽観してしまいます。しかしそれが投資にとって常に得策ではありません。Harris Associatesの解説によれば、私たちはニュースサイクルの情報だけで判断しがちですが、企業の価値(ビジネスのキャッシュフロー)は恐怖や楽観よりもずっと安定しているのです。
実例を考えてみましょう。2019年8月にWSJが「世界同時景気後退の警鐘」などと伝えたとき、株価は一時下落しました。しかしその見出しを信じず5年間投資を続けた場合、結果的に資産は5年で約117%増加したといいます。世界同時不況やパンデミック、戦争、インフレなど数々の悪材料が出ても、高品質企業のキャッシュフローはしぶとく伸び続けるからです。株価は市場予想によって上げ下げしますが、本質的な事業価値はすぐには狂わないことを、心に留めておきましょう。
つまり、今回のARMについても「競合との提携報道」や「決算見通し」のワードに踊らされるのではなく、企業開示をしっかり読む目が大事です。たとえば決算短信の注記(ノート)には、売上の認識方法やロイヤリティ計算の仕組み、顧客上位企業の情報など、見出し報道では触れられない大事な情報が書かれています。ARMの場合、ライセンス収益がどのように時期判断されるか、ロイヤリティの変動要因は何か(市場環境や契約条件によるスライドなど)などは注記で確認できます。日々のニュースではなく、セグメント情報や注記を読むことで、「ARMが次に収入を得る条件は何か」「将来性はどうか」が見えてくるのです。
ヘッドラインに即反応して売買するのではなく、一歩引いて事業内容を咀嚼する。これがプロ投資家の鉄則でもあります。ARM株を語る際に重要なのは「●●が〜と発表したから株価が下がった」という話よりも、「ARMの基盤技術は全世界で10億台以上のデバイスに採用されている」という事実です。どんなに一時的に荒れた市況でも、堅実な収益モデルと顧客基盤がある企業は最終的に評価されます。
結論:事業価値を灯りに未来を照らす
投資の旅は時に不安や疑心暗鬼の連続です。しかし、夜が最も暗いのは夜明け前。ARMの株価も、今日一日で3%下がったからといって会社の本質が変わるわけではありません。ARMは今日もエンジニアが新技術の研究に没頭し、世界中のスマホやIoT、自動車、サーバーの発展を支えています。その底力を信じられるかどうかが、長期投資家の腕の見せ所です。
「ニュースは時限爆弾ではなく、その先に事業がある」と肝に銘じましょう。今日は揺れ動いているように見えても、見方を変えれば膨大なユーザー数・開発力・特許ポートフォリオという灯りがARMの経営を照らしています。私たち読者は、このブログで会計や投資理論という魔法のランプを手に入れました。これで今後の荒波も、少しは落ち着いて渡れるはずです。
最後に、このブログで得た知識を宝にしまいましょう。「次の大きなニュース」は、山積みの決算書の中に潜んでいるかもしれません。情報の海で溺れず、真実の灯りを頼りに前を向く。ARMの未来は、その先に見えています。技術革新の旅路で紡がれるストーリーに耳を澄ませ、またこのブログの灯りを頼りに、新しい発見を重ねていきましょう。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
IFRS財務諸表の表示・開示実務
IFRS第18号(表示・開示)の要点を中心に、P/L・B/S・CFの表示と注記の作り方を実務的に整理。業種別P/L例もあり、ARMの「ライセンス/ロイヤルティ」などの見え方・注記の当たりどころが掴みやすくなります。
IFRS「財務諸表の表示・開示」プラクティス・ガイド
新設のIFRS第18号を核に、IAS 7(キャッシュ・フロー)やIAS 8など“表示・開示”を横断。投資家として「どの注記に何が出るのか」をシステマティックに把握できます。
ベーシック国際会計〈第3版〉
IFRSの考え方を最新動向込みで解説。第3版はIFRS第18号のフォローを含み、初心者〜実務経験者の橋渡しに最適。ARMの収益区分・注記の読み方を“原理”から土台強化できます。
半導体産業計画総覧(2024–2025年度版)
GPU/HBM、各国の巨額投資や新設計画を俯瞰。ARMの需要ドライバー(スマホ→データセンター/自動車へ)の地合いを、設備投資・供給網の視点から把握できます。
努力は仕組み化できる——努力の行動経済学
ナッジ/行動設計の実践書。見出しに流される“可得性ヒューリスティック”を避け、意思決定を仕組みで安定化するヒントが得られます。ニュース耐性を高めつつ投資ルールを運用したい人に。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21512012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6213%2F9784502526213_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21535112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4011%2F9784502524011_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21563173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9411%2F9784502539411_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21403200&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3817%2F9784883533817_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21339234&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2153%2F9784296002153_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)






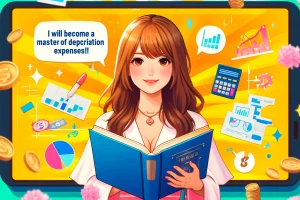






コメントを残す