みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
正規が“いちばんラク”になったら、転売はまだ魅力的?
転売は「迷惑行為」より、まずは“在庫の毀損(インベントリー・ロス)”として捉えると、意思決定が一段クリアになります。チケットは席という在庫。悪質な買い占めや高額転売で本来のファンが離れると、客単価だけでなくLTV(物販・配信・次回公演)まで目減りします。この記事では、①認証・顔認証などのセキュリティ投資を資産か費用かでどう仕訳・評価するか、②公式リセールで“正価→回収→再販売”というループをどう回すか、③「高額転売=レアだから得」という“ハウスマネー効果”をUIで打ち消す――この3点を、現場で使える目線でまとめます。日本では2019年に「チケット不正転売禁止法」が施行され、無許可の転売・転売目的の取得が禁止されました。ルール面の後押しはある一方、実装次第でコストだけが嵩むリスクも。法的枠と運用の“噛み合わせ”が勝負どころです。
まず投資の話。入場の本人確認や顔認証、モバイルチケット基盤などは、“複数公演にわたり便益が見込める”ハード・ソフトは資産計上の余地があります。一方で、クラウドSaaS型の認証サービスに払う利用料や、ベンダーがホストするソフトのカスタマイズ費は、IFRSの解釈では原則費用処理となる場面が多い(SaaSの設定・カスタマイズ費の扱いに関する2021年アジェンダ・ディシジョンが参考)。実装の切り分け次第で、損益の見え方とROIが大きく変わります。
次に流通設計。国内主要プレイガイドは「定価リセール/公式リセール」を整備しつつあります(例:イープラスの定価リセール、アプリ型のAnyPASSも公式リセール導線を実装)。公式枠で需給を吸収できれば、在庫の再循環が起き、未入場・空席のダメージを圧縮できます。海外の二次流通では高値転売や誤掲載が社会問題化し続けており(英国での規制検討など)、公式経路を“最短距離の正解”として提示する意味は大きい。
そして行動設計。人は「市場価格が上がっている=お得感」という錯覚に弱い。販売画面やマイページで“正価”と“手数料内の再流通価格”を常時対比表示し、需要過多時も「抽選・ウェイトリスト→公式リセールで繰り上げ」という安心導線をUIで見せる。顔認証やアプリ入場は、セキュリティ強化だけでなく“出品→譲渡→入場”の摩擦を下げるUXとしても効きます(USJ等の顔認証導入例や国内ベンダーの活用例も参考)。この3本柱で“在庫の毀損”を最小化しつつ、ファン体験を削らない――ここが狙い目です。
セキュリティ投資は「資産」か「費用」か
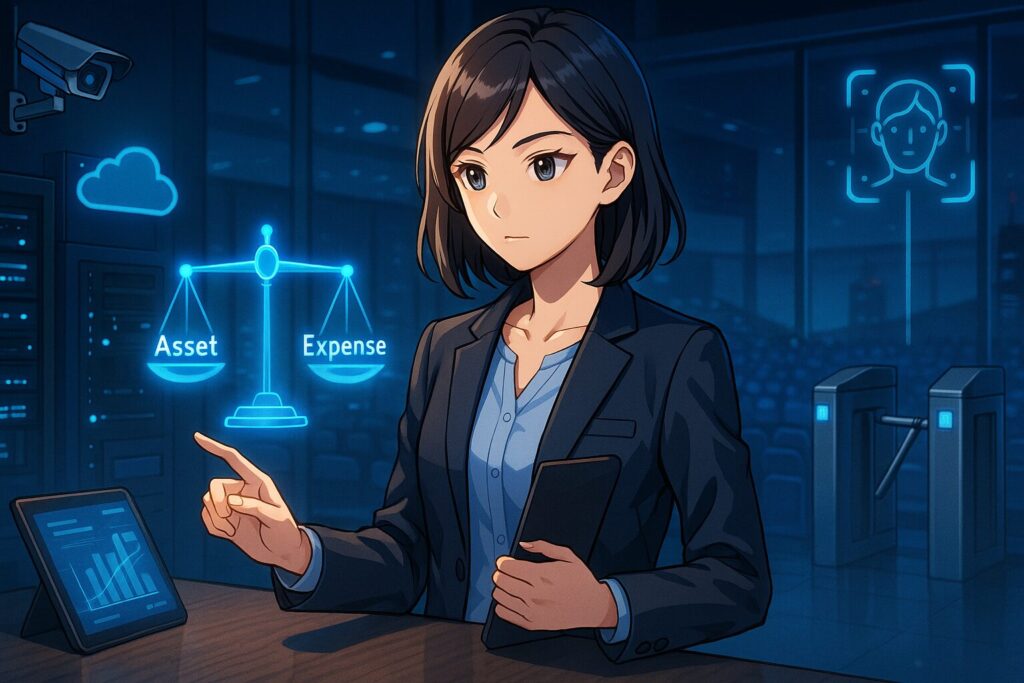
入場認証、顔認証、転売検知の仕組み――こうした対策は“コスト”に見えますが、会計上は「資産」か「費用」かで扱いが分かれます。区別をつけるだけで、損益の見え方、税負担、投資判断が整い、現場の意思決定が軽くなります。ここでは、判定の考え方と典型パターン、実務で迷いにくくするチェックポイントを整理します。
基本の考え方:便益の“期間”と“支配”
資産計上のカギは、①複数期間にわたる便益があるか、②その便益を自社がコントロールできるか、の2点です。たとえばゲートに恒常設置するカメラや認証サーバ、将来公演でも繰り返し使うアプリ機能のコア部分は、来期以降も役に立つため資産候補になります。一方、単発イベントの設定費やオペレーター増員の人件費は、その期の売上のために消費されるので費用に寄りやすい。ここで混同しがちなのが“高価=資産”という誤解。金額の大小より、便益の持続性と自社の支配可能性(再利用権・改変権・解約自由度)が判断の土台です。
ケース別の線引き:ハード・ソフト・SaaS
ハードウェア(ゲート機器・専用端末):耐用年数を設定して減価償却するのが基本。保守契約は期間費用。
自社または専用に開発したソフト:コア機能を自社が保有・再利用できるなら資産計上の余地が出ます。追加の小規模改修やバグ修正は費用処理が一般的。
SaaS(クラウド認証・顔認証API):月額利用料やベンダー側に残る設定・構築は原則費用。例外は、自社に帰属するモジュール化された成果物があり、今後も独立して使える場合。
データ活用:顔認証の精度向上用データやブラックリストのルール群は、契約上の権利や再利用性が鍵。自社の“資産”にできる設計か、早い段階で法務・ITと擦り合わせておくとブレません。
評価と予算:ROIを“イベント横断”で測る
判定だけで満足せず、投資の回収設計まで落とし込みます。減価償却のスケジュールを「公演カレンダー」と重ね、①不正入場の抑止による売上保全、②公式リセール誘導率の改善、③入場オペの人件費削減、をKPIとして束ねて追うのが実用的です。便益をイベント単体ではなく“年間通算”で測れば、費用処理になった支出も含め、総体としてのROIが見えます。さらに、運営・プレイガイド・会場の三者で便益配分を整理し、誰がどこまで負担するかを事前に合意しておくと、予算取りの心理的ハードルが下がります。帳簿の見かけだけでなく、キャッシュ回収と現場の負荷軽減まで一枚で説明できる資料を持つと強いです。
まとめると、資産か費用かは“期間”と“支配”で決め、ケース別の線引きを用意し、ROIは年間横断で測る。この型を先に決めておくほど、導入判断は速く、説明もシンプルになります。
公式リセールで“回収しながら再販売”を回す

公式リセールは、売り切りで終わらせず「来られない人の席を、欲しい人へ正規ルートで戻す」ための循環装置です。空席を減らし、定価ベースの価格秩序を守り、手数料で運営コストも回収できる。ここでは、設計のコアとなる“在庫の戻し方・見せ方・値付け”を、現場で実装しやすい順にまとめます。
需給をつなぐ――抽選・待機列とリセール在庫を一本化
まずは「欲しい人」と「戻したい人」を同じ土管につなげます。やることはシンプルで、販売フェーズの落選者や“通知希望”登録者を、そのままリセール在庫に自動で接続するだけ。具体的には、
- チケット詳細画面に“戻し”ボタンを常設(締切・手数料・返金時期を明記)。
- リセール在庫が出た瞬間、待機列の先頭にプッシュ通知→一定時間の専用購入枠を付与。
- 枠が流れたら次点へ自動送客、最終的に一般販売枠へ合流。
この流れをアプリで見える化しておくと、「正規で待てば買える」という安心感が定着し、高値転売の魅力がしぼみます。重要なのはスピードと透明性。分単位の通知・有効期限、残り人数の簡易表示だけでも十分に効きます。
価格と手数料――“定価基準+上限”で秩序を保つ
価格は、定価を基準に上限(例:定価+手数料のみ、または定価×1.1まで)をルールで固定します。売り手の受取は「購入額−手数料」、買い手は「定価+手数料」で、両者の差額に運営費を含める設計。ここでのポイントは2つ。
- 心理の制御:常に“定価”を太字・先頭に表示し、上限設定の理由(公演の公平性確保、本人確認コスト等)を短文で添える。価格の派手さより“安心して取引できる”ことを前面に。
- 手数料の使途の可視化:入場システム維持、サポート人件費、チャージバック対策など、使い道のカテゴリーをアイコンで並べるだけで納得感が上がります。
値付けの裁量を狭めることは、逆に“ルールに従えば失敗しない”という安心を生み、供給が途切れない限り、結果として流通量が増えます。
不正の芽を摘む――UIとルールの合わせ技で摩擦を最小に
公式リセールは、不正対策の入口でもあります。やり過ぎな厳しさではなく、自然に不正が割に合わなくなる設計を。
- 本人性の担保は入口と出口で:出品時に元の購入アカウントでのみ可能、入場はアプリ+顔(または端末)照合でワンタップ。正規ルートならラク、不正は手間、という差をつけます。
- 在庫の細分化:連番・視界良好席などはタグ化して、待機列の希望条件とマッチング。これにより“価値の見えない高額転売”の余地を減らします。
- データで回すオペ:リセール成立率、通知→購入のコンバージョン、空席率を毎公演で計測。数値が落ちたら通知のタイミングや有効期限を調整し、次公演に反映。
- 最後の保険:開演直前は“公式ラストミニッツ枠”として、当日券カウンターとリセール在庫を統合。会場到着者に最短で供給し、空席を極小化します。
この一連の仕掛けは、難しい説明なしに“正規がいちばん簡単で安全”という体験を作ります。結果として、在庫の毀損は目に見えて減り、収益回収のループが静かに回り始めます。
要するに、待機列と在庫を一本化し、定価基準で価格秩序を固め、UIで不正の旨味を奪う。この三点を丁寧につなげば、公式リセールはコストではなく、収益と信頼を同時に積み上げる仕組みに育ちます。
UIで“高額=得”の錯覚を消す

二次市場で高い値札を見ると、「やっぱり価値があるんだ」と感じやすい。これが価格のアンカリングや“ハウスマネー効果”と呼ばれる認知のクセです。放置すると、正規価格が相対的に弱く見え、焦り買い・あきらめ離脱が増えます。ここでは、販売・マイページ・入場までのUIを整え、「正規で待つのが一番ラクで安全」という体験を作る具体策を3つに絞って紹介します。
“基準”を常に目の前に――定価アンカーの固定化
価格の基準点は、画面が変わっても動かさないのがコツです。
- 常時表示する定価ラベル:チケット詳細、抽選結果、リセール通知、支払い確認の各画面に、同じ位置・同じ太さで「定価(手数料込み)」を固定表示。購入導線のどこにいても基準がぶれません。
- 比較の見せ方は一列で:正規・リセール・受取上限を横並びにせず、縦一列に並べる。視線の流れを上→下に固定すると、上段の定価が自然に“アンカー”になります。
- 文言は短く、理由は一言:「価格上限は公演の公平性を守るため」。長い説明より、短い“納得の芯”を置くほうが迷いを減らします。
- “派手な値札”を外に出さない:アプリ内に他者出品の価格ランキングや“高額成立例”は出さない。成功談がアンカーを汚染します。必要な比較は“定価基準の範囲内”だけで十分です。
不安を減らす導線――待てば届くをUIで可視化
人は見えないものを過大評価しがち。だから“待てば買える”を可視化すると、焦りが静まります。
- 待機列の温度計:自分の順番、おおよその待ち時間、前後の動きが分かる簡易メーターを常設。数字は荒くてOK。進んでいる実感が不安を削ります。
- リセールの“約束された枠”:通知が来た人に、短い専用購入枠(例:15分)を付与。カウントダウンは大げさに煽らず、静かなタイマーで。
- 失効の自動リレー:枠が流れたら即次点に送客。ユーザーは「逃しても列から落ちない」と分かれば、外部の高額オファーに揺れにくい。
- 保険の提示:来場直前の“ラストミニッツ枠”や会場受け取りを、アプリの下段タブに常時表示。最悪のケースが見えていれば、無茶な購入に走りにくくなります。
ラクさで勝つ――正規行動が最短になる設計
「正規のほうが面倒」と感じた瞬間、裏ルートに魅力が生まれます。手触りの勝利を取りに行きます。
- ワンタップ譲渡→リセール:行けなくなった人が“譲渡”と“公式リセール”を同じボタンから選べるように。面倒なら正規に出す、が自然になります。
- 本人確認の“柔らかい自動化”:アプリ入場・顔照合は、正規ならQR提示だけで通過。不正のときだけ追加確認が入る設計にし、正規の体験をとにかく滑らかに。
- 席の価値をタグで説明:「連番」「視界良好」「通路近く」などをバッジ化。価値が言語化されると、訳の分からない高値に流れにくい。
- 支払いの安心装備:返金時期・手数料の内訳・チャージバック対応の有無を、決済直前に“3行”で常時表示。安心感は最強の説得材料です。
まとめると、定価をアンカーとして固定し、待てば届く道筋を見せ、正規行動を最短にする。この三点を淡々と積むだけで、「高額=得」という錯覚は弱まり、在庫の循環は静かに整います。派手な機能より、基準・可視化・ラクさ。ここを外さないUIが、収益も体験も同時に守ります。
結論:在庫としての席を守る、静かな強さ
転売の話は感情を揺らしがちですが、ここまで見てきたように、やるべきことは驚くほど地に足がついています。席=在庫。ロスを最小にするという、ごく普通の経営判断です。会計では、便益の期間と支配を軸に資産/費用を切り分ける。運用では、公式リセールで「戻す→待っている人へ渡す」を滞りなく回す。行動設計では、定価を基準に固定し、正規導線を“最短でラク”に整える。三つは別物に見えて、実は一本のロープです。どれか一つが弱いと、他の二つも効き切らない。逆に、三つが噛み合えば、派手な規制や過剰な締め付けがなくても、在庫は自然に循環します。
始め方はシンプルです。まずは“現状のロス”を測ること。空席率、不正疑い件数、リセール成立率、通知→購入の転換率――今ある数字を一枚に並べ、次回公演までに「どの数字を何%動かすか」を一つだけ決める。会計は、その目標達成に資する投資を“イベント横断”で見て、耐用年数と回収計画をセットで明文化する。UXは、定価アンカーと待機列の可視化、ワンタップ譲渡/リセールの3点に絞って先に出す。小さく回して、数字で確認し、次の公演に積む――この繰り返しがいちばん速い。
大切なのは、「転売を撲滅する」ではなく「正規が自然に選ばれる」状態を作ること。ファンは善悪の説教で動くより、安心と手触りで動きます。運営は“守りのコスト”を“循環する仕組み”に置き換えるほど、収益も信頼も積み上がる。在庫としての席を丁寧に扱うことは、作品と観客の距離を一歩近づける行為です。静かな強さで、回る興行へ。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A』
2019年施行の同法をQ&Aで整理。本人確認・指定席の扱い・罰則・「正規の再流通」をどう位置づけるかなど、運営の判断に直結する論点が拾えます。条文の背景や実務上の注意もまとまっているので、社内合意用の根拠づけにも便利。
『デザイナーのための心理学』
“人はなぜそのボタンを押すのか”を、認知心理の観点から短章で解説。アンカリング、損失回避、社会的証明など、リセールUIで効く原則を実装レベルに落とし込むのに向いています。設計前の「用語合わせ」にも使いやすい。
『UXグロースモデル ― アフターデジタルを生き抜く実践方法論』
“ビジネス成長=UX改善の連鎖”をモデル化。待機列→通知→購入→入場の各KPIを“横断でつなぐ”考え方がわかりやすい。機能投入→計測→改善の型を、チケットの回収ループに当てはめやすい一冊。
『図解即戦力 情報セキュリティの技術と対策がこれ1冊でしっかりわかる教科書』
ゼロトラストや認証・暗号化・インシデント対応まで、運用寄りに俯瞰。顔認証やモバイル入場の“本人性担保”をシステム全体でどう支えるか、社内説明の素地づくりに向いています。
『図解即戦力 画像センシングのしくみと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書』
カメラ・画像処理・認識の基礎から応用までをフルカラーで解説。入退場ゲートや不正検知の“現実的な精度・制約”を把握するのにちょうどいい。ベンダー選定の目利き力を底上げできます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47107875.467d2aee.47107876.b217f4b1/?me_id=1220950&item_id=12848682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_1310%2Fneobk-2368578.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20988903&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3703%2F9784839983703_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=20465899&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0412%2F2000010290412.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20303385&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1068%2F9784297121068.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20935369&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5577%2F9784297135577_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





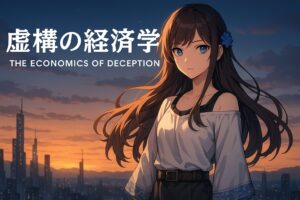







コメントを残す