みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
深夜の一本、数字で決めていますか?
コンビニの“夜間配送”って、現場ではKPIで語られがちですよね。積載率○%、リードタイム○時間、配送回数○本――どれも大事。でもPLに落ちた瞬間、数字の意味がガラッと変わります。例えば、車両・人件費は夜間帯ほど固定化しやすい一方、店舗側では深夜〜明け方の欠品が“見えない機会損”として積み上がる。ここを翻訳できると、「もう1本走らせるか」「まとめて朝に寄せるか」の判断が、勘ではなく収益ロジックで語れるようになります。加えて、都市部ではマイクロハブ(小規模中継拠点)を挟む設計が有効です。最終区間を短くし、在庫を“待ち”ではなく“流れ”で回すことで、過剰在庫と緊急便の両方を圧縮できます。日本でも行政・民間でマイクロハブ導入や共同配送が具体的に進み、ルート最適化や拘束時間の短縮とセットで成果が出始めています。
もう一つ、見落としがちな論点が“行列=税”という考え方。レジ前の待ちやバックヤード不足による品出し遅延は、価格のように明示されない“心理コスト”。人はこの“税”を嫌って離脱します。夜間の在庫精度や補充タイミングがズレるほど、客導線に摩擦が生まれ、CVR(購入率)は下がる。だからこそ、配送KPIは店内のサービス動線と不可分に設計すべき。夜間に一気に荷を落として朝まとめて品出し――は一見効率的でも、深夜帯の需要山に穴を開け、結果として粗利を削ります。都市型店舗では、共同配送・マイクロハブ・AI配車の三点セットで“必要な時に必要な量を短距離で”届ける体制を作り、レジ前の滞留や欠品を同時に潰していく。この記事では、①車両・人件費の固定化 vs 欠品の機会損、②マイクロハブでリードタイム短縮→在庫縮小、③“行列=税”を避ける動線設計でCVR↑――この3本の柱を、ロジ会計×サービス設計×行動経済の視点でやさしく解きほぐします。明日からの会議で、そのまま使える“配送KPI→PL翻訳の型”を持ち帰ってください。
目次
固定費と欠品の“見えない損”を同じ土俵に並べる

まずやることはシンプルです。配送側の「固定化しがちなコスト」と、店舗側の「欠品による見えない機会損」を、同じ単位に変えて比べられるようにすること。単位は“1便あたり/1時間あたり/1店舗あたり”のどれでもOK。大切なのは、判断の土台をそろえることです。ここを揃えないまま「もう1本走らせるべきか?」を議論すると、声の大きさ勝負になって迷子になります。
配送の固定費の正体をほぐす
配送は変動費に見えて、夜間ほど“ミニマム固定費”が顔を出します。車両(リース・減価償却・保険)、ドライバー(基本給+深夜割増)、拠点(夜間管理・仕分け人員)、そしてルートの空走リスク。これらを便数で割って「1便あたり原価」に直します。
カンタンな型はこうです。
- 1便原価 ≒〔車両コスト/日+人件費/日+拠点夜間コスト/日〕÷ 実運行便数
- さらに、距離と時間で割って「1kmあたり」「1分あたり」にも展開しておく
ポイントは“実運行便数”。見込みではなく、実績に合わせて週次で更新します。夜間は便数が減るほど、1便原価がグンと跳ねやすい。もう一点、混載率(積載重量やケース数)も補助指標に。積載が薄いのに“慣習で走らせている1本”は、原価を押し上げる最有力候補です。
欠品の機会損を数字にする
欠品はPL上“売上が立たなかっただけ”に見えますが、実態はもっと広い。単品の粗利を逃すだけでなく、「ついで買い」が消え、レジ前の待ちが伸び、次回の来店確率まで下がる。これを小さくても数字に寄せます。
- 欠品粗利損 ≒ 平均単価 × 粗利率 × 需要量 × 欠品率 ×(1−代替率)
- ついで買い損 ≒ 欠品に遭遇した客数 × ついで買い平均粗利
- 行列“税”の損 ≒ 待ち時間増分 × 離脱率 × 平均粗利
現場での集め方は難しくありません。POSで「欠品時刻前後15~30分の販売数差分」を拾い、フェイス前の在庫ゼロ時刻(前回入荷時刻+品出し完了時刻)と照合。ついで買いはレシートバスケットの組み合わせ頻度で近似。行列は人感センサーや簡易カメラで“並び長・待ち秒”を取れば、離脱との相関が見えてきます。完璧である必要はなく、定義を固定して毎週ブレずに積み上げることが肝です。
“もう1本走らせるライン”を決める
最後に、追加1便の判断ラインを用意します。考え方は限界比較です。
- 追加1便の限界費用(1便原価+追加で増える仕分け/積替えの微増分)
- その便で減らせる“欠品由来の限界粗利損”(深夜帯の需要山に合わせて補充することで回収できる粗利)
判断メモの雛形はこれで十分。
走らせる=「限界粗利の回収見込み」>「追加1便の限界費用」。
補正として、①曜日係数(週末・給料日後は需要山が高い)、②時間帯係数(0–2時より2–5時の方が回収幅が大きい店舗もある)、③品種係数(代替が効きにくいフラッグシップ商品は回収粗利が厚い)を掛けます。さらに、レジ待ちが伸びやすい店は“行列=税”の影響も上乗せ。ここまで定義すれば、会議で「体感」をぶつけ合わずに、しれっと数字で決まります。
夜間配送の1本は、原価の話であり、同時に“欠品と行列の連鎖”をほどく投資でもあります。両者を同じスケールに並べると、やる・やらないの線が静かに浮かび上がるはず。
マイクロハブで“近くて速い”を作り、在庫を軽くする
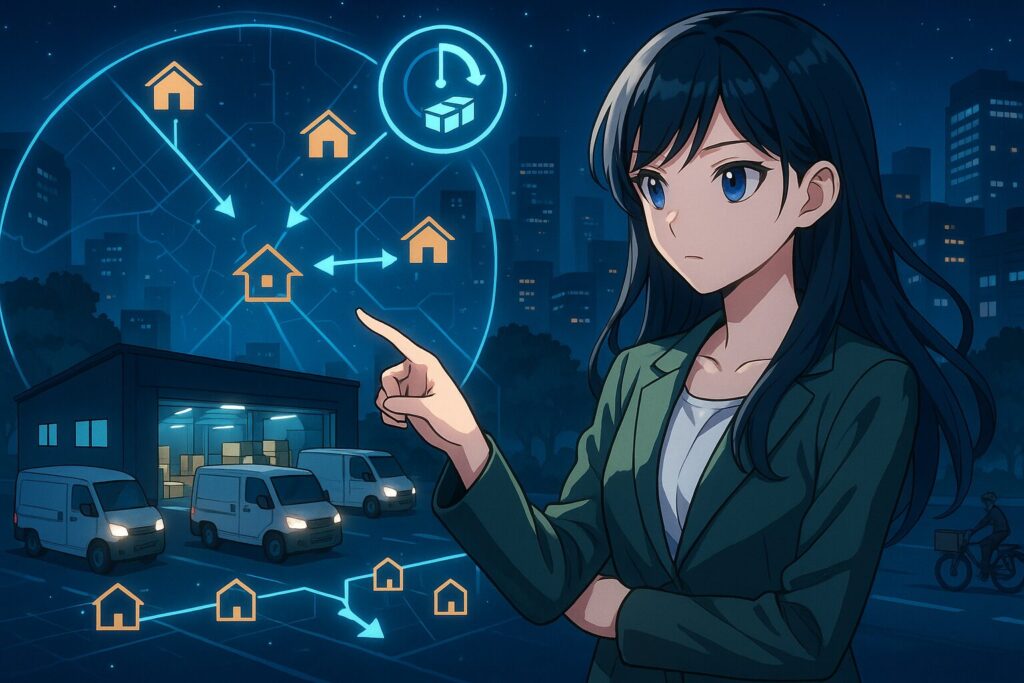
マイクロハブは、都市内に置く小さな中継拠点。幹線(センター→街)でまとめて運び、ハブで店別に切り分け、最終区間を“短い・軽い・回数多め”に変える仕組みです。メリットはシンプルで、①店着までのリードタイムが縮む、②店内の安全在庫が下がる、③緊急便や空走の削減でムダが消える。夜間帯の“あと一山”を取りに行くには、遠いセンターから太い便を引っ張るより、近いハブから細い便を回す方が合理的になりやすい。ここでは、時間の分解→在庫式への翻訳→導入の設計図、の順で手なりに掴んでいきます。
時間を分解し、短縮レバーを見つける
店に商品が並ぶまでの時間は、ざっくりこう分解できます。
T合計=発注~積込+幹線走行+中継処理+最終走行+荷降ろし+品出し。
マイクロハブは「最終走行」と「荷降ろし前後の待ち」を直撃します。センター直行だと、①店間距離がバラつき、②夜間の受け入れ枠に集中し、③1便が重くて品出しが遅れがち。ハブを挟むと、最終走行の平均距離が短くなり、便を“薄く”できるので、店着後すぐ棚に載せやすい。やることは二つだけ。
- 距離の短縮:ハブを需要重心(多店舗の真ん中)に置く。軽バン・カーゴバイク・徒歩台車を混ぜて、信号・路地に強い車両で刻む。
- 待ちの平準化:店別の到着時刻を波ではなく“縦に細く”並べる。中継処理はクロスドック(通過型)で滞留ゼロを狙う。
試しに、センター→店の平均8km/25分が、ハブ→店で3km/10分になるだけで、1周回あたり15分浮く。これを夜間に4周回まわせば、単純計算で1時間の回収。浮いた時間は“欠品帯”に差し込む短便に変えられます。
リードタイム短縮が在庫をどれだけ軽くするか
店の在庫は“売れ行きのブレ×時間”で太ります。安全在庫の考え方をやさしく置き換えると、
必要在庫 ≒ 日販のブレ(σ)× 供給までの時間(L)に比例。
つまり、Lを短くすれば在庫は素直に軽くなる。夜間のマイクロハブ運用で「1日2便→3便」にできると、実質のLが約1/3短縮。結果、①バックヤードの占有が減り、②棚前の補充が小刻みになって陳列精度が上がり、③賞味期限リスクも下がる。
もう一歩踏み込むなら、“足りなくなる確率”を下げるには、在庫を増やすよりLを縮める方が効くという発想を持っておくと判断が揺れません。店舗に“置いて守る”より、“近くから運んで守る”。これがマイクロハブの本質です。
導入ミニ設計図(小さく始めて、早く学ぶ)
実装は難しく見えて、段取りに落とすとこうなります。
- 地図で重心を見る:直近3か月の売上×欠品率で“重たい店”を色付け。円の重心付近に候補エリアを3つ。
- 最終区間の分布を出す:現行の店別“センター→店”距離・時間のヒストグラムを作り、中央値と裾(遠い店)を把握。
- 器の確保:夜間に使える小型物件(駐車場の一角、空き倉庫、商業施設のサービスヤード)をあたり、電源・照明・騒音の条件をチェック。
- KPIを3つだけ:ハブ滞留時間(分)、店着時刻の偏差(分)、ケース通過コスト(円)。増便してもこの3つが暴れなければ合格。
- 車両のミックス:軽バン+原付カーゴ+台車。細い道路・夜間の静音・短停車に強い組み合わせに。
- 運用の細工:店別カゴで“棚順”に並べる/レジ混雑時間帯を避けて納品枠を刻む/品出しを“到着10分以内”のルールで回す。
- POC(2週間):テスト期間だけ“深夜の短便”を1本増やし、欠品率・レジ行列・売上を観察。費用より、まず効果の感度を掴む。
注意点は、ハブの固定費と近隣配慮。夜間作業音・照明・搬出入の導線は最初から“静かに・短く”を設計に入れておくと揉めません。
マイクロハブは“倉庫を増やす話”ではなく、“距離と待ちを削る話”。近くに置いて短く回すだけで、棚は痩せ、欠品の谷が埋まり、売り逃しが減っていきます。
“行列=税”を減らす動線設計でCVRを上げる

「並ぶ=お金は払っていないけど、時間で課税されている」——この感覚を前提に店を組み直すと、売上は静かに伸びます。やることは3つだけ。①今どこに“税”が乗っているか見える化、②動線を短く・交差を減らす、③決済までの“最後の30メートル”を軽くする。配送の回し方を変えるだけでは足りません。店内の摩擦を同時に削ると、欠品の谷もレジ離脱も一気に浅くなります。
行列の“見える化”とCVRのつなぎこみ
まず、測らないと直せません。最低限はこれで十分。
- レジ待ち秒:10分粒度で平均・最大を記録。
- 離脱率:列に並んだが購入しなかった人数/来店者数。
- CVR:購入者/来店者。
ここで大事なのは、1分待ち増でCVRが何%落ちるかの“感度”を出すこと。1週間分のデータを散布図にして、ざっくり傾きを読むだけでも意思決定は変わります。例えば「+60秒でCVR−3%」と見えたら、60秒を削るために必要な在庫・補充・レジ体制のコストを、売上の戻りで比較できる。さらに、“欠品×行列”の掛け算にも注意。人気商品が欠けた時間帯は、ついで買いも減り、レジは短いのにCVRが落ちることがある。指標は分けて、原因を取り違えないようにします。
動線を短く、交差を減らす——棚とバックヤードの微整形
行列の多くは、店内の“交差”が生む渋滞から発生します。処方箋はシンプル。
- 一筆書き導線:入口→主力棚→ドリンク・スナック→ホットスナック→レジ、の順で人の流れがUターンしない並びに。特にドリンクと会計を遠ざけない。
- 補充の“細切れ化”:夜間の到着便を“薄く”し、10〜15分で出し切れる単位に。台車で通路を塞ぐ時間を最小化。
- ホットスポット緩衝:レジ前1.5mは“滞留専用レーン”として空け、突き当たりにPOPやカゴ置き場を作らない。
- 棚前の即応在庫:欠けやすいフラッグシップは、棚下に“1回分の追い出し箱”を常備。補充1回=60秒以内を目標に。
- バックヤード⇄売場の距離短縮:マイクロハブで入荷ケースを“棚順”に組んでおくと、店内歩数が半分以下になることが多い。歩数が減れば、補充の隙間時間が増えて列も縮みます。
効果は「補充1回あたりの通路占有秒」「ピーク帯の通行量(人/分)」で追うと因果が掴みやすい。交差が減ると、自然にCVRは上がります。
決済を“最後の30メートル設計”で速くする
レジ前こそ“税”の本丸。設備投資の大小に関わらず、できることは多いです。
- 支払いの分散:セルフレジ1台でも“現金派の渋滞”を逃がす効果が高い。有人=現金・複雑処理、セルフ=キャッシュレス中心で役割を分ける。
- 会計前ピットイン:レジ手前に“忘れ物救済”のミニ棚(電池・ガム・カップ麺トッピングなど高回転小物)を置き、列離脱を逆に“ついで買い”へ転換。
- 袋詰めゾーンの独立:支払い完了後に半歩ずれる台を用意し、次の客がすぐ会計に入れるレイアウトに。
- 90秒ルール:ピーク時は「並び開始→会計完了」まで90秒超過を警戒ラインに。ラインを超えたら、即席で“補充→レジ応援”へ役割転換。
- メニューの摩擦を削る:ホットスナックやレジ横コーヒーは、グラム表記やカップサイズを一目で比較できる表示に。選択時間が5秒削れれば列はみるみる短くなる。
この“最後の30メートル”が軽くなると、配送や在庫の改善がダイレクトに売上へ伝わるようになります。逆にここが重いと、良い在庫もレジで蒸発します。
行列は“店の課税制度”みたいなもの。課税率(待ち秒)を下げる設計を重ねると、CVRは素直に上がります。配送の本数、ハブの距離、棚の順番、レジの一歩——全部つながっている。現場で触れる小さな摩擦から削っていけば、粗利は静かに積み上がります。
結論:深夜の一本は“勘”ではなく“翻訳”で決める
夜の道路は静かでも、店のPLは静かじゃない。配送のKPI、棚の欠け、レジ前の息づかい——全部が一本の線でつながっています。ここまで見てきた通り、鍵は“翻訳”。積載率や回転数といった現場の指標を、1便原価・限界粗利・在庫とリードタイムの関係へ地道に写し替える。そのうえで、マイクロハブで距離と待ちを削り、店内の交差を減らし、最後の30メートル(決済)を軽くする。この流れが揃うと、「深夜に一本増やすべきか?」の問いは、熱量ではなく数式で静かに答えが出ます。
実務で迷いやすいのは、“完璧なデータが揃うまで動けない”罠。ここは割り切って、小さく回して早く学びます。週次で1便原価を更新し、POSと観測で欠品粗利損の当たりを掴む。マイクロハブは暫定ロケーションでいい。ハブ滞留(分)/店着偏差(分)/ケース通過コスト(円)の3点だけを守り、2週間のPOCで“深夜短便”の効き目を測る。店内は、台車の占有秒とレジ待ち秒を削る小細工を重ねる。すると、多少粗くても“限界比較”が回り始める——追加1便の限界費用 < 回収できる限界粗利か、否か。線を越えたら走らせ、越えなければやめる。それだけ。
もう一つ、続けるコツ。現場の手触りを、会議室に“輸送”すること。棚前で起きた30秒の滞留や、バックヤードから売場への歩数のムダは、エクセルだけだと見えません。だから、散布図1枚と、現場写真3枚をセットで持っていく。数字で仮説、写真で納得。この二段構えが、部署をまたいだ合意形成を速くします。物流と店舗運営、設備と人、どれか一つだけを尖らせても、行列という“税”が回収してしまう。だから、近いハブ×薄い便×軽い動線を一本の施策として束ねる。投資は小さく、学習は速く、翻訳は一貫して。
最後に、粗利を守る視点。深夜の一本はコストではなく、“粗利を取り戻す権利”です。欠品の谷を埋めることで、ついで買いは戻り、レジの列は縮み、次回来店の確率が上がる。つまり、今日の一本が、明日の常連を連れてくる。数字は冷たいけれど、意思決定は温度を帯びます。あなたの店、あなたのエリアで、まずは2週間。一本の短便、ひとつの棚順、90秒のライン——小さく始めて、静かに勝つ。それが、配送KPIをPLに翻訳するということ。深夜の道路に一本、正しい線を引きましょう。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
物流革命2025
最新の物流DXや共同配送の事例を横断。2024年問題以降の人手・コスト制約下で「どこに投資し、どこを削るか」を掴める。マイクロハブや短距離多頻度配送の方向感を確認するのに最適。
図解即戦力 物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]
業界構造・KPI・コストの考え方をフルカラー図解で整理。“1便原価”の分解やドライバー不足・燃料高の影響など、本文の基礎式を裏打ちしてくれる。
ビジュアル ロジスティクスがわかる
コンパクトに要点を押さえる入門新書。在庫とリードタイム、SC全体最適の関係を図で直感的に理解できるので、「L(供給時間)を縮めて在庫を軽くする」という本記事の主張と噛み合う。
ドライバーの働き方改革
ラストワンマイル現場の制度・運用を最新事情で解説。夜間帯の運行設計や役割分担の考え方に具体例が多く、“増便の限界費用”を読むときの現実解を補強できる。
Pythonによる実務で役立つ最適化問題100+ (2) ― 割当・施設配置・在庫最適化・巡回セールスマン
マイクロハブ候補地の重心計算、ルート最適化、在庫水準のチューニングに直結。サンプルで回しながら、「もう1本走らせるライン」の感度分析まで持っていける。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21525848&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3384%2F9784296123384_1_20.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21133047&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9254%2F9784297139254_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21380772&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9561%2F9784296119561_1_35.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21345286&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5267%2F9784837805267_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20788715&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2749%2F9784254122749_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す