みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
その含み益、本当にあなたのものですか?
このブログでは、2025年秋に吹き荒れた“AIブーム”による株高の裏側をひもときながら、皆さんが読むことで得られる知識と安心感をお伝えします。まず、最先端半導体企業のNVIDIA(エヌビディア)が株価12倍と急騰し、時価総額5兆ドルに達したことや、日経平均が5万円超まで駆け上がる熱狂ぶりを振り返ります。その一方で、財務省の新しい為替政策トップである三村篤志氏が「AIブームが株式市場をあまりにも急上昇させているのではないか」と懸念を示したニュース(参照:reuters.com)も大きな話題になりました。
これらの情報を踏まえ、読者の皆さんにはこうした“熱狂”のリスクや、投資と会計の視点から得られる重要な教訓をお届けします。具体的には、含み益(未実現益)が実は“ペーパー上の幻”であり、急落時には一気に吹き飛ぶ可能性があることを会計論や心理学論で解説します。さらに、初心者・中級者向けに、AI銘柄を適切に手放す逆指値注文(ストップロス)や利益確定ルールの立て方、ポートフォリオの見直し方まで踏み込んでお話しします。難しい専門用語もなるべく噛み砕いて解説するので、これを読むことで「AIバブル」への過度な心配を和らげ、長期的に賢く資産を増やすヒントをつかんでいただけるはずです。興味深い裏話や実践的なアドバイスで飽きさせない内容にしましたので、何度読み返しても新発見があるブログになるでしょう。
目次
【AI狂騒の背後】過熱する相場と警戒の声

ここ数年、AI関連銘柄は“時代の寵児”となり、株式市場を席巻してきました。中でもNVIDIAは代表格で、会話型AI「ChatGPT」が登場した2022年以降、その株価は実に約12倍にも跳ね上がり、時価総額は世界初の5兆ドル突破を果たしました。米国市場ではNVIDIAの大躍進に連動してアップルやマイクロソフトも時価総額4兆ドルに迫り、S&P500やNASDAQを牽引しています。国内でも日経平均は高市政権の経済政策への期待と相まって急上昇し、2025年には5万2000円を超える勢いです。このような熱狂の背景には、新NISA制度による個人資金の流入や、余剰資金の行き場が株式に集中しているという事情があります。まさに「金余り」と呼ぶ状況で、市場は一気に加熱してきたわけです。
しかし、過度な期待には必ず影があります。今夏~秋にかけて、半導体株の好決算やAI技術への熱狂的期待により上値を追う投資が目立ちましたが、一部では「果たしてこの上げ幅は正常なのか」という冷静な声も上がっています。米国では一部のヘッジファンド経営者やCEOがバリュエーション(株価水準)の急騰を懸念し、調整(大暴落)の可能性について語り始めました。日本でも、10月下旬には日経平均が移動平均から15%も乖離する場面が出現。これは過去の「アベノミクス・ラリー」時に匹敵する過熱サインで、専門家は「そろそろショック安が起きてもおかしくない水準」と警告しています。たしかに短期では、NASDAQ指数が4月安値から50%以上上昇していましたが、11月初旬には2%押し戻しが入り、「下げはむしろ健康的な利益確定だ」との見方も出ています。実際、アジア市場ではAI関連銘柄の短期的な急落が起こりましたが、投資家は大パニックに陥らず、むしろ冷静に利益を確定しようとしていました。
そして2025年11月5日、日本の為替政策トップ(三村篤志氏)が公の場でAIバブルの“過熱”に言及したのです。三村氏は「今の株式市場の状況はあまりにも急すぎて、行き過ぎているのではないか」と懸念を表明し、市場参加者に“冷や水”を浴びせました。この発言は当日、日経平均が一時5万円を割り込む一因ともなり、多くの個人投資家を驚かせました。いずれにせよ、「AI株の急騰」に心踊らされるだけでなく、為替の司令塔からも注意喚起が出たことは大きな示唆です。セクション1のまとめとしては、「過熱した相場には必ず冷却局面がある」という歴史的教訓を忘れずに、足元の連騰に安易に飛びつかない警戒が必要だと言えるでしょう。
【含み益の罠】会計と心理の視点で解くリスク

急騰する相場では、保有株の評価額が膨らみ「含み益」が膨れるのは気分のいいものです。しかしこの「含み益」はあくまで幻に過ぎないことに注意が必要です。含み益とは字義通り「含み(まだ売らないで保有している)利益」のことで、売却していない以上は実際の現金収入ではありません。投資家の間ではこれを「ペーパープロフィット(紙上の利益)」と呼ぶこともあり、発生した含み益が次の瞬間に消えてしまうリスクを常に抱えています。
含み益とは何か?
含み益は投資家が保有株の価格上昇によって得られる「未実現の利益」です。例えば100万円で買った株が150万円になれば50万円の含み益が出ますが、これを現金化しなければまだ「仮の数字」でしかありません。投資教育の分野では、含み益は「ある程度売却されたら利益」と教えられることが多いです。つまり、「含み益は確定すれば利益だが、確定するまではリスク資産の一部」であると心得る必要があります。税金面でも含み益には課税されず(未実現なので)、この点でも実際に手元に残るまでの余裕感が出てしまうわけですが、その分、油断は禁物です。
のれん・減損の教訓
ここで一段高度な視点を導入しましょう。企業の財務会計における「のれん」という概念です。企業が他社を買収する際、買収価格がその会社の純資産価値を超える部分はのれん(無形資産)として会計に計上されます。こののれんは「将来得られるブランド価値やノウハウへの期待」とでも言えるもので、実体が目に見えない点で含み益に似ています。ところが、市場が冷え込んだり買収先企業の業績が予想を下回ると、会計ルールではのれんの減損処理を行い、バランスシート上から大きく消し込む必要が出てきます。減損損失は損益計算書に計上されるため、企業利益は一気に吹き飛び、株価も急落します。個人投資家に例えれば、あなたのポートフォリオの含み益も企業ののれん同様に“未実現の期待”であり、市場急落という“減損テスト”が来たら一瞬で消滅しかねないのです。
つまり、会計上は一度膨らんだバランスシート上の数字でも、突発的な下落によって帳消しになる危険性があるという教訓がここにあります。「含み益が紙くずにならないように」というのは、投資家として当然意識すべき姿勢なのです。
心理会計:利食いは早く、損切りは遅く?
含み益をめぐる投資家の行動には、心理学的バイアスが強く働きます。行動経済学のプロスペクト理論によれば、同じ金額の利益と損失では「損失の痛み」の方が大きく感じられるため、投資家は勝っている(含み益のある)銘柄を早く手放し、負けている(含み損のある)銘柄を粘って保有しがちです。実際、野村證券の解説コラムでも「含み益がある株は『利益が得られるうちに』と売り急ぎ、含み損がある株は『いつか戻るかも』と売り遅れてしまう傾向がある」と明言されています。また、メンタル・アカウント(心の会計)理論では、人は得た利益を「別腹扱い」しやすく、損失はいつか取り戻せると思い込んでしまうとも言われます。その結果、心理的には「含み益は確実に手元に置いておきたい神聖なお金」になりがちで、いったん上昇した価格で売却せずにいると後で売りどきを逸してしまいます。一方で、含み損の確定には必要以上に抵抗し、損失を抱え込んでしまうのです。
このような心のクセに抗うためには、自分なりのルール作りが欠かせません。次節ではその具体策を見ていきますが、まずは「含み益=ただの幻」という意識づけが重要です。含み益は決して永続するものではなく、「いつでも消える可能性がある」という覚悟を持って投資に臨みましょう。
【個人投資家の防衛策】ルールで守るAI銘柄投資
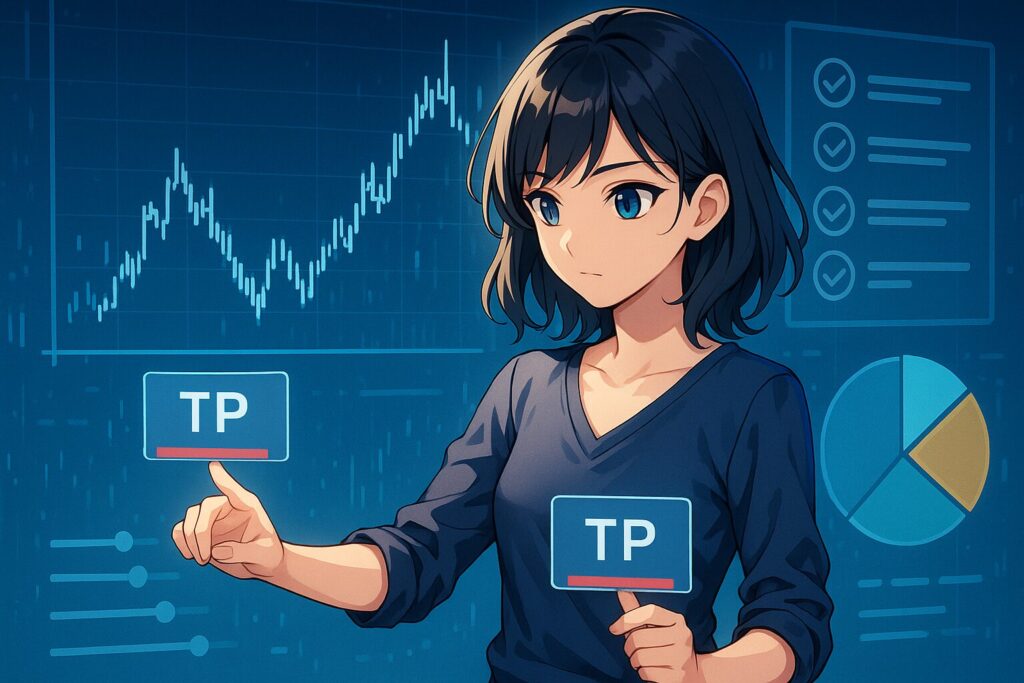
AI関連株の急騰相場では、「もっと上がってくれ!」というワクワク感と同時に「どこで売ればいい?」という悩みが付きまといます。ここでは個人投資家が取るべき具体的アクションプランを提案します。カジュアルな投資家目線で、簡単に実践できる利食い・損切りルールを数字付きで考えてみましょう。
ストップロスで逆指値設定
まず最も基本となるのが損切りラインの設定です。逆指値(ストップロス)注文を使えば、株価が一定の下落幅に達したときに自動的に売却が行われ、大きな下落被害を防げます。投資知識サイトによれば、逆指値は「投資における自動安全装置」のようなもので、設定した価格に株価が達すると市場売り注文に切り替わり損失を限定してくれるツールです。たとえばNVIDIAを200ドルで買っていたら、下落リスクを10%程度に抑えるために180ドルに逆指値を置く、といった具合です。こうすれば、不意の急落が来ても事前に決めた範囲外には損失が広がりません。
実は心理学的にも逆指値は強力です。研究によれば、投資家は往々にして損切りをためらい、含み損を抱え込む傾向がありますが、逆指値を設定すると感情を排して冷静に売却できるメリットがあります。Investopediaでも、逆指値注文は「感情を取引から排除する有効な手段」だと説明され、実際に「損失ポジションを持ちすぎて、利益ポジションを早く手放しすぎる」という投資家の悪いクセ(ディスポジション効果)を抑えられるとされています。つまり、ストップロスをあらかじめ入れておけば、暴落時に狼狽(ろうばい)せず、あらかじめ決めたルールどおりに淡々とポジションを手放せるわけです。
利益確定ルールを数字で宣言
ストップロスと対になるのが利益確定(利食い)ルールです。これも同様に数字で宣言しておくと強い味方になります。例えば「この銘柄は○%上がったら売る」と目標を定めておく方法があります。実は投資ツールには「テイクプロフィット注文」という、含み益が一定額に達したら自動的に売却する機能もあります。たとえばNVIDIAが12倍になったような急騰局面では、利益確定の感覚が鈍りがちですが、具体的な目標値を決めておくことで感情に左右されずに売却できます。Nomuraのコラムでも、「利益が出ている株は全て売ってしまうのではなく、一部だけ売って様子を見る」という合理的な売り方が紹介されています。上昇相場の最中には、ある程度売却して利益を確保し、残りはさらに伸びるかもしれないというプランBを持つのが安心です。目標を定める際には、大きく伸びた銘柄は20~30%上昇地点、小さな値動きの銘柄は5~10%幅など、個別にルールを変えておくと良いでしょう。
分散とキャッシュ比率で守りを固める
最後に、ポートフォリオ全体の防御力を考えます。AI関連銘柄に全ての資金を投じるのはギャンブルに等しいため、全体の資産配分を見直すことが重要です。リスク管理の基本は分散投資です。具体的には、AI銘柄の比率をあらかじめ20%程度に抑える、残りの資金は複数の業種・地域に振り向けるといった工夫が考えられます(あるアドバイスではAI関連株は20%以下に調整するよう推奨されています)。また、金(ゴールド)や債券といったリスク回避資産に一部を配分し、キャッシュ(現預金)も一定比率持っておけば、市場急落時に買い増しや損失補填の余裕が生まれます。急いでナンピン(含み損株の買い増し)して資金枯渇…といった最悪パターンにならないよう、「万一の下落時に使える資金」を常に手元に残しておきましょう。
さらに、メンタル面のルールも持っておくと安心です。たとえば「1ヵ月経って○○円以上の利食いがなかったら、ポジションの半分を整理する」「含み損が●%に達したら必ず全決済する」といった具体的なシナリオを自分なりに持っておけば、感情に流されにくくなります。こうした「損切り・利確ルール」も、事前に書き出しておくことで実行しやすくなります。どんなに上昇相場でも、冷静な投資計画があれば慌てずに対処できるはずです。
【まとめと未来へ】学びを力に変える
AIバブルの加熱と急落は、私たち個人投資家にとって大きな学びのチャンスでもあります。含み益に目が眩むと判断を誤りがちですが、今回のように市場全体に過熱感が広がるときこそ「含み益は幻」と割り切る勇気が必要です。企業会計の「のれん減損」のように、上昇相場は必ず反転する時が来る――この事実を肝に銘じておけば、暴落時にも冷静に対応できます。
これからもAI技術は社会に大きな恩恵をもたらすでしょう。しかし、それを織り込んだ株価には過剰が伴いやすく、どんな先端企業でも成長には限界があります。だからこそ私たちは、長期的な目線と堅実なリスク管理を同時に持つべきです。今回学んだ「損切りラインを決める」「利益目標を宣言する」「分散で守りを固める」といった教訓は、決して大げさな保守ではなく、どんな投資環境でも生き残るための自衛策です。特にこれから投資を始める初心者の方は、相場の荒波に巻き込まれる前に、しっかりと地力をつけておくことが肝要です。
最後に、投資は一人旅ではないことを忘れないでください。同じ時代を生きる投資家仲間として、今回紹介した知識や経験を共有し合えば、苦しい局面も乗り越えやすくなります。市場がどんなに荒れても、学びと工夫で自分の資産を守れるという自信があれば、投資は単なるギャンブルではなく、人生設計の力強いパートナーになり得るのです。このブログが皆さんの投資旅路の一助となり、波乱が去った先に穏やかな達成感をもたらすことを願っています。読者の皆さんがリスクをしっかり管理しながらAI時代の恩恵を享受し、笑顔で成果を分かち合える未来を心から応援しています!
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書
インフレ下での「守り×攻め」の設計図を、投資理論・行動経済学・地政学・リスク管理の4本柱でわかりやすく整理。初心者~中級者が“数字で語るルール作り”(利確・損切り・比率管理)を学ぶのに最適。「AI銘柄で含み益が出てる、でも出口戦略が曖昧…」→出口を“方程式化”できます。今のうちに。
いちからわかる!株入門 2024年新NISA対応版
超やさしい基礎固め。口座開設~注文の種類(逆指値含む)・リスク分散・NISA活用まで“つまづきポイント”を丁寧に解説。「まずは“仕組み”と“型”を正しく覚えたい」→はじめの一冊として鉄板。AI相場の波に乗る前に、転ばない歩き方を。
60分でわかる! 行動経済学 超入門
ディスポジション効果(含み益は早売り/含み損は持ち続けがち)や損失回避など、“心のクセ”が投資を歪める理由を1時間で把握。実践の矯正ポイントまでコンパクト。「頭では分かってるのに手が動かない」→行動を変える“心理のショートカットキー”を手に入れよう。
富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッド
行動ファイナンスの第一線が、良い投資家に共通する10の基本ルールを明快に示す。テイクプロフィット/ストップロスの“感情排除”を促す実践的フレームが役立つ。「ルールは作った。でもブレる」→迷いを“仕組みで封じる”ための決定版。
決算書楽ちん理解(週刊ダイヤモンド 2023年6/24号)
「のれん」「減損」を含む実務寄りの特集。企業会計側の“期待の資産”が、景気後退や見通し悪化で一気に減額されるメカニズムを掴めます。“含み益=未実現のれん”という今回の比喩が腑に落ちるはず。「会計視点で“含み益の危うさ”を腹落ちさせたい」→1冊で要点をすばやく。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21692136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1314%2F9784295411314_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21195593&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8889%2F9784295018889_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21321963&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3831%2F9784297143831_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21046889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6928%2F9784198656928_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=22428309&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8038%2F2000013168038.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す