みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
そのAI投資、本当に“未来の利益”になっていますか?
いま世界中でAI(人工知能)の活用が加速する中、その裏側で見逃せない動きが起きています。それは、「AIを適切に使うためのコスト」にスポットライトが当たり始めていることです。特に欧州連合(EU)ではAI規制(通称「AI法」)の施行に向けて、企業への負担を和らげるための微調整が検討されています。このブログを読むことで、「AI時代に賢く投資するには何に注目すべきか」が見えてきます。
AIビジネスに関心のある20〜30代の皆さんにとって、規制対応やガバナンス(AIの管理・統制)への投資が一時的な設備投資(CAPEX)なのか、それとも継続的な運用コスト(OPEX)なのかは重要なテーマです。一見地味に思えるかもしれませんが、この視点を持つことで、企業の真の実力を見抜いたり、自分のキャリア戦略を考えるヒントを得られたりします。結果として「この会社は将来AIで伸びるのか?」「持続的な成長のために何が必要か?」といった問いに答える材料が手に入るでしょう。
本記事では、EUの規制動向からガバナンス投資の性質、そして投資家として見るべきポイントまで、社会人として押さえておきたいポイントを徹底解説します。読み終えたとき、あなたはAIガバナンスの費用を「コスト」ではなく「未来への投資」として捉え直し、明日からの意思決定に活かせるようになるはずです。
EU AI法の微修正:何が起きているのか?
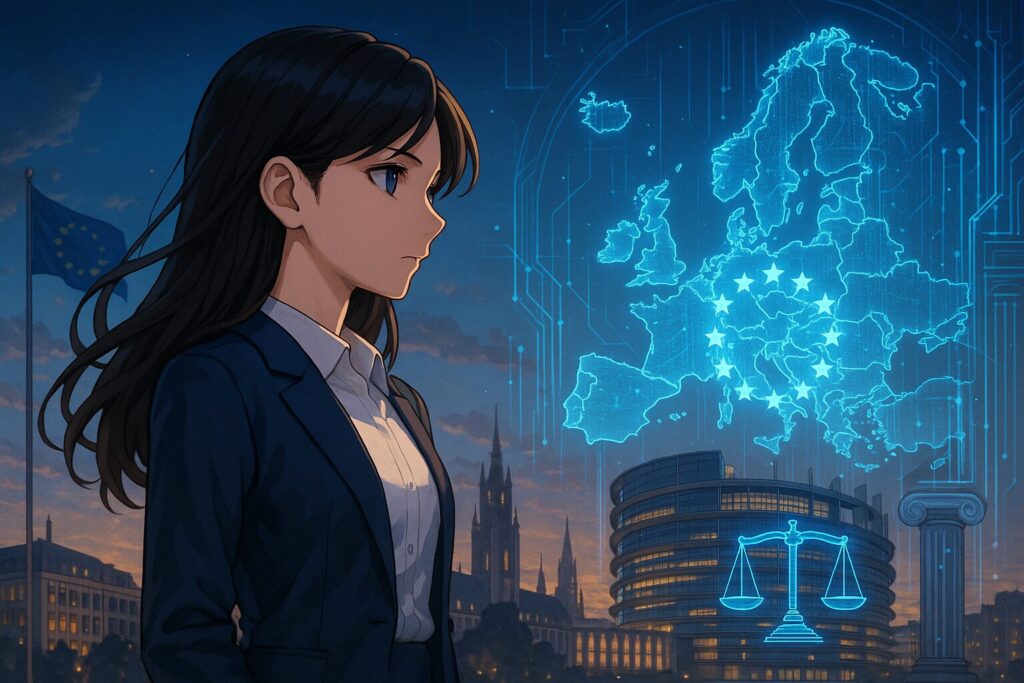
規制のアップデートに潜むドラマ
昨年成立したEUの「AI法」(人工知能に関する包括規制)は、世界初の包括的AI規制として大きな注目を集めました。しかし、規制の細かな運用を巡ってテク業界や加盟国から懸念の声が上がり、EU当局はその適用方法について微修正を検討しています。2025年11月、欧州委員会は「デジタル簡素化パッケージ(Digital Omnibus)」なる一連の見直し策を準備し、AI法の一部義務の施行を遅らせることや企業の実務負担を軽減する措置を発表する見込みです。この動きの背景には、「AI規制が厳しすぎるとイノベーションを阻害する」というビッグテック企業や一部加盟国の強いロビー活動があります。実は、このドラマの舞台裏にはAI産業の未来を左右するせめぎ合いがあるのです。
規制強硬路線から一転、柔軟路線へ?
EUのAI法は2024年に発効したものの、各条項の施行時期は段階的に数年かけて進む予定でした。当初は欧州らしく厳格な規制を掲げ、違反すれば最大で年間売上の7%または3,500万ユーロの罰金という強い姿勢でした。しかし、2025年に入って業界から「現実的な対応が難しい」「技術基準がまだ整っていない」という悲鳴にも似た声が上がります。たとえばAI法では「高リスクAIシステム」を提供・利用する企業に対し、リスク管理や透明性確保、膨大な技術文書の整備、人による監督などが義務付けられています。これらは社会にとって必要なルールですが、中小企業やスタートアップにとっては負荷が大きい。さらに決定的だったのは、AI法の詳細を支える技術標準(スタンダード)が未整備だったこと。欧州委員会のテック担当委員ヘンナ・ヴィルッカネン氏も「来年8月の主要施行までに標準が揃わず、このままでは業界に法的不確実性を与えてしまう」と認めています。こうした状況を受け、EUは強硬一辺倒ではなく実務に即した柔軟路線を模索し始めたのです。
負担軽減策の具体像
では具体的にどんな緩和策が検討されているのでしょうか。報道によれば、AI法の一部義務について1年間の「グレースピリオド(猶予期間)」を設け、違反時の罰金適用開始を2027年まで遅らせる案が浮上しています。例えば、本来2026年8月から全面適用となる高リスクAIの要件について、2027年夏まで当局が罰則適用を控えるといった措置です。これにより、既に市場投入済みのAI製品を持つ企業も事業を止めずに必要な調整ができる猶予が生まれます。また、AIで生成したコンテンツの表示ラベル義務(「AI生成」と明示するルール)など一部の透明性規定についても、施行を数年遅らせることが検討されています。さらに新設される「EU AIオフィス」による集中的な執行で各国ごとのバラつきを減らし、企業がワンストップで対応できるようにする構想もあります。要するに、骨太なルール自体は維持しつつ、スケジュールと運用面で企業に息継ぎの時間を与える狙いです。欧州委は「圧力に屈したわけではなく、目的達成のための最適化だ」と強調していますが、この緩和が「必要な融通」か「過度な譲歩」かは関係者の間で議論が分かれています。
安全と革新のバランスシーソー
規制緩和には当然ながら賛否があります。一方には「これで企業は助かる、欧州でもAIイノベーションが続くだろう」という期待の声。他方には「核心となる保護措置を骨抜きにしかねない」という懸念もあります。人権団体などからは「負担軽減ばかり強調すると安全がおろそかになる」という批判が出ており、EU内でも慎重論が根強い状況です。欧州評議会の人権担当者は「規制の肝心な保護要素まで捨てないよう注意すべきだ。大企業のロビーに迎合しすぎると市民の安全が危うくなる」と警鐘を鳴らしています。つまり今、EUは安全と革新のシーソーのバランス取りに苦心しているわけです。しかしビジネスの視点から見れば、こうした調整は「規制対応コスト」をどう見るかという本質的な問題を浮かび上がらせます。企業はAIの開発・導入にどれくらいコストを割くべきか? そのコストは一過性なのか恒常的なのか? 次のセクションでは、この点を掘り下げていきましょう。
EUのAI規制は、その理想主義ゆえに現場との摩擦が生じ、一部軌道修正を迫られています。ビッグテックの圧力や技術標準の遅れを背景に、施行期限の延長や運用簡素化といった負担軽減が講じられようとしています。これは「抜け道」ではなく「滑走路の延長」です。着地点は、安全確保とイノベーション促進の両立。その成否は、企業が規制対応コストをどう捉え戦略に組み込むかに懸かっているとも言えるでしょう。では、その「規制対応コスト」とは具体的に何なのか、次の章で見ていきます。
AIガバナンスへの投資:CAPEXかOPEXか?

お金の使い方で見える企業の本気度
AIプロジェクトにまつわる費用には、派手なGPUサーバーの購入費用やクラウド利用料だけでなく、「ガバナンス(統制)コスト」と呼ばれる見えにくいお金が含まれています。ガバナンスコストとは、AIの安全・倫理・法令遵守のために必要な体制整備や管理運用の費用のことです。問題は、これが単発の設備投資(CAPEX: Capital Expenditure)なのか、毎月毎年かかる運用費(OPEX: Operating Expense)なのかという点です。例えば、新しいAIシステムを導入するために高性能サーバーを一度買ってしまえば終わり(CAPEX)でしょうか?それとも導入後も点検・監査・モデルの更新にずっと費用がかかる(OPEX)でしょうか?多くの実例を見ると、AIのガバナンス費用は一度きりでは済まず、むしろ継続的に発生する傾向があります。このセクションでは、開発現場・監査プロセス・モデル運用という3つの観点から、AIガバナンス投資の内訳を深掘りします。それによって、なぜこれらが「継続費(OPEX)化しやすい」のかを明らかにしましょう。
開発体制に組み込むコスト:品質管理と文書化
AIを開発する段階から既にガバナンスのコストは始まっています。AI法の下では、高リスクAIを扱う企業は「品質管理システム(QMS)」の確立が義務づけられます。これはソフトウェア開発プロセスにおけるルールや基準のことで、データ収集・モデル設計・テスト・リリースに至る全工程でのリスク管理を含みます。具体的には、データの偏りをチェックする仕組みや、モデルの意思決定ロジックを説明できるように記録するドキュメント作成などが求められます。これらを最初に構築するには専門知識を持った人材の投入やツール導入が必要で、確かに初期投資的な面もあります。しかし重要なのは、その後です。技術は常にアップデートされ、リスク評価も状況に応じて更新が必要なので、一度作った文書や手順も定期的に見直さねばなりません。モデルに使うデータが変われば文書を更新し、新たなリスクが判明すればプロセスを修正する…と、開発体制に埋め込まれたガバナンスは生きた仕組みとして手入れが欠かせないのです。いわば庭の手入れのように、ガバナンスの仕組みも「雑草」を抜き取り、水をやり、継続的に手間とコストをかける必要があります。一度フェンス(仕組み)を建てたからもう安心、とはいかないわけです。このように、開発体制への投資は初期費用プラス継続的なメンテナンス費と捉えるのが現実的でしょう。
監査と検証:止まらないチェック機構
AI法では高リスクAIシステムに対し、提供前の適合性評価(第三者または自己適合宣言)と、提供後の監督・監査義務が課されています。モデルをリリースして終わりではなく、「ちゃんと動いているか」「バイアスや不具合が顕在化していないか」を継続監視し、必要に応じて再評価するプロセスです。ここにも費用が発生します。例えば社内にAI監査チームを置いて定期的にモデルの精度や公正性をチェックしたり、外部の専門家に年次レビューを依頼したりするケースが考えられます。これら監査費用は、当然毎年(場合によっては四半期ごと)発生する運用コストです。さらに、AIの世界では次々と新たなリスクや課題が見つかるため、監査項目自体もアップデートが必要です。昨年問題なかった項目が今年は規制当局から新たに指摘される可能性もあります。企業はそのたび監査手順を追加・変更しなければなりません。例えて言えば、AI監査は健康診断というよりも日々のバイタルチェックに近く、常時見守る人件費・システム費用がかかるのです。また国ごとに規制の細部が違えば、各地域向けにチェックリストをカスタマイズする必要も出てきます。グローバル企業なら地域別の法規制に対応するための追加コストもばかになりません。結局のところ、監査・検証に関わる支出はランニングコストとして計上せざるを得ない性質を持っていると言えます。
モデル運用と管理:AIは作って終わりではない
AIモデルは一度作って終わりではなく、運用段階でも様々な管理が必要です。まず、モデルのバージョン管理やログの保存があります。誰がいつどのデータでモデルをアップデートしたのか、結果はどう変わったのか、といった履歴情報をきちんと蓄積する体制が求められます。これは将来問題が起きた際に原因を追跡したり、当局への説明責任を果たすために不可欠です。そのためのMLOpsツール(機械学習の運用管理ツール)やデータガバナンス用ソフトに投資する企業も増えています。これらはクラウドサービスで提供される場合も多く、月額・年額のサブスクリプション料金(OPEX)として計上されます。また、モデルを継続運用する中で、精度の劣化や環境変化(データの変化によるドリフト現象)が起これば、追加の再学習やチューニング作業が必要です。生成AIのように大規模モデルであれば、新しい知見へのアップデートやプロンプトの最適化など、運用フェーズでも手が抜けません。さらにAI法への適合性を維持するため、定期的な安全テスト(ロバストネス検証や精度確認)も義務化されます。このテスト費用もやはり繰り返しかかるものです。例えば、ある分析ではAIシステム1つあたり年間約3万ユーロ(約450万円)のコンプライアンス維持費用が見積もられています。これは上限的な試算とはいえ、モデル運用中ずっと費用が積み上がることを示唆しています。要するに、AIモデルのライフサイクル全体にわたって、ガバナンス維持のコストは継続発生するのです。
以上のように、AIの開発から運用に至る各フェーズで要求されるガバナンス対応には継続的なリソース投入が不可避です。開発プロセスへの品質管理の埋め込み、定期的な監査・検証、モデル運用時の監視とアップデート――これらはいずれも「やりっぱなし」にできない性質であり、月日とともに人件費やツール費用が積み上がります。もちろん、一部には最初の環境構築に大きなCAPEX(例えばガバナンス用の社内システムを構築する等)がかかるケースもあるでしょう。しかし多くの場合、その後の運用・維持にかかるOPEXが主役となります。AIガバナンスへの投資は、派手な設備よりむしろ地道な運用費として表れてくるのです。この現実を踏まえると、企業がAIに本気で取り組むなら「ガバナンスの固定費」をしっかり予算化し続ける覚悟が要ります。そして投資家の立場から見れば、その固定費を会社がどう位置付けているかが一つの見極めポイントになるでしょう。次のセクションでは、投資や経営の視点からこのガバナンス固定費についてさらに掘り下げます。
投資家は何を見るべきか:ガバナンス固定費と持続可能性

経費の中身から企業の未来を読む
AI時代の企業を見るとき、「この会社はAIにちゃんと責任を持って取り組んでいるか?」という視点が重要になっています。なぜなら、どんなに革新的なAIサービスでも、規制違反や不祥事でストップがかかれば元も子もないからです。投資家やビジネスパーソンにとって、企業のIR資料(投資家向け情報)や年次報告書を読む際には、AIガバナンスにどれだけリソースを割いているかに注目する価値があります。このセクションでは、まずガバナンス固定費を軽視した場合に起こり得るリスクを確認し、次に企業がそれをどう開示・対処しているかを見抜くポイントを紹介します。そして最後に、ガバナンス投資を「コスト」ではなく「価値創造」へ転じている企業が実際に成果を上げている事例も交え、読者である皆さんが感動する(!)ようなポジティブな未来像を描いてみます。
「安物買いの銭失い」のAI版:ガバナンス軽視のツケ
まず強調したいのは、ガバナンスに投資を惜しむと結局高くつくということです。日本語で言う「安物買いの銭失い」のAI版が、まさにこれに当たります。初期にきちんとガバナンス体制を整えないままAIを導入すると、後になって法的リスク・運用コストの膨張・システム作り直しという三重苦に見舞われる可能性があります。例えば、AIの判断ミスで人命や人権に関わる事故が起これば、多額の訴訟コストや社会的信用の喪失につながります。また、ずさんなデータ管理のままシステムを走らせた結果、予期せぬ挙動(いわゆる「AIの暴走」や「ハルシネーション」)が頻発し、対処のために後からシステムを大改修する羽目になるかもしれません。ガートナーの予測でも、適切なガバナンスを欠いたAI導入による法的トラブルが今後急増すると警告されています。実際、AI規制への不遵守や倫理問題に起因する損失を経験した企業はほぼ全て(ある調査では99%)に上り、平均損失額は4億円超との報告もあります。要は「ちゃんと対策するコスト」と「問題が起きてから火消しするコスト」を比べると、後者の方がはるかに高いのです。投資家にとって怖いのは、ガバナンス軽視が企業価値を一夜にして蒸発させるリスクです。罰金だけでなくブランド毀損や株価暴落を招くリスクファクターとして、AIガバナンスは無視できません。極端な例を出せば、ある自動運転AIスタートアップでは1回の導入に34万ドルものコンプライアンス費用(R&D費の2倍以上!)がかかったケースも報告されています。高くつきますが、裏を返せばそれだけしないと安全確保できないとも言えます。ガバナンスに投資を惜しんだ企業は、いずれもっと大きな代償を払うことになる——この認識をまず持つことが大切です。
IRでここをチェック!「ガバナンス固定費」の開示
では実際に企業を見る際、どんな点に注目すればガバナンス投資の実態が掴めるでしょうか。ポイントは、企業が自分からその重要性を語っているかどうかです。たとえば上場企業であれば、年度の経営報告や決算説明資料に「AI戦略」の項目があることがあります。そこに「AIガバナンス体制の構築」「AI倫理委員会の設置」「コンプライアンス費用○○億円計上」などの記載があれば前向きな兆候です。また、有価証券報告書など法定開示資料のリスク情報欄に「AIに関する規制順守コストやリスク」が丁寧に説明されているかも確認しましょう。実際、S&P500企業の7割以上がAIに関するリスクを2025年時点で開示していますが、その中で「法規制対応コストの増大」や「グローバルでの規制の断片化による負担」を具体的に挙げている企業は、経営陣が真剣に課題認識していると見て良いでしょう。逆に、AIを積極活用していそうなのにまったくそうした言及がない場合は要注意です。「大丈夫かな、この会社はちゃんとやっているのかな?」という目で見る必要があります。さらに投資家としては、直接IRに問い合わせたり説明会で質問したりするのも有効です。「AIのガバナンスにどれくらいの予算を割いていますか?固定費として見ていますか?」といった問いかけに明確に答えられないようだと、その企業は本質的な部分にフタをしている可能性があります。企業側も昨今は投資家からのESG(環境・社会・ガバナンス)目線に敏感ですから、質問する価値は十分あります。要するに、IR情報で「ガバナンスの固定費」をちゃんと開示・説明しているかをチェックすることが、未来の成長企業を見極める一手なのです。
ガバナンス投資が生むプラスの価値
ここまでガバナンス怠りのリスクや費用の話をしてきましたが、最後にぜひ知っておいてほしいのは、ガバナンスへの投資が企業にもたらすプラス効果です。実は、しっかりAIガバナンスを実践している企業ほどビジネス上の成果も上がっているという調査結果があります。あるグローバル調査では、リアルタイムのAIモニタリング体制やAI倫理委員会を持つ企業は、収益成長が加速しコスト削減効果も高い割合で報告されています。具体的には、リアルタイム監視を導入した企業はそうでない企業に比べてコスト削減が達成できた割合が65%も高いというデータもあります。これは、ガバナンスがしっかりしているとトラブル対応など無駄な出費が減り、また安心感から顧客やパートナーの信頼を得てビジネス拡大につながるためでしょう。さらに、AI法のような規制を単なる足枷ではなく「競争優位のチャンス」と捉えている企業も存在します。彼らはあえて早期に規制順守を果たし、業界標準をリードすることで「うちは安全で信頼できるAIを提供できます」というブランドを築いています。そうした会社は、大企業から調達先として選ばれやすくなったり、規制対応に出遅れた競合を尻目に市場シェアを伸ばしたりしています。投資家にとっては、ガバナンスをきちんとやっている企業は中長期で見てリスクが低いだけでなく、市場での信頼プレミアムという価値を享受できるという点で魅力的です。事実、あるベンチャーキャピタルは「高リスクAI領域のスタートアップに投資する際は調達額の15〜20%をコンプライアンス費用に充てるよう見積もる」と述べています。これは裏を返せば、それだけ上乗せしても将来リターンが見込めると判断しているからでしょう。ガバナンス投資は決して「コストセンター」ではなく、信頼という無形資産を積み上げる戦略的投資なのです。
投資家やビジネスパーソンにとって、AIガバナンスへの支出は企業の持続可能性を占う重要なファクターです。ガバナンス軽視は一時的にコスト削減になるように見えて、結局は法務リスクや事故対応でより大きな損失を招く「負ける戦略」です。一方で、積極的にガバナンスに取り組む企業は規制対応力そのものを競争力に変え、信頼を武器に成長しています。IR情報を読む際は、その企業がAIガバナンスを固定費(いわば守りの経費)としてしっかり組み込んでいるかを見極めましょう。そこには経営陣の本気度と先見性が表れます。そして、そうした企業は短期的な利益だけでなく長期的な企業価値の向上を狙っていることが多いのです。次章の結論では、私たち読者自身がこの知識をどう活かせるか、そして未来にどんな展望を持てるかを締めくくりたいと思います。
結論:未来への投資としてのガバナンス
AI時代のビジネスにおいて、「ガバナンスへの投資」は単なるコストではなく未来への先行投資です。ここまで見てきたように、EUの規制動向から学べるのは、どんなに革新的なテクノロジーも信頼なくしては社会に受け入れられないということです。ガバナンスにかかる費用は一見地味で利益を生まないように思えるかもしれません。しかし、それは企業にとって信頼という名の礎を築くための必要経費であり、ひいては安定した成長と持続的なイノベーションを支える土台となります。AIガバナンス投資を怠った企業が一瞬の躓きで巨額の代償を払う一方、地道に取り組んだ企業がユーザーや社会から愛され長く繁栄する——そんなコントラストがこれからますます鮮明になるでしょう。
私たち若い世代の社会人もまた、この変化のただ中にいます。自分の働く会社や応援する企業に対し、「この会社はちゃんとAIを責任持って使っているだろうか?」と問いかけてみてください。その問いは、単にリスク回避のためだけではなく、より良い社会を共に創るパートナーを選ぶことにもつながります。ガバナンスに真摯な企業は、従業員にとっても誇りとなり、顧客にとっても信頼のブランドとなります。そうした企業を見極め支えていくことが、私たち自身の安心と成長にも返ってくるのです。
最後に、AIガバナンスにまつわるある種の感動的な光景を思い浮かべてみましょう。厳しい規制を「壁」と捉えるのではなく、それを乗り越えることでかえって企業文化が研ぎ澄まされ、社員一人ひとりが倫理観と使命感を持ってAI開発に取り組む。そんな組織はきっと強い絆で結ばれ、困難にも柔軟に対処できるでしょう。ガバナンスへの投資は、人と技術の信頼関係への投資でもあります。AIがもたらす便利さと驚きの陰で、それを支える縁の下の力持ちとしてガバナンスがあります。その存在に気づき、大切にする人や企業が増えれば、私たちのAI社会はもっと安全で豊かなものになるはずです。
AI時代の幕開けに立ち会う私たちだからこそ、長い目で見た価値に注目していきたいですね。目先の利益だけでなく、未来の安心と信頼をも見据えた意思決定——それこそがこれからの時代を生き抜くカギなのかもしれません。ガバナンスという名の未来への投資を惜しまない企業と共に、私たちもより良い明日を築いていきましょう。そう信じられるからこそ、このテーマを深掘りしてきましたし、あなたにもぜひその目で確かめ、応援していただきたいのです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『AIガバナンス入門 リスクマネジメントから社会設計まで』羽深宏樹
AIガバナンスってそもそも何?というところから、リスク管理・制度設計・社会との付き合い方まで一気通貫で押さえられる「土台の1冊」です。
難しい理論書というより、実務と政策のあいだをつなぐ“地図”的な本なので、今回のブログテーマと相性バツグン。
「AIガバナンスって流行りワードじゃなくて、ちゃんと意味あるな…」と腑に落ちるので、AI投資やIR読みの解像度を上げたい人は、まずここから押さえておくとお得です。
『EUのAIガバナンス──新技術に対する国際的な科学技術ガバナンスに向けて』北和樹
EU AI法がどういう発想で作られ、どんな政治・技術的背景から今の形になったのかをがっつり解説する一冊。
「条文をなぞる本」ではなく、EUが何を守ろうとしているのか/なぜここまで規制に本気なのかがストーリーとして見えてきます。
ブログで扱った“微修正”のニュースも、この本の視点を知っているとかなり深く読めるようになるので、EU発のAI規制をちゃんと理解したい投資家・実務家にはほぼマスト本です。
『生成AIの法律実務』松尾剛行
著作権・個人情報・契約・弁護士実務…と、生成AIを巡る「実際に揉めるポイント」が全部乗せで整理されている本です。
生成AIを導入する企業の側から見ても、どこに法的地雷が埋まっていて、どう避ければいいのかがかなり具体的にイメージできます。
「リーガルは難しそう」と敬遠しがちなビジネスパーソンこそ、この1冊を読んでおくと、IR資料の“AIリスク”の中身がちゃんと読めるようになるので、投資判断の精度が一段上がります。
『AI時代のベンチャーガバナンス』馬渕邦美・丸山侑佑
スタートアップのガバナンスをテーマにしつつ、AI時代ならではのリスクとチャンスをどう経営に組み込むかを掘り下げた本です。
章立ての中に「AIガバナンス」「AIを活用するコーポレート・ガバナンス」が入っていて、まさに今回のブログとド直球にリンクします。
VC目線・経営者目線の話が多いので、「AIガバナンスにちゃんとお金を割いているスタートアップのどこを評価すべきか」を具体的に学びたい人にはかなり刺さる内容。未上場も含めてテック投資している人には特におすすめです。
『図解でわかる ESGと経営戦略のすべて』
ESG全体を扱う本ですが、ガバナンスと経営・事業ポートフォリオ・情報開示まで一気におさらいできる“ESG×経営戦略”の総合ガイドです。
図解が多く、財務・会計バックグラウンドがある人には「これこれ、この整理が欲しかった…」となるタイプの構成。
AIガバナンスはESGの「G」に直結するテーマなので、
- AIガバナンスをどこまで固定費として許容するべきか
- その投資が中長期の企業価値にどうつながるか
を考えるうえで、ベースフレームとして1冊持っておくとかなり心強いです。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21111528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0177%2F9784153400177.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21528224&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9216%2F9784771039216_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21558108&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0138%2F9784335360138_1_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21278679&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5356%2F9784296205356_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21075582&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0648%2F9784534060648_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す