みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
その“マイナス成長”ニュース、本当にあなたの持ち株にどこまで効いていますか?
ここ最近、「日本経済マイナス成長」「6四半期ぶりの景気後退」といった少し物騒なヘッドラインを目にする機会が増えてきました。7–9月期の日本の実質GDPは年率換算で▲1.8%、6四半期ぶりのマイナス成長。背景には、アメリカによる日本製品への関税引き上げで、輸出がじわじわ削られている現実があります。
ただ、多くの個人投資家にとっては、「GDPがどうなろうが、正直よくわからない」「関税ってニュースには出てくるけど、自分の持ち株とどう関係あるの?」という感覚が本音ではないでしょうか。この記事では、その“モヤモヤ”をスパッと解消することを目指します。
ポイントはシンプルで、「関税は、最終的にあなたの保有銘柄のPL(損益計算書)のどこを削ってくるのか?」という一点です。関税は企業から見れば“仕入原価の上昇”と同じようなインパクトを持ちます。その結果、粗利率がじわっと悪化し、しかも在庫を経由することで、決算に効いてくるタイミングが“数カ月遅れ”になる、というクセがあります。今ちょうど、7–9月期決算・GDPという形で、その影響が数字として表に出てきたフェーズです。
この記事では、
- なぜ「マイナス成長」と「関税ショック」がセットで語られているのか
- 関税がPLのどこから企業を痛めつけていくのか(売上?原価?粗利?)
- 投資家として今すぐできる「輸出比率×粗利率×在庫回転」による“信号機チェック”のやり方
を、できるだけ専門用語を避けつつ、社会人1〜3年目の方でもスッとイメージできるように解説していきます。難しいマクロ経済の話というより、「この銘柄、今は“赤・黄・緑”のどれ?」を自分で判定できるようになることがゴールです。
読み終わるころには、「ニュースのGDPマイナス成長って、こういう銘柄には特に効いてくるんだな」「この企業は在庫回転が速いから、関税ショックのダメージが早く出て、逆に回復も早そうだな」といった視点を、自分のポートフォリオに当てはめて考えられるようになるはずです。日々の“嫌なニュース”をただ不安材料として受け取るのではなく、数字と会計の目線で、自分の投資判断に変換する力を一緒に鍛えていきましょう。
――ということで次からは、まず「日本経済は今どんな状態なのか?」をざっくり整理しつつ、関税がどのように企業の売上・原価・粗利を侵食していくのかを、具体例ベースで見ていきます。
目次
日本の「マイナス成長」と関税ショックをざっくり整理する

まずはニュースで出てきた「日本、6四半期ぶりマイナス成長」とは何が起きたのかを、投資家目線でかみ砕いておきましょう。
7–9月期(第3四半期)の日本の実質GDPは、年率換算で▲1.8%、前期比で▲0.4%のマイナスとなりました。約1年半ぶりの「マイナス成長」です。政府統計と報道ベースでも、「6四半期ぶりの縮小」「主な要因は輸出の落ち込み(米国の関税)」と整理されています。
一方で、個人消費はわずかにプラス(+0.1%)を維持しており、「国内の需要が完全に死んでいる」という状態ではありません。外需、つまり海外向けの稼ぎが関税で削られ、全体としてマイナスになったというイメージです。
ここからは、
- GDPマイナスの“ざっくり構図”
- 関税が企業にもたらす「3つの痛み」
- それが最終的にPLのどこに出てくるのか
を、初心者向けに一つずつ見ていきます。
ニュースの「GDPマイナス」は、投資家にとって何のサイン?
まず、「GDPがマイナスです」と言われてもピンと来ないですよね。投資家的にざっくり翻訳すると、「企業全体として、売上と利益を伸ばしにくい環境に入りました」という警告灯です。
今回のマイナスの主因は、
- 米国が日本からの輸入品に15%前後の関税をかけた
- その結果、日本から米国への輸出が落ち込んだ
という流れです。
輸出が落ちるとどうなるか?
- 自動車、機械、電機など「輸出比率が高い業種」の売上が頭打ち
- その企業から部品を受け取っている中小企業の仕事も減る
- 海外で儲けていたぶんが減るので、日本全体のGDPも押し下げられる
という“連鎖反応”が起きます。つまり、GDPマイナスは「輸出・グローバル銘柄の逆風強まり中」というマクロなサインと捉えると、投資家としてはイメージしやすくなります。
関税は、企業から見ると「原価がじわっと上がる」仕組み
次に、「関税って、結局なに?」という話を、会計っぽく超シンプルに整理します。
- 輸出側から見る関税
→ 自社製品が相手国に入るときに「上乗せコスト」が発生
→ 価格に転嫁できなければ、値引きしたのと同じ効果 - 輸入側から見る関税
→ 海外から仕入れる部品・原材料に追加コスト
→ 企業から見ると、仕入原価が上がるのと同じ
会計の言葉でいうと、関税は多くの場合、売上原価(コスト)を押し上げる要因としてPLに効いてきます。コストの増加をすべて販売価格に転嫁できれば利益は守れますが、実際には「競合もいるし、値上げしたら売れなくなる」という壁があるため、
- 価格に転嫁しきれない
- その分、粗利率(売上総利益率)がじわっと悪化する
という形で、利益を圧迫していきます。
この「関税=原価UP→粗利率DOWN」という流れが、冒頭で触れた1行会計メモ
関税=仕入原価↑→粗利率↓
の意味です。
なぜ「在庫を通じて遅れて効く」のか?
ここが投資家的には重要ポイントです。関税はニュースが出た瞬間にPLへドン!と出るわけではなく、在庫をワンクッション挟んで、数カ月遅れて効いてくることが多いです。
イメージをざっくり作ると:
- まだ関税がかかっていない時期に仕入れた部品・商品が在庫として残っている
- その在庫を使って作った製品を売っている間は、まだ「安い原価」の世界
- 関税がかかったあとの“高い仕入れ”で作った在庫に切り替わるタイミングで、
→ 売上原価がグッと上がる
→ 粗利率がストンと落ちる
つまり、ニュースと決算のタイミングにズレがあるわけです。関税が決まった瞬間に株価が揺れ動くのは「将来の粗利悪化」をマーケットが織り込みにいっているからで、実際の決算数字としては、在庫が切り替わるタイミングで本格的に表れます。
- 在庫回転が遅い企業:
→ 影響が出るまで時間がかかるが、いったん効き始めると長く続く傾向 - 在庫回転が速い企業:
→ 影響が早く数字に出るが、その分、対策(値上げ・コストカット・供給地変更)を打つのも早くなる余地
だからこそ、投資家としては「輸出比率」だけでなく、粗利率とともに在庫回転も見ておく必要があるわけです。
今回のGDPマイナスは「関税ダメージがPLに出始めた第一波」
ここまでを一度まとめると:
- 日本の7–9月期GDPは、輸出減少+住宅投資の落ち込みなどで年率▲1.8%
- 背景には、米国による日本製品への関税引き上げがあり、主に自動車など輸出産業が直撃
- 関税は企業目線では「原価UP→粗利率DOWN」のショック
- その影響は、在庫が切り替わるタイミングで決算にじわじわ反映される
今回のマイナス成長は、まさにその「第一波」が数字に表れた段階と見ることができます。まだ完全に出揃ったわけではなく、今後数四半期にわたって、
- 粗利率のじわり悪化
- 在庫評価や生産計画の見直し
- 価格転嫁の成否
といった形で、各社のPLにばらつきが出てくるフェーズに入っていきます。
投資家としてのスタンスは、「関税でダメージを受ける国・業種だから全部アウト」と雑に見るのではなく、
- どの銘柄がどの程度“関税ショック”を食らいやすい構造なのか
- 逆に、在庫回転が速くて立ち直りも早そうな銘柄はどれか
を、数字で選別していくことです。
次では、いよいよ本題として、
「輸出比率×粗利率×在庫回転」で、あなたの保有銘柄を“信号機”にする具体的なチェック方法
を解説していきます。
「輸出比率×粗利率×在庫回転」を“信号機”として使う

ここからが、個人投資家として一番おいしいパートです。
ニュースやGDPの数字を、「自分の持ち株をどうするか?」という具体的なアクションに変えていきましょう。
キーワードは、この記事の軸になっている
「輸出比率 × 粗利率 × 在庫回転」
です。
難しそうに見えますが、イメージとしてはこんな感じです。
- 輸出比率:その会社の「売上のどれだけが海外頼みか?」
- 粗利率:その会社が「どれくらい“おいしいビジネス”をしているか?」
- 在庫回転:その会社が「在庫をどれくらいのスピードで現金に変えているか?」
この3つを組み合わせることで、
「この銘柄、関税ショックに対して赤(縮小)・黄(様子見)・緑(維持)のどれ?」
をざっくり判定する“信号機”が作れます。
輸出比率——「どれだけ海外で稼いでいるか?」
まずは輸出比率です。これはざっくり、
売上のうち、海外向け(特に関税リスクの高い地域)でどれだけ稼いでいるか
を見ます。
初心者的には、以下のような感覚でOKです。
- 海外売上比率が70%以上:
→ 「かなり海外頼み」。米国・欧州向けの関税や景気悪化の影響をモロに受けやすい。 - 30〜70%:
→ 「バランス型」。海外の影響は受けるが、国内もそれなりに下支え。 - 30%未満:
→ 「主に国内ビジネス」。関税ショックの直撃度合いは比較的弱いことが多い。
ポイントは、「輸出比率が高い=即アウト」ではなく、
“関税ショックの入口”に立っているかどうかを知るためのラベル
だと考えることです。
決算資料や有価証券報告書には「地域別売上高」が載っているので、
- 北米向けの売上比率
- 欧州向けの売上比率
を軽く確認して、「お、この会社はけっこう海外比率高いな」とか、「意外と国内比率高いな」とラベリングしておくだけでも、ニュースの見え方が変わります。
粗利率——「どれくらい“クッション”があるビジネスか?」
次に粗利率(売上総利益率)です。
これはシンプルに言うと、
売上から“仕入や製造のコスト”を引いたあと、どれだけ残っているかの割合
です。
たとえば、
- 10,000円で売って
- 原価が6,000円なら
- 粗利は4,000円 → 粗利率は40%
となります。
関税ショックを考えるうえでの粗利率の意味は、
- 粗利率が高い会社:
→ 多少コストが増えても、「粗利の厚み」で吸収しやすい。
→ 価格転嫁(値上げ)もしやすいビジネスモデルのことが多い。 - 粗利率が低い会社:
→ ちょっとコストが増えただけで、一気に利益が削られてしまう。
→ 値上げするとすぐ顧客が離れやすい“価格競争型”ビジネスの場合も。
ここで思い出したいのが、冒頭の1行会計メモ、
関税=仕入原価↑→粗利率↓
という流れです。つまり、粗利率が低い会社ほど、関税ショックに弱いと言えます。
ざっくりの目安としては、
- 粗利率40%以上:
→ 利益のクッションが厚め - 20〜40%:
→ 一般的な製造業・メーカーなど、中庸ゾーン - 20%未満:
→ 原価勝負・価格勝負の世界。関税でじわっと効いてきやすい
というイメージで、自分の保有銘柄の粗利率を一度ざっと並べてみると、“関税耐性マップ”が見えてきます。
在庫回転——「ダメージがいつ、どのくらい続くか?」
最後が在庫回転です。これが、関税ショックの「タイミング」と「継続時間」に関わる重要な指標です。
在庫回転とは、
1年のあいだに、在庫が何回“入れ替わっているか”
を示すイメージです。
- 在庫回転が速い
→ 在庫をどんどん売って、すぐ現金に変えている
→ 市場環境の変化が、PLに早く反映される - 在庫回転が遅い
→ 在庫を長く抱えがち
→ 一度仕入れた“高い原価の在庫”の影響が、長く尾を引く
関税ショックと組み合わせて考えると、
- 輸出比率が高く × 粗利率が低く × 在庫回転が遅い
→ 高い関税がかかった原材料・部品の在庫を抱え、
それをゆっくり消化するので、
「長くじわじわ効くタイプのダメージ」になるリスク。 - 輸出比率が高く × 粗利率がそこそこ高く × 在庫回転が速い
→ 影響は早く出るが、同時に価格転嫁や調達先見直しも早く打ちやすい。
→ 中期的には「対応力が問われるタイプ」の銘柄。 - 輸出比率がそこまで高くない × 在庫回転も速い
→ 関税ショックの直撃度は相対的に小さめで、ポートフォリオの防御枠候補になりやすい。
在庫回転は、決算書だと少し見つけにくい指標ですが、
- 「在庫回転日数」
- 「棚卸資産回転率」
などの表現で出ていることがあります。もし見つからなくても、
売上高 ÷ 棚卸資産(在庫)
のようなシンプルな計算で、“ざっくり比較”するだけでもOKです(細かい定義にこだわるより、「この会社は在庫多めだな」くらいの感覚をまず持てれば十分です)。
「輸出比率×粗利率×在庫回転」で信号機を作るイメージ
ここまでの3つをまとめて、“信号機”として使うイメージを文章で描いてみます。
- 赤(縮小検討)
- 輸出比率:高い(とくに米国向けが多い)
- 粗利率:低め(20%未満が目安)
- 在庫回転:遅い(在庫を長く抱えがち)
→ 関税による原価アップが、そのまま粗利悪化に直撃しやすく、
その影響も長引きやすい構造。ポジションを一段軽くする候補。
- 黄(様子見・決算を見ながら判断)
- 輸出比率:中〜高
- 粗利率:中〜高
- 在庫回転:中程度
→ 関税の影響は受けるが、自力である程度は吸収・調整できそうなゾーン。
決算で粗利率や在庫の増減を確認しながら、段階的に判断。
- 緑(基本維持・むしろ押し目候補のことも)
- 輸出比率:低め or 海外でも関税リスクが小さい地域中心
- 粗利率:そこそこ高い
- 在庫回転:速い
→ 関税ショックの直撃度が相対的に低く、ビジネスモデルの耐性も高い。
マクロの悪材料で全体が売られているときに、逆に仕込み候補になる場合も。
もちろん、これはあくまで“ざっくりフレーム”です。
ですが、この3つの軸を頭に入れておくだけで、ニュースを見たときに
「あ、この材料は“赤寄り銘柄”には強烈に効くやつだな」
「この会社は粗利厚くて在庫回転も速いし、そんなに慌てなくてよさそう」
といった具合に、冷静に判断しやすくなります。
実践編——あなたのポートフォリオを“信号機”で仕分けする
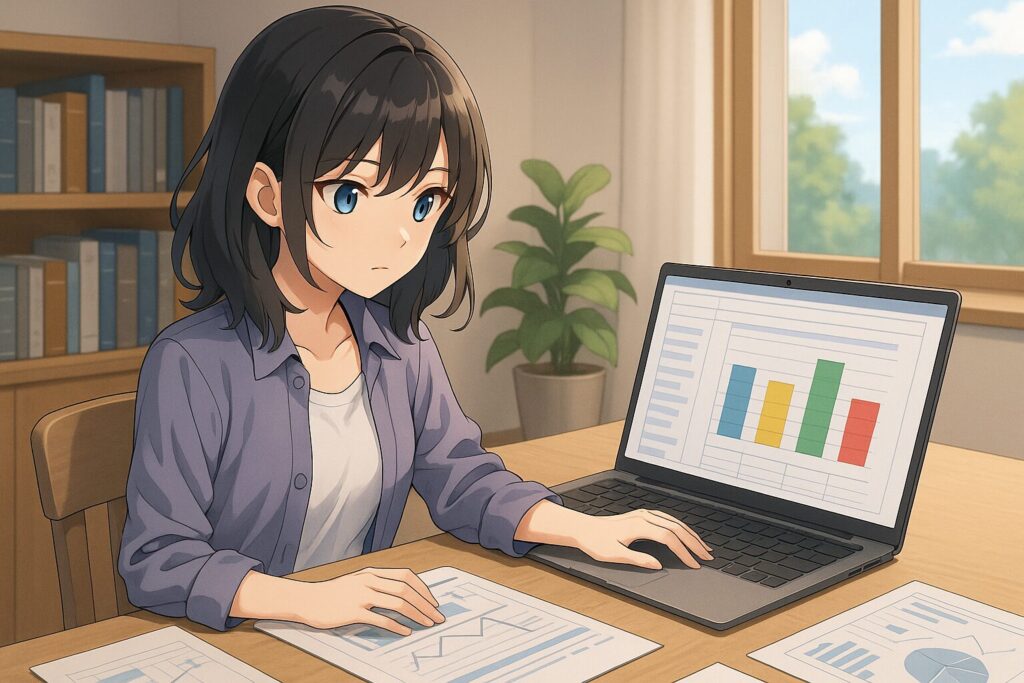
ここからは、いよいよ「手を動かすパート」です。
難しいことは一切しません。紙のノートでも、エクセルでも、証券会社アプリのメモ機能でもOKなので、“自分専用の信号機リスト”を一緒に作るイメージで読んでください。
やることはシンプルに3ステップです。
- 保有銘柄(気になる銘柄)をリストアップ
- 「輸出比率・粗利率・在庫回転」をざっくり3段階評価
- その組み合わせで、赤・黄・緑に色分けする
完璧な数字よりも、「ざっくり方向性がわかること」を優先してOKです。
STEP1——保有銘柄リストと“3つの数字”を集める
まずは、今持っている銘柄、もしくはウォッチしている銘柄を10〜20社くらい書き出します。
メモの列イメージはこんな感じです:
- 銘柄名
- 銘柄コード
- 輸出比率(海外売上比率のざっくり感)
- 粗利率(売上総利益率)
- 在庫回転(速い・ふつう・遅いの感覚でOK)
- 信号機(赤・黄・緑)
「いや、その数字どこから取ればいいの?」という話ですが、初心者なら細かく計算しなくてもだいたいで大丈夫です。
- 輸出比率(海外売上)
→ 決算説明資料やIR資料に「地域別売上高」「海外売上比率」としてグラフが載っていることが多いです。
→ 見つからなければ、会社紹介に「海外売上が○割」と書いてあるケースも。
→ ざっくり「海外7割っぽい」「半分くらい」「ほぼ国内」とメモするだけでOK。 - 粗利率
→ 証券会社アプリの「指標」タブに“売上総利益率”が出ていることもあります。
→ 出ていなければ、- 売上総利益 ÷ 売上高 ×100
を電卓でサクッと計算するだけでも十分です。
→ 「40%台」「20%前後」「10%台」くらいの大雑把なくくりで問題なし。
- 売上総利益 ÷ 売上高 ×100
- 在庫回転
→ 決算資料に「棚卸資産回転率」や「在庫回転日数」が出ていればそれをチェック。
→ なければ、- 棚卸資産(在庫)の額が売上に比べて大きい → 在庫多め=回転遅め
- 在庫の額が小さい → 回転そこそこ速そう
くらいの“感覚評価”でまずは十分です。
ここで大事なのは、一気に完璧を目指さないことです。
最初は「○」「△」「×」の3段階でもいいので、“なんとなくの位置づけ”を自分の手でつけてみることが、後々効いてきます。
STEP2——3つの数字を「強・中・弱」にざっくり分類する
次に、それぞれの指標を3段階でラベリングします。目安はこんな感じ。
- 輸出比率
- 高:海外売上が70%以上 or 「ほぼ海外向け」と書いてある
- 中:30〜70%
- 低:30%未満(国内中心)
- 粗利率
- 高:40%以上
- 中:20〜40%
- 低:20%未満
- 在庫回転
- 速:在庫が少なめ/回転率高め
- 中:特に多くも少なくもない
- 遅:在庫が売上に対してかなり多い/回転率が低い
この3つを組み合わせて、
「この銘柄は“関税ショックに弱いセット”が揃ってるか?」
をチェックしていきます。
イメージしやすいように、仮想のA社・B社・C社で例を出します。
- A社
- 輸出比率:高(北米向けが多い)
- 粗利率:低(15%)
- 在庫回転:遅(在庫山盛り)
→ 「高×低×遅」の危なっかしいセット
- B社
- 輸出比率:中(国内・海外半々)
- 粗利率:中(30%)
- 在庫回転:中〜速
→ そこそこ耐性あり。「様子を見つつ決算で判断」タイプ
- C社
- 輸出比率:低(ほぼ国内)
- 粗利率:高(45%)
- 在庫回転:速
→ 関税ショックの直撃度は低く、ビジネスの“強さ”も感じる
この3社を並べると、「関税」という環境変化に対して、誰が一番殴られやすいかがだいたい見えてきますよね。
STEP3——赤・黄・緑で“行動の優先順位”を決める
最後に、行動の目安として「信号機」をつけます。ルールはざっくりで構いません。
- 赤(縮小・要注意)
- 輸出比率:高
- 粗利率:低
- 在庫回転:遅
→ 3つのうち2つ以上が“弱い”方向なら、赤寄り判定でOKです。 - アクションの例:
- ポジションを少し軽くしておく
- 決算で粗利率・在庫が悪化していたら、さらに縮小も検討
- 黄(様子見・ウォッチ強化)
- 強いところも、弱いところもある“中庸タイプ”
→ 「すぐに売るほどではないが、放置もしない」ゾーン。 - アクションの例:
- 次の決算で、粗利率と在庫の推移を必ずチェック
- 経営陣が、「値上げ」「調達先変更」などの対策を打っているかも見る
- 強いところも、弱いところもある“中庸タイプ”
- 緑(基本維持・場合によっては買い増し候補)
- 関税ショックの直撃度が低く、ビジネスモデルも安定気味
- マクロの悪材料で全体が下げているときでも、
「この銘柄は長期で持っていてもいいかな」と思えるグループ。 - アクションの例:
- 基本ホールド
- 市場全体が悲観モードのときに、少しずつ拾う候補としてウォッチ
ここで大事なのは、
赤だから即ゼロ、緑だから絶対安心、ではない
ということです。
信号機はあくまで、
- 「どの銘柄のリスクを先に点検すべきか?」
- 「どこに時間とエネルギーを優先的に使うか?」
を決めるための、簡易レーダーのようなものです。
ヘッドラインを“恐れる側”から“使う側”へ
「日本経済マイナス成長」「関税ショック」みたいな見出しって、何となく不安をあおる方向に働きがちですよね。
でも、今つくったような簡単なフレームを持っていると、
- 「このニュースで一番しんどくなりそうなのは、赤ゾーンの銘柄だな」
- 「緑ゾーンは、むしろ“巻き込まれ安売り”が来たらチャンスかも」
と、ニュースを“材料”として自分の判断に変換できるようになります。
大事なのは、「完璧に当てること」ではなく、
“なんとなく不安”をやめて、“数字をベースにした不安”に変えること
です。
数字に落とせれば、
- どれくらいリスクを取るか
- どれくらいポジションを軽くするか
- どこで深呼吸して待つか
を、自分の頭で決めやすくなります。
結論:ニュースに振り回される人から、「数字で選ぶ人」へ
ここまで読んでくれたあなたは、もうすでに「マクロニュースにただビビるだけの投資家」ではありません。
日本の7–9月期マイナス成長というヘッドライン、その裏側にある関税ショック、そしてそれが仕入原価↑→粗利率↓→在庫を通じて遅れて効くという流れでPLに落ちてくることを、一通りイメージできるようになったはずです。
そして何より大事なのは、
「輸出比率 × 粗利率 × 在庫回転」
という、シンプルだけど実戦的な“ものさし”を手に入れたことです。
- ニュースを見るときに、「この話はどの銘柄の“輸出比率”に関係しそうかな?」と考えてみる
- 決算が出たら、「粗利率は上がった?下がった?」「在庫は増えた?減った?」と数字を1〜2個だけでも追ってみる
- ポートフォリオを見直すときに、「この銘柄は赤寄り?黄?緑?」とざっくりラベルをつけてみる
たったこれだけでも、投資の解像度が一段上がります。
プロの機関投資家のように、完璧なモデルを組む必要はありません。
むしろ個人投資家の強みは、
- 気になった銘柄を自分のペースで深掘りできること
- 「わからない」「苦しい」と感じたら、ポジションを軽くして一歩引けること
です。今回の“信号機フレーム”は、その判断を少しだけ後押しするためのライトな会計メガネだと思ってください。
もちろん、現実の相場はこのフレームどおりには動きません。
赤判定の銘柄が急騰することもあれば、緑だと思っていた銘柄が急落することもあります。でも、それでもなお、
「なぜその銘柄を持っているのか」
「なぜ今、そのポジションサイズなのか」
を、自分の言葉で説明できるかどうか——ここに、長く続けられる投資と、ストレスで折れてしまう投資の差が出てきます。
もし今日の記事を読み終えて、「よし、まずは3銘柄だけでも信号機をつけてみるか」と思えたなら、それだけで大きな一歩です。
最初はガタガタな表でもかまいません。月に1回でもいいので見直していくうちに、「この企業は粗利率が落ちてきたな」「在庫が増えてきたな」と、ニュースより一歩早く“変化の兆し”に気づけるようになっていきます。
ヘッドラインはこれからも、“不安になる言葉”であなたを揺さぶってくるはずです。
でも、そのたびにこの記事を思い出して、
- 関税は原価と粗利率にどう効く?
- この銘柄の輸出比率・粗利率・在庫回転は?
- 赤・黄・緑、今の自分ならどう判断する?
と、一呼吸おいてから動ける投資家でいてください。
ニュースに振り回される側から、ニュースを自分の武器に変える側へ。
その一歩目として、今日のフレームをぜひあなたの投資ノートに刻んでおいてもらえたらうれしいです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『決算書「分析」超入門2026 ー 100分でわかる!』佐伯良隆
「決算書アレルギー」の人が、まず1冊だけ読むならこれ。
シリーズ累計18万部超の人気入門書で、最新2026版ではトヨタやメタ、メルカリなど実在企業の数字を使いながら、「どこを見れば会社の“体調”がわかるのか」をサクッと教えてくれます。
- BS・PL・CFのつながりを、“人の体”にたとえた説明がとにかくわかりやすい
- 「売上よりも、この数字の変化を見よう」といった“プロっぽい視点”を短時間でインストールできる
- 本文のテーマで出てきた粗利率や在庫の見方も、図解でしっかりフォロー
「ニュースを見て“なんとなく不安”から、“決算書でちゃんと確かめる”にレベルアップしたい人」に、かなり刺さる一冊です。
『これならわかる決算書キホン50!〈2026年版〉』木村直人
キーワード単位で“おいしいところだけつまみ食い”できる、最新決算書辞典。
2025年版の新しい解説書で、「売上総利益」「営業利益率」「在庫回転率」など、決算書でよく見る50ワードだけをギュッと絞って解説してくれます。
- 1トピックがコンパクトにまとまっているので、スキマ時間で1項目ずつ読める
- 会計用語が“ニュースの言葉”とセットで説明されているので、記事の内容と相性抜群
- 「この指標が悪化してきたら要注意」といった“赤信号のサイン”も明確
ブログで紹介した「信号機チェック」を、実際の決算書に当てはめていきたい人におすすめです。
『儲かる会社にはパターンがある! 決算書の基本と読み解き方』足立武志(監修)
「どの会社が“儲かる構造”なのか?」を、決算書から読み解く実践本。
2022年発売と比較的新しく、個人投資家にも人気の足立武志さんが監修した一冊。財務3表やPER・PBRなどの指標を、「儲かる会社のパターン」を軸に解説してくれます。
- 決算書の基本だけでなく、株式投資でどう使うかまで踏み込んでいる
- いい会社・微妙な会社の決算書を比べる“ビフォーアフター”的な説明があり、初心者でも直感的に理解しやすい
- 「この数字の組み合わせの会社は要チェック」という“スクリーニングのヒント”が多い
ブログの「赤・黄・緑フレーム」を、“儲かるパターン”という視点から補強してくれる一冊です。
『株で資産3.6億円を築いたサラリーマン投資家が教える 決算書「3分速読」からの“10倍株”の探し方』はっしゃん
「全部読むのは無理。でも伸びる株だけは見逃したくない」人向けの、時短・決算書本。
サラリーマンを続けながら、成長株投資で3億円超の資産を築いた“はっしゃん”氏が、決算短信1ページから伸びる株を見つけるコツを教えてくれます。
- 「精読は要らない、速読で十分。見るのはここだけ」という割り切りが痛快
- 売上・利益の伸び、ROEなど、個人投資家が本当にチェックすべき数字だけを厳選
- 実際に10倍株になった銘柄を例に、「どんな決算書の“形”をしていたか」を具体的に解説
この記事で扱った「ざっくり信号機チェック」を、“3分速読”スタイルで日々の投資に落とし込みたい人にぴったりです。
『コンサルタントが毎日見ている経済データ30(日経文庫)』
マクロニュースを“怖い見出し”から、“使える数字”に変えるための1冊。
現役コンサルタントが、GDP・物価・雇用・為替など、ビジネスパーソンが押さえておきたい30の経済指標の読み方を解説している本です。国内外のニュースと絡めながら、「この指標が動くと、現場では何が起きるか」が語られます。
- 「このデータが悪化したら、どの業界・どの銘柄が影響を受けがちか」がイメージしやすい
- グラフや事例が多く、数字が苦手な人でも“ストーリー”として理解できる
- 日々のニュースと自分のポートフォリオをつなぐ、“マクロ視点の地図”として使える
この記事のテーマである「日本のマイナス成長」「関税ショック」を、より広い経済データの中で位置づけて理解したい人におすすめです。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21710681&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0814%2F9784022520814_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21683845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9113%2F9784502549113_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20662785&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2353%2F9784816372353_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20461532&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3749%2F9784046053749_1_11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21322945&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0246%2F9784296120246_1_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












コメントを残す