みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
なんか、ChatGPTの文章って、“丁寧だけど回りくどい”──まるで“おっさんLINE”じゃない?
そんな印象を抱いたことがあるなら、あなたの感覚はかなり鋭い。実はそれ、偶然じゃなく“構造的な必然”なんです。
ChatGPTをはじめとするAIが生成する文章と、巷で話題の“おっさん構文”──実はこの2つ、情報の詰め込みすぎ・空気の読めなさ・読者との距離感という意味で、不思議な共通点を持っています。
でもこれは、AIだけの問題じゃない。Slack、企画書、Xの投稿、日常のLINE…あなた自身の言葉も、知らぬ間に“情報が多いだけで、伝わらない”文章になっていませんか?
このブログでは、そんな「伝わらない現代病」の正体をあぶり出し、
“読者の時間と感情を奪わない”新しい情報整理術を提案します。
✅ 本記事で得られること
📌 ChatGPTと“おっさん構文”の意外な共通点
── なぜ似てしまうのか?構造・心理・UX視点から分析します。
📌 “伝わる文章”をつくるための実践テクニック
── 要約・感情タグ・余白の使い方まで、具体例を交えて解説。
📌 会計・投資の視点で文章の“資産価値”を見直す方法
── 企業IRやSNS戦略にも応用可能な、“言葉のキャッシュフロー思考”。
ビジネスでも、SNSでも、私たちは毎日「言葉の投資家」だ。
この5,000字は、あなたの文章力を「読みやすく、伝わる、好かれる」へと進化させる知的アップデート。
では最初に、“AIもおじさんもやりがちな情報過多の罠”を解体していきましょう。
目次
なぜChatGPTは“おっさん構文”になりがちなのか?

ChatGPTはなぜ回りくどいのか?
ChatGPTを使ったことがある人なら誰もが一度は感じる、「文章は丁寧だけど、なんだか遠回しで冗長だな…」という印象。それ、実はChatGPTの“優しさ”が原因なんです。AIは、ユーザーの意図を取りこぼさないようにあらゆる可能性を網羅しようとします。その結果、自然と「断定を避ける」「複数の視点を提示する」「条件をつける」文章になりやすい。これは、悪気のない“保険だらけの会話”であり、情報密度を上げる代わりに「読むコスト」を跳ね上げてしまっているのです。
しかも、ChatGPTは“正解”を出すモデルではなく、“もっともらしい会話”を生成する言語モデル。ゆえに、明確な結論よりも、言い回しのバランスを優先しがち。これが、丁寧すぎるビジネスメールや「ご無沙汰しております」連打LINEに似てしまうゆえんです。丁寧語と曖昧語で構成された文体は、一見礼儀正しいようで、実は“感情距離が遠くて情報価値が低い”という、現代の文章病を象徴しています。
情報密度の高さは“伝わる”を保証しない
人は1日に34GBもの情報を浴びているとも言われます。まさに脳のハードディスクは常に満杯状態。ここで誤解しがちなのが、「たくさんの情報を伝えるほど有益」という思い込みです。しかし現実は逆。情報を詰め込みすぎると、相手のワーキングメモリを圧迫し、内容が頭に残らないどころか、「読むのが面倒」と切り捨てられてしまうリスクがある。特に、SNSやSlackのような“流し読み文化”の中では、ファーストビューで理解できない文章は、たとえ中身が正確でも評価されません。
これは、財務分析で言えば“情報はあるけどKPIが見えない”状態に似ています。決算資料が10ページあっても、重要な数字が埋もれていたら、投資家は読むのをやめます。それと同じことが、文章でも起きているのです。
読者が求めているのは“要約+感情の余白”
読みやすい文章には、ひとつの共通点があります。それは「余白」です。ここで言う余白とは、見た目のスペースではなく、“読み手の脳に解釈の余地を残す構成”のこと。たとえば、すべてを説明しきらずに「あなたならどう思いますか?」と問いかけを残す文章は、読者にとって“参加可能なストーリー”になります。これはちょうど、投資家向け資料で未来予測のロジックだけを提示し、結論は相手に委ねる手法と同じ。言い換えれば、“余白のある文章”は、読み手に思考の主導権を渡す強力なコミュニケーション設計なのです。
そしてこの「余白」を削ってしまうのが、“おっさん構文”や“過保護なAI文章”です。何でもかんでも説明しようとすると、読み手の解釈の余地は奪われ、結果として「親切すぎてうざい」「読んでも残らない」印象を与えてしまう。
このように、ChatGPTが“おっさん構文”に似てしまうのは、AIの特性ゆえの必然。問題は、そのままでは「伝わらない情報」が量産されてしまうこと。次のセクションでは、この情報過多をどう整理し、読者との感情距離をどう縮めるかを探っていきます。
伝わる文章に必要なのは「感情距離の設計」

会話で信頼を築くのは、情報量ではなく“距離感”
人はなぜ、たった一言で信頼する相手と、1時間話しても距離が縮まらない相手がいるのでしょうか?その答えは“情報量”ではなく、“感情距離”にあります。心理学では、相手との距離が近いほど曖昧な言葉でも通じやすく、遠い相手には具体的で構造化された表現が必要だとされています。つまり、同じ文章でも、前提の共有度や関係性次第で「伝わる/伝わらない」が大きく分かれるのです。
ここに、AIの文章が“よそよそしい”と感じられる理由があります。ChatGPTは基本的に、ユーザーと関係性を持たない“ゼロ距離の他人”として出力をするため、どうしても丁寧すぎて回りくどい。距離が近い相手には不要な前置きも、AIはすべて説明しようとするため、“読み疲れ”が生まれてしまうのです。だからこそ、現代の情報発信には、読者との距離を縮める“感情デザイン”が不可欠なのです。
「余白」と「問い」が感情を引き寄せる
情報を削るのは勇気が要ります。何かを伝えたいときほど、つい言葉を増やしてしまうものです。でも、実際に人の心を動かすのは“完璧な説明”ではなく、“余白”です。たとえば「自分だったらどうするだろう」と考えさせる問いかけや、「あのときの感情に近いな」と感じさせる抽象度の高い比喩。これらはすべて、読み手の感情を“参加者”として物語に巻き込む仕掛けです。
優れたマーケティング文章は、すべて「感情の余地」があります。行動喚起するボタンにも、“今すぐ始める”ではなく“ちょっと覗いてみませんか?”と柔らかく誘う表現が選ばれるのは、クリック率だけでなく「抵抗感」を減らす設計がされているから。これは読み手の“心理コスト”を下げるUXライティングの発想であり、感情距離の設計でもあります。
ChatGPTがこの余白を作れないのは、“完結して出力すること”が設計思想だからです。だからこそ、私たち人間が一文一文に“余白と問い”を意識的に設計してあげることが必要なのです。
感情設計は投資の世界でも通用する
実はこの“感情距離のデザイン”は、投資家とのコミュニケーションでも極めて重要です。たとえば、あるスタートアップが、決算説明資料において「前年比○%増」だけを載せるか、「このKPIに賭けた理由」といった背景ストーリーまで開示するかで、投資家の印象は大きく変わります。後者は、数値以上に「この経営者がどんな視点で未来を見ているか」を伝えるものであり、数字に感情を添えることで距離を縮め、信頼を生むのです。
つまり、文章にも“ROE”がある。限られた文字(=自己資本)で、どれだけ相手の感情(=リターン)を動かせるか。その視点で言えば、丁寧すぎる説明も、過剰なデータ提示も、無駄なコストです。感情設計された一言が、人を動かし、信頼を生み、やがてキャッシュフローや企業価値にまでつながる。伝わる文章とは、投資リターンの高いコミュニケーションそのものなのです。
次のセクションでは、この“感情距離を縮めた”上で、どのように情報を整理し、読者の脳に残る文章に変えていくか。その実践的テクニックを、投資や会計の視点を交えて紹介していきます。
情報整理は「言葉の財務モデル」だ
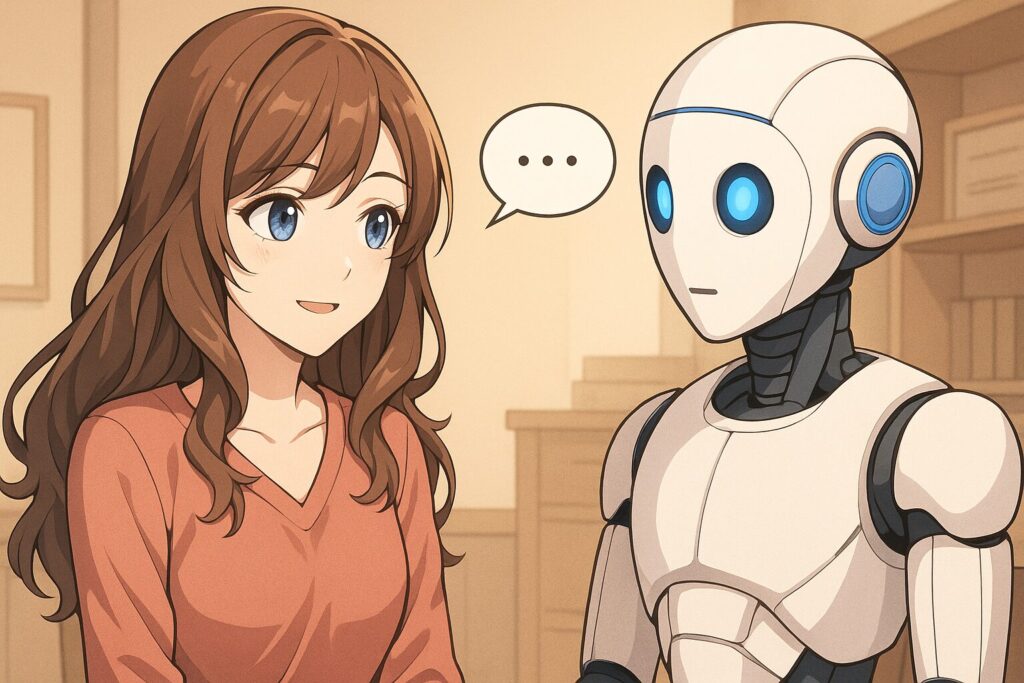
箇条書きはキャッシュフロー、本文はPL
文章にも“財務三表”に似た構造があると考えると、驚くほど整理がしやすくなります。たとえば、本文=損益計算書(PL)。これは主張やエピソードなど、伝えたい本筋が詰まっている“収益の源泉”です。一方で、脚注・注釈や補足的な情報は貸借対照表(BS)のような存在で、全体のバランスを保ちつつも直接的な印象は薄い。では箇条書きや見出しは? これはまさにキャッシュフロー計算書(CF)に相当します。読者がすぐに“使える情報”、つまり脳に残り、行動に転化される“即効性の高い要素”です。
多くの人が「とりあえず全部書いておこう」と情報を詰め込みすぎてしまう背景には、この構造の不在があります。整理されていない文章は、BSに現金がない企業のように、読む側の脳内リソースを枯渇させる。伝えたいことを“分離・分類・見える化”するだけで、文章は一気に流動性を帯び、読者の理解スピードが跳ね上がるのです。
ナラティブは非財務資産を磨く武器
今やIRやプレゼン資料の世界では、“ナラティブ”が企業価値を左右するとまで言われています。ナラティブとは、数字に意味づけを与える“物語”のこと。売上や成長率の羅列ではなく、「なぜその数字が出せたのか」「その数字に込められた意志は何か」を語ることが、投資家との距離を縮め、企業への信頼を深める鍵になります。
これを文章に置き換えれば、「なぜ今これを書くのか」「読者にどんな行動を促したいのか」を文中で語ることがナラティブです。ただ情報を提示するだけでは、人の心は動かない。たとえば「節税対策」ではなく「子どもの未来のための経済的な備え」と表現したほうが、人はずっと共感しやすい。これは会計でいうと、非財務情報の“人的資本”や“ブランド力”に相当する要素であり、可視化されにくいけれど価値の源泉になるのです。
良い文章とは、数値と感情が連動する“言葉のナラティブ会計”。数字だけでも、ストーリーだけでも足りない。その両方が融合したとき、読者の信頼という「資本」が蓄積されていくのです。
情報整理も“減損回避”が命
最後に重要なのは、「情報を管理することは、資産を守ること」と捉える視点です。文章を書いていると、「過去の資料を流用した」「思いついたことを全部メモに残した」という情報の山ができあがります。これは言わば、償却されないまま溜まり続けた無形資産。もし定期的に見直さなければ、読み手にとっては価値のない“情報のゴミ”です。
企業でいう“のれん減損”のように、意味のない情報が溜まり続けると、文章全体の信用度が下がります。これはNotionやGoogleドライブでも同じで、整理されていない情報空間は、結果として「読み手に探させる」「理解させる」という隠れたコストを生んでしまう。情報を定期的に捨て、構造を見直すことは、読者との信頼関係を損なわないための“リスク管理”でもあるのです。
整理とは、伝えるための贅肉を落とすこと。そして削ぎ落とされた言葉が残すものこそが、本質であり価値です。
次はまとめとして、なぜこの“文章力×会話術×会計思考”が、あなたの仕事・キャリア・ブランド価値にまでつながっていくのか。その結論をお届けします。
結論:言葉は「感情の資産」、あなたの未来を変える投資である
ChatGPTが“おっさん構文”に似てしまう理由は、単なる設計の癖ではなく、私たち自身の“伝える技術”が問われている証でもあります。情報を詰め込みすぎて伝わらず、感情を配慮しすぎて距離ができる──そんな現代の文章病に、私たちはもう気づき始めています。
けれど、希望はここにあります。情報を整理し、余白をつくり、感情との距離を丁寧にデザインすることで、たった一文が、人の行動を変え、信頼を生み、人生の流れを変えることさえある。言葉には、無形の価値を持った“資産”としての側面があるのです。
そしてその資産は、誰にでも磨けます。あなたが今日書くSlackの一文、上司に送るメール、SNSの投稿。そのひとつひとつが、未来のあなたを形づくっている。言葉とは、日々積み上げる“感情の複利”なのです。
伝えることを恐れず、削ることを恐れず、余白に信頼を込めて。あなたの文章が、誰かの背中をそっと押す瞬間を、きっと未来が待っています。だからこそ、次の一文から、変えてみましょう。
あなたの言葉には、世界を少しだけやさしく変える力があるのです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『UXライティングの教科書 ユーザーの心をひきつけるマイクロコピーの書き方』
ボタン文言やエラーメッセージの言い回しなど、UXライティングの基本と実践を豊富な事例で解説。CTRやCVR改善につながる微調整の技術が学べます。
『戦略的UXライティング ― 言葉でユーザーと組織をゴールへ導く』
GoogleやMicrosoft出身の著者が、UXコピーの書き方、プロジェクト進行、効果測定まで、組織の目的とユーザー体験を両立させる手法を体系的に解説。
『秒で伝わる文章術』
日本語UXライターが執筆。漢字・ひらがな・カタカナ混在の日本語特性にフィットした“速く読ませて伝える”具体技術を紹介。練習問題も豊富。
『CFO思考 日本企業最大の「欠落」とその処方箋』
企業の財務面に鋭く切り込む一冊。会計・キャッシュフローの視点を文章や資料に応用する「会計的思考法」を学べ、ビジネス文章の説得力を高めます。
『60分でわかる! ファイナンス超入門』
簿記やファイナンス未学習の人に向け、キャッシュフローや貸借対照表など基礎概念を短時間かつわかりやすく解説。文章の論理構造にも通じる知識が身につきます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20234637&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7336%2F9784798167336.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20616376&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9878%2F9784873119878_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20599769&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1773%2F9784866801773_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20935006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8047%2F9784478118047.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21606358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9079%2F9784297149079_1_47.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す