みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
VIXが45を超えた今、本当に恐れるべきものは“市場”ですか?それとも“決算書”ですか?
2025年4月4日、世界の金融市場に激震が走りました。VIX指数――いわゆる「恐怖指数」が45.33を記録。
これは2020年のコロナ・ショック以来、実に5年ぶりの水準です。
その引き金となったのは、2日前、トランプ大統領が突如発表した関税政策の再導入。
それはまるで、誰も予期しなかった“第二の関税戦争”の開戦宣言のようでもありました。
「これは一時的なパニックなのか? それとも本格的な下落相場の始まりなのか?」
この問いに対する答えは、単にニュースを追うだけでは見つかりません。
本稿では、VIXの急騰が何を意味するのか、そしてその裏で静かに動く会計上の数値変化を丁寧に読み解くことで、投資家が今どんな選択をすべきかを導き出していきます。
▼このブログで得られる3つのポイント
- 歴史が語るVIX急騰の“型”を可視化
リーマン、コロナ、ボラマゲドン……過去のボラティリティ急騰局面と会計データを重ねて、今の市場の「温度感」を定量的に測ります。 - 関税が財務諸表に与える“静かな爆弾”を解説
関税の影響はニュース以上に、企業のPL(損益計算書)やBS(バランスシート)に遅れて出てくる。このタイムラグが投資判断の落とし穴です。 - 三段ロケット式ポートフォリオ戦略を提示
守る・測る・攻める」の三段階で、具体的なオプション戦術・会計KPI・セクター配分に落とし込んだ再現性の高いアクションプランを公開します。
VIXが急騰した局面は、たしかに“恐怖”が支配します。
しかし、歴史をひもとけば、恐怖の裏側には常に“過剰”という投資チャンスが存在していました。
数字を正しく読み、恐怖を言語化できる者だけが、そのチャンスを掴めるのです。
目次
歴史は韻を踏む:VIX急騰3大事件を会計データで紐解く

恐怖指数が語る“過去の構図”──それは投資家心理と会計イベントの掛け算だった
VIX指数が跳ね上がるとき、市場では「予測不能な危機」が語られます。
しかし、過去のVIX急騰を冷静に並べると、浮かび上がる共通項があります。
それは、単なる“突発的な出来事”ではなく、投資家心理と会計インパクトが共振したときにこそ恐怖が爆発的に可視化されるという事実です。
例えば2008年のリーマン・ショック。
VIXは89という前代未聞の水準を記録しましたが、背景には金融機関の資産の時価評価ルール変更(FAS157)がありました。
特に Level 3 資産―すなわち「市場価格が存在しない金融商品」の評価が、企業の損益計算書とバランスシートを一気に揺らしたのです。
資産の“幻の減損”により自己資本が急激に毀損し、投資家の信頼が消えました。
決算書の数値が信用できない、それが真の恐怖の正体でした。
数字が読めなくなることへの恐怖──2020年コロナ・ショックの教訓
もうひとつ忘れてはならないのが、2020年のコロナ初期に起きたボラティリティの爆発です。
VIXは一時80を超えましたが、このとき企業が最も苦しんだのは“未来の数字”が立てられなくなったことでした。
IFRSやUS‑GAAPでは、将来のキャッシュフロー予測に基づいて固定資産やのれんを減損評価します。
ところが、世界中がロックダウンし、売上予測も、資材調達も、為替前提も“一寸先は闇”となったとき、企業は一斉に減損や棚卸資産の評価損を計上せざるを得なくなったのです。
このように、「明日、企業がどれだけ稼げるか」を計算できなくなった瞬間、市場の不確実性は指数関数的に跳ね上がりました。
単にパンデミックという外的要因だけでなく、企業決算の“可視性”が失われたこと自体がボラティリティを呼び込んだのです。
“構造の歪み”が作る瞬間爆発──2018年ボラマゲドンのケース
そして2018年のいわゆる「ボラマゲドン」は、もっと異質なVIX急騰でした。
このときは実体経済に目立った悪材料があったわけではありません。
しかし、VIXのショートポジションに特化したETN「XIV」が、1日で90%以上下落して強制償還されたことをきっかけに、金融工学と流動性の歪みが市場を襲いました。
これは、まさに金融商品の設計と会計処理の落とし穴が暴かれた瞬間であり、VIXの本質が「市場の感情」ではなく「構造的脆弱性」を映し出す鏡であることを証明した出来事でした。
以上の歴史が教えてくれるのは、恐怖指数の“跳ね”は、心理的ショックと数字の信頼性が同時に失われたときに発生するということです。
ニュースヘッドラインやチャートだけでは捉えきれない“会計の地雷”を見逃さないこと。
それこそが、VIXという荒波を読むための第一歩です。
2025年4月「45.33」の真実:トランプ関税×決算シーズンの地雷原

電撃発表された関税政策が引き起こした“72時間の混乱”
2025年4月2日、トランプ大統領はホワイトハウスで緊急記者会見を開き、突如として全輸入品に一律10%、また国ごとにそれぞれ相互関税を課すと発表しました。
狙いは「米国の製造業を取り戻す」というお馴染みのスローガン。
しかし、市場が驚いたのはそのスピードです。
発効日はわずか72時間後の4月5日午前0時。つまり、週末を挟んでたった3日で、あらゆる企業が価格改定・在庫再評価・契約条件の見直しを迫られたのです。
とくにアパレルや食品、日用品など、輸入比率が高く価格転嫁が難しいセクターは対応に苦慮し、翌日にはすでに大手小売数社が「即日値上げ」を発表。
消費者心理を冷え込ませるトリガーとなりました。
企業現場の混乱に反応するように、株式市場も動きました。
4月4日の米国市場では、S&P500がマイナス5.97%と急落、VIXは45.33で引け、これは2020年コロナ初期以来の水準です。
VIXがここまで跳ねるのは、単に価格変動への恐怖ではなく、「企業の未来が読めない」という深層心理の表れです。
まさにそれを裏付けるように、同日、プットオプションの出来高は過去最高を更新。
多くの機関投資家がヘッジに走り、“恐怖”が市場全体のコストとして価格に反映されていきました。
会計的に見える“3つの地雷”が、企業の財務を静かに揺らす
では、関税は企業の会計にどう影響するのか?
まず一つ目は売上原価の増加です。
関税コストが直接商品単価に上乗せされるため、粗利率が悪化し、営業利益が圧迫されます。
とくに値上げが難しいディスカウント系小売や外食企業では、2〜5%の原価上昇が致命的打撃になりかねません。
二つ目は棚卸資産の評価の問題です。
関税発効前に仕入れた商品は“旧価格”ですが、以降は“高コスト商品”となります。
FIFO(先入先出法)を採用している企業では、決算タイミングによって利益が一時的に水増しされる可能性があります。
これは翌四半期以降に逆回転し、EPSが急落するというリスクに変わります。
投資家は、数字だけを見て判断すると、帳簿の“時間差トリック”に引っかかってしまうのです。
三つ目の地雷は繰延税金負債(DTL)の膨張です。
関税増加は損金として処理されますが、税法上の資産償却や一部控除との時差により、バランスシート上のDTLが膨らみます。
これはキャッシュフローと利益の“逆転現象”を生み出し、フリーCFの予測を困難にします。
つまり、財務モデルが不安定になるため、企業価値評価に使用するDCF法などにも影響を及ぼすのです。
決算カレンダーとの“時間差”が恐怖を延命させる
今回の関税ショックの特異点は、VIXの高騰が“継続的な恐怖”を誘発する構造にあることです。
4月5日に関税が発効したということは、4月〜6月期(Q2)の業績にダイレクトに影響が出るということ。
そしてその決算発表は7月下旬から8月にかけて行われるため、今の時点で市場は「どれくらい悪化するのか」を予測するしかありません。
これこそが“見えない恐怖”の正体です。
さらに、企業側もこのタイミングで通期の業績見通しを修正する可能性が高く、決算発表のたびに市場がショックを繰り返すリスクがあります。
つまり今回の関税は、「一撃で終わらず、段階的に市場心理を冷やしていく」という特徴を持つ、時間差爆弾型の政策なのです。
このように、2025年4月のVIX急騰は表面的な価格変動以上に、会計的な時差と市場心理のズレが生み出した構造的な不安に根ざしています。
恐怖の本質は“わからないこと”にあります。
だからこそ、投資家には数字の奥にある意味を読み解く力が問われているのです。
投資家がとるべき“三段ロケット”戦略

第1段階:守る──ヘッジコストを最小化しながら防御ラインを構築せよ
市場に急激な恐怖が走る局面では、まず“守る”が最優先です。
VIX45超という極端な状態では、インプライド・ボラティリティ(IV)が高騰しており、保険としてのオプション価格が跳ね上がっています。
だからといって無策でポジションを持ち続けるのは、火中の栗を素手で拾うようなものです。
最も現実的な戦術は、プロテクティブ・プットの分散購入です。
S&P500やNASDAQ指数に対して、2カ月満期、デルタ‑0.25のプットオプションを保有することで、大きな下落に備えつつ、日々の値動きに振り回されるのを防ぎます。
また、VIX先物市場では“バックワーデーション”が観測されており、期近のVIX先物が期先より高くなっています。
この環境では、短期ヘッジ商品のロール戦略(期近売り・期先買い)が有効です。
これにより、毎月のロール時にキャリー益が発生し、単なる保険コストではなく収益源として機能する可能性があります。
さらには、長期国債や金(ゴールドETF)をポートフォリオに組み込むことで、恐怖が極まったときに資金が流れ込みやすい「逆相関資産」としてリスクを分散させることも忘れてはなりません。
第2段階:測る──財務KPIと会計指標で“耐性企業”を見極めよ
守りを固めたら、次にやるべきは“測る”です。
すなわち、市場の混乱に対してどの企業がどれだけの耐性を持つかを、定量的に評価する段階です。
ここで有効なのが、輸入コスト比率と価格支配力の組み合わせです。
例えば、輸入比率が20%以下かつ、価格決定権を持つ企業(SaaS企業、医療サービス、小売のPBブランドなど)は、関税コストの転嫁が比較的容易で、収益性の維持が期待できます。
また、在庫回転日数×関税影響率の指標は非常に実用的です。
これは、関税ショックが企業業績にどのくらい滞留するかを示す“ダメージ持続指数”ともいえます。
たとえば在庫回転30日で関税影響が5%なら、「150」という数値になり、この数値が小さい企業ほど被害の持続時間が短く済みます。
投資先を選ぶ際には、こうした指標をスクリーニングの基準にすることが、次の攻めに繋がります。
さらに、繰延税金負債(DTL)/総資産の比率が5%未満の企業は、税効果のブレが少なく、将来キャッシュフローの安定性が高いことを示しています。
これはDCF評価などにおける“信用度”に直結し、EPSの修正耐性にも反映されるため、特に中長期投資では重要な観点となります。
第3段階:攻める──“過剰な恐怖”にこそ収益機会が宿る
守りと測定が完了したら、ようやく“攻める”フェーズです。
VIX45超という高インプライド・ボラティリティ環境では、IV>RV(実現ボラ)が極端になりやすく、オプションの売り手にとって有利な状況が生まれます。
ここで有効なのがショート・ストラングル戦略です。
満期近く・IVがピークアウトした銘柄に対して、適度な価格帯でプットとコールの両方を売ることで、プレミアム収益を狙います。
ただし、ブラックスワン的な急落に備えて、OTMプットによるテールヘッジを忘れてはいけません。
もうひとつ、相場の乱高下を「利回り強化」に変える方法として、配当成長株+カバードコール戦略があります。
株式を保有しつつ、短期コールオプションを売却することで、キャピタルゲイン+プレミアムの“二重取り”が狙えるだけでなく、配当による下支えがリスク緩和にもつながります。
さらに、セクター全体の“重心移動”を捉える意味では、セクター・ローテーション戦略が重要です。
関税によってメリットを受ける産業、たとえば米国に製造拠点を持つ航空宇宙、防衛関連、医療機器などは強くなる一方、輸入依存度が高い小売・自動車セクターはアンダーパフォームが想定されます。
これらのマクロ的視点と、個別企業のファンダメンタルを組み合わせることで、戦略的な“攻め”が現実のリターンに結びついていきます。
この“三段ロケット”は単なる理論ではなく、恐怖の渦中でも落ち着いて行動するための実践的なフレームワークです。
どんなに市場が荒れていても、会計とロジックに基づいた意思決定をすれば、他の投資家が狼狽する瞬間こそ、あなたの優位性が最大化するタイミングとなるのです。
結論─恐怖は“価格”であり“価値”ではない
VIXが45を超える市場は、確かに荒れています。
ヘッドラインは不安を煽り、SNSには“暴落”や“崩壊”という言葉が飛び交います。
でも、歴史を振り返れば、そんな混乱の中にこそ、静かに種を蒔いていた投資家たちが、後に最も大きな果実を手にしてきたのです。
数字が揺れる。未来が読めない。恐怖はその隙間に忍び込みます。
だからこそ、私たちには冷静に「決算書を読み解く目」と「時間を味方につける構え」が必要です。
会計は、ただの記録ではありません。それは、企業の内なる声であり、未来に向かう足音なのです。
あなたのポートフォリオは、いま嵐の中にあるかもしれません。
でも、嵐は必ず過ぎ去ります。
そしてその後には、情報と知性を武器に動いた者だけが立てる“静かな高台”があります。
このブログが、あなたにとってその高台に向かう羅針盤でありますように。
恐怖に惑わされず、数字の奥にある真実を見つめる力を信じて、次の一歩を踏み出してください。
市場がどれほど揺れようとも、確かな分析と意志を持った投資家にとって、未来は常に希望に満ちているのです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『計数感覚スキル入門 – 投資家目線の会社数字に強くなる』
企業活動と財務数値の関連性を理解し、「計数感覚」を養うための基礎知識をやさしく解説しています。
投資家として会社の数字を読み解く力を高めたい方に最適です。
『CFO思考 – 日本企業最大の「欠落」とその処方箋』
4年連続で「ベストCFO」を受賞した著者が、企業成長と日本経済復活の鍵としてのCFOの役割を解説。
企業と個人が目指すべき道を示しています。
『企業価値向上のための資本コスト経営 – 投資家との建設的対話のために』
コーポレートガバナンス・コード改訂以降、投資家と企業の対話の基準となる資本コストについて、第一人者たちが解説。
具体的な対話事例も豊富に紹介しています。
『コーポレートファイナンス 戦略と実践』
ファイナンスの全体像を理解するための会社のライフサイクルや、コーポレートファイナンスに必要な会計の知識を体系的に解説しています。
『株式投資で勝つための指標が1冊でわかる本』
会計関連の書籍で信頼のある小宮氏が、ファンダメンタル分析を基に、景気指標や投資信託についても解説。財務諸表分析や経済指標の読み方を学べます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20757309&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3015%2F9784502443015_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20935006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8047%2F9784478118047.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20078718&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8662%2F9784532358662.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19454384&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5412%2F9784478105412.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20420510&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0429%2F9784569850429.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
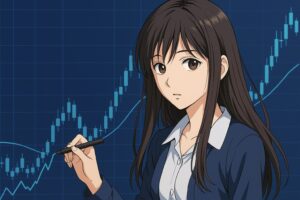












コメントを残す