みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
補助金が降っても、“製造原価”は本当にあなたの投資を守ってくれる?
みなさんはニュースで「半導体メーカーの稼働率ショックにより業績急落」なんて見聞きしたことはありませんか?例えば、世界最大の半導体受託生産企業TSMC(台湾積体電路製造)は、2025年上半期だけで各国政府から約22億3千万ドル(約3000億円)の補助金を受け取っています。ところがその同じ期間に、TSMCの日本・熊本の新工場は稼働率わずか50%程度にとどまり、約45億台湾ドル(約200億円)もの赤字を計上したのです。巨額の補助金が投入されても、工場の稼働率が低ければ製造コストの壁に阻まれてしまう――これが「稼働率ショック」の正体です。
では、なぜ稼働率が半導体メーカーの明暗を分けるのか?また、在庫の山や政府補助金といった要素が決算に与える影響を、私たちはどう読み解けばいいのでしょうか。本ブログでは、半導体企業の決算に潜む“山と谷”を読むための3つの指標を取り上げます。それは「稼働率(設備の稼働状況)」、「棚卸資産(在庫)の動き」、そして「政府補助金の会計処理」です。この3つのポイントを押さえることで、皆さんは半導体業界の景気変動を数字の裏から理解できるようになります。言い換えれば、決算書の行間を読んで“次に何が起こりそうか”を見抜く力が身につき、投資判断やビジネスの会話でも一歩リードできるでしょう。
本記事は会計と投資の視点から、難解に思える半導体決算の読み方をやさしく解説します。20~30代の社会人にも親しみやすいカジュアルな口調で、最新の事例を交えながら深掘りしていきます。読み終える頃には、半導体メーカーのアップダウンに振り回されず冷静に分析できる自分にきっと出会えるはずです。それでは早速、3つの指標のミニ講座を始めましょう!
目次
指標1:稼働率と固定費吸収 – 利益を左右する見えざるカギ

半導体製造の世界では「稼働率」が利益の命綱です。稼働率とは工場設備の稼働状況を示す指標で、100%ならフル稼働、50%なら生産能力の半分しか使われていない状態を意味します。なぜこれほど重要かというと、クリーンルームや最新鋭マシンを揃えた半導体工場は稼働していようが止まっていようが巨額の固定費(設備投資の減価償却費や人件費・光熱費など)がかかり続けるからです。高い稼働率で製品を量産すれば固定費が製品あたり薄まりますが、低い稼働率だと一つひとつのチップに重く固定費がのしかかり、製造原価(コスト)が跳ね上がってしまいます。「製造原価は待ってくれない」というのは、まさに生産を絞っても固定費だけは容赦なく積み上がる状況を指した言葉なのです。
実際、稼働率の違いが収益を大きく左右した最新事例があります。TSMCが米国アリゾナ州に建設した最先端工場は、月3万枚のウエハをフル生産しほぼ100%の稼働率で動いています。アップルやAMDなど大口顧客が生産枠を確保しており、稼働開始から間もない2025年Q2に早くもNT$42.32億(約190億円)の純利益を計上するなど異例の速さで黒字化に成功しました。フル稼働=即採算ラインを証明した形です。一方で、同じTSMCでもソニーと共同で立ち上げた熊本の工場(JASM)は苦戦しています。稼働率50%程度と半分しか動かせず、2025年上半期はNT$45.2億の損失(約4.52億台湾ドルの赤字)を出しました。需要に対して生産能力が余っているため、十分に工場を回せていないのです。その背景には、熊本工場が手掛ける成熟世代のチップ市場の供給過剰や競合激化、日本国内顧客(主に自動車産業)の需要低迷などがあり、肝心の生産ラインが埋まらない状態が続いています。
このように稼働率の高低がダイレクトに損益を左右するのが半導体製造ビジネスの宿命です。一般に、ファウンドリ(受託生産)では稼働率が90%を超えると需給が逼迫して価格交渉力が増すと言われる一方、逆に稼働率が7~8割に落ちると固定費の負担が重くなり利益率は急低下します。実際TSMCでも、AI特需で好調とはいえ粗利率(グロスマージン)がじわり低下する傾向が見られています。2024年末に59.0%あった粗利率が、2025年4-6月期には58.6%へ下がり、さらに次の7-9月期は56.5%前後になる見通しと発表されています。これはドル高など為替要因に加え、稼働率の低い海外新工場への先行投資コストが収益を圧迫し始めているためです。投資家にとって稼働率と粗利率の推移は、景気変動や固定費負担の兆候を読み取る重要なシグナルとなります。決算発表では生産稼働に言及する経営者コメントや、工場の稼働調整(増産・減産)のニュースにも注目してみましょう。それが次の業績の山谷を先取りするヒントになるのです。
指標2:棚卸資産の山と評価損 – 在庫から読み解く需要サイクル
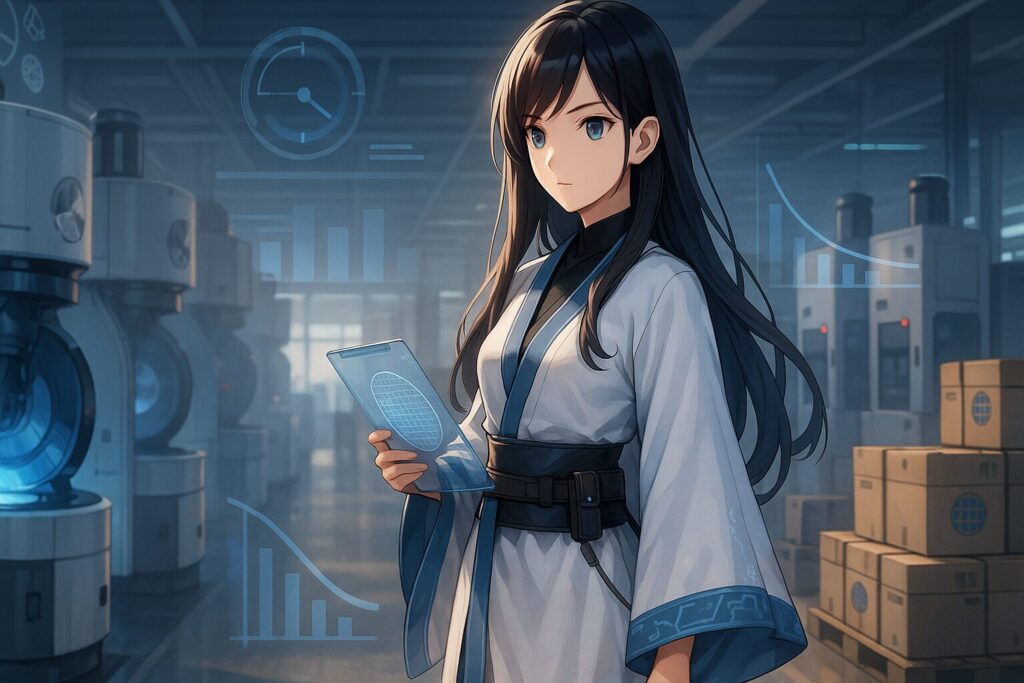
次に注目すべきは棚卸資産(在庫)の動きです。半導体は需要と供給の波が激しく、一度需要が急減すると売れ残りの在庫が工場や倉庫に積み上がります。問題は、半導体は鮮度が大事な商品だということです。技術の進歩で価格がどんどん下がる分野では、在庫を長く抱えると市場価格が製造コストを下回ってしまうことも珍しくありません。そうなると企業は在庫価値を見直し、帳簿上「在庫評価損」として一部を費用計上せざるを得なくなります。これは業績にとって大きな痛手です。
実際、メモリ業界では2022年後半から2023年にかけて需要が落ち込み、市場価格が暴落したため各社が巨額の在庫損失を計上しました。韓国のSKハイニックスは2022年第四四半期だけで約7000億ウォン(約700億円)もの在庫評価損を計上し、10年ぶりの営業赤字に転落しています。売上はほぼ横ばいだったのに利益が大幅悪化した主因が、この在庫の価値下落でした。同社は「第4四半期に在庫水準がさらに積み上がり、価値の低下が見られたため、最大7000億ウォンの在庫評価損を計上した」と説明しています。また、日本企業でも似た現象が起きました。大手のルネサスエレクトロニクスは山梨県甲府の新工場を9年ぶりに再稼働させましたが、電気自動車向け半導体の需要が予想を下回ったため量産開始計画を延期する決断をしています。需要がないまま動かせば在庫過多に陥るリスクが高いため、「もったいないけど工場を遊ばせておく」という選択をしたのです。
このように在庫は半導体メーカーの置かれた市場環境を映す鏡です。決算書では「棚卸資産」の項目や、決算説明会で語られる在庫調整の状況に注目しましょう。在庫が前年同期や前四半期比で増えているのに売上が伸びていなければ、近い将来に在庫調整(減産)や評価損計上が必要になるかもしれません。逆に「在庫が底をついて受注残が積み上がっている」ような状況であれば、それは次の好況期の兆しです。半導体の需給サイクルは在庫の山と谷として表れます。投資の視点では、在庫が過剰で各社が生産縮小や在庫処分セールに走る局面こそ次の買い場かもしれませんし、在庫が薄くどの工場もフル稼働している局面は過熱のサインかもしれません。決算資料や業界ニュースで各社の在庫日数や在庫評価損の有無をチェックしてみてください。それは、短期的な利益の増減以上に業界の未来を先読みするヒントを与えてくれるでしょう。
指標3:政府補助金の光と影 – 公的支援策と会計の裏側を読む

最後に取り上げるのは、各国から提供される巨額の政府補助金です。昨今、半導体は国家戦略物資という位置づけで、米・欧・日・中をはじめ世界中で前例のない規模の補助金や奨励策が相次いでいます。TSMCのケースでは、2024年に約75億台湾ドル、2025年上半期に約67億台湾ドルと、18ヶ月で総額NT$1423億(約47億ドル=約7000億円)の補助金を台湾以外の各国から受け取っています。内訳を見ると、米国・ドイツ・日本・中国の4ヶ国(地域)からの支援ですが、日本政府からの支援額は特に突出しています。日本はTSMCの熊本進出に際し、最初の工場に4760億円、第2工場に追加で7320億円もの補助金を拠出すると発表しており、累計1兆円超の税金投入となります。これは米国のCHIPS法による補助(全米で約390億ドル規模)や、EU各国の補助と並んで世界的にも桁外れの手厚さです。
国家がこれほどまで支援に乗り出す背景には、地政学リスクやサプライチェーン確保の狙いに加え、半導体市場の巨大な成長期待があります。2024年に世界半導体市場は6270億ドルに達し、2025年には6970億ドルへ拡大する見通しとされ、各国とも自国に工場を誘致すれば将来の産業優位性と雇用創出が見込めるからです。また、日本の場合はかつて1980年代に世界シェア50%を誇った半導体産業が2024年にはシェア7.1%まで低下し史上最低水準になっており、「国家の威信」をかけて半導体復権を目指す事情もあります。
では、こうした補助金は企業の決算にどう効いてくるのでしょうか?光の部分は、言うまでもなく巨額の設備投資負担が和らぐことです。例えばTSMC熊本工場の建設費用の約半分は日本政府が負担する計算になり、赤字が出ても親会社TSMC本体への打撃は限定的になります。また米国でも、TSMCはアリゾナに3工場建設するために最大66億ドル(約9900億円)の補助金や25%の投資税額控除を受けられる見込みです。各国政府との協議で有利な条件を引き出し、自社負担を減らしていることは投資家にとって安心材料と言えるでしょう。
一方、補助金には影の部分、すなわち会計上の扱いと条件面の注意があります。会計ルール上、受け取った補助金はすぐ全額を利益計上できるわけではありません。国際会計基準(IFRS)では、設備投資に対する政府補助金は繰延収益として一旦負債に計上し、その後工場や設備の減価償却費に対応させる形で徐々に収益認識する方法が一般的です(あるいは固定資産の帳簿価格から直接控除する方法も選択可)。簡単に言えば、補助金は「将来の費用を埋め合わせるためのもの」とみなされ、工場が稼働するにつれて少しずつ決算に貢献する仕組みです。例えば、1000億円の補助金を受けて工場を建てた場合、その恩恵は数年間にわたって分散計上されます。したがって、補助金漬けのプロジェクトでも稼働率が低ければ当面の損益は赤字になり得るのです。実際、TSMC熊本の第1工場も政府支援を受けていますが、それでも稼働率50%では固定費を賄いきれず赤字となりました。逆に言えば、将来フル稼働してさえくれれば、補助金の分だけ他社より有利なコスト構造で利益を出せる可能性があります。補助金はあくまで長期的な支えであり、短期的な業績悪化を魔法のように防いでくれるものではない点に注意が必要です。
もう一点、補助金には条件が付くことも押さえておきましょう。各国政府はただお金を渡すだけでなく、一定の契約を結んでいます。TSMCも各地の子会社を通じて現地政府と契約を結び、定められた建設スケジュールや投資額の達成など条件を満たさなければ補助金を満額もらえない仕組みです。例えば工場建設が大幅に遅れたり計画を縮小したりすれば、支援額が減額されたり返還を求められたりするリスクもあります。また補助金の背景には各国の思惑があり、政治関係が変化すれば方針が変わる可能性もゼロではありません(極端な例では、海外企業への補助に国内世論の反発が起きて支給が遅れる、といった事態も考えられます)。したがって、企業側は補助金に頼りすぎず、自社資金でもプロジェクトを遂行できる体力を求められます。投資家としても、単に「〇〇社が政府から△△億円もらえるらしい!」と聞いて飛びつくのではなく、その条件面や進捗、そして実際の需要をしっかり見極めることが大切です。
補助金は半導体産業にとって諸刃の剣です。うまく活用すれば新規事業の呼び水となり将来の収益源を育てられますが、補助金が無ければ成り立たないような投資案件は、裏を返せば純粋な市場原理では採算が合わないリスクを孕んでいます。会計上も、補助金収入は徐々にしか表れません。ですから決算を読む際は「この利益は補助金で底上げされていないか? 将来補助が切れたらどうなるか?」といった視点で疑問を持つことも重要です。その上で、各社が補助金を原資にどんな戦略を描いているのか(先端技術開発か、地産地消ニーズの獲得か 等)を見極めれば、単なる数字以上の理解が得られるでしょう。
おわりに – 山谷の先に見える未来へのまなざし
半導体業界の決算は、一見すると専門用語や巨額の数字が飛び交い難解に感じられるかもしれません。しかし、本記事で紹介した稼働率・在庫・補助金という3つの指標に注目すれば、その裏側にある物語が驚くほどクリアに浮かび上がってきます。稼働率の低下に苦しむ企業があれば、「次の追い風が吹くのはいつか?」と考えてみましょう。在庫の増減に一喜一憂する数字の陰には、現場で懸命に需給調整する人々の努力があり、補助金に支えられた新工場のニュースには、国を挙げて産業を育てようとする大きなビジョンが潜んでいます。
これらを読み解けるようになると、半導体企業の決算発表をただ受け身で聞くだけでなく、自分なりの仮説を持って臨めるようになります。「この会社は今は厳しいけれど在庫調整が進んだから来期は復活しそうだ」「補助金のおかげで乗り切ったけれど、本業の競争力はどうだろう?」――そんな風に先回りして考えられる自分に気づくでしょう。周囲が業績悪化のニュースに驚いている中でも、あなたは「それでもこの会社は次の成長へ種を蒔いている」と冷静に分析できるかもしれません。これは投資のみならず、ビジネス全般において非常に大きな強みになります。
半導体産業は山あり谷ありの波を繰り返して発展してきました。そのサイクルの中で、企業も働く人も試練に直面しながら次のイノベーションを生み出しています。たとえ“製造原価”という現実は待ってくれなくても、知識という武器を持った私たちはその現実に立ち向かい、乗り越えていくことができます。本ブログを何度も読み返し、ぜひ自分の中に「景気の波を読む物差し」を携えてください。数字の奥に隠れたストーリーを読み解く面白さに気づいたとき、きっとあなたの中に小さな感動が生まれているはずです。そしてその感動こそが、変化の激しい半導体業界をしたたかに生き抜く原動力になるのではないでしょうか。今日得た洞察を糧に、ぜひ明日からのニュースや決算書をクリアな目で読み解いてみてください。あなたの視界には、きっと以前より明るい半導体の未来が映し出されていることでしょう。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『2030 半導体の地政学(増補版)— 戦略物資を支配するのは誰か』
半導体を“国家戦略物資”として捉え、米・中・欧・日・台湾などの産業政策と企業戦略を地政学の視点から読み解く一冊。各国の補助金や産業誘致の背景理解に最適です。増補版でアップデートが入っている点も◎。
『半導体戦争 — 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防(チップ・ウォー)』
半導体サプライチェーンの覇権争いを歴史と現在進行形の事件から描く決定版。補助金政策の意味、製造拠点の地理リスク、“なぜ今が投資合戦なのか”を俯瞰できます。
『テキスト国際会計基準 新訂第2版』
IFRSの体系を横断的に解説する定番テキスト。2024年4月公表のIFRS第18号の追加にも対応。政府補助(IAS 20)や設備投資に絡む会計処理の全体像を押さえたい人に。
『新版 基礎からわかる 工場経理の実務』
製造業の現場経理に必要な「棚卸資産管理」「固定資産管理」「原価計算」を図表と事例で整理した入門〜実務書。稼働率低下時の原価インパクトや在庫評価の基本を固めるのに役立ちます。
『図解!製造業の「経営改善」に正しく使える「管理会計」— 経営課題を解決し付加価値を稼ぐための75のタスク』
2024年10月発売の比較的新しい管理会計実務書。製造現場のKPI設計やコスト管理、値決め・値上げ交渉の論点など、“固定費吸収×稼働率”の感度を高めたい現場・企画職にフィット。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21141738&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8960%2F9784296118960_1_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20839435&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5466%2F9784478115466_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21287410&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2365%2F9784561352365_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c40f3c3.3f30297d.4c40f3c4.045074cf/?me_id=1409199&item_id=10557204&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiteki-life%2Fcabinet%2Fhp-2550%2Fca3f51566dab47d29-0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21340628&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3518%2F9784526083518_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す