みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
遅延を“ノイズ”ではなく“値札”に変える準備、できてる?
TSMC熊本フェーズ2をめぐって、「25年後半に着工」という公式筋の報道と、「最大18カ月の遅延」という観測が同時に存在しています。前者は6月時点で“7月以降に起工=25年後半”と整理され、量産ターゲットは27年維持とのトーン。後者はインフラ要因等により量産が29年にずれ込む可能性まで言及します。投資家に必要なのは、この“計画−現実ギャップ”を前提としたリスクプレミアムの設計です。
資金面では日本政府の追加補助(最大7,320億円)が軸。IFRSでは補助金は「条件充足と受領の合理的確実性」が得られるまで認識せず、資産関連の補助は繰延収益として耐用年数に応じて利益に振り替える運用が一般的です。よって、着工や装置搬入など“条件達成の客観的マイルストーン”がKPIになります。
収益面の落とし穴は低稼働。IAS 2は固定製造間接費を“正常操業度”で按分するため、立ち上がりが遅れると固定費の未吸収が原価に直撃し、粗利を圧迫します。起工時期や搬入遅延がそのまま損益のタイミングと傾きに跳ね返る構造です。
したがって投資家の実務KPIは次の通り。①補助金条件の充足進捗(起工・建屋完成・ツール搬入・試作開始)②補助金の繰延収益残高と減価償却のマッチング③キャパ増分に対する稼働率・歩留まりのランレート④27年量産シナリオと29年遅延シナリオの感応度(売上・粗利・FCF)。政策支援は下支えになる一方、プロジェクト会計の“タイミングのズレ”が価値評価を大きく揺らす点を、モデルに織り込むべきです。
それでは、本文に行ってみましょう!
目次
『計画』と『観測』を仕分けする

まず“公式に示された計画”を押さえます。TSMCは熊本・菊陽の第2工場(JASMフェーズ2)について、2025年後半の起工を想定するトーンを繰り返し打ち出しています。6月のDIGITIMES Asiaは「7月以降に起工=25年後半」と整理。8月の続報でも、取締役が「25年内の起工スケジュールは維持」と述べ、対日投資の重心は変わっていないと強調しました。ここから読み取れるのは、少なくとも“会社側のガイダンス”はH2/2025起工を前提に動いているという点です。
一方で“現場の摩擦”に着目した観測も根強い。代表例は最大18カ月の遅延=量産は2029年にずれ込む可能性を指摘する報道です。論点は物流・インフラ、とりわけ大型装置の搬入に絡む交通ボトルネックで、建設の初動や立ち上げ試作のタイムラインに波及しうるというもの。こうした観測は6〜7月の海外メディアで相次ぎ、熊本のフェーズ2は環境整備次第で“後ずれリスク”が顕在化しかねないと読み解かれています。
もっとも、会社側は「対米優先で日本・独が犠牲」というストーリーを公式に否定しています。米アリゾナの前倒しは事実でも、地域間の資源配分を巡る一部報道に対し、TSMCは「各地域の計画は顧客需要・効率・政府支援・コストで決める。日本計画に影響は与えない」と反論。したがって“遅延は日本軽視の結果”という単線的な理解は避け、インフラ要件と需給の見極めという足元の実務課題に回帰してフレーム化するのが実務的です。
資金面の裏づけも整理しておきましょう。日本政府はフェーズ2向けに最大7,320億円の追加補助をコミット。補助の存在は、資金調達コストを下げるだけでなく、プロジェクトの“続行オプション価値”を高め、社内の資源配分競争で日本サイトの防御力を上げます。つまり、遅延観測があっても政策支援が前提のシナリオは生きており、投資家は補助金の交付条件やマイルストーン(起工・建屋完成・ツール搬入・試作)に連動したKPI設計を優先順位高く管理すべき、というのが実務的な結論です。
総じて、私たちがやるべきは「計画=会社の公式トーン」「観測=外部の遅延リスク指摘」を二層に分け、両者を条件付き確率で結び直すこと。H2/2025起工をベースに、インフラ進捗・装置搬入の可用性・需給サイクル(特にN6/N7系の稼働見通し)という3つの変数でシナリオの重み付けを更新していく。次章では、この重み付けを財務モデルに落とすための補助金会計(IAS 20)と、立ち上がりの低稼働リスク(IAS 2の固定費按分)を、KPIに直結する形で解像度高く整理します。
補助金会計の実務(IAS 20)を“KPI化”する

起工・装置搬入・試作——フェーズ2の進捗はニュースで追えますが、投資家として本当に効くのは“どの局面でPL・CFに効いてくるのか”を会計基準で言語化してKPIに落とすこと。日本政府の追加補助最大7,320億円は大きいですが、いつ・どれだけ利益に効くかはIAS 20のルールで決まります。
まず「認識のトリガー」:合理的確実性と条件充足
IAS 20は、条件を満たし受領できる“合理的確実性”があるときに補助金を認識、と定めます。交付決定のプレスは材料でも、実務では「交付条件(設備投資・雇用・稼働開始等)をどの時点で客観的に満たしたか」を監査可能な形で積み上げるのが肝。したがってKPIは“起工”そのものより、交付申請→交付決定→実績報告→確定額の各マイルストーンでの達成証憑の有無に紐づけると、予実管理がぶれません。
表示と配分:資産関連なら“繰延収益”で耐用年数に沿って戻す
設備取得を目的とする資産関連の補助金は、(a)繰延収益として計上→減価償却期間で規則的に利益へ振替、または(b)資産の帳簿価額から控除のいずれか。どちらでも経済的効果は「減価償却費と歩調を合わせる」点で同じです。つまり稼働前は減価償却が始まらない=補助金の収益化も進みません。逆に“設備は稼働可能”だが歩留まり低下などで売上が立たない局面でも、減価償却は進むため補助金も機械的に収益化されます。ここをKPIに反映するなら、「補助金繰延残高/関連資産の純額」「当期償却額に連動する補助金振替額」をトラックし、モデル上は耐用年数・稼働開始時期の感応度で揺らぎを試算するのが実務的です。
低稼働の落とし穴:固定費吸収(IAS 2)とWIPの重さ
立ち上がり期は生産量が“正常操業度”を下回りがち。IAS 2は固定製造間接費を正常操業度ベースで配賦すると定め、著しい低稼働の部分は期間費用に落ちます。結果、粗利は圧迫され、補助金の規則的な振替益では吸収しきれない“谷”が生まれる。ゆえにKPIは、(i)正常操業度の前提(ライン別の月間Wafer out基準)、(ii)実際稼働率との乖離、(iii)未吸収固定費額、(iv)補助金振替額との純効果をワンセットで見るべきです。シナリオ上は27年量産と29年シフトの両ケースで、在庫・売原・営業利益の感応度テーブルを最低限用意しておくと、決算ブリッジの説明力が上がります。
実務メモ:フェーズ2の追加補助(7,320億円)は資本的支出とのひも付きが強いとみられ、上記の“資産関連”の扱いが基本線。ゆえに短期の損益ボラティリティを和らげる一方、キャッシュの入金時期と損益認識のズレが必然化します。モデルでは交付スケジュール(入金)/繰延収益の分母(耐用年数)/稼働開始月の3変数をダイヤル化し、インフラ進捗ニュースをトリガーに見直す運用が有効です。
低稼働リスクをどうヘッジするか──契約・運転資本・設備稼働KPI
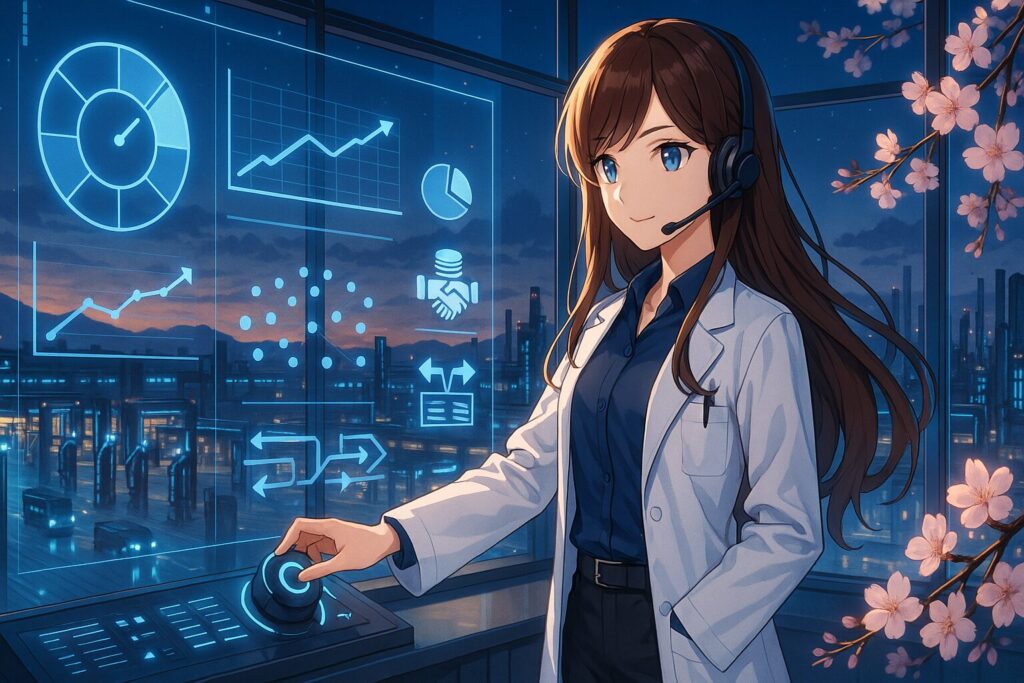
量産時期がずれ、立ち上がり稼働が“正常操業度”を下回ると、固定製造間接費の未吸収が原価に直撃します。IFRS(IAS 2)は固定費の配賦を「正常操業度」ベースで求め、著しい低稼働分は期間費用化せよと定めるため、立ち上げの谷は会計的に不可避です。だからこそ“前広のヘッジ設計”が肝になります。
契約で守る:キャパ予約・ミニマムコミット・価格の枠組み
ファウンドリはキャパシティ予約(前受金や預り金)で稼働の下振れを吸収できます。TSMCは20-Fで「将来キャパ確保のための顧客デポジット」を開示しており、2017年末で約4.5億米ドルの預り金があったと記載。これは顧客が一定量の生産枠を押さえる代表的スキームです。
さらに、ミニマムバイ/テイク・オア・ペイやキャパ予約料を明記するLTA(長期供給契約)は、売上と稼働のボラティリティを抑えます。たとえばGLOBALFOUNDRIESの契約例では、顧客がノンリファンダブルな予約料を支払って四半期コミットを確保する条項が公開されています。
価格面はコスト指数連動(電力・人件費)や価格コリドーで粗利の下振れを平準化。分散投資のコスト増や海外新拠点の立ち上げでグロスマージンが希薄化する局面では、こうした条項の価値が増します。TSMCも多地域展開でGM圧迫が続く可能性を示唆しており、“新工場立ち上げ=マージン希薄化”は前提条件化しています。
運転資本で効く:前受+在庫・WIPの“重さ”をコントロール
キャッシュ面は前受金・デポジットの拡充が第一選択肢。これはFCFの防波堤であると同時に、需給が緩む局面での交渉力にもなります(予約・預り金スキームの開示実績は前述)。一方で、立ち上がりは仕掛(WIP)と在庫の積み上がりが避けにくい。IAS 2の枠内では、低稼働の未吸収固定費は在庫に載せられず当期費用化されるため、WIPの滞留は粗利・営業利益の“二重の重し”になりがちです。従って、ウェハースタートのゲーティング(段階導入・装置リリースと同期)とNRV(正味実現可能価額)リスクの早期モニタリングをKPI化するのが実務的。KPI例:①前受金残高/受注残との比率、②WIP日数・在庫回転、③未吸収固定費額と在庫評価の乖離。
稼働KPIで攻める:OEE・CT・歩留まり学習の“初速”
立ち上がりの利益率は稼働率×歩留まりの初速でほぼ決まります。業界研究は、量産立ち上げ後1年以内に利益の大半を稼ぐ“歩留まり学習”ダイナミクスを指摘。初年度の学習速度を引き上げる設計(装置可用性、欠陥密度の早期低下、ボトルネック工程のCT短縮)がカーブ全体を押し上げます。
具体的な“見える化”は、(a) OEE(可動率・性能・品質)、(b) 工程別CT(サイクルタイム)、(c) WAT/PCM由来の歩留まりKPIの三点セット。これらを月次のキャパ実績とGMブリッジに直結させ、「稼働1pt↑=GM何bp」の換算係数を随時更新します。事実、TSMCは24年のGM改善要因として高い稼働率と生産性向上を挙げています。逆に言えば、フェーズ2の立ち上げ期に稼働が想定を割れれば、GMは同係数分だけ素直に毀損しやすい。
まとめると、契約(LTA・予約)でボラティリティを減らし、運転資本(前受・WIP管理)でキャッシュの谷を浅くし、稼働KPI(OEE・CT・歩留まり)でGMの“初速”を底上げする三段構えが、低稼働リスクの王道ヘッジです。モデルには予約・ミニマムコミットの件数/金額、未吸収固定費、稼働率→GM換算係数を紐づけ、ニュース(インフラ・装置搬入・顧客需要)をトリガーに感応度を更新していきましょう。
結論:リスクは“時間差”として現れる——だからこそKPIで可視化し、プレミアムを値付けする
TSMC熊本フェーズ2は、「H2/2025起工」という計画の直線と、「最大18カ月遅延」という現実の摩擦が同居する案件です。政策補助が分厚く、産業政策の追い風は確かに強い。一方で、プロジェクト会計の世界では、その追い風がいつPLに効くのか、あるいは効かせるまでの資金繰りの谷をどう跨ぐのかが勝負どころになります。要は、投資家が背負うリスクの正体は“できる・できない”の二分法ではなく、タイミングのズレとして表れる、ということです。
この“時間差”を翻訳する道具が、IAS 20とIAS 2の二本柱でした。資産関連補助金は繰延収益→耐用年数で規則的に戻る(=キャッシュ入金とは非同期)。立ち上がり局面の低稼働は、正常操業度を下回った部分が期間費用として粗利を直撃する。すると、補助金があっても損益は滑らかにしか改善しない——ここに市場が要求するリスクプレミアムの根拠が生まれます。だからこそ、私たちは“ニュースの見出し”ではなく、マイルストーン→会計処理→KPIという回路でストーリーを組み直す必要がある。
実務での合い言葉はシンプルです。(1)補助金の条件充足KPI(起工・建屋・装置・試作)で“いつ認識できるか”を掴み、(2)繰延収益の残高と償却のマッチングで“どれだけ効くか”を測る。さらに(3)正常操業度・稼働率・未吸収固定費で“立ち上がりの谷”の深さを先読みし、(4)契約(LTA・前受・ミニマムコミット)×運転資本(WIP/在庫回転)×稼働KPI(OEE・CT・歩留まり)で谷を浅くする。最後に、27年量産/29年シフトの二面シナリオで売上・粗利・FCFの感応度を常時更新——これが、国策半導体×補助金×プロジェクト会計を投資の言葉に翻訳する“投資家の作法”です。
フェーズ2は、政策と企業、財務と現場の同期の難しさを露出させる案件でもあります。けれど、それは悲観の理由ではありません。むしろ、条件付き確率でスケジュールを重み付けできる投資家にとっては、ミスプライスを拾う機会が生まれる。ニュースが“遅延”を叫ぶ時こそ、KPIの数字がどう動いたかで判断する。——時間差を恐れず、数式とKPIでプレミアムに値札を付ける。それが、長い立ち上がりを伴う国家プロジェクトとの賢い付き合い方です。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
2030 半導体の地政学(増補版)
各国の産業政策・補助金競争の最新動向を整理。対外環境と国内投資(熊本含む)を結ぶフレームづくりに有用。
半導体ビジネス最前線
主要プレイヤーの戦略、日本の復活シナリオ、有望領域までを俯瞰。フェーズ2の位置づけを業界全体で捉え直すのに役立ちます。
テキスト国際会計基準 新訂第2版
IFRSの全体像を網羅。IAS 20(政府補助金)やIAS 2(棚卸資産)の考え方を日本語で体系的に確認したいときの定番です。
IFRS(R)会計基準 2024〈注釈付き〉
IFRS原文の日本語公式訳。個別論点の原典確認用に必携(会計処理の根拠条文を当てに行くとき用)。
在庫戦略の教科書
需給変動下のS&OP・在庫KPI・キャッシュ変動の勘所を実務視点で解説。立ち上がり期のWIP/未吸収固定費と資本効率管理の橋渡しに最適。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21141738&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8960%2F9784296118960_1_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21467944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3346%2F9784296123346_1_17.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21287410&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2365%2F9784561352365_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21384591&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8318%2F9784502508318_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20849598&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1211%2F9784296201211_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す