みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
あなたのオフィス、その空席は“在庫”だと気づいていますか?
働き方改革やハイブリッドワークの普及でオフィス空席率は上昇中。そのまま空けっぱなしにしていると家賃や光熱費、人件費などの固定費が膨らみ、知らず知らず赤字を埋め込むことになります。しかし「空席=在庫」と考えれば、企業は利益追求の視点で空間活用を見直せるようになります。本記事では不動産×リース会計×働き方の切り口で、空席が企業財務に与える影響と有効活用策を探ります。具体的には、サブリース契約で問題になりがちな「逆ザヤ」による損失、IFRS(新リース会計基準)対応で露呈する使用権資産・リース負債の再評価、そして社員満足にもつながるハブ&スポーク型オフィスの導入などを掘り下げます。ここで得られるのは、固定費を「見える化」して削減につなげるアイディアと、投資家目線で企業価値を上げる新たな発想です。
サブリースの逆ザヤと会計処理

サブリースとは、企業がビルやオフィスを一括借上げし、自社グループの他部門や子会社・関連会社に転貸する賃貸経営形態です。サブリース契約では、オーナーに支払う賃料が保証される一方、転貸先から得られる賃料が賃料相場の下落や空室率増加で低下すると、「逆ザヤ」(マイナス利ザヤ)が発生しやすくなります。実際に1990年代後半のバブル崩壊時には多くのサブリース物件でテナント収入が激減し、支払賃料を下回る逆ザヤが問題化しました。たとえばA社が月100万円で本社を借り、毎月90万円でサブリース契約していても、空室増加で転貸収入が80万円に落ちれば毎月10万円の赤字です。年間で120万円、5年で600万円の赤字となり、財務に与える影響は決して小さくありません。しかしこの赤字は通常、営業外費用として処理されるため、一見営業利益には影響しないように見えます。例えば大企業の本社で月額1億円の家賃がかかっていれば、空室率が10%異なるだけで年間1.2億円、5年で6億円もの差が生じます。このような見えないコストは放置すれば経営効率を低下させます。
この違和感を解消するには会計基準の理解が不可欠です。IFRS(国際会計基準)第16号でも、サブリースの貸手はヘッドリースとサブリースを別個に会計処理します。サブリースは原資産ではなく借りた使用権を第三者に貸す取引とみなされ、ヘッドリース部分では借手として使用権資産とリース負債を計上し、サブリース部分では貸手として収益と費用を認識します。その結果、転貸先との賃料差損は会計上、借手側のリース負債増加や利息費用、貸手側の収益減少として表れます。会計上はたとえば、利益保障や解約不能期間中に発生する転貸損失を「転貸事業損失引当金」として翌期以降に見込む例もあります。逆ザヤ分が営業外費用に回ると経営指標上は隠れてしまいますが、貸借対照表の負債や引当の増加として確実に数字に現れます。つまり、見かけ上の黒字に騙されず財務全体を把握することが求められます。なお、新リース会計基準は2027年4月期から強制適用となり、大企業を中心に早期適用も検討されています。上場企業はこれに備え、サブリースも含むあらゆる賃貸契約の影響を洗い出しておく必要があります。
さらに、IFRSはサブリースの分類方法についても明示しています。IFRS草案では「サブリースの分類は使用権資産ではなく元の資産(原資産)ベースで行うべき」とされており、つまりファイナンス・リースに該当するかどうかは原資産のリスク移転で判断します。この点はKPMGなどの解説でも確認されており、サブリースでも本質的には元のオフィスビルを貸す意識で会計処理することになります。
使用権資産の再評価と原状回復義務

2027年から日本でも適用される新リース会計基準では、これまでオペレーティング・リースだったオフィス賃貸も原則オンバランス化されます。すべてのリース契約で借手が使用権資産とリース負債を計上する「使用権モデル」が導入されるため、サブリース業者の貸借対照表は大きく変わります。従来は賃料費用で済んでいた契約でも、同じ契約内容で使用権資産とリース債務が計上される結果、資産・負債が数倍に膨れ上がるケースも考えられます。MoneyForward社も、新基準ではバランスシートに計上される負債が増大し、自己資本比率が低下する可能性が高まると警告しています。これは財務の透明性向上を目指す改革とはいえ、短期的には財務指標の見かけ上の悪化を招くため、投資家や金融機関への説明が課題になりそうです。たとえばIFRS第16号では、使用権資産の初期測定額はリース負債の現在価値に前払リース料や受領リースインセンティブ、初期直接コスト、原状回復費用見積額を加えたものになります。これにより今まで見えなかったコスト要素も資産に組み込まれ、貸借対照表上の資産規模がさらに膨れ上がります。
加えて、退去時の原状回復義務も隠れた債務となります。IFRS第16号では、賃貸契約に原状回復義務が含まれる場合、その費用見積りを資産除去債務として現在価値で計上し、使用権資産に含める規定があります。たとえばオフィスの内装を原状回復して返却する契約なら、壁や床を元に戻す工事費用を債務計上し、同額を使用権資産に上乗せします。日本の会計基準でも、企業会計基準第18号および適用指針では、有形固定資産の除去義務として事業用定期借地権や建物賃貸の原状回復が例示されています。敷金で賄えない範囲は負債計上となるため、結局退去時のコストは企業の将来負担として積み上がるのです。
ハブ&スポークモデルで通勤税を減らす
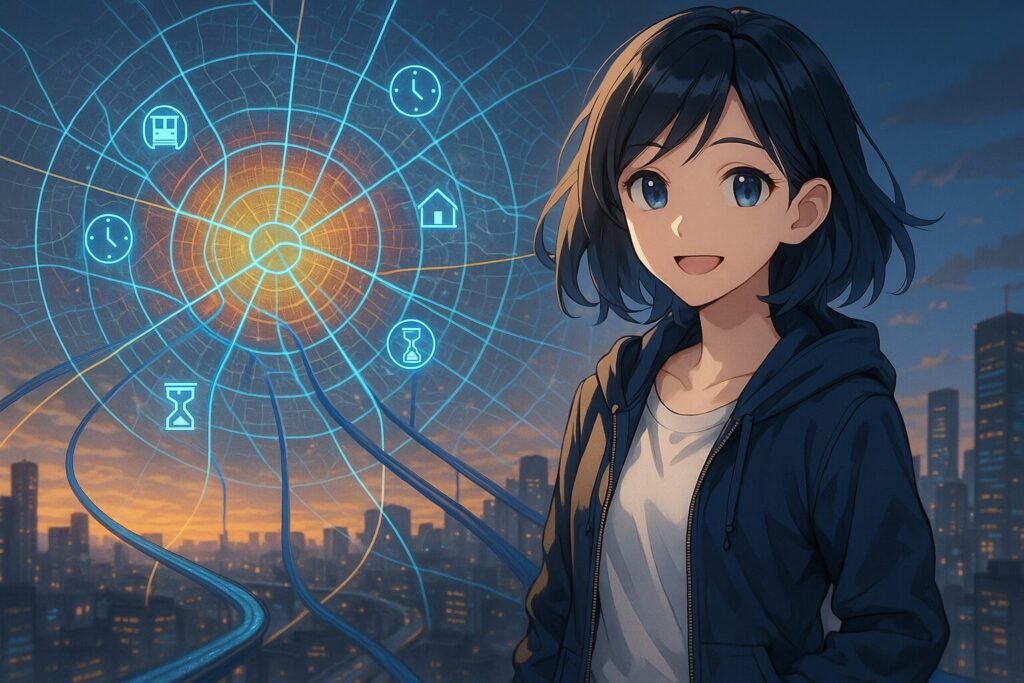
こうした固定費重視の視点に対し、オフィスそのもののあり方を再考する動きも出てきました。注目の一つがハブ&スポーク型オフィスです。これは大規模な中央本社(ハブ)機能は維持しつつ、社員の居住地近くや営業エリアに小規模サテライト(スポーク)を複数設置する方式です。WeWorkなども多くの企業がこのモデルを採用しており、中央オフィスに全社員を通勤させる必要がなくなった結果、本社機能の削減・スリム化が可能になったと報告しています。WeWorkのSandeep Mathrani氏も「通勤時間を最小化するにはスポークを従業員の住居近くに配置すべきだ」と述べ、「巨大な本社の時代は終わった」と強調しています(参考:wework.com)。実際、同社はニューヨーク市内に本社以外の複数拠点を展開し、社員が自宅から近いWeWorkオフィスで仕事できる環境を整えました。その結果、通勤に要する時間が劇的に短縮されただけでなく、新設した拠点間でのコラボレーションも生まれ、オフィスポートフォリオとしての活用効果が高まったと言います。
このような分散型オフィスの利点は、要するに「通勤税」を下げる点にあります。TKPレンタルオフィスはデジタル化とテレワークの進展で「ワークプレイス=リアルオフィス」の考え方は前時代的になり、誰でもどこでも働けるABW時代が到来したと説明しています。コロナ禍で需要が急増しているのがハブ&スポーク方式であり、都市部や郊外にサテライトを設置することで「通勤時間・混雑の軽減」が期待できるとしています。実際、自宅近くの拠点を利用できれば往復の通勤時間を丸ごと浮かせることができ、片道1時間(往復2時間)の通勤だと年間約500時間(約20日分)もの時間が節約できます。これはまさに個人にとっての「通勤税」と言える巨大なコストです。さらに、最新の座席管理システムで日々のデスク利用状況を可視化すれば、利用率の低いオフィス区画を削減して戦略的にオフィス面積を最適化できます。オフィスを分散し必要座席数を削減すれば、浮いた固定席を別用途に回すなど運用効率が向上し、同時に社員のワークライフバランス改善にもつながります。
結論:固定費も社員満足も可視化しよう
オフィスの空席は単なるスペースの無駄遣いではなく、企業がコストとして抱える「在庫」です。サブリースの逆ザヤも原状回復義務も、放置すれば知らず知らず経費に埋没してしまうものの、新基準下では確実に財務諸表に表れます。IFRS16の導入で退去コストも債務計上され、使用権資産もオンバランス化されます。特に大企業では2027年適用に向けた準備が急がれており、IFRS第16号との整合性を図った新基準は企業の財務諸表の透明性向上を狙いとしています。逆に言えば、これらの可視化が進めば投資家から見た企業比較もしやすくなるというメリットがあります。
読者のみなさんも、この記事を機に自社のオフィス利用の数値化に着手してみてください。在宅と出社、サテライト拠点の配置、サブリース契約の収支、原状回復費用の見積もり――可能な限り棚卸しすることで、「埋もれていた赤字在庫」が浮かび上がるでしょう。そして、それらのコストを削減する具体策を考え抜いてください。この記事を読んだあなたは、すでにオフィス空席の棚卸しの先駆者です。将来訪れる赤字を未然に検出し掘り出すことで、企業の財務体質は確実に強化されるはずです。経営者やチームを巻き込み、率先して改革を進めましょう。空席という『在庫』を掘り起こし、企業の成長ストーリーの主人公になる瞬間は、もうすぐそこです。
もう一度まとめると、遊休オフィスを「在庫」と捉え会計・財務の視点でコストを検証することで、意外な改善点が見つかるという点です。あとは行動あるのみ。今日から自社の空席率やリース費用をデータで見える化してみてください。見えてきた数字こそが、次の一手のヒントになるはずです。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
図解&徹底解説 新リース会計基準
2027年適用の新リース基準を、IFRS16の考え方と突き合わせながら“どこが変わるのか”を要点整理。図表・設例が豊富で、サブリースや使用権資産、割引率、注記まで一通りキャッチアップできます。
実務解説 新リース会計基準のすべて
新基準の全体像から契約識別、要素分解、変動リース、再評価、サブリースの分類まで“実務の勘所”を網羅。IFRS16との比較も明示され、社内方針の策定や影響分析の土台づくりに適します。
新リース会計の実務対応と勘所
現場で迷いやすい論点をQ&Aで整理。具体例ベースで判断プロセスを解説しており、原状回復費用の扱い、再交渉・条件変更時の再測定、サブリース逆ざやの見え方など“日々の決断”に効く1冊。
IFRS会計基準2024〈注釈付き〉
IFRSの原典に立ち返りたいときの“最後の拠り所”。注釈付きで最新改訂を反映しており、IFRS16の条文確認やIAS37(引当金・偶発負債・偶発資産)との横断チェックにも役立ちます。
ハイブリッド・イノベーション ― イノベーションの障壁をリモートワークで乗り越える!
“ハブ&スポーク型”や分散ワークが生産性・創造性に与える影響を実例で解説。通勤時間(=通勤税)の削減や分散拠点運用の発想を、会計以外の経営視点から補強できます。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47107875.467d2aee.47107876.b217f4b1/?me_id=1220950&item_id=15815559&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_2111%2Fneobk-3130730.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21584381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7912%2F9784502537912_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21518291&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8684%2F9784793128684_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21384591&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8318%2F9784502508318_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21094481&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5460%2F9784909125460_1_116.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す