みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
のれんで飛ぶか、確率で着地するか?
特許切れ(LOE)は、製薬企業にとって「いつか必ず来る決算イベント」。売上の屋台骨が一気に削られるその瞬間、よく選ばれる処方箋が「大型買収で穴を埋める」ことです。ところが、この応急処置は会計の現場で別のリスクを連れてきます。PPA(取得原価配分)で計上される無形資産と“のれん”、買収後に続くR&Dの費用化、そして将来キャッシュフローの読み違いが重なると、のれん減損が利益を直撃する——そんな構図が珍しくありません。実際、大手でも買収由来ののれんやIPR&D(開発中無形資産)の減損が話題になることは増えています。たとえばロシュは近年、買収関連ののれんと無形資産でまとまった減損を計上しました。
この記事は、「製薬×のれん×確率思考」という切り口で、(1)大型買収のPPA/のれん減損/買収後R&D費用化の要点、(2)特許切れ後の売上カーブとコ・プロ契約(共同販促)の利益配分が損益に与える効き目、(3)投資家が“成功確率×期ズレ”でパイプライン価値を評価する現場感、の3本立てで整理します。背景として、今後数年で世界の製薬は総額数千億ドル規模の「新・特許クリフ」に直面すると見込まれ、補充策としてのM&A・ライセンス・自社開発の目利きが一段と重要になっています。
会計論点も避けて通れません。US GAAPでは、買収で取得したIPR&Dは利用可能になるまで“無期限”の無形資産としてテスト対象、のれんは減損のみ——という扱いが基本線。一方IFRSでは、研究段階は費用、一定の条件を満たす開発支出は資産計上、といった線引きがあります(買収で得たIPR&Dの初期認識は資産)。この境目が、買収後のP/Lの表情を変えます。
さらに現場の手触り。LOE後の売上下落は“直線”ではなく、AG・後発品の浸透スピード、提携やコ・プロの報酬設計でカーブが曲がります。実務の契約を見ると、販促活動や売上達成に応じた料率やフィーの階段が細かく設定され、利益配分の重心が動く設計になっているのがわかります。
そして投資家は、パイプラインをrNPVで捉え、各フェーズの成功確率と上市時期の“期ズレ”を織り込んで評価します。ここ数年は、ブロックバスターのLOEを、次の成長薬(例:自己免疫領域の新薬群など)でどこまで埋められるかが焦点。延命策や新適応の進捗ひとつでバリュエーションが揺れます。
読み終えるころには——のれんを積んで崖を越えるのではなく、「どの無形資産にどう価値配分し、どこで確率を上げ、どこで期ズレを吸収するか」を自分の言葉で設計できるようになります。会計と事業、そして確率思考を一本の線で結ぶ。その準備、ここから始めましょう。
M&Aで穴を埋めると、会計が重くなる理由
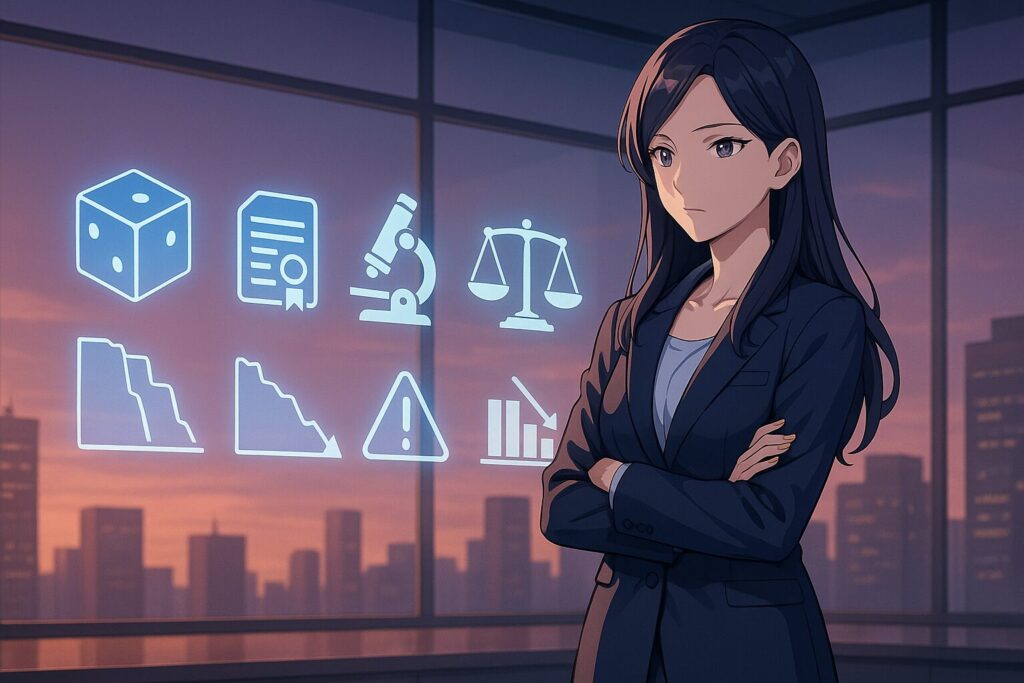
特許切れ(LOE)の穴をM&Aで一気に埋める——製薬でよく見る一手です。ただし、その瞬間から損益とバリュエーションの“重力”が変わります。買収価格はPPA(取得原価配分)で「のれん」と「無形資産(特許・ブランド・契約・IPR&Dなど)」に割り振られ、以後は減損テストや償却、フェーズ移行時の再見積りに追われる。数字は膨らむのに、キャッシュは増えない——そんな違和感が出やすい。ここでは(1)PPAで何が起きるか、(2)のれん減損の現実、(3)買収後R&D費用化の効き方、の順に“手触り”で押さえます。
PPAの実像:のれんとIPR&Dの線引き
PPAの初期認識では、契約や法的権利に基づく無形は原則として“のれんから切り出す”のがルールです。とくに開発中資産(IPR&D)は、買収で取得した場合は個別の無形資産として計上(US GAAPでは耐用年数未確定=非償却・減損テスト対象)。一方、研究開発を自前で積み上げる場合は費用処理が原則——ここにM&Aとの会計差が生まれます。
IFRSでも、事業結合で得たIPR&Dは個別無形として認識されます(IFRS 3)。ただし、買収「後」に自社で発生する研究段階の支出は費用、一定条件(技術的実現性・商業化可能性など)を満たす開発支出は資産計上(IAS 38)。US GAAPは原則費用、IFRSは段階で振り分け——この違いが同じ案件でもP/Lとバランスシートの“表情”を変えます。
のれん減損の現実:崖の上で揺れる“期待値”
のれんは償却しない代わりに、将来キャッシュフローの見積りで毎期テストされます。レポーティングユニットへの配賦と回収可能価額の判定が核心で、マクロや競争、パイプラインの期ズレ次第で一気に評価が崩れることも。直近ではロシュが24年決算で製薬部門におけるのれん36億ドル、無形資産14億ドル規模の減損を計上。買収起点の期待が、足元のパフォーマンスや見通しの修正で反転する典型例です。
US GAAPの実務では、のれんは“配賦した単位”で減損テストを行い、のれん自体がキャッシュを生まない以上、結局は将来CFの前提に賭けているのと同じ。LOEの深さ・スピード、価格改定、上市のタイミングのブレが小さく見積もられていると、のれんは「崖の上の空気」を吸った瞬間に重力に負けます。
買収後R&Dの費用化:KPIをどう読み替えるか
買収直後はIPR&Dが“非償却の無形”として鎮座し、上市すれば減価償却が始まります。そこに自社で追加する研究開発費は、US GAAPだと原則費用、IFRSだと条件次第で資産化されるため、同じ開発スケジュールでも営業利益・EBITDAの見え方がズレます。投資家サイドでは、rNPVで成功確率と期ズレを織り込む一方、会計KPIは「費用化バイアス」「資産化バイアス」を含むため、キャッシュ創出力と前提(ピーク売上、浸透速度、コスト・オブ・セールス、コ・プロ料率)に引き直すのが筋です。
この読み替えが難しくなるのが“新・特許クリフ”の局面。2025〜2030年にかけて、数十の大型品が特許切れを迎え、2,000〜2,360億ドル級の売上がリスクにさらされるという試算が相次ぎました。穴埋め策としてのM&Aは続くはずですが、PPAで増えた無形・のれんが、のちに減損リスクとして跳ね返る可能性も同時に高まる——この二律背反を、確率とタイミングでどう均すかが経営の腕の見せ所です。
まとめると、M&Aは「時間を買う」代わりに「前提に縛られる」選択です。PPAで切り分けた無形と、のれんに埋め込んだ将来CFの仮説、そして買収後に積み増すR&D費用——これらは同じストーリーの別カット。LOEの谷を越えるなら、(1)PPA段階で無形の価値配分を現実的に、(2)のれんのテスト前提を保守的に、(3)R&Dの費用化・資産化の会計差を投資家の“目線”に合わせて翻訳する。この3点が決まると、数字はブレても物語はブレません。
特許切れ後の“売上カーブ”とコ・プロの利益配分

LOE(特許切れ)の後に売上がどう落ちるかは、事業の姿勢そのものを映します。小分子はジェネリックが一斉参入しやすく、値下げ競争が急角度。バイオは浸透が緩やかになりやすいが、PBM(米調剤給付管理)や置換性の可否で“曲線”が歪む。そこへコ・プロ(共同販促)や共同販売の設計が重なると、見た目の売上と実質の取り分がズレます。ここでは(A)売上下落カーブの型、(B)コ・プロの利益配分と会計の素朴なルール、(C)実務モデリングのコツを俯瞰します。
“崖”は一枚板じゃない:小分子・バイオ・AG
小分子は後発が6社以上になると価格は95%超下がり得る——FDAの分析が示す通り、参入数が深掘りを決めます。したがって典型的には“早い・深い”カーブ。逆にバイオは製造難度と切替障壁のせいで初期の浸透が鈍りやすい(同じくIQVIAの見通しも、成長は新製品で相殺されるもののLOEの押し下げが続くと整理)。この差を読むのが第一歩です。
実例で輪郭が見えます。ヒュミラ(adalimumab)は2023年に米国でLOE、24年の米売上は前年から約4割減まで沈んだ一方、PBMの採用やリベートの力学で“粘り”も観測されました。つまりバイオでも、価格・フォーミュラリ・置換性が絡むと、下落は段差的になることがある。
さらに、ブランド自身が出すオーソライズド・ジェネリック(AG)は初期180日で売上の大きな塊をAG側に引き寄せ、価格下落を一段促す場合がある。AGを出すか否かで、最初の半年の“落差”が別物になる点は、曲線設計の定番論点です。
コ・プロの設計:誰が“顧客”で、どこが“分け前”か
コ・プロや共同販売は「売上を増やす契約」でも、会計上はしばしば“コラボ契約(ASC 808)”。相手があなたの“顧客”かどうか(ASC 606のスコープ)で処理が割れます。販促や流通など“相手に商品・サービスを提供して対価を受け取る部分”は606、純粋な利益分配や費用折半は808の世界——この仕分けで、PLの“売上”に出るのか、“協働収益/費用”に出るのかが変わる。
実務の開示でも、たとえば共同販売の“利益シェア”は「協働取引からの収益/費用」として純額処理されるケースが散見されます。一方、相手に提供する明確な販促サービスやマイルストンは606の5ステップで認識される。単一契約の中で606部分と808部分を“素直に”分けるのが近年の基本です。
契約書の条文も昔から多様ですが、典型は(i)売上段階別のロイヤルティ(スライディング)、(ii)粗利起点のプロフィットシェア、(iii)販促人数やアクティビティに応じたフィーの複合。どの基準で分けるか次第で、同じ売上でも手取りと変動費のプロファイルががらりと変わる。
モデル化の勘所:カーブ×配分=“見かけ”と“実質”
モデルではまず、①価格下落(競合数とAGの有無で勾配を変える)、②数量下落(置換性・PBM採用で遅行/先行を分ける)、③販促強度(コ・プロで相手が増える分、浸透をどれだけ延命できるか)を別軸で組む。小分子なら“6社到達時の価格水準”を固定、バイオなら“フォーミュラリ転換率と四半期ラグ”をパラメトリックに。
次に配分。粗利ベースのプロフィットシェアなら、変動費の定義(コ・プロ販促費はどちら持ちか、リベートは総額か純額か)が取り分を大きく動かす。606に入る“サービス対価”は売上表示を押し上げ得る一方、808の“利益分配”は純額でブレの少ない系列に映る——見かけの売上成長とキャッシュ創出力が乖離しないよう、両系列を併記して管理するのが無難です。
最後に現実チェック。業界マクロは2030年まで新薬の伸びとLOEが綱引きする構図。EvaluateやIQVIAの見立てを“外生条件”として、あなたの製品カーブとコ・プロ配分を上から押さえにいくと、モデルに“無理な期待”が混ざっていないかが見えます。
要は、売上カーブの“形”とコ・プロの“取り分”は同時に決めないと読み違える、という話。初期価格の切れ方、PBM・置換性・AG、そして利益配分・会計スコープの線引き——この4点で曲線は別物になります。数字の背後にあるルールをきちんと見極めれば、“売上は落ちてもキャッシュは守る”設計は可能です。
投資家の目線:成功確率ד期ズレ”で価値はこう動く

新薬の価値は「いつ、どれだけ、実現するか」の掛け算。投資家はrNPV(リスク調整NPV)で成功確率を織り込み、さらに上市時期の“期ズレ”で現在価値がどれだけ痩せるかをシビアに見る。ここでは(A)確率の置き方、(B)期ズレの破壊力、(C)現場で効く“契約と設計”の合わせ技を整理します。
確率の置き方:フェーズ別の“通過率”を土台にする
リスクの土台はフェーズ別の通過確率。BIOの大規模データ(2011–2020)では、Phase Iから承認までの全体LOAは約7.9%、最難関はPhase IIの移行という結果。領域差も大きく、血液領域は高く、泌尿器は低いといったばらつきがある。まずは自社案件を、この“産業平均の地図”に重ねるところから始まる。
近年はモダリティ差も無視できない。たとえば細胞・遺伝子治療は他モダリティ比で臨床成功率が2~3倍高いとする分析も出ている一方、製造・供給のボトルネックで“時間リスク”は大きい。確率の高低だけでなく、時間軸の不確実性まで含めて重みづけするのが、いまの標準装備です。
rNPV自体は「各フェーズの期待キャッシュフロー×通過確率」を足し合わせる素朴な方法。資本コストで割り引く点は通常のNPVと同じですが、成功確率をステージごとに掛けるのが実務のキモ。早期資産ほど確率の重みが効き、ポートフォリオ評価では“確率×ピーク売上×市場浸透速度”の三点で議論が収束します。
“期ズレ”の破壊力:1年遅れると、価値はこう減る
同じ確度でも、1年の遅延は現在価値を確実に削る。割引率は会社ごとに違うが、業界の資本コスト(WACC)は足元でおおむね一桁後半〜一桁台。つまり「1年の遅延=1年分の割引」を素直に食らうと同時に、競合の先行・PBMの採用・価格交渉でピークと浸透速度の想定まで崩れる。数字の二重苦です。
“期ズレ”の現実味は、買収対価に埋め込まれるCVR(条件付価値権)を見るとよくわかる。BMS×Celgeneの案件では、特定薬の期日内承認が条件だったが一部が期限後承認となり、CVRは失効。司法判断の経緯を含めて争いは続いたが、投資家の評価軸としては「期日を守れない=キャッシュの現在価値と追加対価が同時に消える」ことを象徴した出来事だった。
臨床・申請の“詰まり”は現場でも常態化。被験者募集、サイト負荷、プロトコル複雑化——このあたりはもう構造問題。だからこそ、タイムライン短縮のオペレーション(eConsent、分散型試験、供給最適化)まで含めて価値設計に織り込むのが、いまのベンチマークになっています。
“設計”で守る:契約、段階ゲート、リアルオプション
投資家は確率と時間に加えて“柔軟性の価値”も見る。前臨床~早期での大型コミットは避け、マイルストンや段階的出資で下方リスクを切る——いわゆるリアルオプション的な設計。理屈はシンプルで、「今は少額で権利だけ買い、確率情報が更新されたら打ち手を増やす」。不確実性の高い局面ほど相性がいい。
買収・提携の条件面でも“期ズレ”の吸収策は定番化。例えば(i)承認期日連動のCVRやマイルストン、(ii)コ・ディベロップで費用折半と地域分担を組み合わせる、(iii)供給キャパ増強の投資コミットを対価に織り込みボトルネックを先回りで潰す、といった設計です。外部イノベーションをどう束ねるかは、R&D生産性と同じくらいバリュエーションに効いてきます。
最後に“線の引き方”。確率は産業平均を鵜呑みにせず、(1)領域×モダリティ、(2)先行臨床データの質、(3)供給・価格の実装可能性で上書きする。時間は“名目スケジュール”ではなく“実効スケジュール(サイト立上げ〜供給確立まで)”で見る。契約は“期日と品質”に連動するインセンティブを埋め込む。——この3点で、のれんに詰め込んだ期待を“確率×時間”で現実化させる筋道ができます。
確率は地図、期ズレは重力、契約は足場。3つを同じ座標で扱えると、M&Aで積み上がったのれんは“崖の上の空気”に耐えやすくなる。逆にどれか1つでも脇が甘いと、期待値は一夜で蒸発する。数字は正直です。あなたのモデルが「確率」「時間」「柔軟性」の3枚看板で立っているか、ここで一度見直しておくといい。
結論|“のれん”に未来を詰め込みすぎない
のれんは希望の塊だけど、希望はキャッシュになってからが本物です。特許切れの崖は、いつか必ず来る。だから私たちが磨くべきは「崖を飛び越える脚力」ではなく、「崖の向こうに安全に着地する技」。PPAでどの無形にどれだけ配分するか、のれんのテスト前提をどこまで現実に寄せるか、買収後のR&Dをどう費用化/資産化し、どのKPIで翻訳するか——この“設計の粒度”が、決算数値の揺れを事業の手触りに戻してくれます。売上カーブは競合数と置換性とPBMで曲がり、コ・プロの配分で見かけと実質がズレる。だからモデルは“価格・数量・配分”を別軸で持つ。投資家はrNPVで確率を、割引率で時間を測り、契約で柔軟性を値付けする。ならば経営側は、確率は“産業平均+自社根拠”で上書きし、時間は“名目スケジュールではなく実効スケジュール”で見直し、契約は“期日と品質”に連動するインセンティブで骨組みを固める。のれんを積んで崖を越えるのではなく、のれんがあってもなくても着地できる体幹をつくる。そうすれば、減損が来ても物語は折れない。会計と事業と確率思考を一本に通し、「いま確実に作れる価値」を積み上げること。それが結局、最短で遠くへ行く道です。
——あなたの次の一手はどこから始めますか。のれんの仮説? 売上カーブ? それとも期ズレを吸収する契約? 選び方こそ、あなたの戦略です。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
医薬品業界の会計実務ガイド
製薬の収益認識・M&A・IFRS/税務まで網羅。コ・プロやライセンスの会計整理に強い実務書。
IFRS「企業結合」プラクティス・ガイド
IFRS第3号の最新論点を平易に整理。PPA、のれん、IPR&Dの扱いを“実務の手順”で押さえたい人向け。
表解 IFRS・日本・米国会計基準の徹底比較
IFRS/日本基準/US GAAPの差異を俯瞰。R&Dの資産計上可否や減損の考え方を横並びで確認できる。
時価評価ガイドブック—金融商品の時価算定と株式価値評価
割引率・評価技法の基礎からPPA/減損テストの前提作りに直結。rNPVの割引パラメータ検討にも。
海外大型M&A 大失敗の内幕
失敗事例で学ぶ“のれんが折れる瞬間”。製薬案件も登場し、前提の置き方の怖さを体感できる。
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21082834&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0564%2F9784495210564_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21099338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784502472411.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21622631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9916%2F9784502539916_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20710914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1715%2F9784502431715_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=15956335&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6935%2F2000004736935.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す