みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。
Jindyです。
あなたの電気代は、AI時代のどんな未来につながっていますか?
生成AIブームで「NVIDIAすごい!」というニュースは毎日のように流れてきますが、その裏側で静かに、しかし確実に効いてくるのが「電気代」です。家庭のエアコン代から、GPUがぎっしり詰まった巨大データセンターまで、すべては同じ「電力PL(損益計算書)」の上に乗っています。
国際エネルギー機関(IEA)は、データセンターやAIなどによる世界の電力需要が、2022年の約460TWhから、2026年には約800〜1,000TWhへと倍増しかねないと見ています。これは、日本全体の電力消費量に匹敵する規模です。
つまり、「AIの計算量」が増えるということは、「世界中のどこかで発電所をもっとフル回転させる」ということと、ほぼ同じ意味を持ち始めているわけです。
こうした状況のなか、キヤノングローバル戦略研究所などの論考では、「再エネ最優先」を見直し、AI・半導体産業の競争力を守るために、とにかく電力単価を下げろ、というかなりストレートな主張も出てきています。
「電力が安い国」がデータセンターや半導体工場を引き寄せ、そこで生まれる付加価値や雇用を総取りしてしまう――そんな“電気版の通貨戦争”のような時代に入りつつある、という見方です。
マクロに見ると、電力単価は「国の競争力」そのものになりつつあります。AI、半導体、クラウド、EV、あらゆる成長産業のコスト構造のど真ん中に「kWhあたり何円で電気が手に入るか」が居座っているからです。一方でミクロ、つまり私たちの暮らしに引き寄せてみると、電気代は家賃や通信費と並ぶ「家計の固定費」。ここがじわじわ上がると、知らないうちに可処分所得が削られ、投資に回せる余力も小さくなってしまいます。
この記事では、この「電力単価=国の競争力」「電気代=家計の固定費」という二つの顔をつなぎながら、次の3つの問いに向き合っていきます。
1つ目は、「AI・データセンター特需で電力需要が膨らむ時代に、エネルギー政策はどこへ向かおうとしているのか」。
2つ目は、「そんな環境で、普通の家計はどんな“省エネ投資”をすれば、自分のPL(損益計算書)を守れるのか」。
3つ目は、「投資家の視点から見たとき、どのセクターの減価償却や設備投資が“電気の時代”の勝ち組・負け組を分けるのか」。
キーワードは、「同じ電気の上に、みんな乗っている」という感覚です。リビングのエアコンも、オフィスのPCも、NVIDIAのGPUも、巨大半導体工場の露光装置も、すべては“電気というコスト”をどうコントロールするかで利益が決まっていきます。国レベルのエネルギー政策の話は、つい遠い世界の議論に聞こえますが、実はあなたの電気料金明細や、あなたが持っている投資信託の中身とも、がっつりつながっています。
難しい数式や専門用語は抜きにして、「電気代」という身近な入り口から、AIとエネルギー政策、そして投資の世界までを、一本の線でつなげていきます。読み終わるころには、「電気代のニュースを見る目」と「投資先を見る目」が、少しだけ変わっているはずです。
目次
「安い電気」がAI時代の国力になる理由

AIの話というと、どうしても「どの会社のGPUが速いか」「どの国が何nmの半導体を作れるか」といった“チップ側”に目が行きがちです。でも、そのチップを動かしているのは、ただの「電気」です。しかも、AIブームで世界中のデータセンターが増え続けている今、「どれだけ安く安定して電気を供給できるか」が、そのまま国の競争力になりつつあります。
国際エネルギー機関(IEA)は、世界のデータセンターが使う電力は2030年までに今の2倍以上になり、約945TWh(テラワットアワー)に達するかもしれないと見ています。これは、日本全体が1年間に使う電気を少し上回るくらいの規模です。AI向けのデータセンターだけを見ると、その電力使用量は4倍以上に増える可能性があるとも言われています。
こうした状況の中で、「再エネをただ優先するだけでなく、AIや半導体産業のために電力単価そのものを下げるべきだ」という議論が、シンクタンクなどから出てきています。要するに、「電気が安い国に、AIと半導体の仕事とお金が集まる」というシンプルな構図です。ここでは、そのメカニズムを、できるだけ生活感のある言葉でほどいていきます。
データセンターは“巨大な電気ストーブ+冷蔵庫”
AIを動かすデータセンターは、イメージとしては「部屋中にゲーム用PCをぎっしり並べて、24時間フルで回している」ようなものです。そこで発生する熱を冷やすために、さらに大量の電気を使います。かなり乱暴にたとえると、「すごく熱くなる電気ストーブを何万台も並べて、その熱を冷やすために巨大な冷蔵庫をつけっぱなしにしている」ような感じです。
今のデータセンターの電力消費は、世界全体の電気使用量の中ではまだ1〜2%程度とされていますが、ここ数年は毎年2ケタ近い伸びで増えていて、2030年には2倍以上になるという見通しも出ています。AI向けのGPUサーバーは特に電力を食うため、「AIを増やす=電力負担が重くなる」という図式は避けにくくなっています。
企業の立場から見ると、この電気代はそのまま「原価」の一部です。GPUサーバー1ラックあたり何kW食うのか、その電気をいくらで調達できるのかで、1回の推論(推しのAIに質問する1回分)あたりのコストが変わってきます。ほんの1円の差に見えても、それが世界中のユーザーのアクセス回数分積み上がると、利益を大きく左右します。
だからこそ、クラウドやAIで世界を取ろうとしている企業は、「どの国にデータセンターを置けば、安くて安定した電気が手に入るか」を真剣に計算しています。電力単価が安い国は、それだけでAI時代の“誘致力”が高い、ということになります。
電力単価が工場立地と雇用を動かす
AIだけでなく、半導体工場(ファブ)も同じ構造です。先端の半導体工場は、1つの工場で原発1基分に近い電力を使う、という表現がされることもあります。それくらい、電気をじゃぶじゃぶ使う産業です。
日本の経産省がまとめた半導体戦略でも、「電気料金を含む生産コストが高いと、そもそも投資の候補地として選ばれにくい」という問題意識が繰り返し語られています。世界では、アメリカのCHIPS法やヨーロッパの補助金政策など、「工場を誘致するための補助金+安い電気+税制優遇」のパッケージ競争が激しくなっています。
企業から見れば、とてもシンプルです。
「A国:電気が安いけど人件費がやや高い」
「B国:電気が高いけど補助金が出る」
「C国:電気も人件費もそこそこだけど、政治リスクが低い」
こうした条件を全部足し合わせて、どこに工場やデータセンターを建てるかを決めます。その中でも、電力単価は「毎日確実に出ていく固定費」なので、長期的な投資判断にかなり効いてきます。
結果として、「電気が安い国」には工場やサーバーが集まりやすく、そこで働く人の雇用や、周辺ビジネスも増えます。逆に、「電気が高い国」は、せっかく技術や人材があっても、コストが合わずに投資を取り逃がすリスクを抱えることになります。
日本の電気料金は世界でどのあたり?
では、日本の電気料金は世界の中でどのポジションにいるのでしょうか。経産省の資料を見ると、家庭向け・産業向けともに、日本の電力料金は主要国と比べて「やや高め〜高いグループ」に属していることがわかります。
IEAの電力市場レポートでも、2023年時点で日本の卸電力価格(電気を大量に売買する市場の値段)は、2019年より3割ほど高い水準にあり、一方でアメリカはほぼ2019年レベルまで落ち着いていると指摘されています。
燃料価格の急騰が落ち着いたとはいえ、日本はもともと燃料のほとんどを輸入に頼っているうえ、送配電網の整備コストや再エネの買い取り制度の負担などが電気代に乗っているため、構造的に「電気が安い国」とは言いにくい状況です。
もちろん、最近はガス価格の落ち着きや政府の負担軽減策などもあって、電気料金そのものはピークから少し下がってきています。ただ、「AIや半導体を呼び込みたい」「家計の電気代負担も減らしたい」という目標を同時に達成するには、発電の構成、送電網への投資、料金メニューの工夫など、かなり長期的で地道な政策パッケージが必要になります。
ここまで見てきたように、「電力単価=国の競争力」という話は決して大げさではありません。AIデータセンターの立地、半導体工場の投資先、そしてそこで生まれる雇用や税収まで、かなりの部分が「電気がいくらか」に左右されています。
そして、この“国レベルの勝ち負け”の話は、実はあなたの家の電気料金明細ともつながっています。次のセクションでは、マクロな話から少し視点を落として、「電気代=家計の固定費」として、私たち一人ひとりがどんな省エネ投資を考えられるのかを掘り下げていきます。
「電気代=家計の固定費」をどう攻めるか
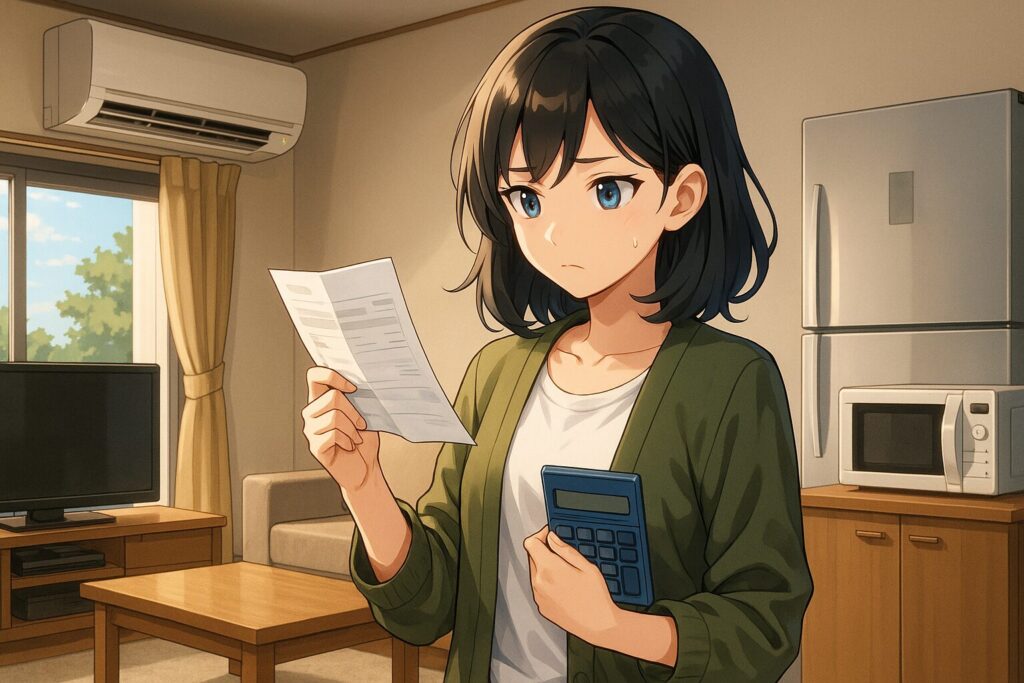
ここからは視点をぐっと下げて、「国の電力単価」の話を「うちの電気代」に落としていきます。マクロでは電力単価が国の競争力を左右しているように、ミクロでは電気代があなたの家計の競争力をじわじわ削ったり、守ってくれたりします。
家計の感覚でいうと、電気代は家賃やスマホ代と同じ「ほぼ毎月必ず出ていくお金」です。しかも、電力料金の単価は自分ではコントロールしにくいので、「高くなっても、まあ仕方ないか」と受け入れてしまいがちです。でも、本当にコントロールできないのは「単価」だけで、「どれだけ使うか」という“量”のほうには、意外と打ち手があります。ここをきちんと設計しておくと、長い目で見て家計に効いてきます。
電力会社から届く明細書を、ひとつの「ミニPL(損益計算書)」だと思って眺めてみてください。上のほうに「電力量料金 〇〇kWh」、下のほうに「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」などが並び、最後に「ご請求金額」が出てきます。今までは一番下の金額にしか目がいかなかったとしても、その中身は「単価」と「量」の掛け算でできている、ということに気づくと、少し見え方が変わってきます。
省エネというと、「こまめに電気を消す」「エアコンを我慢する」といった“根性論”のイメージが強いかもしれません。でも、AIやデータセンターが巨大な電気PLを持っているように、家計も「電気PL」を、もっと冷静に設計し直すことができます。ここでは、精神論ではなく、「どこにお金を投じれば、長期的に電気代が軽くなるのか」という“省エネ投資”の考え方に絞って話を進めます。
「単価」と「量」を分けて考えるだけで、戦略が見えてくる
まず押さえたいのは、「電気代=単価 × 使った量」という、とてもシンプルな構造です。このうち、単価は基本的に電力会社や国の制度で決まる部分が大きく、個人で動かしにくいところです。一方で、使った量は、家電の選び方や住まいの性能、暮らし方でかなり変わってきます。
たとえば、同じ1kWhでも、古いエアコンで冷房するのか、新しい省エネ型エアコンで冷房するのかによって、部屋の快適さは変わります。同じ電気量でより涼しく(あるいは暖かく)できる家電に入れ替える、というのは「量」を下げるための典型的な投資です。
もう一段引いて見ると、「一番電気を食っているのは何か」を知ることがスタートラインになります。多くの家庭では、エアコン、給湯(電気温水器やエコキュートなど)、冷蔵庫、照明あたりがトップグループです。この“上位メンバー”に対して優先的にお金を投じるほうが、細かい節約術を頑張るよりも、効果が大きくなります。電気の世界でも、「ボスキャラから倒す」のが効率的です。
エアコンと給湯という「2大どんぶり」を攻略する
家計の電気PLで特に重たいのが、エアコンと給湯です。どちらも「我慢すれば下げられる」タイプのコストですが、無理をすると健康を崩したり、生活の質が下がったりします。ここで考えたいのは、「我慢」ではなく「設備のアップデート」です。
エアコンでいうと、10年以上前の機種と最新の省エネ型では、同じ能力でも消費電力にかなり差があります。カタログに書いてある「年間電気代の目安」は、あくまで標準的な使い方をしたときの参考値ですが、それでも新旧の差ははっきり出ます。もし、リビングのエアコンだけでも最新機種に変えたとしたら、毎月数百円〜千円単位で電気代が軽くなるケースもあります。
給湯も同じです。電気でお湯を作る「エコキュート」のような給湯器は、初期費用こそそれなりにかかりますが、効率の良い機種を選ぶと、ガスや古い電気温水器に比べてランニングコストが下がる場合があります。毎日お風呂に入る家庭ほど、この差は大きくなります。
ここで大事なのは、「値札の金額」だけでなく、「何年使う前提で、トータルいくらの電気代になるのか」という視点を持つことです。AIデータセンターが、電気代込みで何年で投資回収できるかを計算しているように、家庭のエアコンや給湯器も、「トータルコスト」で比べると、意外な発見があります。
省エネ投資を「利回り」で見る発想を持つ
もう一歩踏み込むと、省エネ投資を「利回り」という感覚で見てみるのもおすすめです。利回りというのは、ざっくり言うと「投じたお金に対して、毎年どれくらいのリターン(この場合は節約効果)があるか」というものです。
たとえば、30万円かけて高断熱の窓に替えた結果、毎年の冷暖房費が2万円浮くとします。単純計算で、2万円 ÷ 30万円 = 約6.7%の“利回り”です。定期預金や、元本保証の金融商品ではなかなか見ない数字ですよね。もちろん実際には、住んでいる地域や使い方で変わりますが、「設備への投資が、自分にとってどんな利回りになりそうか」という目線を持つと、判断がしやすくなります。
屋根に太陽光パネルを載せる場合も同じです。初期費用は大きいですが、発電した分だけ電気を買わずに済み、余った電気を売ることもできます。これを10年、15年と続けたときのトータルのメリットを見て、「この家に何年住むつもりか」「電気代が今後どうなりそうか」といった要素も加味しながら、投資として合うかどうかを考えていくイメージです。
ここまで来ると、家計の省エネはもはや「節約テク」ではなく、「小さなインフラ投資」に近い世界になります。AIや半導体の工場が、巨大な設備投資で電気コストを最適化しているのと、スケールは違ってもロジックは同じです。どこまで投資し、どのくらいの期間で回収を目指すのか。これをきちんと設計しておくと、「電気代がまた上がった…」というニュースに翻弄されにくくなります。
次のセクションでは、視点をもう一度マクロに戻して、「投資家」という立場からこの“電気の時代”を眺めてみます。どんな業種の、どんな設備投資や減価償却が、これからの成長と利益を左右していくのか。あなたの投資先の中に、どんな“電気PL”が隠れているのかを、一緒に見ていきましょう。
「電気の時代」に投資家はどこを見るべきか

ここまで、「国レベルの電力単価」と「家計レベルの電気代」をつないできました。最後に視点をもう一段引き上げて、「投資家」という立場から、“電気がカギを握る産業”をどう見ればいいのかを整理していきます。
ポイントはシンプルで、「電気代がコストのど真ん中にあるビジネスほど、エネルギー政策や電力単価の変化に敏感になる」ということです。そして、そういうビジネスは、たいてい「でかい箱モノ」と「でかい設備投資」を抱えています。決算書でいえば、貸借対照表の「有形固定資産」と、損益計算書の「減価償却費」がズッシリ重い会社たちです。
AI、データセンター、半導体工場、電力会社、送配電網、再エネ発電、電力関連インフラ…。こうした業界は、見た目はバラバラでも、「電気PL」というレンズで見ると、かなり似た匂いを放っています。投資家としては、この“電気目線”で決算書を眺めてみると、今まで見えなかったリスクとチャンスが浮かび上がってきます。
AI・クラウド銘柄の「電気付きPL」を想像する
まず、AIやクラウド関連の企業について考えてみましょう。彼らのビジネスモデルは、一見すると「ソフトウェア」「サブスクリプション」「課金制サービス」など、電気とは遠そうな単語が並びます。でも実態としては、裏側に巨大なデータセンターがあり、そこにギッシリ並んだサーバー群が、膨大な電気を食べ続けています。
生成AI関連のニュースでは、「計算量が何倍になった」「パラメータ数がいくつだ」といった技術的な話題が取り上げられがちです。しかし、その計算量を支えるのは全部電力です。「推論1回あたりの電気代はいくらくらいなのか」「モデルを大きくすることで、その電気代はどう増えるのか」といった視点は、ほとんど報道されません。
投資家としては、AI・クラウド企業を見るときに、「売上やユーザー数が伸びた」という表側と同時に、「それを支えるデータセンターやGPU投資がどれくらいのペースで積み上がっているか」「その運営コストに占める電気代の割合はどのくらいか」といった裏側を意識しておくと、より冷静な目線を持てます。
決算説明資料の中には、「データセンター投資」「インフラ投資」「設備投資(CAPEX)」といった項目が書かれていますし、場合によっては「電力効率を上げる技術への投資」について触れている会社もあります。こうした項目を、「この会社の電気PLはどうなっているんだろう?」という目線でチェックしていくと、単なる成長ストーリーでは見えてこない、収益構造の重さや、今後の利益率の限界ラインがうっすら見えてきます。
半導体・製造業は「電気インフラ込み」で考える
次に、半導体や電力を大量に使う製造業です。ここは比較的イメージしやすいかもしれません。先端の半導体工場は、建設費だけで1兆円規模と言われることもあり、その中には当然、電力インフラへの投資も含まれています。
工場が稼働し始めると、毎日、ものすごい量の電気を消費します。製造プロセスの中に、24時間止められない設備もたくさんあります。電気料金が上がれば、その負担はそのまま原価に乗り、最終的には製品の価格か、企業の利益率を圧迫します。
投資家の立場から見れば、半導体や電力多消費型の製造業を見るときに、「単なる工場の数」ではなく、「どの国に、どの規模の工場を持っているか」「その国の電力単価や、エネルギー政策の見通しはどうか」というセットで理解しておくことが大切です。同じ1兆円の工場でも、電力が安い国にあるのか、高い国にあるのかで、10年スパンの競争力はかなり変わってきます。
また、決算書の「減価償却費」にも注目したいところです。大規模な設備投資を行った企業は、その設備を何年もかけて経費として落としていきます。ここが重くなっている企業は、「今まさに電気インフラ込みで勝負に出ている」とも言えます。逆に、この減価償却が一段落したタイミングで、次の投資フェーズにどう入るのか――そのあたりの経営戦略にも、電力コストの見通しが強く関わってきます。
電力・インフラ銘柄は「敵」ではなく「裏方パートナー」
最後に、電力会社や送配電網、再エネ事業者など、「電気そのものを供給する側」の企業です。個人として電気料金の明細を見ると、「また値上げか…」「燃料費調整が…」と、つい“敵”のように感じてしまうかもしれません。でも、投資家という立場から見れば、彼らはAIや半導体、製造業を支える「裏方インフラ」です。
再エネの比率をどう高めていくか、原子力をどう扱うか、送電網の更新・増強をどう進めていくか。これらの選択は、政治や社会の議論も絡む難しいテーマですが、少なくとも一つ言えるのは、「AIや半導体の成長ストーリーは、電力インフラの成長ストーリーなしには成立しない」ということです。
電力・インフラ銘柄をウォッチするときは、「規制が多くて分かりにくい業界だから」と避けてしまうのではなく、「AI・半導体ブームの裏側で、どんな設備投資や減価償却が動いているのか」「再エネや蓄電池など、新しい電力システムに向けて、どんな投資が積み上がっているのか」といった視点で眺めてみてほしいところです。
短期的には、燃料価格や規制の影響で利益が揺れやすいセクターですが、長期的には「データセンター・電気自動車・ヒートポンプ・都市インフラ」といった電化の波を受け止める“土台ビジネス”でもあります。AIや半導体だけでなく、その足元を支える電気インフラのPLとBSにも目を向けることで、「電気の時代」の投資地図が、より立体的に見えてきます。
ここまで見てきたように、「うちのエアコン代」から「NVIDIAのGPU」「最先端の半導体工場」「送電網の更新投資」まで、ぜんぶ同じ「電気PL」の上に乗っています。家計・企業・国家、それぞれの損益計算書に、電気という共通の行がある。そう意識してニュースや決算書を眺めてみると、「電気代」の一言の中に、これまで感じていた以上の重みと、投資のヒントが隠れていることに気づくはずです。
このあと、最後の結論パートで、ここまでの話をもう一度一本の線でつなぎ直しながら、「電気の時代」を生きる私たちにできることをまとめていきます。
結論:同じ「電気PL」の上で生きている、という感覚を持てるかどうか
ここまで、国のエネルギー政策、家計の電気代、投資家の視点という三つのレイヤーを行ったり来たりしながら、「電気」の話を輪切りにしてきました。最後にもう一度、それらを一本の線でつなぎ直してみます。
まず、大きな世界から。AI、半導体、クラウド、EV、データセンター。これから伸びていくと言われる産業のほとんどは、「電気をどれだけ安く、安定して手に入れられるか」で勝ち負けが決まる時代に入っています。だからこそ各国は、再エネ、原子力、ガス、送電網への投資など、いろいろなカードを組み合わせながら「自国の電力単価をどうコントロールするか」というゲームを必死に戦っています。電気が安い国に工場やデータセンターが集まり、雇用や税収までくっついていく。この構図は、そう簡単には変わりません。
一方で、私たちの暮らしに目を向けると、毎月の電気代はじわじわと家計の余裕を削る固定費です。「電気料金が上がりました」というニュースは、国のエネルギー政策の話であると同時に、あなたの家のミニPLの数字を直接動かすイベントでもあります。でも、そこでできるのは我慢だけではありません。エアコンや給湯器、断熱や窓、太陽光発電など、「電気の使い方」を変えてくれる設備に投資することで、自分の電気PLをよりタフに作り替えていくことができます。
そのときの考え方は、実は大企業と同じです。いくらかの初期費用をかけて、高効率の設備や省エネ機器に入れ替え、その投資が毎月の電気代の削減として返ってくる。何年で元が取れるか、利回りはどのくらいか。こうした視点を持つだけで、「節約」はちょっと窮屈な我慢大会から、「自分のインフラを育てる投資」に変わります。AIのデータセンターが電気効率を競っているのと、ロジックは同じです。スケールが違うだけで、やっていることは似ています。
そして投資家の視点に立ってみると、「電気PL」を意識するかどうかで、見える世界が変わってきます。AIやクラウドの成長ストーリーだけでなく、その裏側にあるデータセンター投資や電力コスト。最先端の半導体工場が、どこの国のどんな電力インフラに乗って稼働しているのか。電力会社や再エネ事業者が、どんな設備投資と減価償却を抱えながら、この電化の波を受け止めようとしているのか。決算書やニュースを、「この会社の電気PLはどうなっているんだろう」という目で見てみると、これまでとは違う輪郭が浮かび上がってきます。
大事なのは、「うちのエアコン代」と「NVIDIAのGPU」が、まったく別世界の話だと思わないことです。スケールは違っても、どちらも同じ電力市場の上に乗っかっていて、同じエネルギー政策の影響を受けています。国のエネルギー政策は、その国に工場やデータセンターを呼び込むかどうかを決める一方で、あなたの家の電気料金明細にも反映されます。そして、あなたがどの企業に投資するか、どの国の株やファンドを買うかは、再びその国の電力インフラを支える力の一部になっていきます。
「電気代のニュースを見るとき」「家のエアコンを買い替えるか悩むとき」「AIや半導体の株を検討するとき」。そのどれもが、実は同じ一本の線の上に並んでいる。そう意識できるようになると、世界の動きと自分の財布、自分のポートフォリオが、前より少しだけつながって見えるはずです。
電気は目に見えないけれど、確実にすべてのPLを流れています。家計のPL、企業のPL、そして国のPL。そのどれもに、同じ「電気」という行がある。その感覚をひとつ、自分の中にインストールしておくこと。それが、「安い電力を持つ国が勝つ時代」を、ただ傍観する側ではなく、自分の頭で考えて選び取っていく側に回るための、最初の一歩なのかもしれません。
深掘り:本紹介
もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。
『経営に活かす生成AIエネルギー論 日本企業の伸びしろを探せ』岡本浩・高野雅晴
生成AIブームが「電力」「エネルギーシステム」とどう結びついていくのかを、経営視点で整理した一冊です。生成AIとデータセンターの電力需要、各国の最新動向、再エネやスマートグリッドとの組み合わせ、そして日本企業がどこで勝負できるのかまでを、ストーリーとして追える構成になっています。
こんな人に刺さる本です
・ブログのテーマそのままに「AI×電力×経営」を一気につかみたい
・“電気代が高い日本でAIビジネスは本当に戦えるのか?”というモヤモヤを言語化したい
・エネルギー政策のニュースを、自分の会社や投資先のPLとつなげて理解したい
『電力危機 私たちはいつまで高い電気代を払い続けるのか?』宇佐美典也
タイトル通り、「なぜ日本の電気代はこんなに高くなってしまったのか?」を、電力業界の構造・規制・市場メカニズムから丁寧に解きほぐしていく本です。新電力の破綻、燃料高騰、再エネ政策の歪みなど、ニュースでは断片的にしか見えない要素が、一つのストーリーとしてつながります。
こんな人に刺さる本です
・「電気代の値上げニュース」が多すぎて、正直もうよく分からない…という人
・再エネや原発の議論を、感情論ではなく“数字と制度”で理解したい人
・日本株・インフラ関連株に投資している(あるいは検討している)個人投資家
『カーボンニュートラル2050ビジョン』エネルギー総合工学研究所
エネルギー専門シンクタンクが、「2050年カーボンニュートラル」を前提に、日本の電源構成・火力発電・CCUS・再エネ・原子力までを俯瞰して整理した本です。政策のスローガンだけでなく、「現実的にどうやって電気を供給し続けるのか」「コストはどうなるのか」といった、実務寄りの視点が充実しています。
こんな人に刺さる本です
・GXやカーボンニュートラルの議論を、“お題目”ではなく現実解として知りたい
・投資先のエネルギー企業やインフラ企業が、これからどんな方向を向くのかを押さえておきたい
・電力システム全体を俯瞰しつつ、自分の家計や投資判断と結びつけて考えたい
『改訂版 AI時代のビジネスを支える「データセンター」読本』杉浦日出夫
“クラウドの裏側”で何が起きているのかを、データセンターの仕組みとビジネスモデルからわかりやすく解説した本です。改訂版では、近年の通信量の増加や、ハイパースケールDCの登場、最新の省エネ・高効率化の動きなどもフォローされており、「AIブームがどう電力需要を押し上げているのか」をイメージしやすくなっています。
こんな人に刺さる本です
・「データセンターって結局、何をしている箱なの?」という素朴な疑問を持っている
・クラウド銘柄・DC関連REIT・通信インフラ企業に投資している
・AIニュースはよく見るけど、その“電気のインフラ側”を押さえておきたい
『どうする? 電気代 節約完全マニュアル(IPS MOOK)』
2023年の大手電力会社の一斉値上げを受けて作られた、“電気代ショック”に直球で答えるムック本です。なぜここまで値上げが続いているのかという背景説明から、エアコン・冷蔵庫・照明・給湯など、家庭内の「電気を食う場所」ごとの具体的な節約ポイントまで、写真や図解つきで整理されています。
こんな人に刺さる本です
・「とにかく今月の電気代を下げたい」という超・実務志向の読者
・ブログを読んで“省エネ投資”の考え方に興味を持ったけれど、まずは手軽なところから始めたい人
・家族やパートナーと一緒に「どこから見直す?」と会話したい
それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21520906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1328%2F9784296121328_1_26.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20878204&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3115%2F9784065303115_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21230911&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5428%2F9784885555428_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20915571&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4701%2F9784344944701_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=22450113&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6073%2F2000013196073.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













コメントを残す